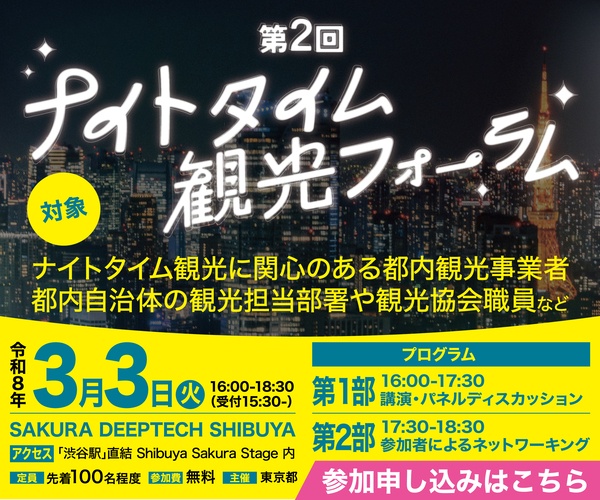大阪・関西万博が10月13日に閉幕した。一般来場者数が当初目標の2500万人を上回り、2557万8986人、関係者(スタッフ、VIP、メディア関係者など)が343万8938人で最終的な総来場者数は2901万7924人という歴史的な数字の記録であった。
並ばないという前触れはかなえられず、私もいろいろ並んだ。
8月13日21時半ごろ、大阪メトロ中央線で電気系統のトラブルが発生し、運転見合わせとなった影響で、万博会場内に翌朝まで滞在するなどした帰宅困難者を含む、足止めされた人の総数は3万人以上に上った。
また、閉幕が近づくにつれ駆け込み需要が高まり、予約のないチケットが死券となる等の問題も少なくなかった。いずれも、想定された問題だけに対応には課題が残る。
しかし、入場者数が確保でき、収支が黒字になったことで世間の風当たりは少ない。そして、インバウンド需要拡大と関西への観光の起爆剤になったことは確かである。
私は4月の会期始めに訪れたが、スタッフの対応の要領の悪さ、気遣いのなさ等が目立った。
過日、土曜日17時、夕食には少し早い時間だが、ファストフードの店に行った。早めの動きもみんな考えることは同じであり、10組30人待ちである。席は4人席が四つと2人席が三つの計22席、そのうち2テーブルは片付けが済んでいない。
しかしたくさん空いているではないか、といらついている自分がいる。
原因は二つ。一つは明らかに人手不足である。食べに来る人は多いが、料理をつくる人間や配膳をする人間が少ない。そりゃそうだ。店側より客側の方がいい。
二つ目は行動が遅い、無駄な動きが多い、要領が悪い、働かされている感満載で仕事に対する前向きな姿勢が感じられない。声がけや笑顔が足りない。つまりは、サービス業のスキルが低く、労働意欲が足りない。
モチベーションが足りない、生きる志が低いのも気になった。私もいくつかの組織の役員をしているが、共通の悩みでもある。働いている当人たちはそのレベルでも自分はとても頑張っていると思っている。上も他も見ないで自分の感情で限界をつくってしまって、伸びるとか、より高みを目指そうとか、低いレベルに甘んじている。
その結果が低い日本の労働生産性につながっている。OECD加盟国の時間あたりの生産性では1位のアイルランド154.9ドル、8位の米国97.7ドル。平均は71.3ドルで、それよりはるかに低い日本は29位の56.8ドルと、加盟33カ国の最下位に近い位置にある。
新内閣で物価対策や減税対策で手取りを増やそうとする政策の検討がなされている。米国では最低自給が30ドル(4500円)で、日本はこれから1500円を目指そうとしている。それでもすでに3倍の差がある。
働き方改革は決して働かない改革でない。どう意欲を持って生産効率よく稼ぐのかが求められている。多客期と閑散期や客待ちしているだけ等、労働時間帯格差が大きいサービス業の生産性アップを精査しなければ業界は発展しない。