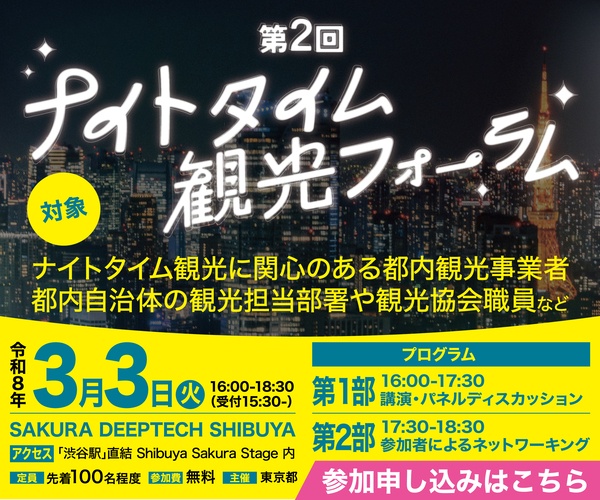写真左から、荒木氏、井上氏、雀部氏、山本氏、髙田氏
Trip.comカンファレンス「ENVISION.2025」上海で開催 日本のホテル幹部座談会
「欧米客も日本人客もTrip.com経由で増加」
トリップドットコム(Trip.com)グル―プは5月26日、グローバルカンファレンス「ENVISION.2025」を上海国際コンベンションセンターで開いた。世界74ヵ国から宿泊施設を中心としたサプライヤー(取引先)約3,100人が出席。その12%は日本からの参加者だった。観光経済新聞社では、日本から出席したホテル4社の幹部とTrip.comの日本代表にお集まりいただき、現地で座談会を行った。ご出席者は、三井不動産ホテルマネジメント取締役会長の雀部優氏、西武・プリンスホテルズワールドワイド常務執行役員の井上画期氏、ホテルモントレ代表取締役社長の山本啓之氏、東急リゾーツ&ステイ マーケティング戦略統括部副統括部長の荒木昌志氏、Trip.com International Travel Japan 代表取締役社長の高田智之氏。司会はkankokeizai.com編集長の江口英一。
「生成AIをシステムに組み込む具体策が見えてきた」
——今回のカンファレンスの印象、ご感想はいかがですか。昨年もご参加されている場合は、昨年と比較してどう感じられましたか。
雀部「昨年も参加しましたが、まず3つの感想があります。1点目は、昨年はTrip.comに限らず、どのOTAもAIへの向き合い方を模索段階で、具体化されていませんでした。今回はTripGenieをはじめとする生成AIをどう自社システムに組み込むか、より具体的になっていると感じました。2点目は、Trip.comの独自路線(テクノロジーを活用した成長戦略)で強く大きくなろうという姿勢が鮮明だったことです。3点目は、前年比といった数字の説明が多かったのですが、Trip.comらしい顧客との感動的なストーリーの方が、参加者の心を掴んだのではないかと思います。他のOTAにはないTrip.comならではのユニークなサービスを前面に出すことで、より共感が高まったのではないでしょうか」

三井不動産ホテルマネジメント取締役会長の雀部優氏
井上「私も昨年参加させていただきました。74カ国3,100名というパートナーが参集し、昨年と比較しても倍以上の規模になっていて勢いを感じました。受け入れ、おもてなしが素晴らしいと思いました。私どもホテル業において、お客様をお迎えしていますが、Trip.comさんも同じ気持ちで私達を迎えてくれているのだなと深く感じました」

西武・プリンスホテルズワールドワイド常務執行役員の井上画期氏
山本「私は今年初めて参加させていただきましたが、74カ国で3,000名以上という集まりのエネルギーに非常に感銘を受けました。Trip.comのリーダーシップが非常に印象的です。私たちは他のグローバルOTAとも付き合いがありますが、おそらく発想の原点が違うと感じました。カスタマーエクスペリエンスから発想しているOTAと、単に部屋を売ろうという発想から来ているOTAでは対極だなと思います。Trip.comはプラットフォームになろうというフィロソフィーが素晴らしいと感じました」

ホテルモントレ代表取締役社長の山本啓之氏
荒木「私は現場に一番近い立場で、自らTrip.comさんと契約して販売していただくような立場です。昨年も参加しましたが、ここまで来たかというのが正直な感想です。3年前のカンファレンスでは、国内開催だったこともあり、ほとんど担当者レベルの参加でした。しかし今や経営者レベルの方が参加されています。いかにこの予約ソースが重要かということが経営者レベルに認知された証です。他のメジャーなOTAと比較しても、Trip.comは抜きん出て、緊密な関係を築いていると感じました。3年前に高田さんとこういうことをやりたいねという話をしたことが、どんどん実現されていっていることに驚きました」

東急リゾーツ&ステイ マーケティング戦略統括部副統括部長の荒木昌志氏
「中国マーケットはインバウンド全体で1.6倍、Trip.com経由では2.3倍に」
——メインランドチャイナを中心とした北東アジア、東南アジア地域からのインバウンド宿泊客の動向はいかがですか。昨年からの変化はどうでしょうか。
雀部「当社全体で2023年と2024年を比較すると、メインランドチャイナからのお客様はおよそ1.6倍になっています。韓国、香港、台湾の伸びより高く、中国からのお客様が他の北東アジアの3カ国よりも急増しています。Trip.com経由で見ると、同じく2023年と2024年の比較で、メインランドチャイナからの送客は2.3倍です。韓国も2.2倍、香港1.5倍、台湾1.88倍と伸びていますが、絶対数でいうと中国から圧倒的に多く送客いただいています。我々の会社全体ではインバウンドの追い風もあり、ADR(平均客室単価)が大きく伸びていますが、その大きな要因の一つがTrip.comからの送客増加です」
井上「2025年度の動き出しで見ると、2024年度と比較して若干マイナスしています。理由としては、戦略的な物で個人予約は増えております。個人は予約サイクルが短いので、時期が近づくにつれて予約は増加してくると思います。いずれにしても、私たちはデジタルマーケティングを活用した促進策を展開していきますので、今後成長するものと考えています」
山本「実績ベースで2024年の1-5月と2025年の1-5月を比較すると、約174%、つまり8割増という実績になっています。2025年度に当社が最も客室を販売した国は中国で、その70%がメインランドチャイナからの予約です」
荒木「去年のマーケットリカバリーから急激な円安トレンドになり、当然ながら単価が高騰しています。コロナ以降は、どのホテルも稼働を上げるよりも、稼働はマーケット連動で単価をしっかり取っていく戦略に変わってきていると思います。我々も同様で、前年同期と比較すると、第一四半期で施設にもよりますが、約20%から30%程度レブパー(RevPAR:販売可能な客室1室あたりの収益)が上昇しています。円安の影響もありますが、特に顕著なのは、メインランドチャイナだけでなく、東南アジアのより南の国々からの旅行者が増えていることです。人口の多い国からの旅行者が活発化しており、ファーストトリップ(初めての日本旅行)という人たちが増えています。特に大阪はそういった方々が最初に訪れる都市の一つなので、市場全体を底上げしてくれています。当社の大阪なんばの施設では、毎月トップの予約国が変わります。シンガポール、タイ、フィリピン、中国と、シーズンによって変化するため、非常にコントロールしやすい状況になっています」
「欧米客も日本人客もTrip.com経由で増加、ブランド浸透が進む」
——Trip.com経由の予約で、欧米客、日本人客は増えていますか。増えている場合は、数、比率などでどれくらい増えていますか。
雀部「国内客は増えています。インバウンドが増加しているため国内市場全体の伸びは減少傾向ですが、Trip.com経由では1.2倍程度増えています。欧米客もTrip.com経由では2.6倍ほど増えています。ただし、全体数でいうと中国のパワーがあまりにも大きいので、欧米客は伸び率に対し、絶対数ではまだそれほど多くないのが実情です。しかし確実に伸びているのは、Trip.comがさまざまな施策を欧米客や日本人向けに展開している結果だと思います」
井上「都内のシティホテルを中心に主要ホテルで見ると、欧米客は1.3から1.5倍、国内客は1.5倍程度の伸びです。Trip.comのアプリは視覚的に使いやすく、アフターサービスも含めてコールセンターの対応も優れていることから、ブランド力が向上していると感じます」
山本「欧米客については微増という表現が適切です。具体的にはアメリカが0.26%増と、本当に微増です。逆に日本人客は3%ほど減少しています。アジア圏内ではメインランドチャイナの影響力が強いため、韓国と香港は1%程度減少しています」
荒木「欧米客についてはTrip.com経由では微増、ほぼ横ばいです。日本人客はむしろ微減の傾向にありますが、これは宿泊単価が上昇しているため、日本人比率自体が下がっているからです。個人的には、ロングディスタンス(遠距離)からの旅行者は連泊する傾向があり、ありがたい客層です。ただ、Trip.comがわざわざ日本のOTAと競争したり、欧米系OTAと戦う必要はないのではないかと思います。皆さんがおっしゃるように、中央アジアや今日のプレゼンテーションでターゲットとして挙げられていたマレーシアなど、これから人口が爆増すると言われる成長市場で、Trip.comが得意とする地域に注力されることで、より大きな効果を発揮されるのではと感じます。同じリソースを使うなら、成長市場に集中していただきたいです。あれもこれもとなると我々も心配になります。得意分野に集中していただきたいというのが正直な気持ちです」
「事前決済率の高さとアフターサービスが他社と大きく異なる」
——Trip.comが他のOTAと比較して魅力的だと思われる点はどこでしょうか。
雀部「Trip.comの強みは3つあります。1点目は圧倒的な中国からの送客力で、これはどの旅館もホテルも認めるところです。2点目は事前決済率の高さです。他のOTAに比しても高く、Trip.comはほぼ100%なので、キャンセルに繋がる可能性も低く、ホテル側からすると確実なお客様を送っていただいていると言えます。これは大きな強みです。3点目は速攻性のある販促施策です。例えばクーポン施策といった、マーケットへの臨機応変な対応力も含め、Trip.comの大きな武器と言えます」
井上「2点あります。1つ目は、エンジニアの割合が半分以上と聞いていますが、今日のプレゼンテーションでも見られたように、ユーザービリティ(使いやすさ)が非常に良く、日々進化していることです。2つ目は、特に小規模な旅館で実感することですが、365日24時間のアフターサービスが素晴らしいです。例えば、私どもが運営する伊豆の小さな旅館では、外国人宿泊客が予定より1時間遅れて到着することがあります。旅館では食事の提供時間があり、言語の問題もあって、なぜ遅れているのか心配になります。そういった時にTrip.comのコールセンターに電話すると、すぐにお客様と連絡を取り、状況を伝えてくれます。このキャッチボールの早さに旅館の女将が驚いています。そのため、『Trip.comからの予約は安心』とスタッフが言っています。これは『売って終わり』ではなく、最後までフォローする姿勢があるからです。シティホテルのように多言語対応スタッフがいる場所は問題ありませんが、小規模な旅館では特に感謝されています。このサービスを外部委託せずに自前で持っていただいている点は、今後もぜひ継続していただきたいと思います」
山本「私も同じ意見です。トラブルが起こった際、他のOTAのカスタマーセンターに問い合わせを入れても、なかなか解決に至らず、社内でたらい回しにされることがあります。Trip.comはそもそもトラブルが少なく、問題があってもその場で解決していただけます。おそらく顧客起点でアプリ開発から全てを行い、海外旅行者のニーズや行動パターンを的確に捉えているからでしょう。これは他社には簡単に真似できません。それを支えるエンジニアの方々やテクノロジーの進化を常に追求するエネルギーが素晴らしいと思います」
荒木「ユーザーとしての立場から言うと、使いやすさが圧倒的です。私は予約操作が苦手ですが、Trip.comは簡単です。また、フェイク表示(安い料金を表示しておいて、実際の予約画面では『満室』となり高い料金を提示するような手法)がなく、レスポンスも非常に早いです。サプライヤーとしては本当に足を向けて寝られません。2022年に大阪・難波に288室の新しいホテルをオープンする際、コロナ明けという時期でもあり、新築ホテルはなかなか売れないという声をいただくこともありました。しかしTrip.comの担当者は工事中の現場を見に来て、『ここはナンバーワンになる』と言ってくれました。そして半年で他を引き離してトップクラスの実績を上げ、2年連続でアワードもいただきました。短期間で全力サポートしていただき、本当に感謝しています。また、ノンリファンダブル(返金不可)の予約で変更依頼があった際の対応も素晴らしいです。例えば『父親が亡くなった』などの理由で返金を求められることがあります。私たちが「返金できません」と伝えると、Trip.comは「わかりました。あとは当社で対応します」と言ってくれます。他のOTAは「直接お客様と交渉してください」と言う対応が多いので、その差は歴然です。このようなサポート体制も現場では非常に助かっています」
「地方分散とデータ活用でオーバーツーリズム緩和を」
——Trip.comに今後期待することは何ですか。
雀部「3つあります。1点目は、テクノロジーに強いOTAとして、AIを活用した新しいサービスの展開です。一方で、人的サービスである電話対応のコールセンターも非常に重要です。実は今回、帰りの上海から成田までの航空券をTrip.comのアプリで初めて予約してみました。予約と決済はすぐに完了しましたが、座席指定ができなかったのでコールセンターに電話しました。OTAのコールセンターは通常つながりにくいものですが、Trip.comは深夜にもかかわらず、3〜5コールで応答がありました。AIによる初期対応でしたが、有用な回答がすぐに得られました。他社との差別化として、高度なAI技術と伝統的なコールセンター対応の両方を強化していくことが大切ではないでしょうか。2点目は、先読み情報の提供です。Trip.comは世界で最もデータを持っている企業の一つです。実際、1月に高田さんと話した際、『韓国からのゲストが減少する可能性がある』と指摘されました。当時は福岡のホテルで韓国人インバウンドが好調だったので一瞬疑問に思いましたが、高田さんは3つのファクト①昨年11月8日に韓国人への中国ビザ緩和が始まった②ソウルから上海への航空券が激安になっている③上海のラグジュアリーホテルの価格が大幅に下がっている。それらから、韓国人アウトバウンドの一部が上海に流れていく懸念を示しました。実際に2月以降から当社への韓国人宿泊客は減少しています。このようなマーケット変化の情報、特に悪化傾向の早期警告は非常に貴重です。3点目は、東京や京都はインバウンドで飽和状態ゆえ、地方都市やリゾートエリアへの送客強化です。地方都市や沖縄などのリゾートは、東京・京都に比べるとまだ苦戦しています。海外旅行者の地方分散は、国の観光戦略でもあるので、ぜひ地方都市やリゾートエリアへの送客も強く期待しています」
井上「2点あります。1つ目は、先ほどの雀部さんのお話と重なりますが、グローバルマーケティングの強化として、小さな観光スポットや施設、ホテル、旅館にもスポットを当てていただきたいです。埋もれた場所を発掘することで、人気観光地の集中を緩和し、オーバーツーリズムの解消にもつながります。2つ目は、管理画面の機能強化です。予約者の地域別データは現在も提供されていますが、地域ごとのリードタイム(予約から宿泊までの期間)や連泊率、ADRなどの分析データがあると、より戦略的な対応ができます。例えば韓国市場の変化にいち早く気づき、別の市場にシフトするといった判断ができます。レベニューマネジメントを行うスタッフにとって非常に有益なツールになります」
山本「2点あります。1つ目は、Trip.comだけが顧客起点でアプリを開発しているので、使いやすさをさらに追求していただきたいです。先ほど登壇者の方が『Trip+X』というコンセプトを紹介されましたが、体験を求めて旅行するという傾向が強まっています。私どものホテルでもさまざまな体験を提供しているので、体験と宿泊を結びつけるアプリ開発をさらに進めていただきたいです。また、東京・大阪・京都だけでなく、地方への分散も促進していただきたいと思います。2つ目は、当社は中国からの旅行者比率が高いので、グローバルOTAとしてもう少し市場分散を図っていただけると、私たちにとってリスク分散になります」
荒木「私は現在ラグジュアリーホテルを担当していますが、グローバルブランドにはベストレートギャランティーなどの課題があります。現地の旅行社やMICE(会議・インセンティブ・コンベンション・展示会)のリーダーとの連携をさらに強化していただきたいです。中国から直接予約しようとしても、アクセスできないサイトも多いため、Trip.comの仲介が重要です。富裕層の取り込みが急務なので、その点でも協力をお願いしたいと思います」
「信頼関係構築のため、予約の透明性を徹底」
高田「皆様お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。たくさんの良いフィードバックをいただき、特にスタッフのことを覚えていただいていることが最も嬉しいです。いくつかのポイントについてお話しします。まず日本のインバウンド戦略についてですが、政府目標の6,000万人に向けた取り組みが進む中、日本へのインバウンドの持続的な増加を当然視する前提は、適切に再評価すべき段階にあると考えています。日本法人の代表としては、日本の観光業がインバウンドを持続的に誘致できるよう、海外から日本へのインバウンドが近隣諸国に流れないように、日本の魅力をしっかりと発信していくことが重要だと感じています。次に日本人客へのアプローチですが、当社は特にアウトバウンド(海外旅行)に力を入れています。航空券も販売しているため、韓国や台湾などアジア圏内の近距離旅行、特に若年層の利用が多いです。そうした方々がアプリをインストールし、日本国内でも少しずつ使っていただける流れができています。宿泊施設様との関係構築については、特に東京や京都のような人気エリアでは、どのチャネルからでも一定の予約は確保できる時代になっています。そこで重要なのは、宿泊施設様の負担軽減です。例えば事前支払いの比率を高めたり、24時間対応のコールセンターを運営したりといった取り組みを行っています。日本国内のコールセンターには100人以上のスタッフがおり、全国各地に事務所を設置しており、宿泊施設様で問題があればなるべく現場に駆けつけることができるように体制を拡大しています。私が2022年末に着任してから特に注力したのは、提携販売の透明性確保です。様々な代理店やランドオペレーターが在庫や料金をアップロードして販売していましたが、実際に宿泊施設様と直接契約関係があるかを全て確認し、確認できない場合は取引を停止しました。その結果、一時的に売上は減少しましたが、予約の経路や販売チャネルを全て把握できるようになりました。これにより、万が一、予約トラブル(喫煙・禁煙の間違いなど)が発生した場合も、迅速に対応できるようになりました。この2年間、宿泊施設様に迷惑をかけない、負担を減らすという方針で取り組んできました。今日皆様からいただいたフィードバックを聞き、その方向性は間違っていなかったと確信しました。これからもパートナーとの信頼関係を最優先に事業を展開していきます」

Trip.com International Travel Japan 代表取締役社長の高田智之氏
江口「本日は貴重なご意見をありがとうございました。Trip.comのグローバルカンファレンスが示すように、インバウンド市場は急速に回復・拡大しています。特に中国市場の成長は著しく、各ホテルグループの戦略に大きな影響を与えています。同時に、地方分散やオーバーツーリズム対策、テクノロジー活用など、業界全体で取り組むべき課題も明らかになりました。今後もTrip.comと日本の宿泊施設の協力関係がさらに発展し、日本のインバウンド観光の質的向上につながることを期待しています」

上海国際コンベンションセンターで座談会を実施した(左端=kankokeizai.com 編集長 江口)

写真左から、荒木氏、井上氏、雀部氏、山本氏、髙田氏
【kankokeizai.com 編集長 江口英一】