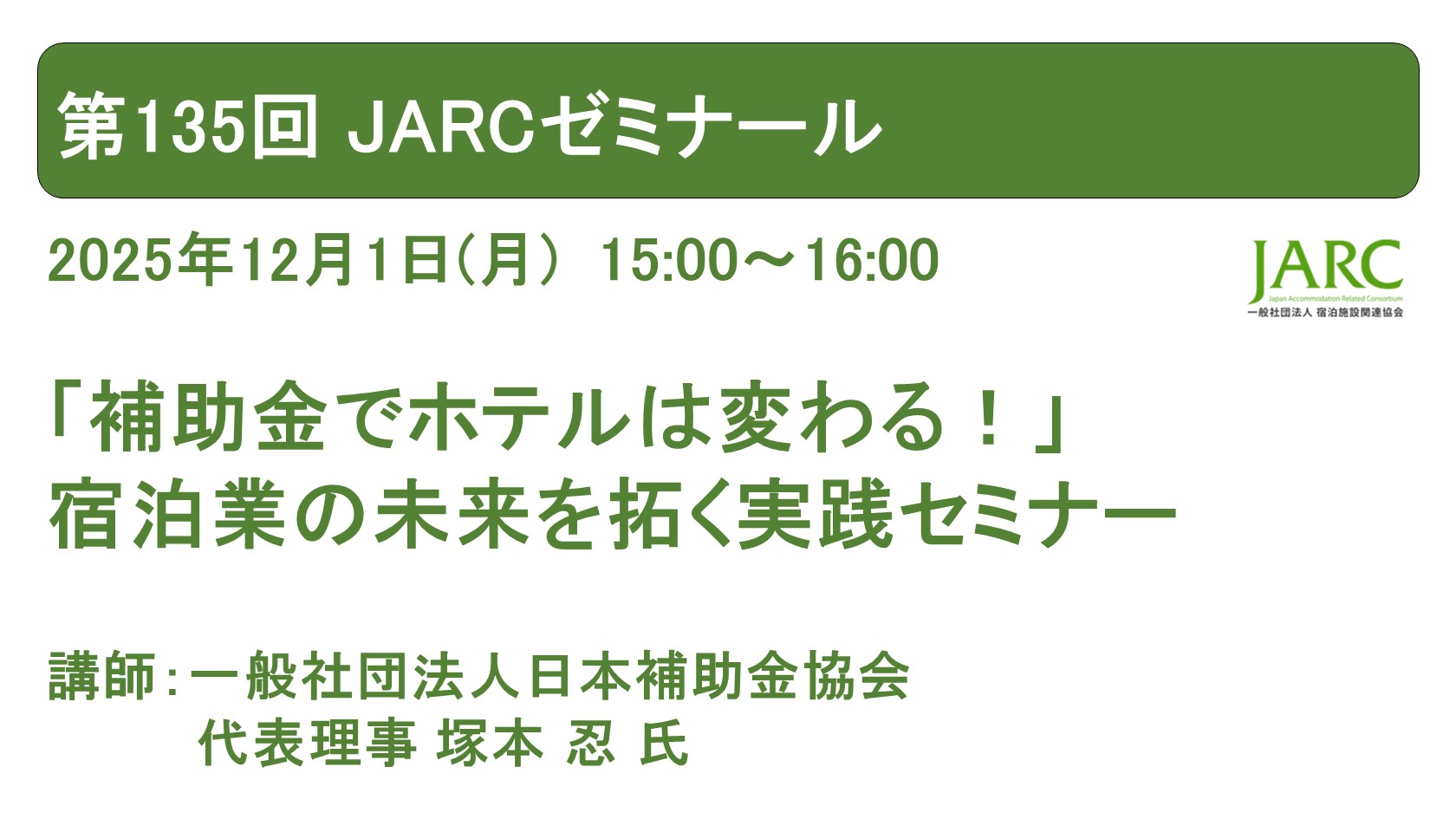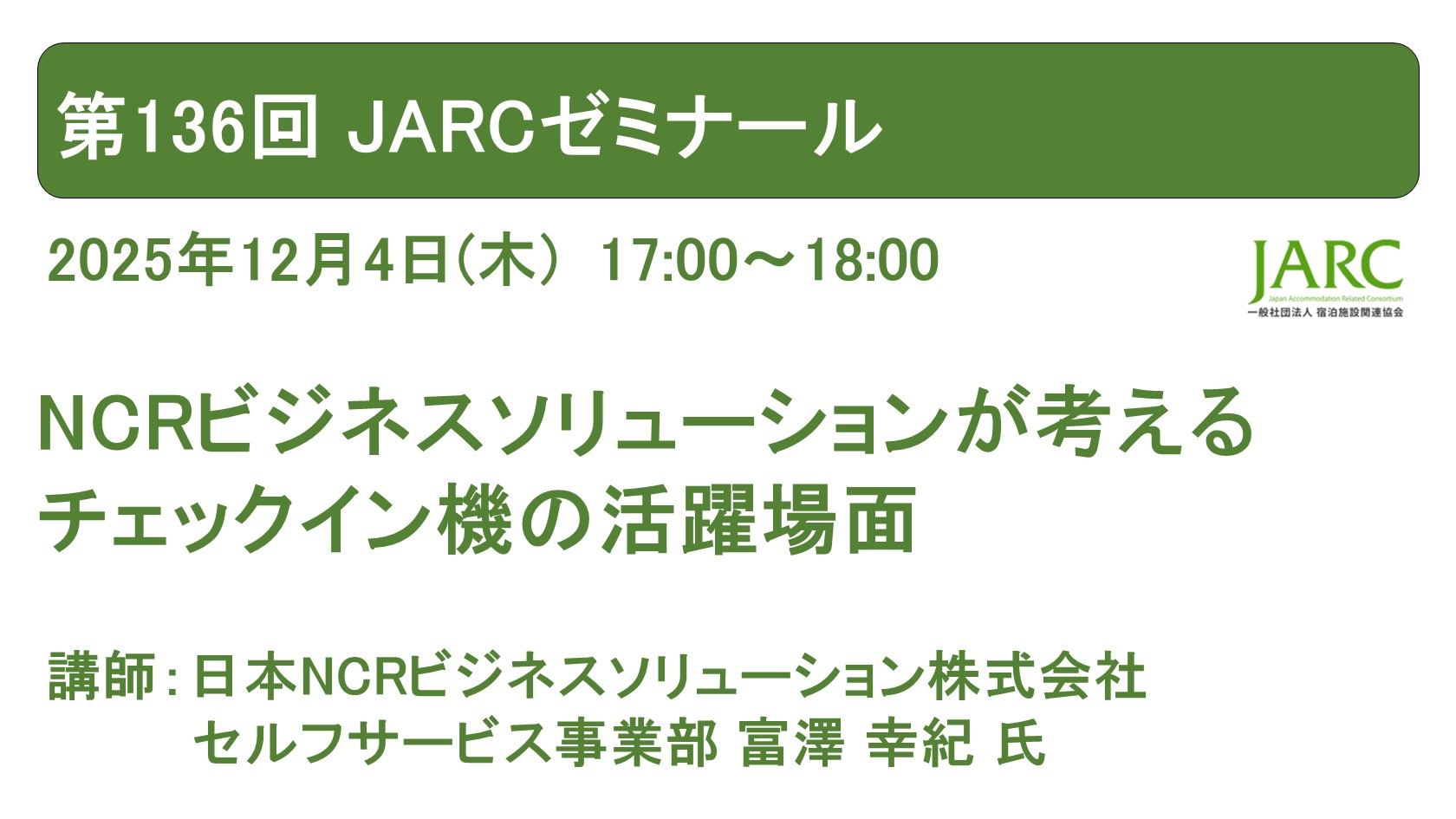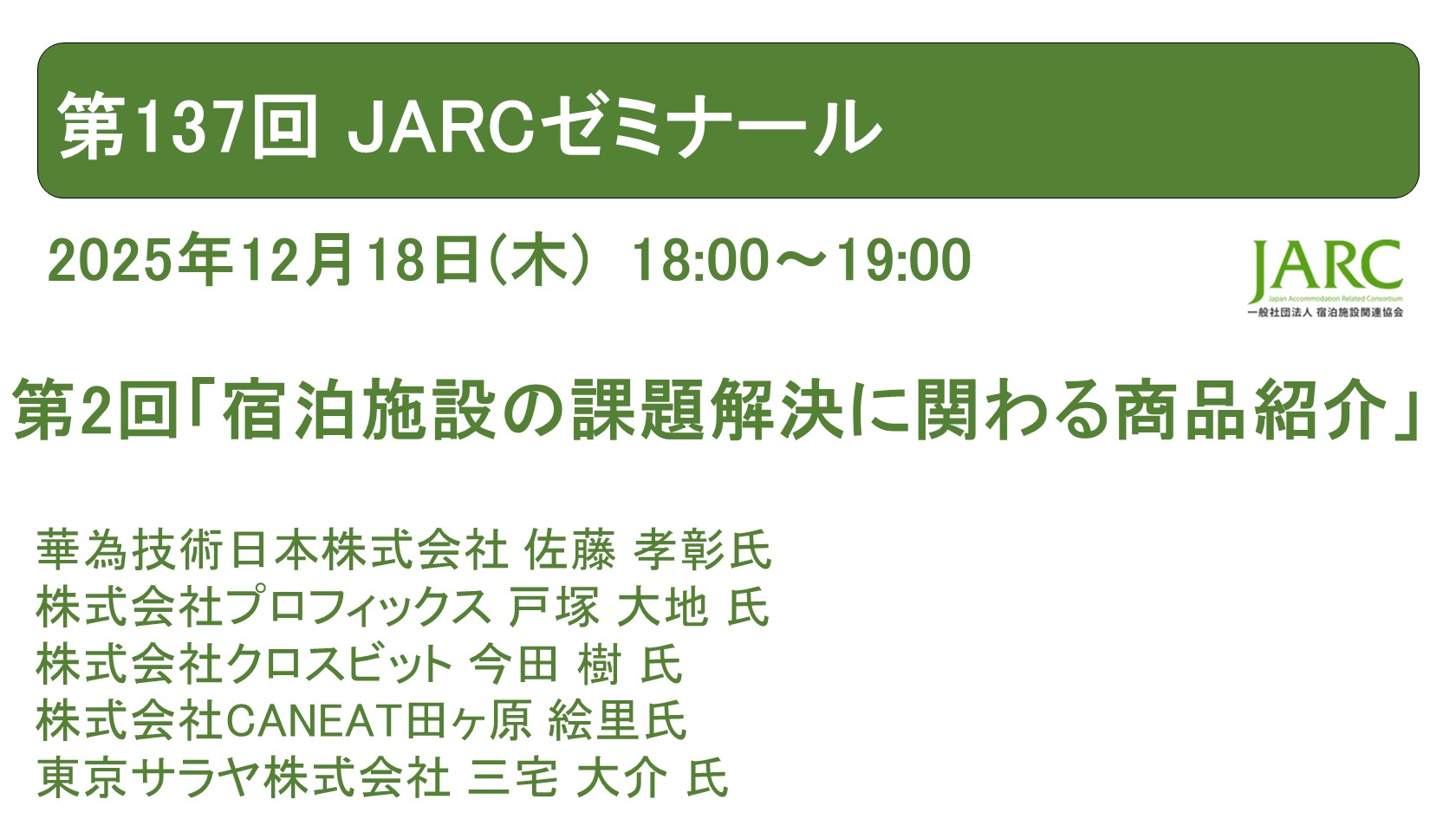全国79駅に拡大、広域防災拠点の機能強化へ
国土交通省は5月14日、広域的な防災拠点として位置づけられている「道の駅」を「防災道の駅」として新たに40駅追加選定したと発表した。これにより、全国の「防災道の駅」は79駅となる。大規模災害時の救援活動拠点や緊急物資輸送の基地機能強化を図る。
今回の追加選定は、能登半島地震での「防災道の駅」の活躍を踏まえたもの。選定された道の駅は、都道府県の地域防災計画等で広域的な防災拠点に位置づけられており、災害時に求められる機能に応じた施設や体制が整っているか、今後3年程度で整備する具体的な計画があることが条件だ。
「防災道の駅」には、建物の耐震化や無停電化、通信・水の確保など、災害時でも業務継続可能な施設整備が求められる。また、支援活動に必要な2500㎡以上の駐車場スペースの確保や、市町村と道路管理者の役割分担を定めたBCP(業務継続計画)の策定も必要となる。
国土交通省は、選定された「防災道の駅」に対し、防災機能の整備・強化を交付金で重点支援するほか、BCPの策定や防災訓練について国のノウハウを活用した支援を最大5年間実施する。これにより、大規模災害時等の自衛隊や警察、TEC-FORCE等の救援活動拠点、緊急物資等の基地機能、復旧・復興活動の拠点としての役割強化を目指す。
能登半島地震では、「防災道の駅」が広域防災拠点として大きな役割を果たした。例えば、道の駅「のと里山空港」は発災直後から避難者へ水や毛布などの備蓄品を提供。その後、支援物資の集配拠点や道路啓開活動の拠点「道路啓開支援センター」として活用された。
 会員向け記事です。
会員向け記事です。