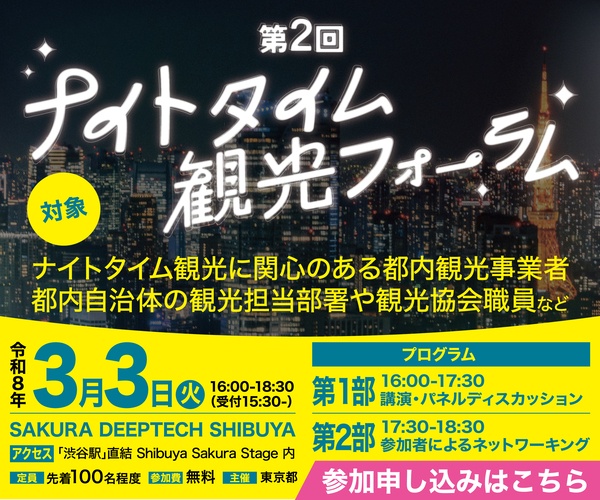兵庫県の斎藤知事(右)と日本旅館協会関西の木下副会長
大阪・関西万博が開幕した。海外と国民の接点などを生んだ70年万博だが、今回の万博は観光にどんなレガシーを残せるのか。関西各府県・旅館業界の取り組みや思いをリレー形式で紹介する。5回目は兵庫県。(聞き手は本社関西支局長・小林茉莉)
地域の取り組み、プログラム化で活性化につなぐ
――兵庫県の万博に向けた取り組みの内容とそのコンセプト、狙いは。
斎藤 万博をきっかけに、多くの人に兵庫県を訪れてもらいたい。そこで県全体を一つのパビリオンと見立てて、農業、地場産業、街づくり、観光などの取り組み現場を多くの人たちに体験してもらう「フィールドパビリオン」というプロジェクトを中心に展開している。
テーマは「Our Field、Our SDGs 私たちのフィールド、私たちのSDGs」。地域の皆さんが持続可能な取り組みを紹介する体験型のプログラムを約260件認定、ウェブで紹介している。例えば豊岡市でのコウノトリ再生の取り組みを学べるツアーや、湯村温泉での湯がき体験、淡路島ならば伝統的な塩づくりの体験などだ。
万博は夢洲の会場がメインだが、地域の活性化にいかにつなげていくかもテーマ。このフィールドパビリオンのようにプロジェクトとして取り組んでいるのは、関西では唯一当県だけだ。フィールドパビリオンの取り組みを中核に据えて、淡路島であれば「AWAJI島博」、丹波篠山の「丹波篠山国際博」などを各地で展開していただくので、地域と連携していくことが大事だと考えている。
併せて、夢洲の会場でも兵庫県をしっかり発信することが大切になる。関西広域連合の関西パビリオン内に、兵庫県ゾーンを設置して、時空を越えた兵庫県の過去、現在、未来を体験できる、アトラクション型映像空間「HYOGOミライバス」を楽しんでいただいている。このほか、万博のテーマウイークに連動させて、県内の市町の地場産業の皆さんと連携した展示も行っている。
万博会場以外では、県立美術館内に「ひょうご EXPO TERMINAL」を設置して、子どもたちがデジタルアート体験などを通して万博を体験できるようにした。また夢洲へのパーク&バスライドの駐車場が尼崎にある。そこで、駐車場横で「ひょうご楽市楽座」と銘打ち、県産品マルシェやステージイベントなどを行うナイトフェスも行う。

斎藤知事
木下 知事がフィールドパビリオンを提唱され、また観光の立場からも伴走支援を行うことで、従前の体験をフィールドパビリオンに当てはめるだけにとどまらない、SDGsコンテンツを生かした本物体験プログラムが県下にたくさんできた。第1次産業や地場産業、伝統産業としっかりとコラボレーションした、旅に出向くための魅力になりうるものばかりで、地場産業などのブランディングにも期待が持てる、非常に大切な取り組みだ。

日本旅館協会関西の木下副会長
――万博に向け、旅館ホテル業界の取り組み状況はどうか。
木下 万博に向けた準備期間がコロナ禍だったので、いったん立ち止まっていろんなことを考えるいい機会になった。国の支援もいただきながら、宿泊施設は高付加価値化を進めた。さらに兵庫県では、知事の提唱でユニバーサルツーリズム(UT)対応施設の認定が行われるようになるなど、取り組みが加速した。この取り組みがさらに充実して、誰もがいくつになっても県内旅ができるようになればいい。
――万博期間中の予約状況はどうか。
木下 開幕が近づいた頃から有馬・神戸地区のゴールデンウイーク以降の予約が伸びている。また開幕後はメディアでも万博関連情報が多く発信されるようになり、さらに予約が伸びてきた。今後は県下全域に万博効果が広がるよう取り組んでいきたい。
レガシーを残し伝える継続的事業を
――万博は、兵庫県や兵庫の観光の発展、進化にどのような役割を果たすとお考えか。
斎藤 今回の万博は、人類共通の社会課題を解決するモデルを示すのが目的の一つだ。フィールドパビリオンは、農業や地場産業、地域そのものが、少子化、高齢化によって、担い手不足などの課題に直面する中、課題を乗り越えるモデルを示すものでもある。今後先進国を中心に同じ課題が出てくる中で、課題先進国・日本として解決につながるモデルとなりうる兵庫県内の取り組みを世界に示すことは、持続可能な地域社会、産業をつくる上で重要だ。
――兵庫県の旅館ホテル業界として、万博を契機に取り組みたいこと、レガシーとしたいことは。
木下 一番に取り組むべきことはさらなる地産地消の推進だ。人口減少の中で、地域外の人を観光で呼び込み、そのエリアで作られる野菜などを食べていただくことで持続可能な発展につなげていくことが非常に大事。それはお客さまから見ても強い魅力になるので進めていきたい。
先日、神戸・有馬、宝塚、淡路の旅館・ホテル4館が、共同で開発したオリジナル日本酒「輪―Rin―」を発表した。兵庫県産山田錦、灘の宮水を材料に、西宮市の日本盛が持つ酵母を使って醸した。うまみのある瀬戸内の白身魚に合う日本酒を作り、万博に来た国内外のお客さまを兵庫の食と日本酒でもてなしたいとの思いから取り組んだ。万博を契機に地域を代表する宿泊施設が協力し合い、日本酒という形にできた。これも一つのレガシーとしていきたいし、このような取り組みをこれからもどんどん進めていきたい。
また4月に神戸空港が国際化したことは非常に大きなチャンスだと捉えている。県内各地域の旅館ホテルは、世界にも通用するように施設の高付加価値化に取り組んできたし、食の磨き上げも行ってきた。現在兵庫のインバウンド客数は京都・大阪に大きく水をあけられているが、今後、今まで京都に3泊していた旅行者が、1泊は兵庫に泊まる、さらには瀬戸内エリアに行くような流れを作って、瀬戸内へのゲートウエイ的な役割を兵庫が担い、兵庫瀬戸内全体が旅のルートとして認知されるようにしたい。
斎藤 大阪のインバウンド客が大きく伸びているのは、関西国際空港のゲートウエイの機能が作用して、大阪の魅力がインバウンド客から「発見」されたのが大きい。神戸空港が東アジア中心に国際化することで、兵庫県の魅力を発見してもらうきっかけになるはずだ。
もちろんインフラが整えばよいわけではなく、ソフト面での充実が大事だ。フィールドパビリオンは、インバウンドにも響くような体験型のツアーを組めるプログラムが多くを占めている。兵庫に宿泊して、翌日の飛行機までに少し時間があるという時に、近くにあるフィールドパビリオンのコンテンツを紹介するといったことも増えている。
万博に向けインフラ面、ソフト面で受け入れ態勢を整えたことは、兵庫の観光の大きなレガシーとして残していけるし、残るように取り組んでいく。
万博は世界中から関西に多くの人たちが訪れる、本当に貴重な機会なのでしっかり生かしたい。各国の首脳クラス、ビジネスのトップなどのVIPも多数関西に来て、随行と共に長期滞在する。そういったVIPに、当県の静かで落ち着いた、ハイクラスの宿を案内することを目指すのも一策だ。私たち行政も一緒になって、方向性の一つとして、高付加価値型の観光を目指していきたい。
木下 淡路島は今年、国際園芸・造園博「ジャパンフローラ2000」(淡路花博)から25年を迎えた。花博の会場は関西空港造成のための土取地で、当時ハゲ山だったが、緑を復活させ、花を植えたことで、たくさんの人が集まるようになった経緯がある。そしてそのレガシーを伝えるものとして「花みどりフェア」を行うことで、「花の島」としての認知、人を元気にする「花のチカラ」の再認識が進んでいる。
フィールドパビリオンやAWAJI島博も万博期間中の一過性の取り組みに終わらないよう、事業者の皆さまと振り返りを行い、プログラムをブラッシュアップし、観光のチカラにより地域全体が良くなる取り組みにつなげたい。
――兵庫県に宿泊する魅力とは何か。
斎藤 現在、UT推進条例を制定して、障害のある方から、高齢者、外国人にとっても旅行しやすい観光県づくりに取り組んでいる。その中では「ひょうごユニバーサルなお宿」の認定・支援を行うことで、ハンディキャップのある人も安心してくつろげる宿泊施設が増え魅力ともなりつつある。この取り組みを広げることが重要だ。
木下 UTは、日本だけではなく、韓国や台湾など同じ問題を抱えている国の人にも響く。ユニバーサルな宿づくりによって、3世代旅行が実現でき、家族の絆を深める場も提供できる。大変素晴らしいことだ。
兵庫県は非常に多様なエリア、多様な宿泊施設がある。神戸には世界的なブランドのホテルも数多くあり、新しく進出する予定もある。施設も高級なところから非常にカジュアルなところ、一棟貸しなど、本当に多様な宿泊施設がそろっているのは魅力だ。また兵庫五国にはそれぞれいい温泉地がある。浴衣を着てそぞろ歩きができる、城崎や有馬のような温泉地もあれば、洲本のように海を見ながらウォーキングやランニングが楽しめる温泉地もある。県内各地で連携を取りながら、周遊、連泊をしてもらえるようにしたい。

対談では万博だけでなく、地域の人材育成などさまざまな話題について意見を交わした(洲本温泉のホテルニューアワジ・ヴィラ楽園で)