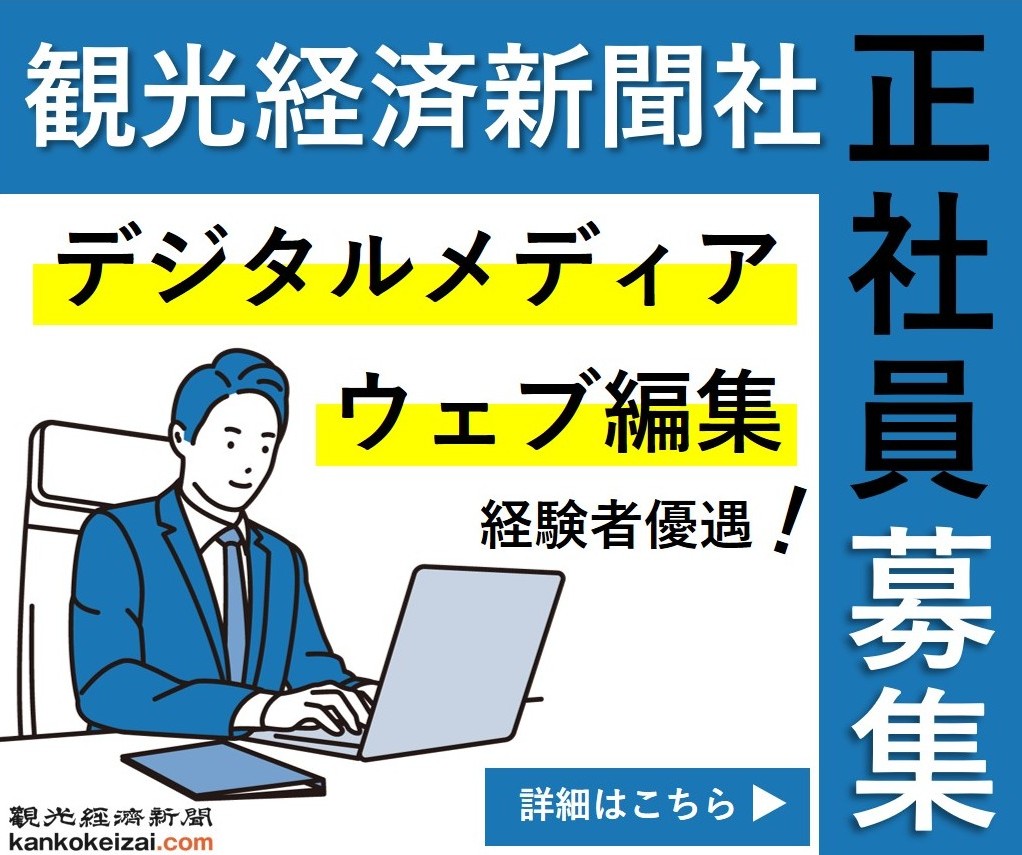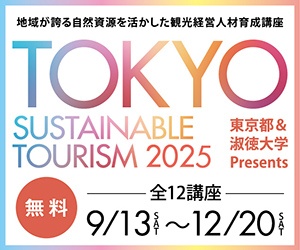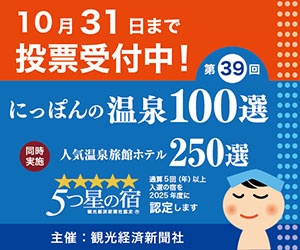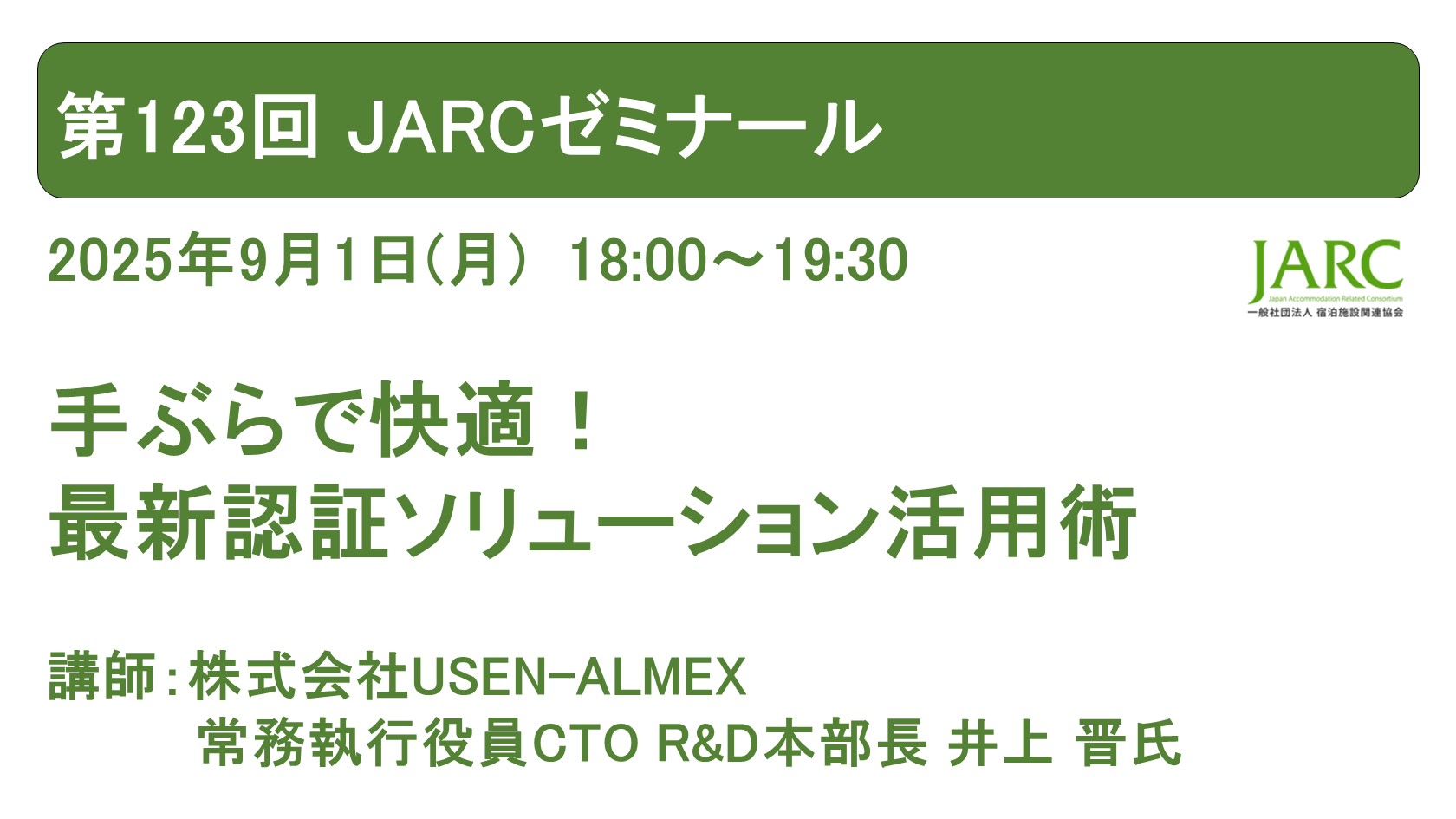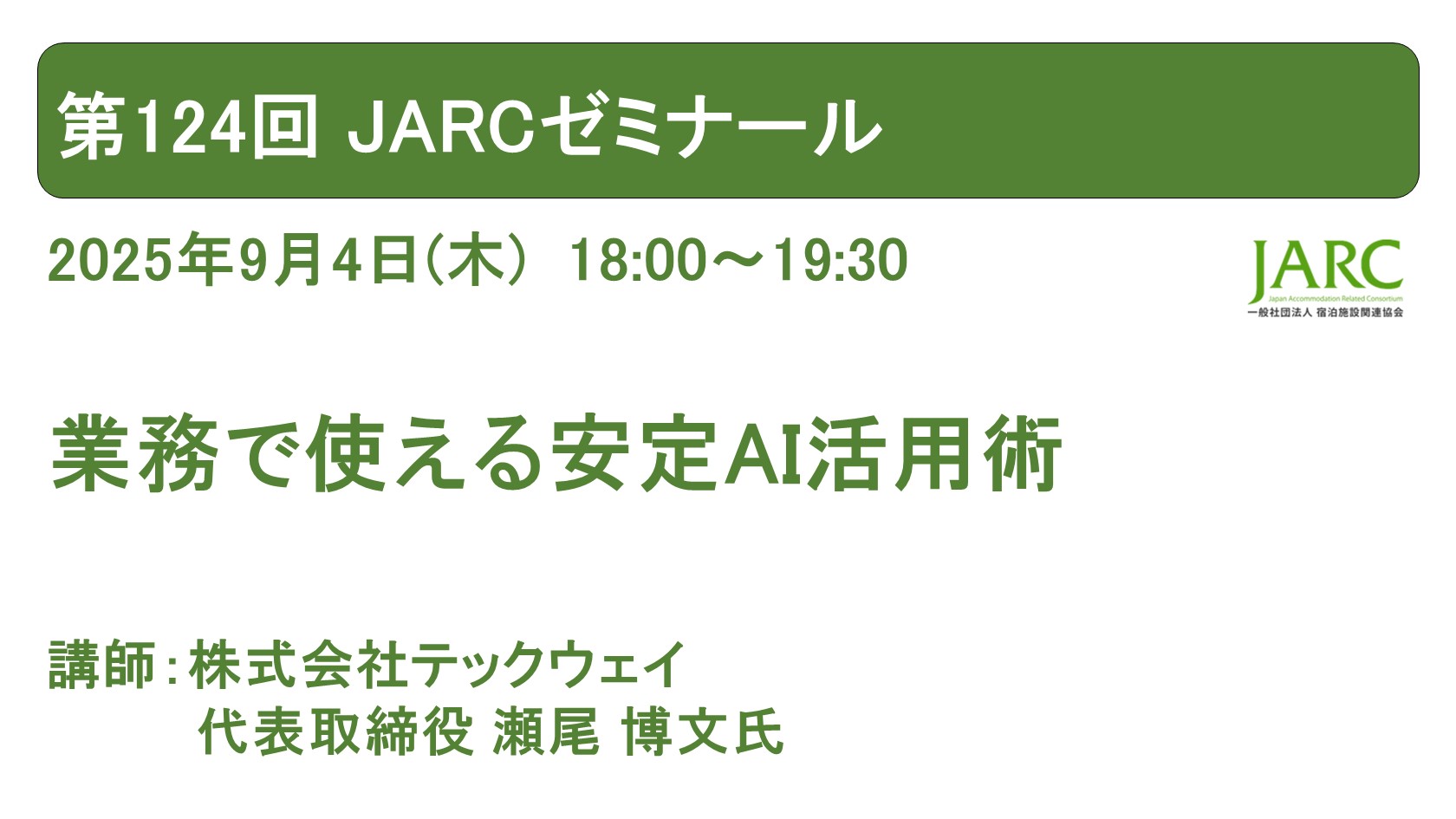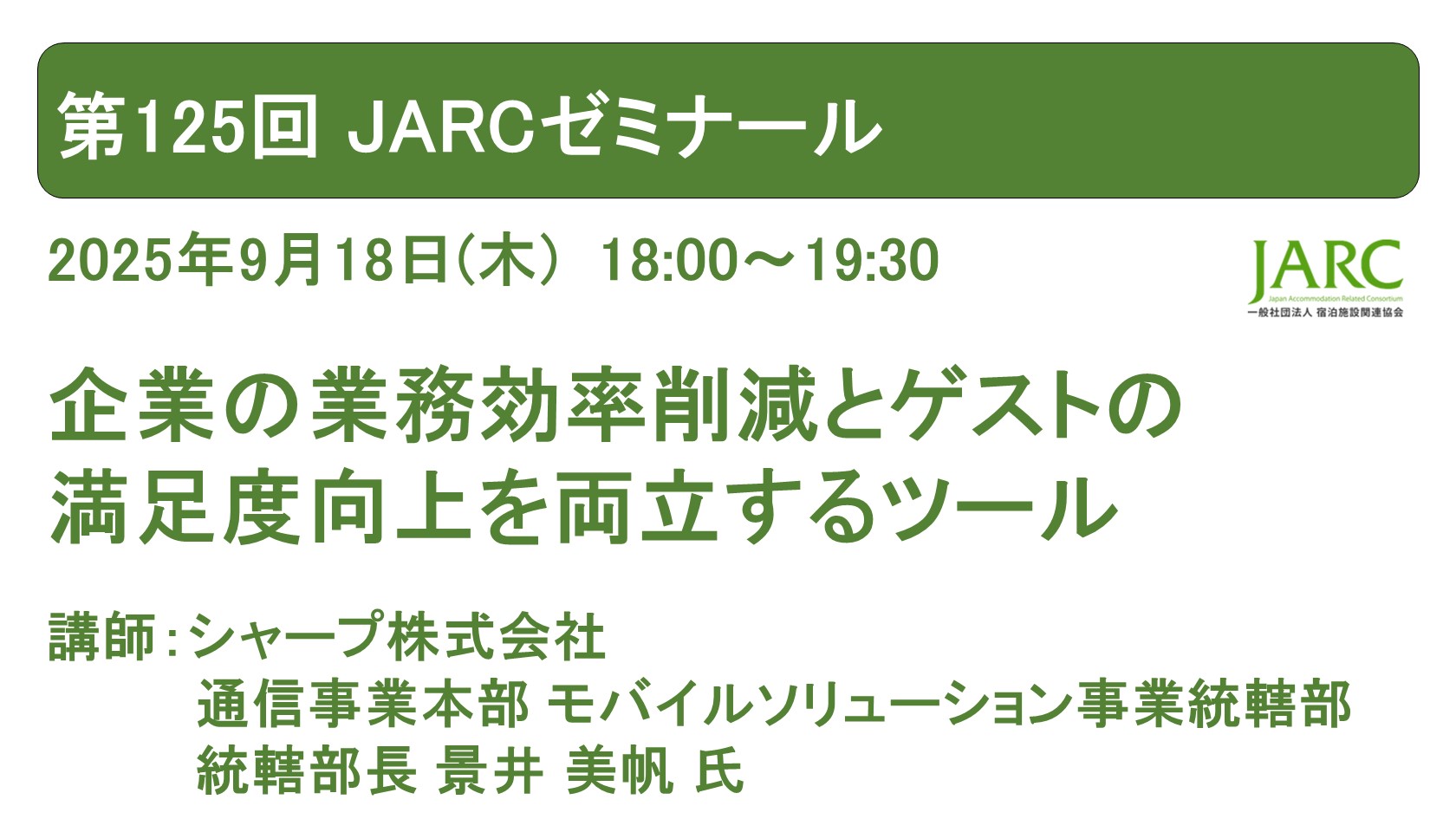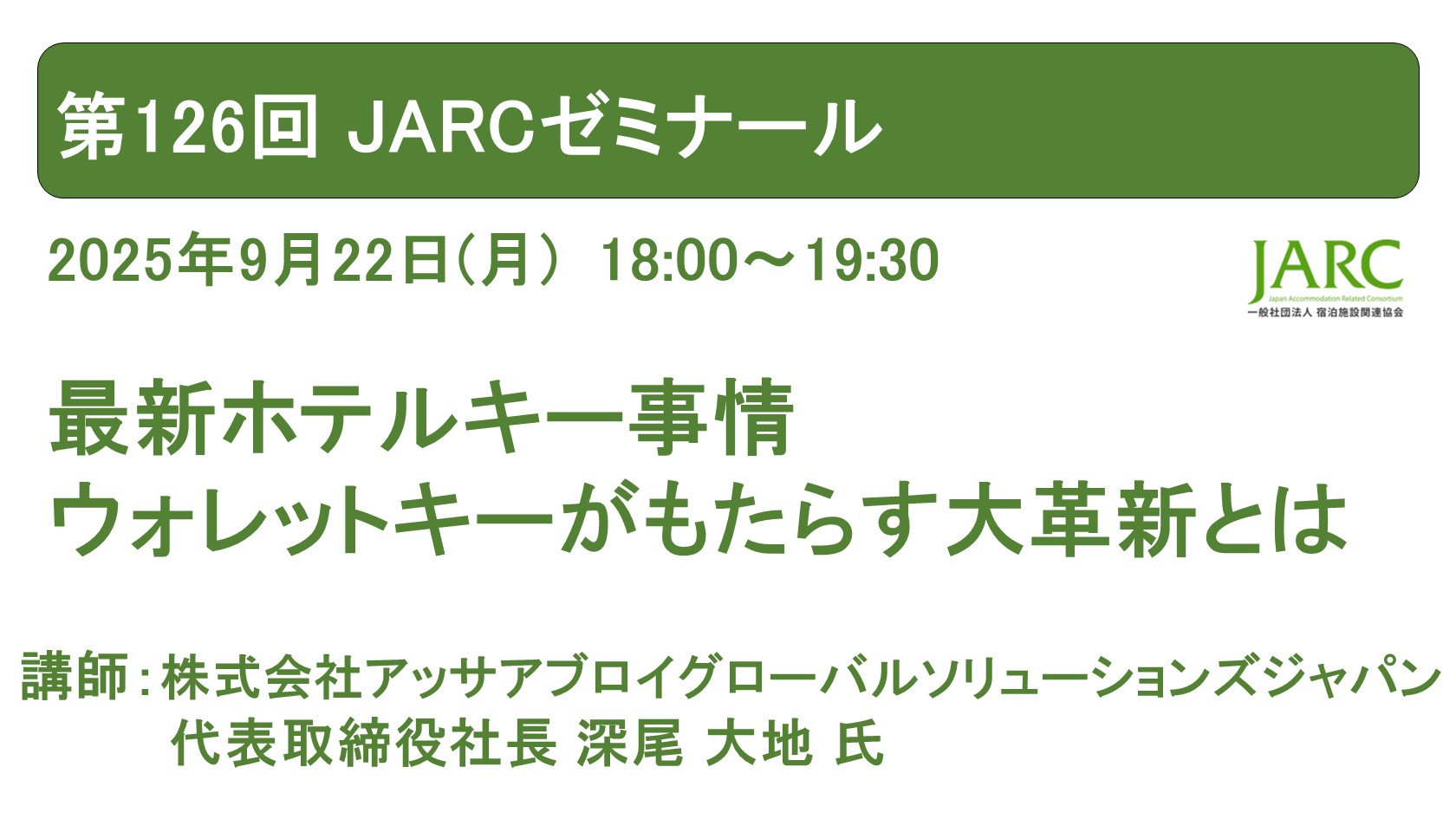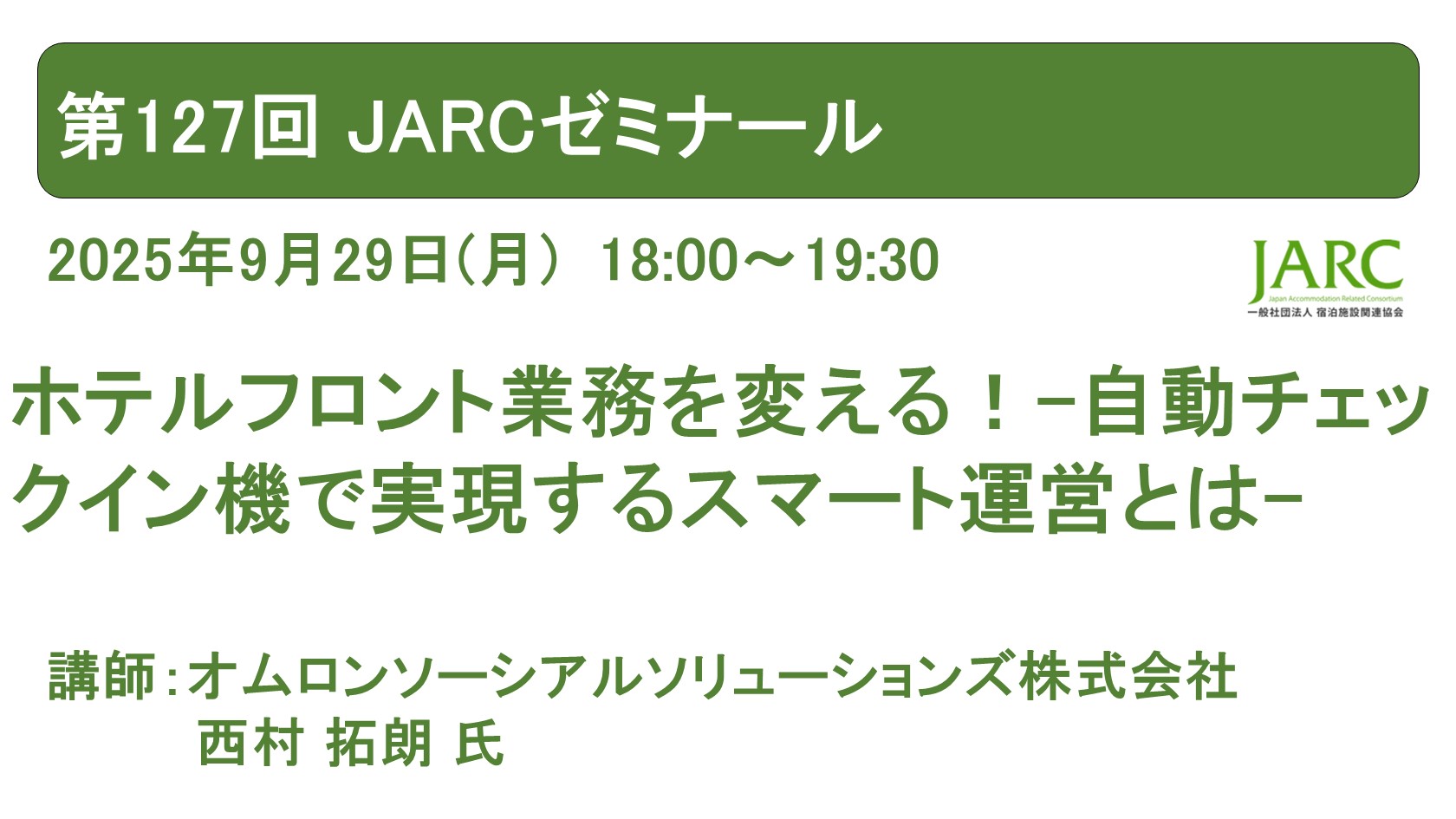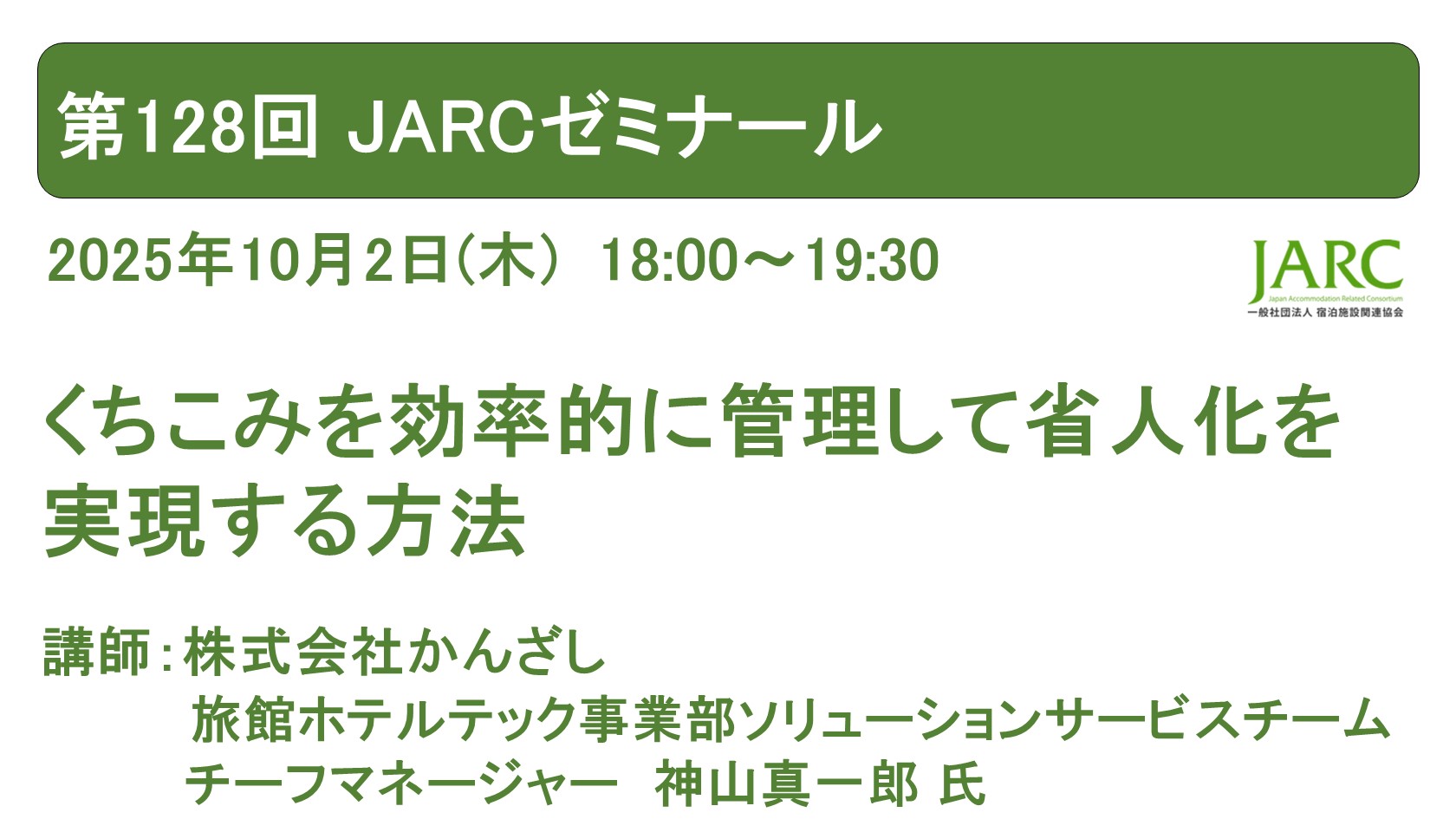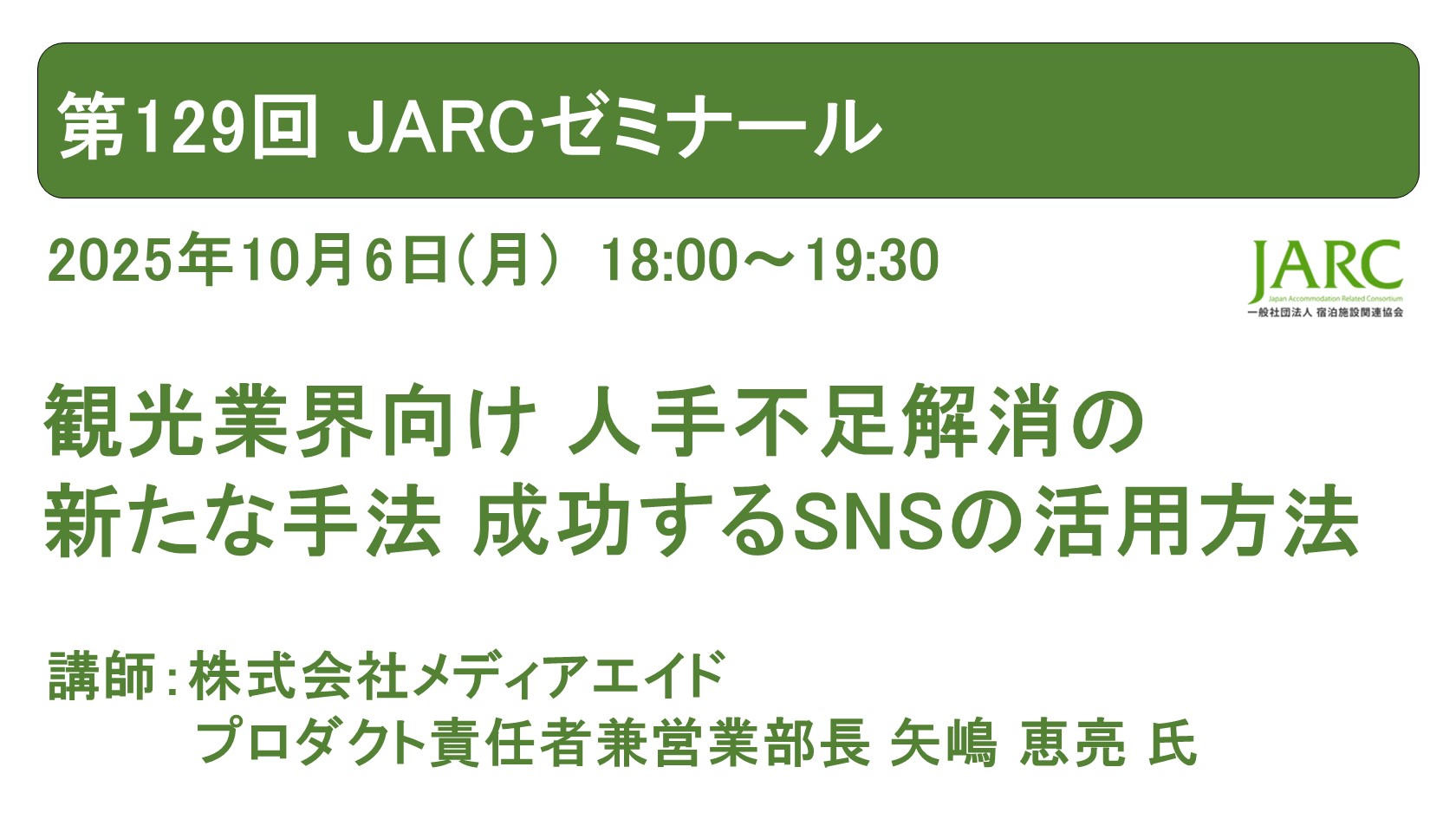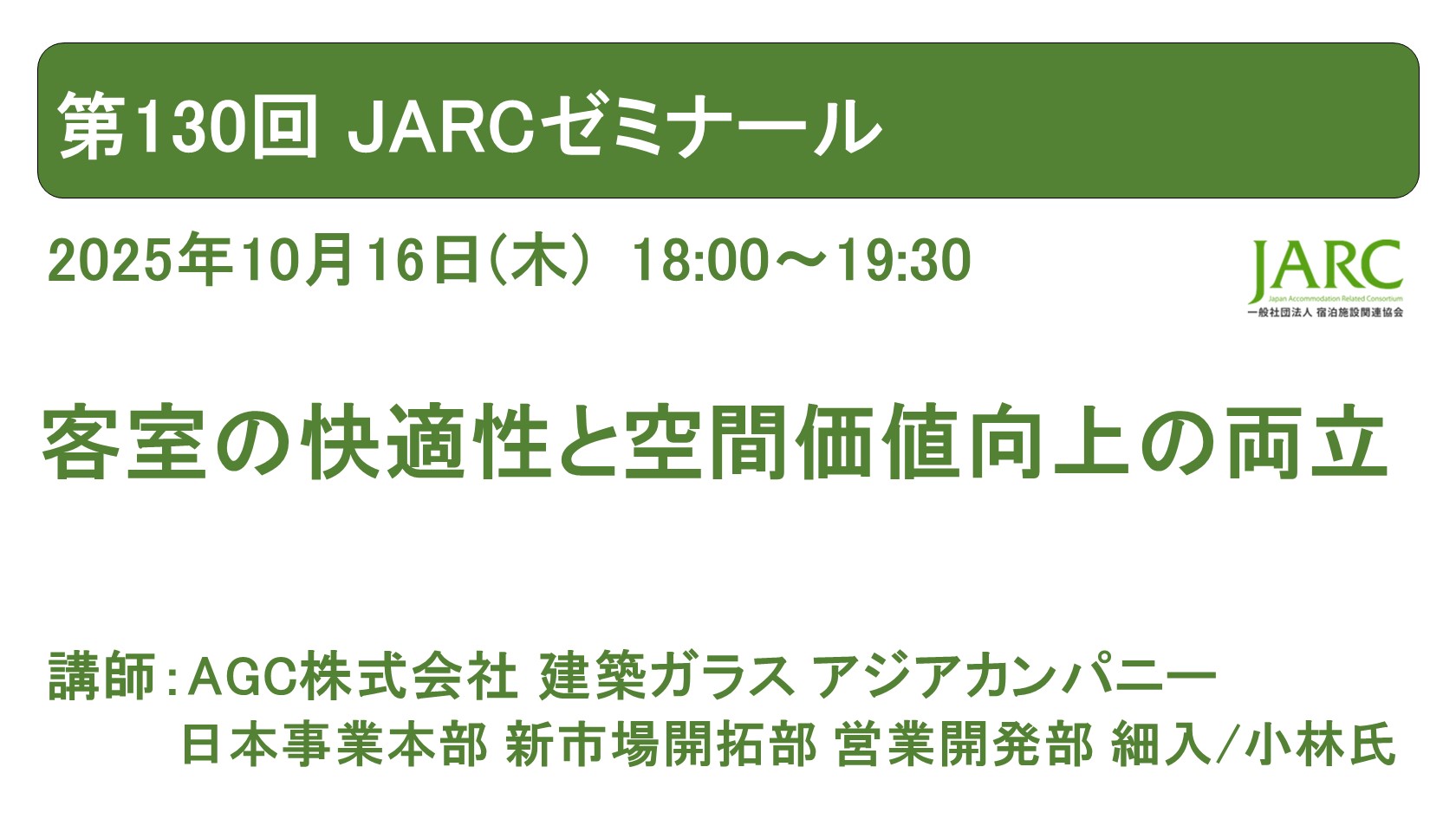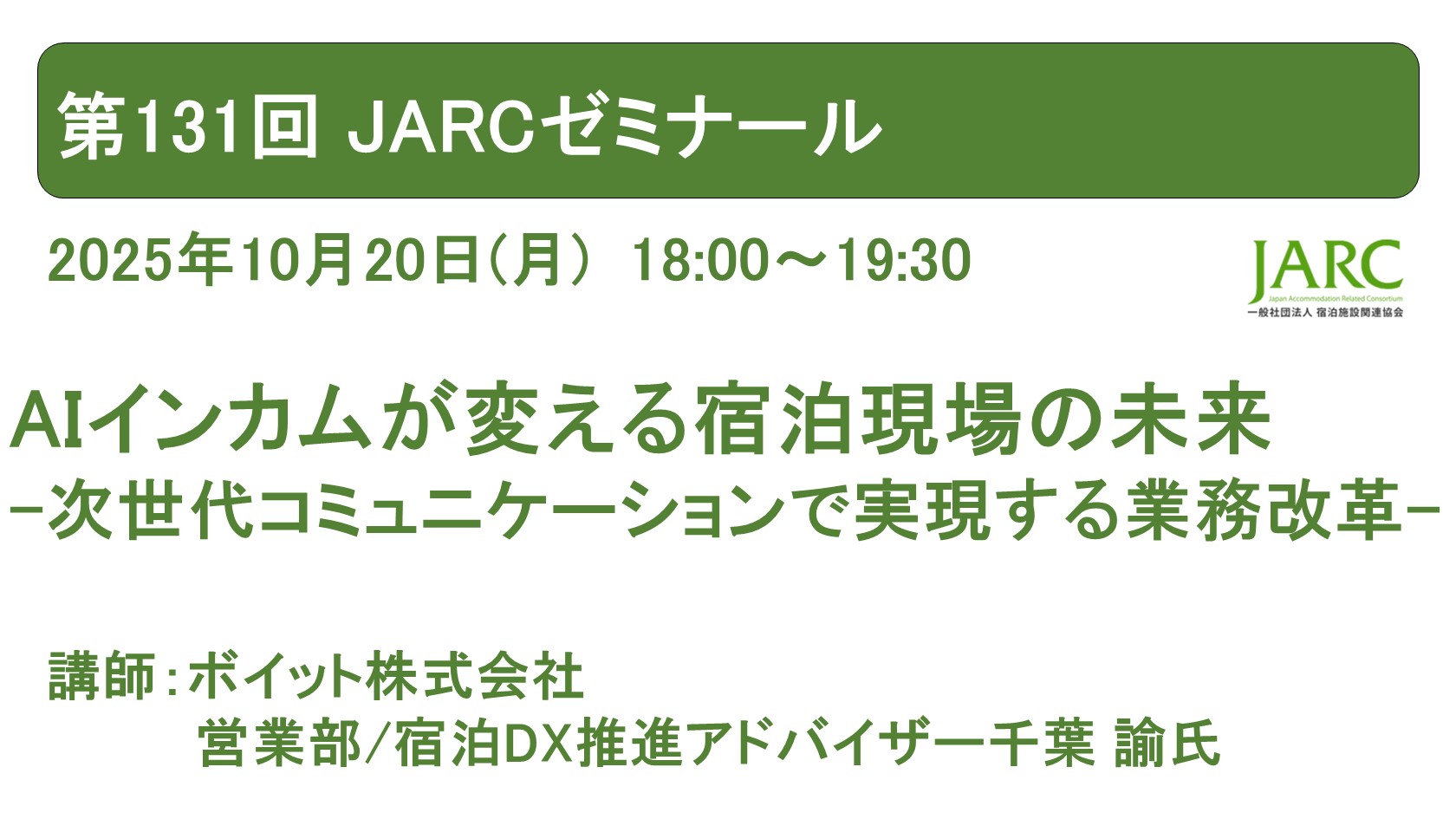学生が5つのグループに分かれ、講演を聴いた
観光を学ぶ22大学の学生でつくる日本学生観光連盟(代表=帝京大学経済学部観光経営学科3年・小幡沙織さん)は13日、東京都町田市の桜美林大学で国際観光の活性化を考える講演会やパネルディスカッションを開いた。メンバーの学生約100人が参加し、観光業界で活躍する5人を講師に、外国人旅行者の誘致、受け入れの課題などを考えた。
講師は、日本ホテル常務取締役(ホテルメトロポリタン総支配人)の塩島賢次氏、日本旅行業協会(JATA)訪日旅行業務グループの三浦雅文氏、フジドリームエアラインズ営業本部長の藤澤隆雄氏、オリエンタルランド営業二部営業三課長の今井啓祐氏、観光マーケティングや紀行作家として活躍する江藤誠晃氏。学生はグループに分かれて各氏の講演を聴いた。
ホテル業の視点からインバウンドの課題などを解説した塩島氏は、言語の障壁に触れ、「世界のホテルが競合相手。少なくとも英語は必要。日本やアジアの基準ではなく、グローバルな基準で話し、考える必要がある」と指摘。語学力が採用の必須要件かと質問した学生に対しては、「最も重視するのは人柄。ホスピタリティの精神が欠かせない。しかし、入社後に語学を含めて何を学ぶかが大事だ」と述べた。
JATAの三浦氏は、アジアでの誘致競争が激化しているMICE(国際会議など)や外国人教育旅行の動向などを解説。人口470万人のシンガポールが年間1100万人の外国人旅行者を受け入れているデータを挙げ、「インバウンドへの取り組みの差が表れている」と説明。学生からは「多民族国家ではない島国で観光大国となった例はあるのか」などの質問も出ていた。
パネルディスカッションでは、国際観光への学生の貢献などをテーマに意見交換。講師の江藤氏は「インバウンドを意識しながら海外に出て、いろいろな国を見てほしい。好きな国を見つけて架け橋になればいい」と学生たちに期待した。

学生が5つのグループに分かれ、講演を聴いた