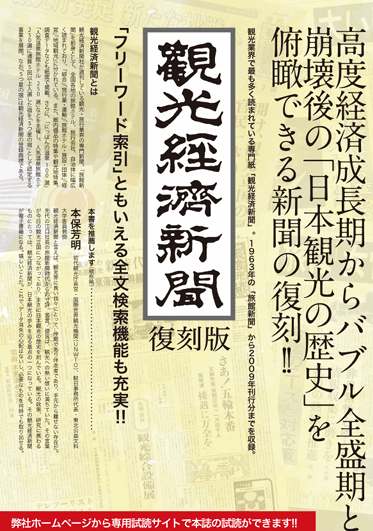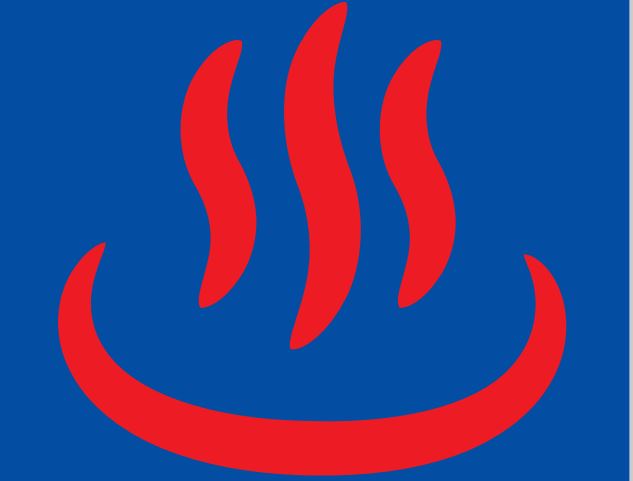無類のキャビア好きである。こう言うと、たいていの人が驚きで絶句するが、好きなものは仕方がない。好きなだけでは飽き足らず、フィンランドやラトヴィアへもキャビアを求めて旅をした。ラトヴィアのキャビアは、母体にストレスを与えないようにお腹を裂かずに、マッサージをして産卵させる方式をとるメゾンがあり、他より爽やかな甘みを含んでいて心地よい。
そして、なんといってもキャビアといえばロシア。約1年ごとに、1人でもロシアへ旅をして、キャビアを手に入れる。ヨーロッパに行く時も、できればロシア経由を選び、帰国時にはキャビアを手土産にするのが慣習だった。もともとロシアでは、漁村で脚気予防に、ビタミンAが豊富なキャビアをおかゆの上にのせて食べていた。それをトルコのツァーが気に入り、高額で大量に購入したことから高級品となったのだ。
数年前、ある女性誌から10万円で、どこでもよいので一つテーマのある旅をしてレポートしてほしいという依頼を受けた。10万円では当然キャビアとはいかず、それでもロシアが恋しく考えた。そこで思い出したのが、旅する先輩たちが声をそろえて話していた「ソ連時代の極東で食べたアイスのおいしさが忘れられない」という言葉。調べれば、S7でウラジオストックまでは2時間半余り。アイスクリームなら食費もかからないので、10万円でも十分足りる。かくして決行となった。
現地では、モスクワやサンクトペテルブルクと違って、冗談かと思うぐらい英語が通じない。これでは、良質なキャビアはもちろん、アイスクリームが探せないと思い、急きょ、自腹でガイドをお願いすることにした。やって来たのは大学生の男の子。一生懸命案内を務め、彼の機転で、遊園地で「絶品のアイスクリーム」に出会うことができた。おまけに、グルジア産の極上ワインも手に入れることに成功。それでも、本当にお薦めしたかったアイスクリーム店がつぶれていたことが気がかりだったのか、彼は「僕が一番だと思う景色を見せたい」と言う。興味をそそられ、地元のバスに1時間ほど揺られて到着したのは、彼が通う大学のキャンパス。その前に広大な公園が広がり、確かに雄大な景色と大学の近代的な建物との融合を楽しめた。「ここのアイスもおいしいですよ」と薦められたものは、残念ながら輸入のものだった。それでも、一介の外国人の珍妙な依頼に、自分のガイドの時間が超えても真摯(しんし)に応えてくれたことが、とてもうれしかった。
帰りは、もちろんたっぷりのキャビアと共に帰国。いつもより思い出が詰まった黒い宝石は格別の味がした。早く、あの味をもう一度と願うのは、私ばかりではないはずだ。