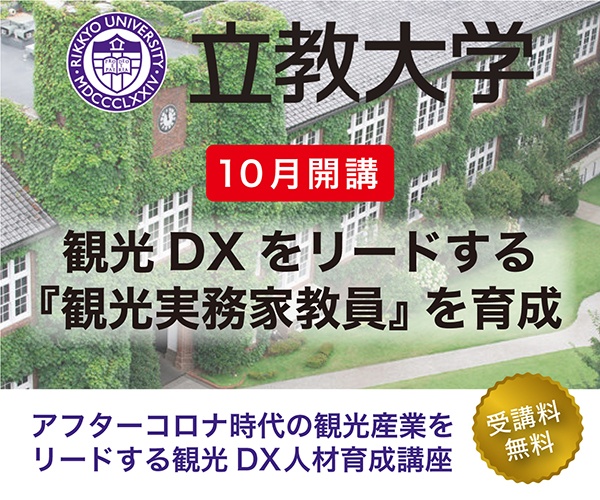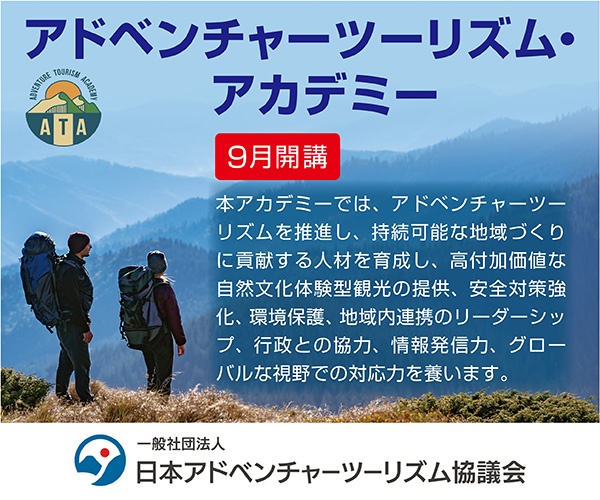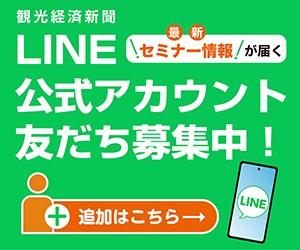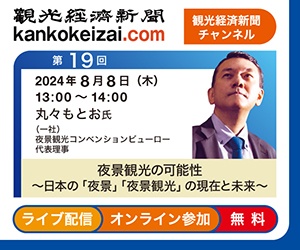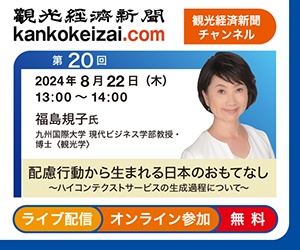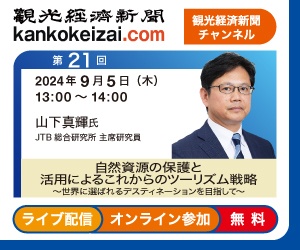青森県観光連盟 専務理事 九戸眞樹氏
転機むかえる青森観光
新幹線開業、DC開催を 全県挙げて生かす態勢に
──青森県は1998年の「文化観光立県宣言」など、早くから観光に取り組んできた印象がある。
「当県の産業構造は、電器産業などのトップ企業などもないため、県全体が観光を大きな産業の1つと捉えてきた。これまでは、自然、歴史など、あるものを見に行く観光がメーンで、その上『十和田湖・奥入瀬渓流』や『ねぶた祭り』などの知名度に頼った観光だった。しかし祭りも自然も、日並びや天候の影響を大きく受けるため、そういったあやふやな要素に頼らない仕掛けづくりに長く取り組んできた」
「また現在、旅行形態が個人で楽しむ旅行へと変わっており、変化への対応策や当県の新しい観光の切り口も模索してきた。その結果が文化観光立県宣言であり、今回の東北新幹線全線開業、デスティネーションキャンペーン(DC)への取り組みだ。当県は『情報発信が弱い、下手だ』とずっと言われてきたが、現在、青森の露出度は高く、さらにこれまで発信してきたものに加えて新しい情報も数多く紹介できている」
──新幹線全線開業、DCに向けた取り組みは。
「県外向けの情報発信として1月、東京・表参道でねぶたの展示、運行などを行ったPRキャンペーン『とことん青森』を行った。食や観光物産のPRに加え、アート活動や本県の自然、文化、歴史を学ぶ講座を実施するなど、幅広く、期間の長い形での青森の見せ方に実験的に取り組み、強い手ごたえを感じた。今年もさらに磨きをかけた形で実施する」
「県内では県民に『身近な宝に気付いてください。新幹線が来たらその宝をどのように見せますか』ということを意識してもらうマインドアップキャンペーンを昨年半年間、テレビや新聞、地域FMなどマスコミと連携して自由な形で放送、掲載してもらった。毎月、毎週、『結集!!青森力』『東北新幹線全線開業』という言葉に触れるようになって、県民にも『いよいよだな』との気持ちが出てきた」
「今年5月からは、おもてなしキャンペーンを展開して、観光客をどうもてなすかをマスコミと連携して啓蒙している。『新幹線を見たら手を振りましょう』などのCMを作っているテレビ局もある(笑い)。各社の企画に頻繁に触れることで、県民のもてなしへの意識が醸成されるはずだ。青森県民は非常にシャイで自慢下手なので、県民自身が隣の町などを歩いて青森の良さを実体験することもすすめている。実体験することで、観光客の人に尋ねられたときにも自分の言葉でおすすめを語れる。県民1人ひとりに新幹線開業、DCを自分のものとして捉えてもらうことが重要だ」
──青森の『人』のよさ、個性も魅力的だ。
「DCの『宝』の1つが人だ。人のよさを感じてもらうためには、来てもらうしかない。まず『行ってみたい』、そして『また行きたい、会いたい』と思わせる仕掛け作りをしていかなければならない。ボランティアガイドについては、ガイドの案内したいものと観光客のニーズのミスマッチも起こっている。観光客の求めるガイド内容、時間などをくみ取りマッチングするコンダクターの存在も必要になってくるだろう。ただ、人のよさは商品にして感じてもらうものではないので、注意が必要だ」
──2次交通の充実策は。
「主要観光地を回るだけの点と点を結ぶだけではなく、全県を面的に楽しんでもらうためにも重要なことだ。青森市内では『観光ガイドタクシー』の認定も行っている。また開業後には2次交通の手段と周遊ルートなどをまとめたリーフレットを作り、来県者に活用してもらえるようにする。もちろん2次交通を生かせるような、観光客が立ち寄れる見どころの整備も必要だ。たとえば青森市の場合、ねぶたの時期以外は県内のほかの観光地への起点になるだけだったが、まずは観光連盟が入っているビル『アスパム』を土産購入だけでなく、郷土料理教室や工芸体験ができる観光拠点として整備したい」
──オフシーズンの冬季に東北新幹線が全線開業することについてはどうか。
「従来型観光で誘客をけん引してきた大型イベントや祭りはないが、青森の冬だからこそ魅力を増す、温泉と食がある。さらに知事のトップセールスや地道な売り込みにより、開業から断続的に1千人規模の大型コンベンションが開催される。学会や各種大会も毎月1、2回開催される予定だ。国際会議などは配偶者同伴で参加するのが当たり前なので、波及効果は大きい。コンベンション誘致は継続的に力を入れていく」
「新幹線開業、DC開催は青森観光の転機だ。仕掛け方の1つとしては、映画『おくりびと』での山形のように映像と一体となった情報発信も新しい観光の芽のつくり方ととらえている。青森を舞台とした小説『津軽百年食堂』『青森ドロップキッカーズ』では、小説執筆の段階から、読者が青森を体感できるような濃い情報を提供した。一般の人が行ってみたいと感じるきっかけをどう作っていくかが、新しい、これからの誘客の在り方だろう」
「観光は決して観光関係事業者だけのものではなく、非常に多面的なものだ。5年間程度の長いスパンで、通年観光を楽しめる態勢づくりを進め、開業効果をより広く長く波及できるよう取り組んでいく」
【くのへ・まき】