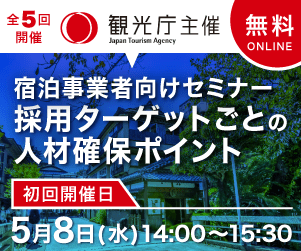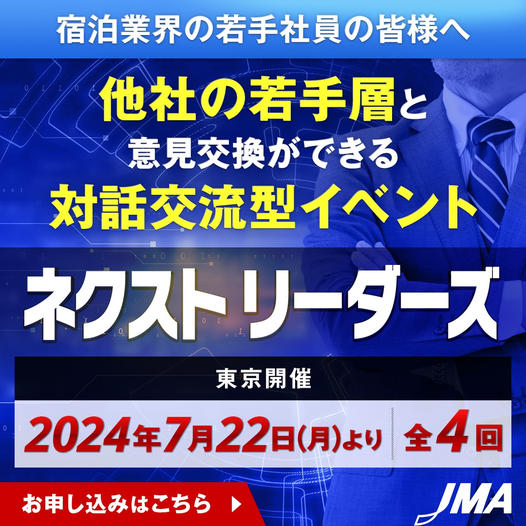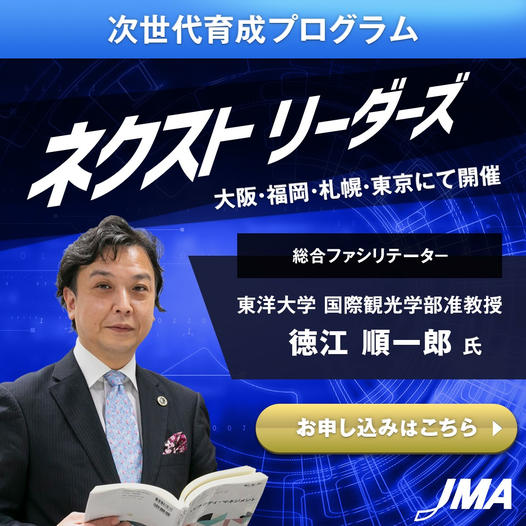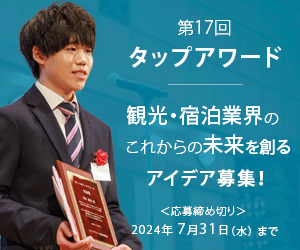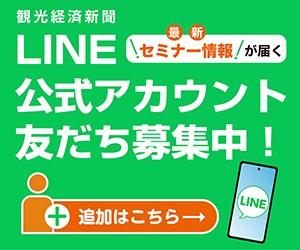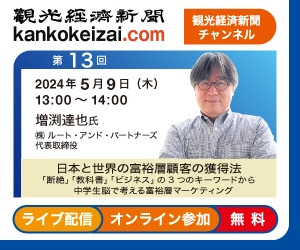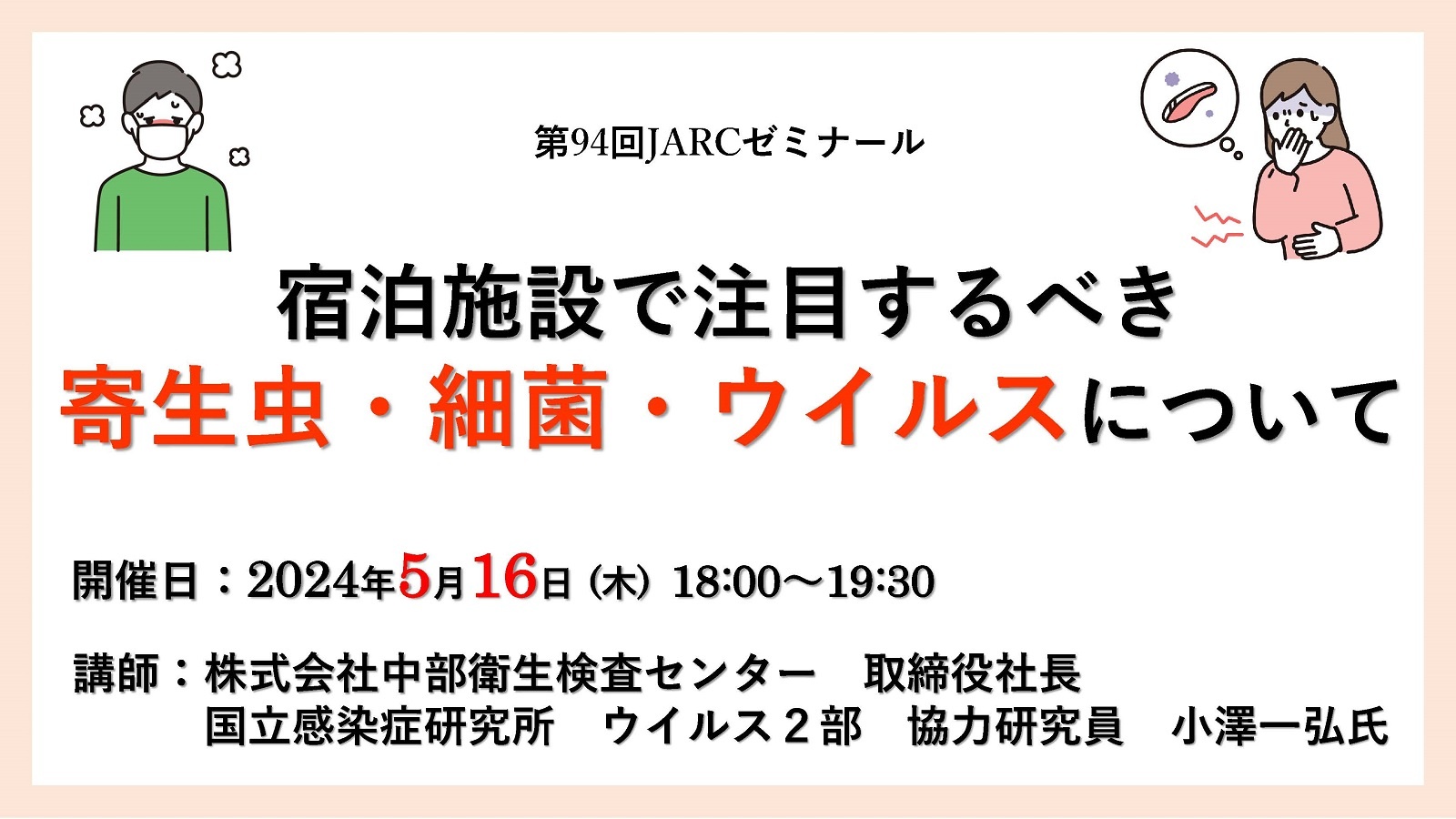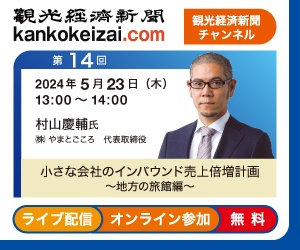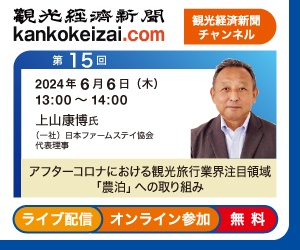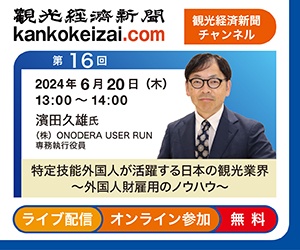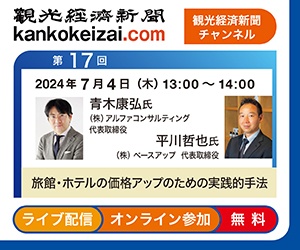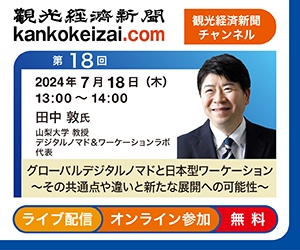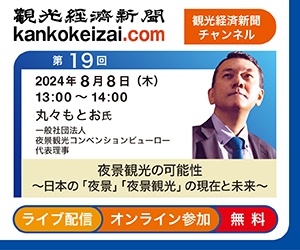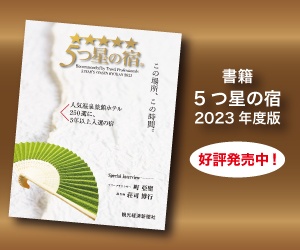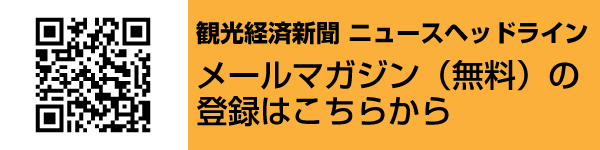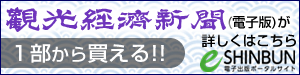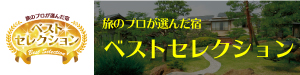9月8日に英国のエリザベス女王が亡くなった(享年96歳)。女王は1952年に25歳の若さで即位し、53年6月2日にウェストミンスター寺院で盛大な戴冠式が行われた。私は当時7歳であったが、なぜか戴冠式のことを鮮明に記憶している。
その理由はテレビで戴冠式の模様が放送されたからだ。日本ではNHKが53年2月1日からテレビ放送を開始しており、父親が頑張って7インチのテレビを購入してくれたので、私はテレビっ子になっていて、訳が分からないままに戴冠式のニュースを熱心に見た記憶がある。
女王は英国史上最長の70年7カ月にわたって在位し、「英国の母」として国民の敬愛を集めた。そのため、9月19日に各国の要人が多数参列してウェストミンスター寺院で国葬が行われた。天皇、皇后両陛下やバイデン米大統領、独仏の大統領はじめ、世界各国の要人が参列したので、史上最大規模の警察官1万人以上が警備に当たった。
一方、日本でも9月27日に安倍晋三元首相の国葬が日本武道館で営まれる予定である(この原稿は26日に執筆)。国民の敬愛を集めたエリザベス女王の国葬とは異なり、安倍元首相の国葬に対しては各種世論調査で半数以上が国葬実施反対を表明していて、いわば国論を二分する形での実施になる。
その上に世界各国からの要人の参列についても、G7(先進7カ国)首脳で唯一来日予定であったカナダのトルドー首相がハリケーン被害対応を理由にして国葬参列を取り止めている。世界各国の要人の参列状況を比較する限り、寂しい国葬になりそうである。
日英両国の国葬実施を比較すると類似する点もある。英国の国葬は65年のチャーチル元首相以来、57年ぶりであり、日本の国葬は67年の吉田元首相以来、55年ぶりだ。
英国ではチャーチル国葬の頃にはすでに「英国病(British Disease)」と称される長期停滞症状(社会保障負担の増加、国民の勤労意欲の低下、労使紛争激化、国際競争力の低下、経済成長不振など)が生じていた。その後、鉄の宰相サッチャーによる新自由主義改革、トニー・ブレアー首相による「新しい労働党・第三の道」改革などを経て、英国病の克服が図られてきた。
一方、日本では吉田茂国葬以後に工業立国・貿易立国を基軸に高度経済成長の実現が図られ大成功を収めた。90年代初頭のバブル経済崩壊後において規制緩和中心の構造改革、財政出動と金融緩和の発動などが実施されてきたが、この30年間に日本のGDPも給与水準もほとんど変化していない。
コロナ禍以前においてすでに世界の識者は、日本の30年に及ぶ長期停滞・衰退状況を「日本病(Japan Disease)」と診断していたが、日本の各界のリーダーたちは病的症状の治療を行ってこなかった。このたびの日英国葬に際して、改めて「日本病」のことを深刻に心配している。
観光業界も日本病を視野に入れながら、観光振興の方策を考える必要がある。
(北海道大学観光学高等研究センター特別招聘教授)