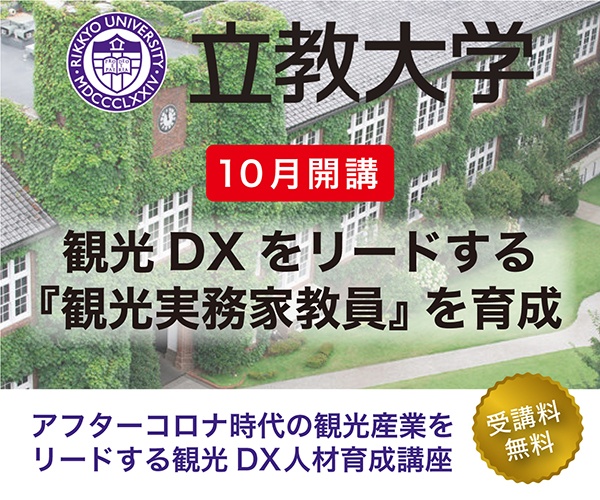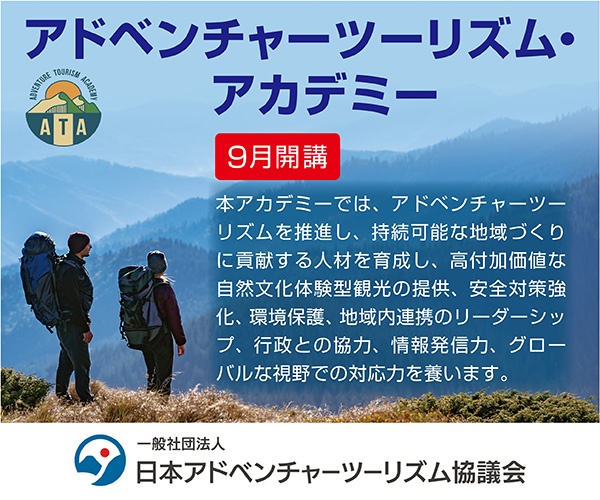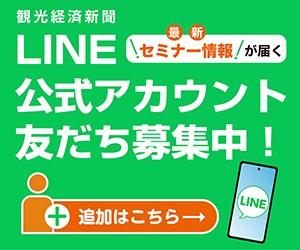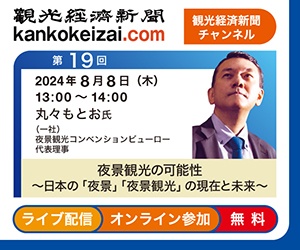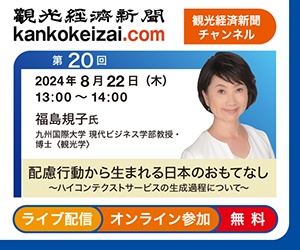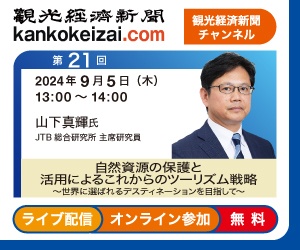ポストコロナを見据えて「地域創生」が大きなキーワードになっている。大学教育の現場では地域創生を学びの本流にする動きがあり、地域の担い手づくりは過熱する一方だ。
そこで注視したいのが、2009年から総務省が推進する地域おこし協力隊の制度である。今では千を超える自治体で、約5500人の隊員が活躍するほどに成長した。政府は、24年に隊員数を8千人に増やす目標を掲げている。
先日、世界文化遺産・石見銀山で知られる島根・大田市へ、隊員として活躍する金田郁也氏を訪ねた。新卒採用された大手旅行会社を4年で退職して大学院に進み、縁もゆかりもなかった大田の地に志をもって移住した若者である。
当地は、世界遺産登録の07年以降、観光客が急増して平穏な暮らしが徐々に脅かされるようになった。その反省から同年、「石見銀山大森町住民憲章」を定め、穏やかさとにぎわいの両立を目指すようかじを切った。世界遺産に登録済みの先行地を町民らで視察して、商業観光にまみれることなく地域資源の保全や活用、地域振興を進めている。そうした点に共鳴したと金田氏は語る。
日本では観光と訳されるツーリズムは、そもそもはラテン語で、陶芸に使われる「ろくろ」を意味する。観光バスやレンタカーは離れた場所で降車して、間歩(まぶ)といわれる坑道や重伝建のまちなみを徒歩でぐるぐる回る石見銀山の手法は、まさにツーリズムそのものだ。さまざまな場所で町民たちが立ち止まり、金田氏に笑顔で声をかけてくる。よそ者を大切にしているのがうかがえた。
ちなみに、ポストコロナにおいて欧州各国の政府観光局は、その成果を人数や泊数だけで追わないことを相次いで発表している。日本も量から質への転換が急がれる。
さて、域外で同じように隊員として頑張る人たちとネットワークを築きたいと、金田氏から相談が寄せられた。そこで、知己の服部真理氏に同行してもらうことにした。彼女は東日本大震災の被災地・山田町で復興支援員として14年から従事して、手がけた事業「マリン・ツーリズム山田」が第15回JTB交流創造賞の組織・団体部門で最優秀賞を受賞するなど地域おこしのプロである。山田町での任期満了後は、地域おこし協力隊として隣町の大槌町に移住した。よそ者がその土地に根をはるのは、並大抵のことではない。蓄積したノウハウを、共有しあう体制が整うことを期待したい。
地域おこし協力隊の入隊条件には住民票を移して生活の本拠にすることが求められ、任期はおおむね1年から3年。その後は定住促進のため自治体側も配慮することなどが定められている。総務省の発表では、近隣市町村を含むエリア定住率が6割を超え、一定の成果がみられる。しかも隊員の活動経費や報償費の上限額が引き上げられ、待遇も多少改善された。とはいえ有能な人材をつなぎとめるには、なおも整備が必要であろう。さらに、独立してからの事業成功率を高めるためには産業界との積極的な関わりが欠かせない。
観光ビジネスは、地域社会と産業経済との車の両輪で展開される。駆動輪に引っ張られるだけの時代は去り、全輪で推進するのがポストコロナのツーリズムといえる。
千葉千枝子(ちば・ちえこ)
淑徳大学経営学部観光経営学科学部長・教授。銀行勤務を経てJTBに入社。1996年有限会社千葉千枝子事務所を設立、運輸・観光全般に関する執筆・講演、TV・ラジオ出演などジャーナリスト活動に従事。近著に「レジャー・リゾートビジネスの基礎知識と将来展望」(第一法規)。