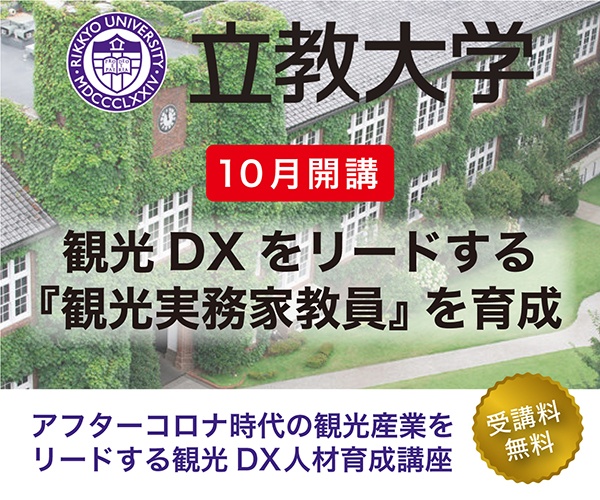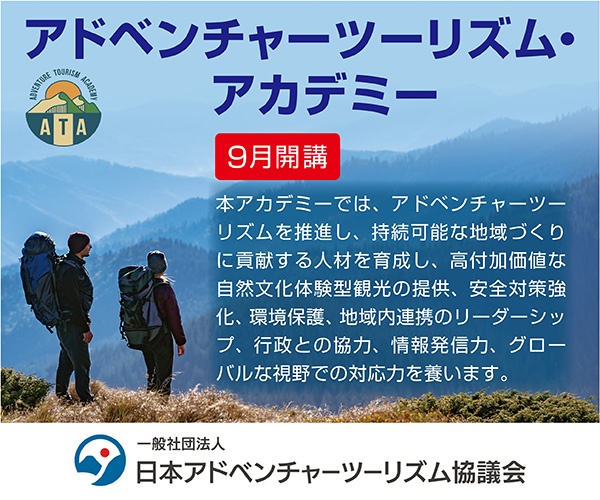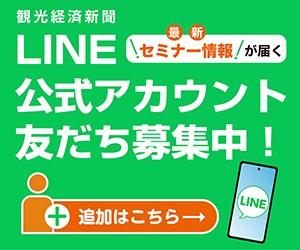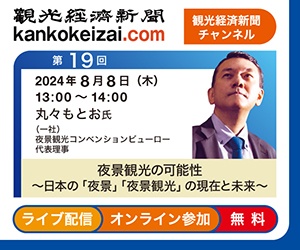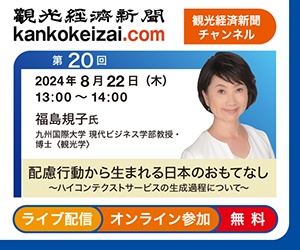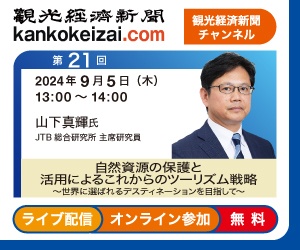竹内氏
本稿を執筆している今、2月1週目。実は、何かと忙しい。今年は3日が節分、4日が立春で5日は初午(はつうま)と、3連チャンで行事が続く。一体何が忙しいのか?…って、食べ物の調達だ。
節分には恵方巻。筆者が役員を務めるお弁当製造販売会社は毎年約千本巻いており、神田明神御祈願の福豆付きなのも有難い。
続く立春には、「立春大吉豆腐」を食べなくちゃ! 古来、白いお豆腐には邪気を祓(はら)う霊力が宿るとされる。白ければ良いというのなら、はんぺんでもバニラアイスでも良さそうなものだが、そうじゃない。お豆腐の原材料、豆は「魔滅(まめ)」とも書くそうで、節分に豆を撒(ま)くことからも分かる通り、古くから鬼や疫病神、邪気などを追い払うとされてきた。豆から作られた食べ物だからこそ、ご利益があるらしい。そして、白くなきゃいけないので、おしょうゆをかけるのはNG!
ちなみに、節分に罪穢(つみけが)れを祓うためにお豆腐を食し、翌日の立春に、清められた体に幸福を呼び込むため、改めてお豆腐を食す風習を持つ地域もあるようだ。
お豆腐の調達は簡単なのだが…。他に、立春にいただく縁起物「立春大福」や、節分の夜からもろみを搾って立春の朝一番に搾りあがった生原酒「立春朝搾り」も、立春の朝に出来たてのモノでないといけないとされる。それを考えると、お豆腐もやっぱり当日にできた商品の方が、パワーがありそう。スーパーに並んでいるお豆腐は、消費期限はあるが、大抵製造日の記載はないのが残念。
…というワケで、今年は験担(げんかつ)ぎにウルサイ真ん中の妹が、近所のお豆腐屋さんに買いに走ってくれた。お豆腐屋さんも心得ていて、「コレで召し上がってください」と藻塩の小袋を下さった。それを振りかけて食した作りたてのお豆腐のおいしさと言ったら! 幸福だけじゃなく口福まで呼び込めて、超満足♪
翌5日の初午とは、節分後最初の午の日で、711(和銅4)年、農業の神、宇迦之御魂神(うかのみたま)が稲荷山に降り立ったという故事が由来だそう。この日は、その稲荷山の麓にあり、全国約3万社ある稲荷神社の総本宮、京都の「伏見稲荷大社」をはじめ、全国各地の稲荷神社で「初午祭」が行われる。
「稲荷」とは「稲生り」「稲成り」を表す田の神様。昔、田の神は、稲刈りが終わると山に上り山の神となり、春になると戻って田の神になると考えられていた。狐(きつね)も同様に、春になると鼠(ねずみ)を食べに山から下りて来て秋には山に帰るので、田の神の使いだと考えられるようになったそうだ。
かつては殺生(せっしょう)がタブーだったため、狐の好物鼠の代わりに油揚げを供えるようになり、いつしか稲荷神の恵である米を中に詰めるようになった。これが稲荷ずしの始まりだとか。初午の縁起物「初午いなり」は、最近コンビニでも売っている。弊社も稲荷ずしに注力してきただけに、恵方巻の再来になってくれ~!と願うばかり。次号は他の験担ぎの食べ物について。こうご期待♪
※宿泊料飲施設ジャーナリスト。数多くの取材経験を生かし、旅館・ホテル、レストランのプロデュースやメニュー開発、ホスピタリティ研修なども手掛ける。