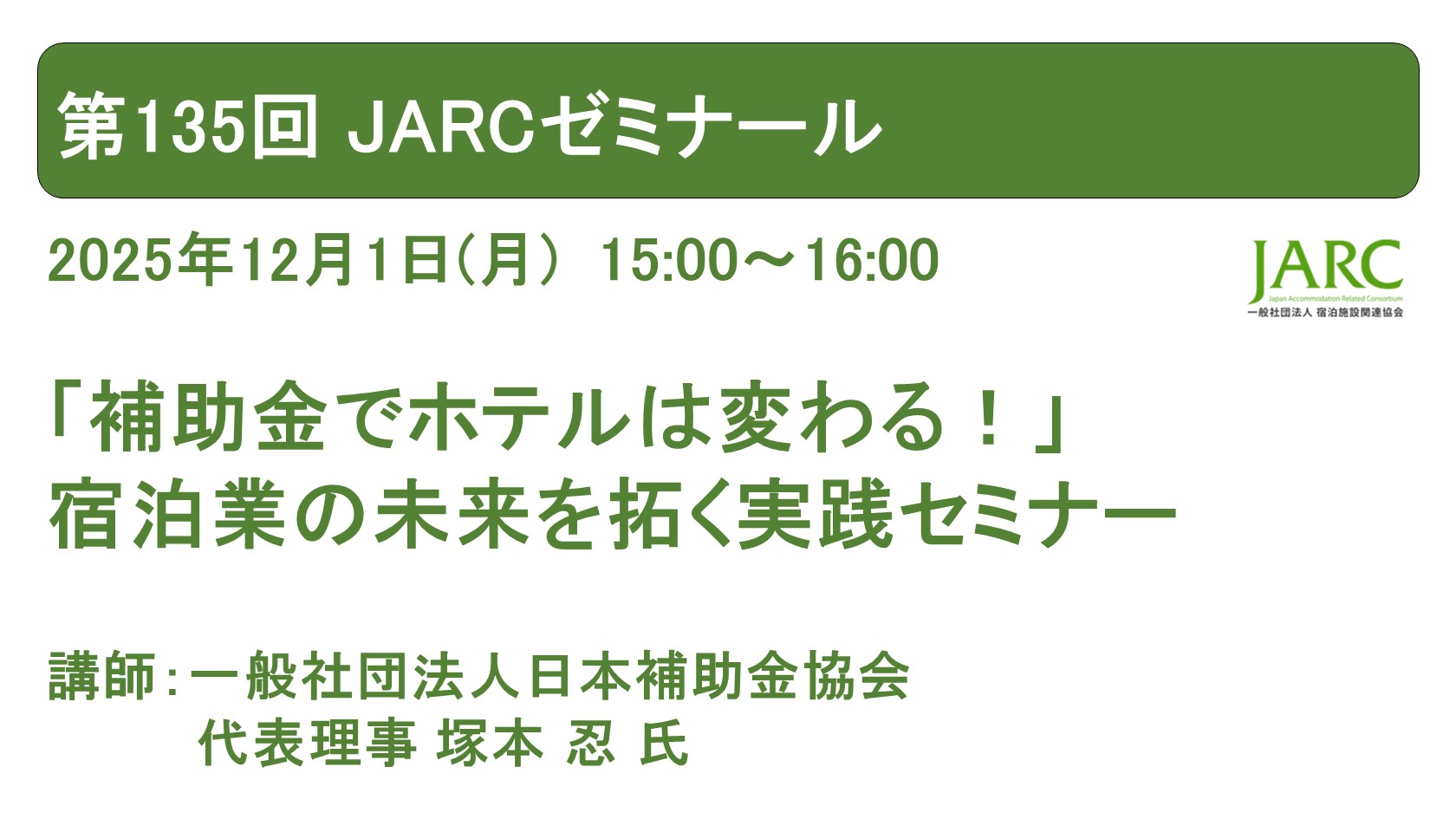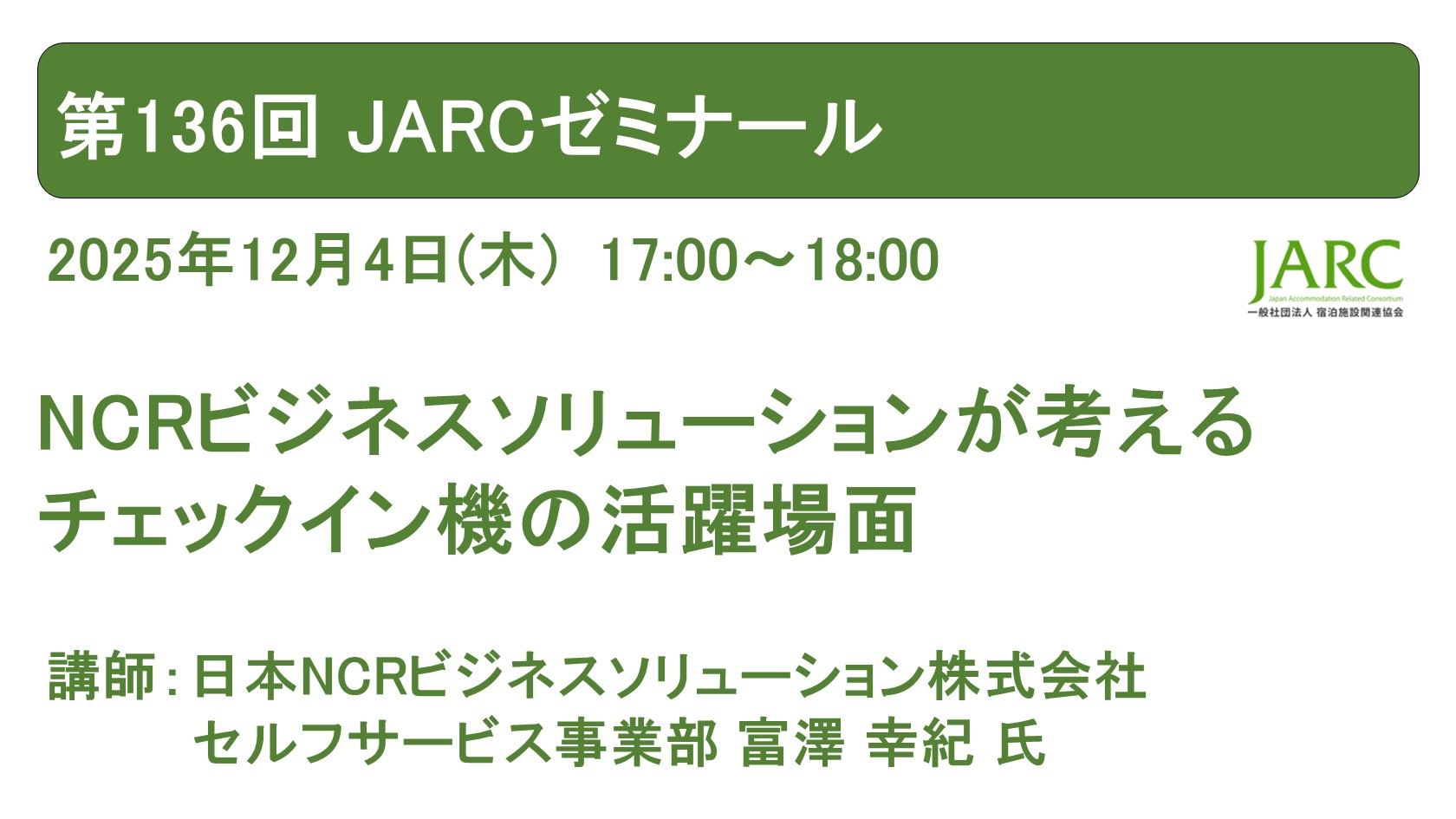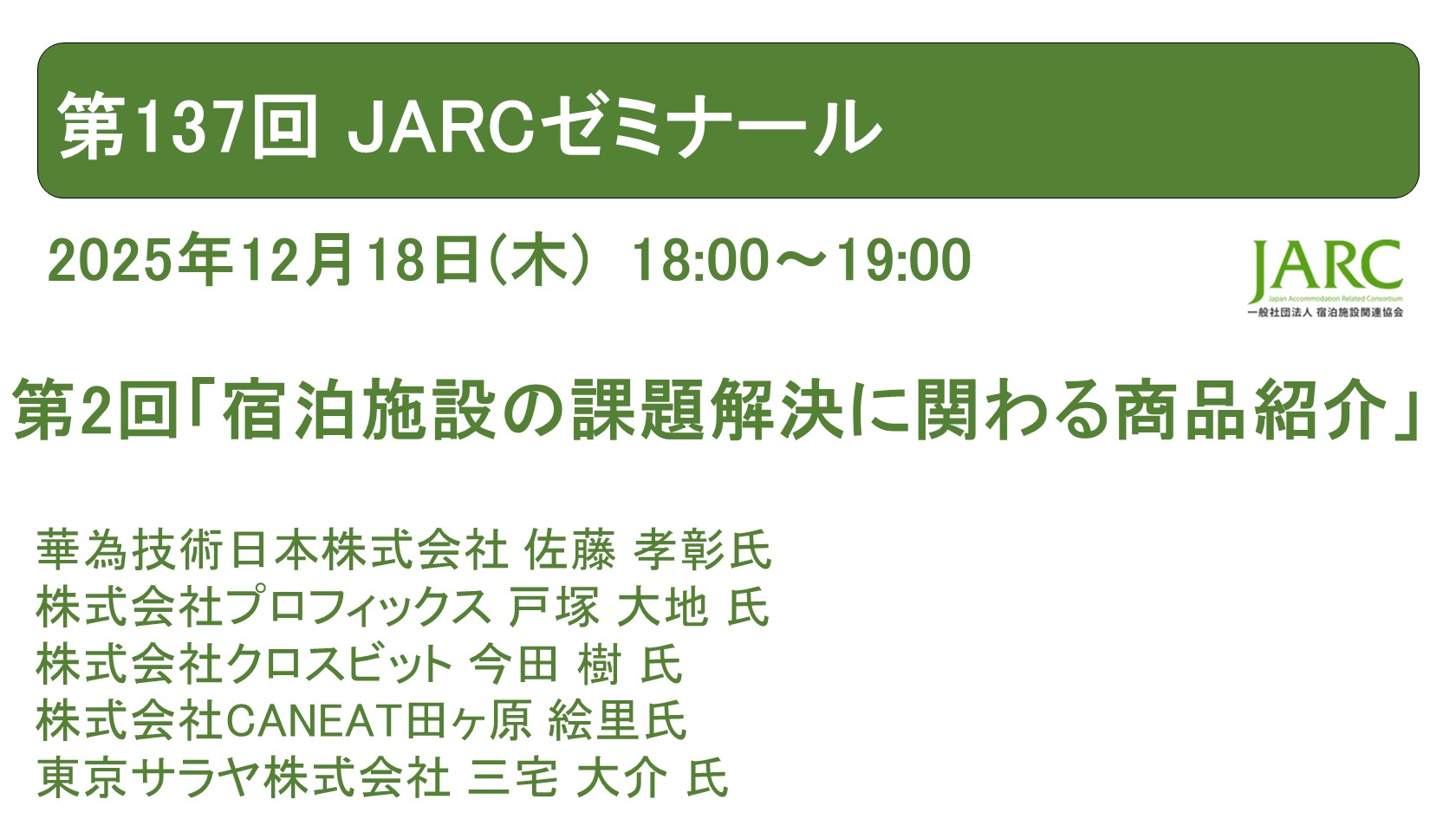トークセッション(左)ヤマザキ・マリ氏、(右)長野恭紘別府市長
温泉の多様な魅力を多角的に検証し、その新たな可能性を国内外に発信するシンポジウム「別府ONSENアカデミア2025」(主催:別府ONSENアカデミア実行委員会、委員長:長野恭紘別府市長)が、2025年11月16日、大分県別府市のビーコンプラザで開催された。
2016年に始まり、コロナ禍による2年間の中止を経て、今回で8回目の開催となる。当日は、温泉に関する最新の研究発表や、漫画家のヤマザキ・マリ氏による講演などが行われ、温泉資源の保存と活用に向けた知見が共有された。
温泉研究の蓄積と観光戦略への連携誓う
開会にあたり、実行委員長である長野恭紘別府市長が挨拶に立った。長野市長は「別府ONSENアカデミアは今回で8回目を迎える。単独の市で温泉を深掘りし、その効能効果を研究、見える化し、蓄積した知見をクロスさせることで新しい発見を重ねてきた」と、これまでの歩みを振り返った。
また、日本古来の温泉文化の重要性に触れ、「現在、日本の温泉文化をユネスコ無形文化遺産に登録すべく取り組みが進んでいる。おんせん都市として、このアカデミアで得られた知見を、いかに観光戦略へ結びつけるかも重要であると考えている」と述べ、研究成果の具体的な活用に意欲を示した。
最後に長野市長は、「本日は温泉に対する知識を深めていただき、我々が掲げる『新湯治・ウエルネス』の未来を想像していただければ嬉しい」と述べ、参加者への期待を寄せて挨拶を締めくくった。
今回のシンポジウムでは、温泉の様々な側面に関する7つの研究発表が行われた。本稿では、その中から特に、飲泉文化、あつ湯の効用、足湯によるストレス軽減、そして温泉と腸内環境に関する研究に焦点を当てて報告する。

『新湯治・ウエルネス』構想を語る長野別府市長
研究発表1:飲泉文化の可能性を探る
研究発表では、まず(一社)温泉水振興協会代表理事で飲泉セラピストの名倉由桂氏が「飲泉でととのう別府温泉リトリート」をテーマに登壇した。
名倉氏は、ヨーロッパではエビアンのように無料の飲泉場が整備されている例を挙げ、「捨てている温泉を飲めるようにすることで、飲泉を通じた新しい温泉の価値を知ることができる」と提言した。
ヨーロッパの温泉保養地(ユネスコ世界遺産)の共通点として、長期滞在の仕組みが充実している点を指摘。「ヨーロッパの温泉保養地と別府は似ており、まだまだ可能性を秘めている」とし、飲泉の普及が新たな滞在型観光につながる可能性を示唆した。また、「入浴と飲泉とでは効能が少し異なることも多い」と述べ、飲泉独自の健康効果にも着目すべきであるとした。

欧州を事例に飲泉文化の可能性を語る名倉由桂氏
研究発表2:「あつ湯」のメカニズムと新たな効用
独立行政法人国立病院機構西別府病院スポーツ医学センター長の松田貴雄氏は、「なぜあつ湯が廃れないのか」というユニークなテーマで発表した。
通常、リラックス効果(副交感神経の活性化)はぬるめの湯で得られるとされるが、松田氏はあえて「あつ湯」の意義を検証した。 松田氏によると、あつ湯に浸かることは交感神経を刺激する行為であるが、人間の体には交感神経が活性化すると必ず副交感神経も働く仕組みがあるという。あつ湯は交感神経を刺激する「身体活動」であり、「おんせんはスポーツである」と松田氏は定義する。あつ湯に浸かることで、意図的に交感神経を刺激し、その後の副交感神経の働き(リラックス)を引き出すことができる可能性を指摘した。
さらに、「昔は妊婦の温泉利用は禁忌とされていたが、妊娠中の運動が推奨される現在、温泉は(適度な利用であれば)良いのではないか」と述べ、温泉利用の新たな可能性についても言及した。
研究発表3:足湯のストレス軽減効果を検証
株式会社バスクリン製品開発部の中村光李氏は、「別府温泉水を用いた足湯の効果について」と題し、同社による実証研究の結果を報告した。
足湯には①血行促進、②自律神経を整える、③痛みの緩和、という3つの効果があるとされる。 研究では別府・鉄輪温泉の湯(ナトリウムー塩化物泉、pH3.5弱酸性、メタケイ酸豊富)を使用。この湯が持つ「保温」と「保湿」の特性に着目し、観光客のストレス軽減や疲労回復への効果を検証した。結果、37℃で20分間の足湯により、血流が増加し、足の深部温度が約2.5℃上昇。その効果は浴後もしばらく維持されることが確認された。
さらに、唾液アミラーゼ活性(ストレス評価指標)が足湯によって低下する効果も確認され、温泉地の足湯が観光客のウエルネス向上に具体的に寄与することが示された。

足湯浴前後の唾液中のアミラーゼ量でストレス度を調査
研究発表4:温泉と腸活、「免疫力日本一」目指す
九州大学教授の馬奈木俊介氏は、「免疫力日本一宣言 個人の腸内環境タイプに基づいた個人レコンドシステム構築へ」というテーマで登壇した。
馬奈木氏は冒頭、別府市の扇山ふもとに計画中の「新湯治・ウエルネス研究施設」構想に触れた。同施設はラボ、市民、ゲスト、民間提案の4ゾーンで構成される先進的な温泉施設となる予定である。
馬奈木氏は、別府温泉「免疫力日本一宣言」プロジェクトを推進しており、約40兆個ともいわれるヒトの腸内細菌に着目。「一人一人で腸内細菌の構造は異なり、温泉入浴は腸活にも有効である」と述べた。個々人の腸内環境に合わせた温泉利用法などを提案するシステムの構築を目指しているという。
また、推計2兆円規模ともされる「温泉医療ツーリズム市場」が拡大している現状を指摘し、こうした取り組みが温泉地域の経済効果にも大きく影響する可能性が高いと、研究の社会的意義を強調した。
特別講演:ヤマザキ・マリ氏「古代ローマと温泉」
シンポジウムの最後には、漫画家・文筆家のヤマザキ・マリ氏が「古代ローマ 千年の繁栄と温泉」と題して特別講演を行った。
ヤマザキ氏は、代表作『テルマエ・ロマエ』の着想源について語った。 イタリア半島が火山地帯であり、災害も多く、温泉文化や銭湯文化が栄えていた点を挙げ、「古代ローマは日本に似ているところが多い」と指摘。
自身も17歳からイタリアに留学し、シャワーばかりの生活でお風呂を渇望していた体験から、「『テルマエ・ロマエ』の主人公・ルシウスは、ヤマザキ氏本人を投影した部分もある」と明かした。 生活費のために漫画を描き始めたこと、帰国後に温泉レポーターなどを経験したことが、古代ローマと温泉を結びつける作品の誕生につながったという。
続編『続テルマエ・ロマエ』では、別府温泉も舞台となっており、鉄輪温泉のひょうたん温泉に主人公ルシウスが登場する。ヤマザキ氏は、制作前に自身で別府市内の多くの温泉に入浴し、調査したエピソードも披露した。
続く長野市長とのトークセッションでは、別府温泉の魅力や、市内42.195湯を巡る「別府フロマラソン」などのユニークな取り組みに話が及び、終始笑いの絶えない時間となった。ヤマザキ氏と長野市長の軽妙な掛け合いに、多くの地元市民が参加した会場は大いに盛り上がり、温泉の持つ多様な価値と楽しさを再認識する形で、アカデミアは幕を閉じた。

トークセッション(左)ヤマザキ・マリ氏、(右)長野恭紘別府市長