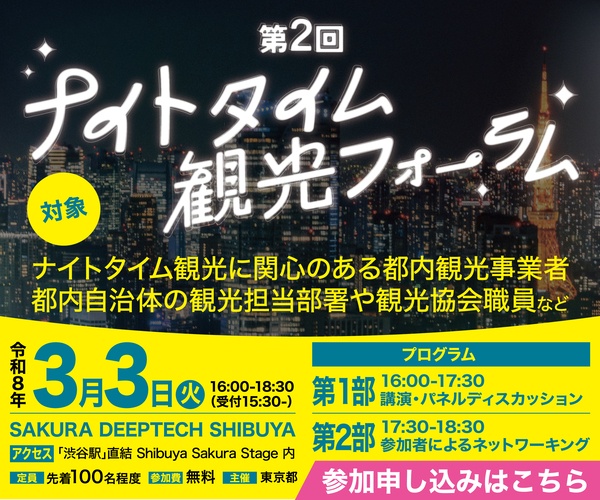上村早苗氏
序論
1.1.はじめに:個人的な体験からの問題提起
こどもの頃、湾岸戦争下で泣き叫ぶ子供たちの映像をテレビで見たとき、私は大きなショックを受けた。自分と変わらない年齢の子供が、ある日突然家を壊され、家族を奪われ、自らの命すら危険にさらされている。この紛争が、今まさに同じ地球上で起きているという事実に、私は言葉を失った。そのとき、幼心に「この世界の課題を解決し、子供たちが笑顔になれる世界を作りたい」と強く願った。
あれから30年以上が経った今も、世界の状況は本質的に変わっていない。グローバル化が進み、情報は瞬時に世界を駆け巡る。遠い国で起きている今日の出来事が、世界中の一人ひとりの手元に届くのだ。物理的にも感情的にも世界は近づいた。生活自体は進化したが、人類自体が進化しておらず、国家間の対立や民族紛争はいまだ後を絶たない。2022年のロシアによるウクライナ侵攻、2023年のイスラエル・ハマス紛争、2024年のイラン・イスラエル間の軍事衝突など、現代においても「争い」は問題解決の手段として選択され続けている。ガザ地区では紛争開始以降の死者が6万人を超え、その約3割が子供であるとイスラム組織ハマス運営の保健当局が発表した。
こうした現実に対し、多くの人々は無力感を覚え、あるいは自国の課題を優先するあまり、世界の出来事から目を背けがちになる。「誰かが何とかしてくれるだろう」「自分にはどうすることもできない」。私自身、長年そう考えてきた一人である。
しかし、観光業に深く携わる中で、その考えは転換点を迎えた。きっかけは、1967年に国連が提唱した「観光は平和へのパスポート」という言葉との出会いである。平和の維持には、軍事力や経済力というハードパワーによる抑止だけでなく、私たち一人ひとりが実践できる人的交流、すなわちソフトパワーが不可欠である。そして、このソフトパワーは、目に見える紛争だけでなく、水面下で燻る不信や憎悪の連鎖という「紛争の火種」そのものを消し去る力を持つ。これは、単に戦争がない状態(消極的平和)に留まらず、貧困や差別といった構造的暴力を取り除き、公正な社会を積極的に構築していく「積極的平和」の考え方そのものである。この考えに、私は一条の光を見出した。
本稿は、この個人的な問題意識から出発し、「旅」や「観光」という個人のミクロな実践が、いかにして「世界平和」というマクロな理想の実現に貢献しうるのか、そのメカニズムと可能性、そして日本の観光業が担うべき役割について論じるものである。
1.2.日本の観光業が掲げるべき大義
日本の観光業は、国内旅行においては自動車産業に次ぐ規模へと成長し、訪日客数はUN Tourism(世界観光機関)の発表によれば、2023年に世界12位となった。日本が掲げる2030年に6000万人の訪日客が実現すれば、世界3位となる。急成長真っ只中の観光業界は、日本の基幹産業として確実にその階段を登り始めていることは間違いない。一方でその社会的評価は経済規模に追いついていない側面がある。それは、観光業が古くから存在する産業であり、最先端のイノベーション事業とは見なされにくいからなのかもしれない。
日本の観光業が真の基幹産業となるためには、経済的規模以上の「大義」が必要である。優れた企業が、目先の利益追求ではなく、社会への貢献というビジョンを掲げることで、顧客だけでなく社会全体から応援されるように、観光業もまた、業界の利益を超えた社会益を提示する必要がある。その大義こそが「旅は世界を平和にする」である。
平和と相互理解に基づく協調関係は、ごく一部の例外を除き、あらゆる産業の活動基盤となる。世界は長きにわたり、軍事力による抑止、つまり「恐れ」と「不信」を前提とした安全保障に莫大な投資を続けてきた。本稿は、それとは異なるアプローチとして、観光がもたらす交流と相互理解というソフトパワーによる安全保障の構築を提言する。このビジョンこそ、日本の観光業が世界に示すべき新たな価値であり、本稿が探求する中心的な主題である。
1.3.100年先を見据えたビジョン:なぜ「平和」を掲げるのか
観光業が「世界平和」を掲げることは、単なる理想論ではない。それは、100年先を見据えた、極めて実践的な生存戦略であり、成長戦略でもある。観光ビジネスが持続的に発展するには、世界の旅行マーケットが安定的に維持・拡大し続けることが絶対条件である。
しかし、このマーケットは極めて脆弱だ。1991年の湾岸戦争時、世界的な情勢不安は瞬く間に旅行マインドを冷え込ませ、マーケットは急激に縮小した。この歴史的教訓は、「観光は平和でなければ成り立たない産業である」という厳然たる事実を我々に突きつける。
マーケットの未来は、平和と安定の先にこそ開かれる。現在、世界の人口の大多数は、経済的な理由などからまだ国際的な旅行を経験していない。これらの潜在的な旅行者がマーケットに参加すれば、その規模は現在の数十倍にも成長するポテンシャルを秘めている。
ここに、日本の観光業が果たすべき役割がある。観光先進国として、国内の多様な成功事例をモデルケースとし、経済的利益の追求を超えた「平和の創造」という大きなビジョンを世界に提示する。それこそが、日本の観光業が世界を牽引し、100年後も輝き続けるための道筋なのである。
1.4.論文の構成
本稿の構成を提示する。第一章では、旅がもたらす異文化理解とステレオタイプの克服について論じる。第二章では、観光という経済活動がもたらす相互依存関係と平和構築への貢献を考察する。第三章では、旅を通じて育まれるグローバル市民意識の重要性を論じる。第四章では、旅の持つ限界と課題を指摘し、平和への貢献を最大化するための方策を探る。最後に、結論として、現代における旅の意義と世界平和への展望を述べる。
本論
第1章:異文化理解の深化と共感性の醸成
1.1.ステレオタイプの解体
旅は、私たちが無意識に抱えている他者への先入観や偏見を揺さぶる力を持っている。メディアや教育、家庭内の会話などから形成される「ステレオタイプ」は、異文化や他国の人々に対する一面的なイメージを固定化させる。しかし、実際にその土地を訪れ、現地の人々と会話を交わし、生活の一端に触れることで、こうしたイメージは次第に揺らいでいく。「思っていたのと違った」「案外、自分たちと似ている」――そうした発見は、相手に対する理解と敬意を育む出発点となる。旅によって解体されるのは「他者」への誤解だけでなく、「自分」や「自国」に対する視野の狭さでもある。多様な価値観と出会うことは、自らの前提を問い直す行為でもある。相手や相手の地域・文化に好感を抱くと同時に、自分たちの地域や文化を見直し、その良さも再認識する効果がある。異文化との出会いはしばしば混乱や驚きを伴うが、それを乗り越えることで人は寛容さと柔軟さを身につけていく。ステレオタイプの解体は、相手方への先入観に留まらず、自分たちのことに対する固定概念すら見直すことができる、平和構築の第一歩である。
1.2.無関心からの脱却と失敗からの学び
旅先での出会いは、単なる観察ではなく「体験」である。他者の暮らしの中に一時的にでも身を置くことは、その人々が抱える日常の喜びや苦悩を肌で感じることに繋がる。この共感は、ニュースやドキュメンタリーなどの情報のみでは得がたいものである、人間として自らが五感で感じて理解した事実である。その事実をどう捉えるのかは、人それぞれでかまわない。最も恐れるべきは「無関心」であり、痛みや喜びを持つ一人の人間として世界の事実を認識することこそ、世界の課題に対して考え始める重要なきっかけとなる。
この「五感体験」は、歴史認識においても決定的な役割を果たす。広島の平和記念資料館、アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所、あるいはカンボジアのキリング・フィールド。これらの場所を訪れる「ダークツーリズム」は、単に悲劇的な歴史を学ぶ行為ではない。日本も戦後80年を迎えても、今なお多くの人の死は日本の歴史と現代に生きる私たちにも、深い影を落とし続けている。どのようにして、このような結果を招くプロセスを経たのか。人類は、対岸の火事ではなく、明日の自分を守るためにも、この失敗の多くを学ばなければならない。その土地の空気を感じ、想像力を通じて過去の出来事を「追体験」することで、自分ゴトとなり、二度と過ちを繰り返さないという人類共通の学びに繋がるのである。
1.3.コミュニケーションの重要性
真の異文化理解は、双方向のコミュニケーションなしには成り立たない。観光の現場では、言語の壁や文化の違いに直面することもあるが、それでも何とか相手に想いを伝えようとするプロセス自体に価値がある。たとえ言葉が通じなくとも、笑顔や身振り手振り、目線の温かさが心を通わせることもある。こうした「伝えよう」とする姿勢が相互理解を深める土壌を育てる。また、観光客と受け入れ側とのコミュニケーションは、時に誤解や衝突を生むこともあるが、それもまた学びの機会である。重要なのは、相手の文化や背景を「知ろう」とする謙虚さと、対話を通じて関係性を築こうとする意志である。旅先での会話の一つひとつが、やがて国境を越えた信頼関係の種となり、距離すら超える強い絆で結ばれた関係が構築される。世の中の課題の多くは、「コミュニケーション不足」によるものである。それはコミュニティの大小に関わらず、国家間でも同じことがいえるものと考えている。交流は人を成長させる。世界中が旅を通じて人的交流を図れば、人類全体が大きく成長し、「争い」とは違った選択肢によって課題を解決できるようになるはずである。
第2章:経済的相互依存の構築と平和への貢献
2.1.観光による経済的相互依存論
経済的な相互依存は、戦争を回避するための有効な土台であると国際政治学でも繰り返し論じられてきた。観光業は、まさにこの相互依存関係を草の根レベルで築く産業である。旅行者は、滞在先で宿泊し、その地域らしい食事を楽しみ、その地域を訪れた証として、地域らしいモノを買う。その支出は、現地の事業者や労働者の収入となり、地域経済に貢献する。観光庁の分析によれば、観光業の経済波及効果は全産業平均の約1・4倍に達し、宿泊業や飲食業だけでなく、小売業や運輸業、さらには農林水産業にまで広く恩恵をもたらすことが示されている。たとえば、ある観光地が外国人旅行者の人気を集めるようになれば、その国の経済は他国の安定と発展に直接的な関心を持つようになる。国家間の関係が一部冷え込んでも、民間レベルでの観光交流が継続していれば、完全な断絶には至りにくくなる。このように観光は、軍事的な抑止とは異なる形で、国家や地域間に「切っても切れない関係性」を築く力を持っているのである。国家で最も影響力のある首相や大統領が、最終的に戦争に舵を切る判断をするが、首相や大統領は民意により選出される場合がほとんどである。従って、民意を加味する必要があり、民意は国の方向性を変えることができる。民間の経済活動への影響と、民間の他国間活動を遮ることは民意に大きな影響を及ぼすことを、国民自体が認識し、無関心から脱却し自分ゴトとして、はっきりとした意志を表明するべきである。
2.2.ソフトパワーとしての観光と民間外交
観光が平和に貢献するメカニズムを理解する上で、「ソフトパワー」という概念は極めて重要である。ハーバード大学のジョセフ・ナイ教授が提唱したこの概念は、軍事力や経済力(ハードパワー)による強制ではなく、その国の文化、政治的価値観、政策の魅力によって他国を惹きつけ、自国の望む結果を得る力を指す。
観光は、このソフトパワーを醸成するための最も効果的な手段の一つである。アニメや和食といった日本の文化、あるいは「おもてなし」の精神に触れた外国人は、日本に対して好意的な感情を抱きやすい。こうしたポジティブなイメージは、国際社会における日本の信頼性や影響力を高める無形の資産となる。
さらに、観光は政府だけでなく、民間企業や個人が主体となって行う「パブリック・ディプロマシー(広報文化外交)」の重要な一翼を担う。一人ひとりの観光従事者や旅行者が行う交流は、草の根レベルで国家間の相互理解を促進し、政府間の公式な外交関係を補完・強化する。このように、観光はハードパワーによる安全保障とは異なる次元で、国家の安定と平和に貢献する力を持つのである。
2.3.紛争後の平和構築と観光
観光は、破壊された地域の再生においても重要な役割を果たす。紛争や災害の被害を受けた地域に人が再び訪れることは、地域住民にとって大きな心理的・経済的な支えとなる。例えば、ルワンダでは、ゴリラトレッキングの観光収入の一部が地域コミュニティに還元され、元兵士を含む住民の雇用創出やインフラ整備に繋がり、和解のプロセスを経済的に支えている。日本においても、自然災害や地震災害後は、当然復旧が最優先で急がれるが、それと同時に災害後も被災者がその土地で経済活動を行うことが可能でなければならない。私たちの中で記憶に新しい災害が、能登半島地震とそれによる津波の被害である。復興と共に、1日も早く能登の賑わいを取り戻し、地域が安心して復興の先に明るい未来を見ることができるような取り組みを行わなければ、その土地を離れてしまうケースが増えることとなる。観光業界が新たなツーリズムを立ち上げ、集客に努めることで、能登の現状をその目で見て、一時的な支援ではなく、経済活動として復興を支援することができる。被災した地域とのすり合わせや、要望の聞き取りは必要だが、これもコミュニケーションによって課題を明確化し、解決へと導くことができるものと考える。
2.4.サステイナブル・ツーリズムとコミュニティの役割
持続可能な観光(サステイナブル・ツーリズム)は、「観光地の環境や文化価値、そこに住む人々の暮らしを守りながら、経済的にも成り立つ観光を未来の世代まで続けられるようにしていこう」という考え方である。主に3つの視点がある。
2.4.1.訪れた地域の在り姿への配慮
観光地の美しい資源や自然を、旅行者が訪れることで、その価値が落ちてしまうことが決してないように、最大限の配慮を行い、最小限の負担に抑えることである。無理な開発による観光地化も、地域の在り姿を変容していることになる。
2.4.2.社会・文化への配慮
その地域に古くから伝わる文化や伝統、歴史へ敬意を払うことである。また、その地域を守る住民の生活にも敬意を払い、その価値が守られるよう、旅行者と住民が良好な関係を築くことを目指す。
2.4.3.経済への配慮
観光によって得られた利益が、外部の大企業に独占されるのではなく、地元の事業者や住民にきちんと還元され、地域経済全体が潤う仕組みを作ることである。これにより、安定した雇用が生まれ、地域が長期的に発展していくことを目指す。
これらの具体的な実践モデルとして、コミュニティ・ベースド・ツーリズム(CBT:地域住民主体の観光)が挙げられる。CBTは、地域住民が観光開発の主体となり、その利益の多くが地域に還元される仕組みである。これは、外部資本による一方的な開発を防ぎ、地域の文化や生活様式を守りながら、経済的な自立を促す。
このCBTは、紛争や占領といった極めて困難な状況下においても、平和を希求する力強い手段となりうる。例えば、パレスチナでは、ウォーキング・トレイル「マスール・イブラヒム(イブラヒムの道)」のように、地域コミュニティが主体となった観光プロジェクトが展開されている。旅行者は、地元のガイドと共に美しい景観や歴史的な村々を歩き、家庭での宿泊や食事を通じてパレスチナの人々の日常と文化に触れる。これは、旅行者に紛争のイメージだけではないパレスチナの多様な魅力を伝え、ステレオタイプを覆す機会を提供する。同時に、地域住民にとっては、自らの文化に誇りを持ち、外部世界との繋がりを保ち、非暴力的な形で経済的・社会的な抵抗を続けるための重要な生命線となっている。このように、CBTは観光を「平和を享受する」だけのものから、「平和を創造する」ための能動的なツールへと転換させる可能性を秘めているのである。
2.5.「地方を生かす」ことが本分
日本でも今年大きな話題になっている米不足。その他の農業・漁業・林業などの一次産業は、観光業に必要不可欠な産業である。私たち観光業はそもそも、地域の宝である観光資源を元に波及した産業である。その「地域の宝」の1つが、地場産業である1次産業そのものである。「地域の宝」「地域の光」が消えてしまえば、そこに人が来ることはない。食や産業がなくなれば、観光業は成立しない。1次産業や地場産業が生きてこそ、私たち観光業は成立するのである。冒頭に述べたとおり、観光業は成長産業であるにも関わらず、1次産業が潤ってきていないことの背景には、正しく地域にその経済効果が波及していないことが窺える。事実、日本の食料自給率(カロリーベース)は38%(2022年度)と低迷を続け、農業就業人口の平均年齢は68・4歳(2023年)に達するなど、一次産業の衰退は深刻な状況にある。しかし、利用客の期待は、地域で採れた食材の価値であり、その地域の地場産業への憧れである。私たち観光業は、顧客に対し、「地域の宝」の価値を正しく理解し正しく届け、1次産業が、より付加価値の高いモノづくりを行うための支援を行わなければ、私たち観光業の未来はない。私たち観光業は、地域への波及効果が高い産業であり、だからこそ他の産業からも応援してもらえる産業である。観光業がより大きな経済規模を創出し、日本の基幹産業の地位を不動のものにするためにも、特に1次産業からの支援が重要な手段となる。まずは日本国内での仕組み化と成功事例に期待する。
第3章:グローバル市民意識の育成
3.1.「国民」から「地球市民」へ
グローバル化が進む現代において、私たちは単なる一国の「国民」ではなく、地球全体の未来に責任を持つ「地球市民(Global Citizen)」としての意識を求められている。この意識は、国境や民族、宗教といった境界を越えて、人類全体の幸福と地球全体の安定した未来を考える視点を育むものである。旅は、この「国民」から「地球市民」への意識の転換を促す。異なる文化圏の中に身を置き、異なる言語や価値観の中で生活することで、自分の常識が相対化され、他者の立場を理解しようとする視野が広がる。「日本人として」だけではなく、「人間として」どう生きるべきかを問う契機となる。旅は、世界に対して開かれた心を育て、平和を個人の関心ごととして捉え直す出発点となる。
3.2.地球規模課題への当事者意識
気候変動、貧困、感染症、戦争、難民問題といった地球規模課題は、いずれも国境を越えて私たちの生活に影響を及ぼす。にもかかわらず、多くの人々はそれを「自分とは関係のない遠い話」として捉えがちである。旅は、こうした課題に対する「当事者意識」を目覚めさせる力を持っている。たとえば、極端な気候変動に苦しむ国を訪れた経験は、気候問題を数字やグラフではなく「人々の現実」として捉える視点を与える。また、難民キャンプを視察したり、貧困地域でのボランティア活動に参加することで、課題の複雑さと人間的側面への理解が深まる。こうした経験は、帰国後のライフスタイルや投票行動にも影響を与え、地球市民としての責任ある行動へとつながっていく。
3.3.国境を越えたネットワークの形成
旅は単なる「一時の訪問」で終わるものではない。特に交流型の観光や学びを伴う旅では、現地の人々とのつながりがその後も続くことがある。SNSやオンライン・コミュニティを通じて、旅先で出会った人々との関係を維持し、時に再訪や情報発信、国際協働プロジェクトへと発展することもある。こうしたネットワークは、個人レベルでの国際関係を築くものであり、国家間の公式な外交とは異なる「民間外交」の形でもある。互いの文化や価値観を尊重し合う人と人とのつながりは、いかなる政治的対立よりも深い理解と信頼を育む可能性を秘めている。旅を通じて広がるこうしたネットワークは、国境を越えた平和のインフラとして、21世紀の新しい社会基盤となり得る。
第4章:旅の限界と平和への貢献を最大化するための方策
4.1.旅がもたらす負の側面
今まで述べてきたように旅は多くの可能性を秘めている。一方で、無条件に「善」とは言えない側面も持つ。過剰な観光開発による環境破壊、地元住民との摩擦、文化の表層的な消費、観光地の高級化など、観光が地域社会に与える負荷は深刻な問題となっているケースもある。具体的な課題としては「訪問者(ツーリスト)」と「生活者(住民)」の間で、地域の限られた資源(住宅、交通、静けさ、文化など)の奪い合いが起こること。これにより、地域住民の心に不満や怒りが蓄積し、「歓迎」を「敵意」に変えてしまう事例がでてきている。これからより多くの訪日客を迎える日本にとって、非常に重要な課題であるため具体的に考察する。
スペイン・バルセロナ:
オーバーツーリズムが最も深刻化した都市の一つ。民泊の急増による家賃高騰で、多くの住民が中心部から追い出された。「Tourists Go Home(観光客は帰れ)」といった過激な落書きが街中に現れ、住民による反観光デモが頻発。一部では、観光バスのタイヤを切り裂くといった襲撃事件も発生し、観光客と住民の間の緊張関係は極めて深刻なレベルに達した。
イタリア・ヴェネツィア:
クルーズ船による環境汚染や、日帰り客による混雑で、街のキャパシティは限界に達した。人口約5万人の都市に、年間3000万人もの観光客が訪れる異常事態となった。住民は「自分たちの街がテーマパークになった」と嘆き、大規模な反観光デモを繰り返し実施。市はクルーズ船の乗り入れを制限し、日帰り客から「入島税」を徴収する措置を取らざるを得なくなった。これは、観光客を歓迎するのではなく、制限・管理しようという明確な意思表示となる。
日本・京都市:
市バスが観光客で満員になり、高齢者などが乗車できない「市バス問題」が社会問題化しました。また、祇園では舞妓さんを追いかけるなどのマナー違反が多発した。住民の不満が高まり、市は「バス一日乗車券」を廃止するなどの対策を取った。祇園の一部エリアでは、私道での撮影を禁止する高札が立てられるなど、住民による自衛措置も取られている。これは、観光客との間に明確な「壁」を作ろうとする動きであり、本来の交流とは逆行するものである。
これらの事例は、観光が適切に管理されなかった結果である。
このような観光であれば、平和と反対の効果をもたらす産業となり、私たちの事業はたちまち立ち行かなくなるのである。観光を平和の手段とするには、こうした負の側面を冷静に見つめ、改善策を講じることが不可欠である。
4.2.「責任ある観光(Responsible Tourism)」の必要性
旅の負の側面に対処するためには、観光客・観光事業者・地域社会それぞれが「責任ある観光(Responsible Tourism)」の実践者となる必要がある。観光客には、訪問先の文化や習慣への敬意、環境への配慮、現地経済への貢献意識が求められる。例えば、ゴミの削減やローカルガイドの雇用、伝統工芸品の購入、そして訪問する地域を知り、そこの風土に合わせるなどの小さな行動の積み重ねが旅の質を変える。また、行政や地域社会も、訪問者への感謝を忘れず、地域に適した観光の在り方を主体的に設計することが求められる。但し、旅は強制されて行くものではない。「見たい」「感じたい」という衝動にかられ、現地では五感が感じるままに過ごし、感動する。もっとも利益を享受する観光事業者は、地域、そして観光客のどちらもがなくてはならないものであり、旅行者に「責任ある観光」を提供するのは、観光事業者の責任であるし、それをエンターテイメントとして提供しなければ、人はこない。あとで述べる「ファシリテーター」として、旅行者と地域社会を繋ぎ、それぞれの責任をすべての関係者が前向きに履行できる仕組みを作り、「共に創る旅」を目指すことが、観光事業者の使命である。

上村早苗氏
【著者略歴】1981年生。2004年3月神戸学院大学法学部国際関係法学科卒業。2005年4月田尾不動産入社。2009年12月淡路島観光ホテル入社。2021年3月同社代表取締役就任。