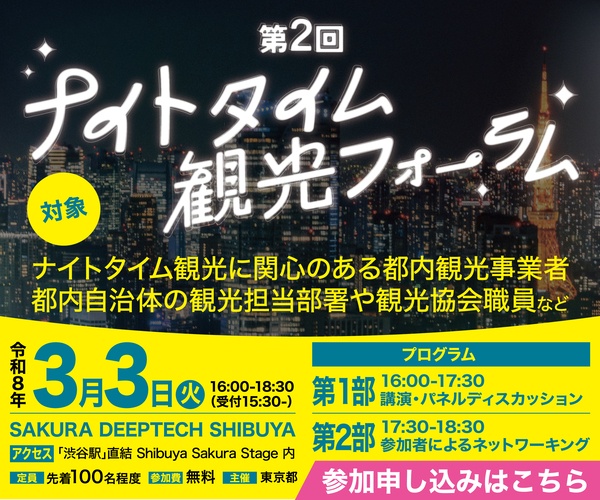「グルテンフリー」と表示するためのルールとは
最近、カフェやスーパーで「グルテンフリー」と書かれたスイーツや食品を目にする機会が増えましたね。健康志向の高まりとともに、すっかり身近な言葉となりましたが、その表示基準が世界と日本で大きく異なることは、あまり知られていないかもしれません。
なぜ「グルテンフリー」が世界で広まったのか、基本をおさらいしましょう。グルテンとは、小麦、大麦、ライ麦などに含まれるタンパク質の一種です。パンや麺類に独特の食感をもたらす重要な成分ですが、欧米では、このグルテンが原因で体に不調をきたす人々がいます。代表的なのが、小腸に炎症などを引き起こす自己免疫疾患「セリアック病」です。
こうした健康上の理由からグルテンフリー食品の需要が拡大する中、テニスプレイヤーのノバク・ジョコビッチ選手が自身の食事法を公開したことで、ブームは一気に加速しました。これをきっかけに、海外のセレブリティやZ世代の間で、グルテンフリーは「ダイエット」や「デトックス」の一環という健康法として広く認識されるようになったのです。
では、食品に「グルテンフリー」と表示するためのルールはどうなっているのでしょうか。
多くの国が準拠しているのが、コーデックス(CODEX)委員会が定めた国際食品規格です。この規格では、食品に含まれるグルテンの含有量が20ppm(0・002%)以下でなければ「グルテンフリー」と表示できないと定められています。この「20ppm」という数値は、セリアック病患者が安全に摂取できる科学的根拠に基づいた基準値です。アメリカのFDA(食品医薬品局)やEU(欧州連合)もこの基準を採用しており、「20ppm以下」が事実上の世界標準となっています。
一方、日本の状況は非常に複雑です。驚くべきことに、現在の日本の食品表示法には、「グルテンフリー」という表示を定義する統一的な基準が存在しません。
その代わりに、特に米粉製品を対象として、農林水産省のガイドラインに基づき、民間の認証機関が「ノングルテン(Non―Gluten)」という認証を行っており、この「ノングルテン」認証の基準は、グルテン含有量1ppm(0.0001%)以下という、世界で最も厳しいレベルに設定されています。
この数値だけ見ると、日本の基準は非常に厳格で安心できるように思えます。しかし、問題なのは、この厳しい1ppm基準は、あくまで「ノングルテン」認証を取得した商品にのみ適用されるという点です。法律による「グルテンフリー」の定義がないため、極論すれば、事業者が独自の判断で「グルテンフリー」と表示することが可能なのが日本の現状なのです。
海外では、GFCO(グルテンフリー認証機関)のような信頼性の高い第三者認証が消費者の安全を守っていますが、日本ではこのような明確なルールがないため、「世界一厳しい認証」と「表示ルールの不在」が共存する、世界との大きな格差が生まれています。
(メイドインジャパン・ハラール支援協議会理事長)

「グルテンフリー」と表示するためのルールとは