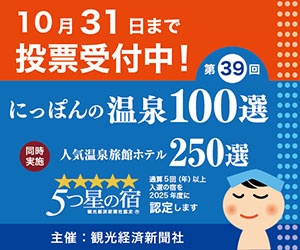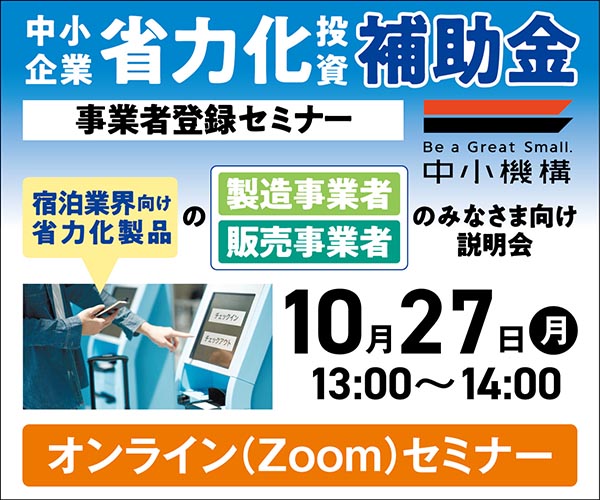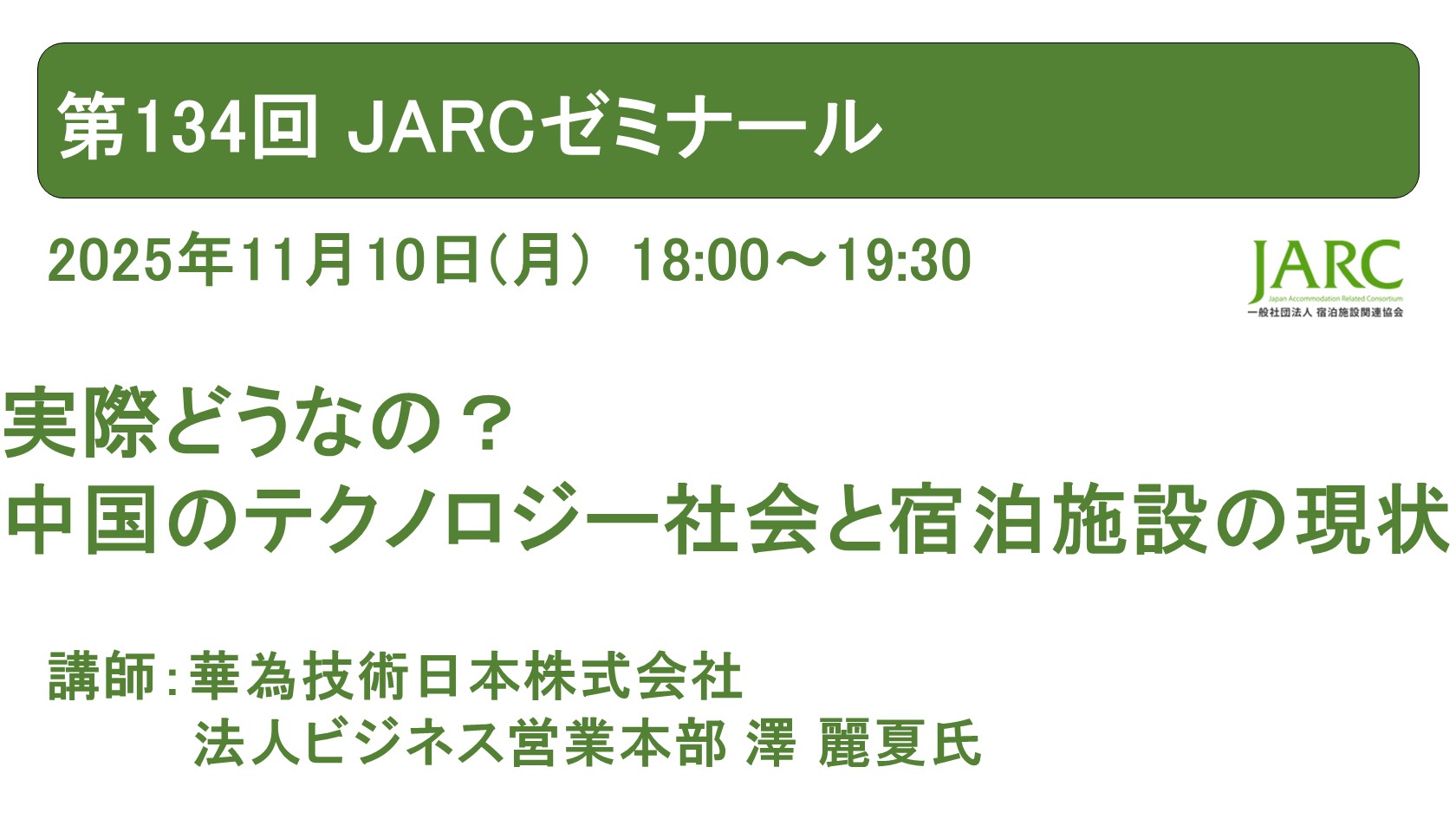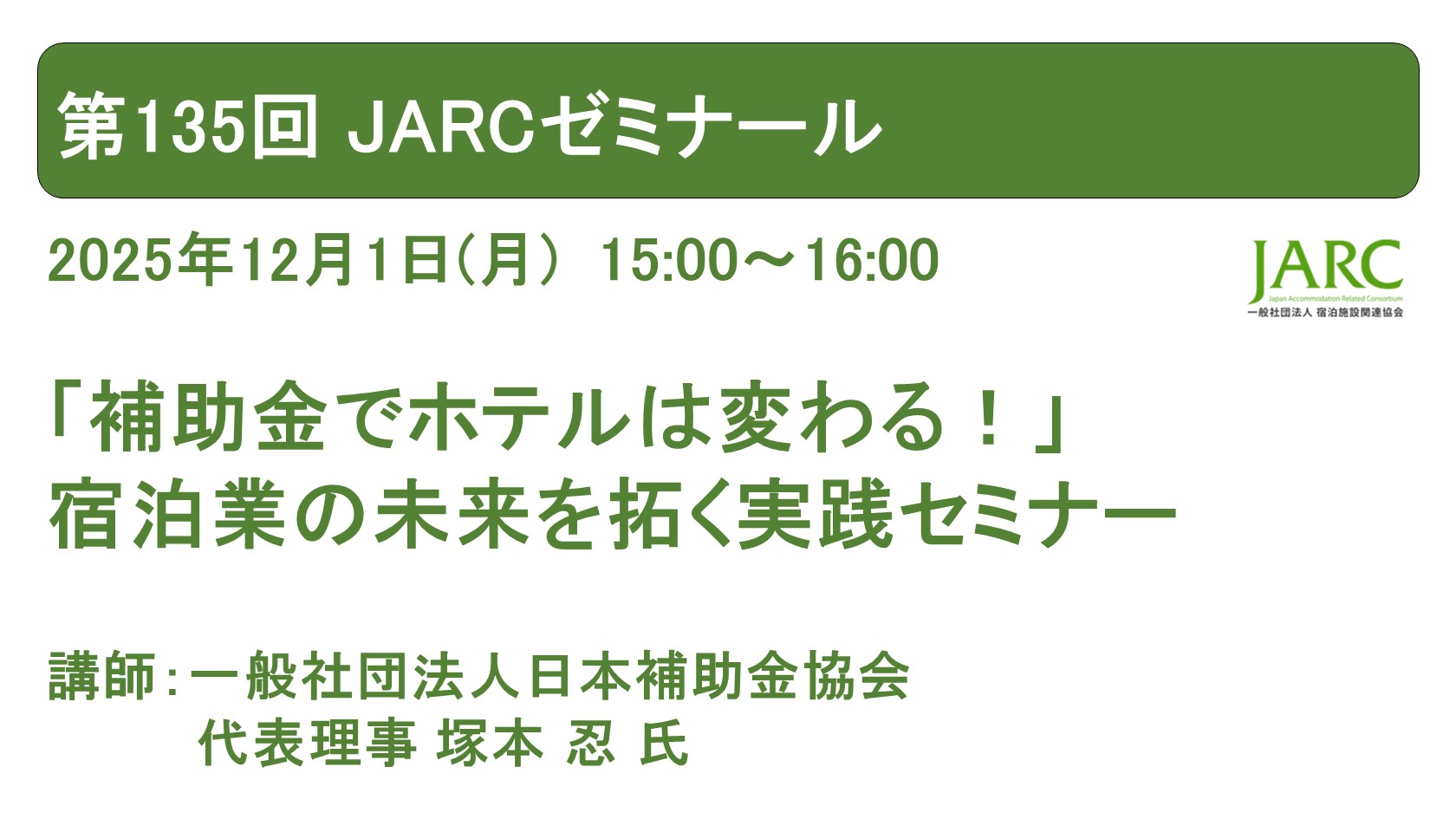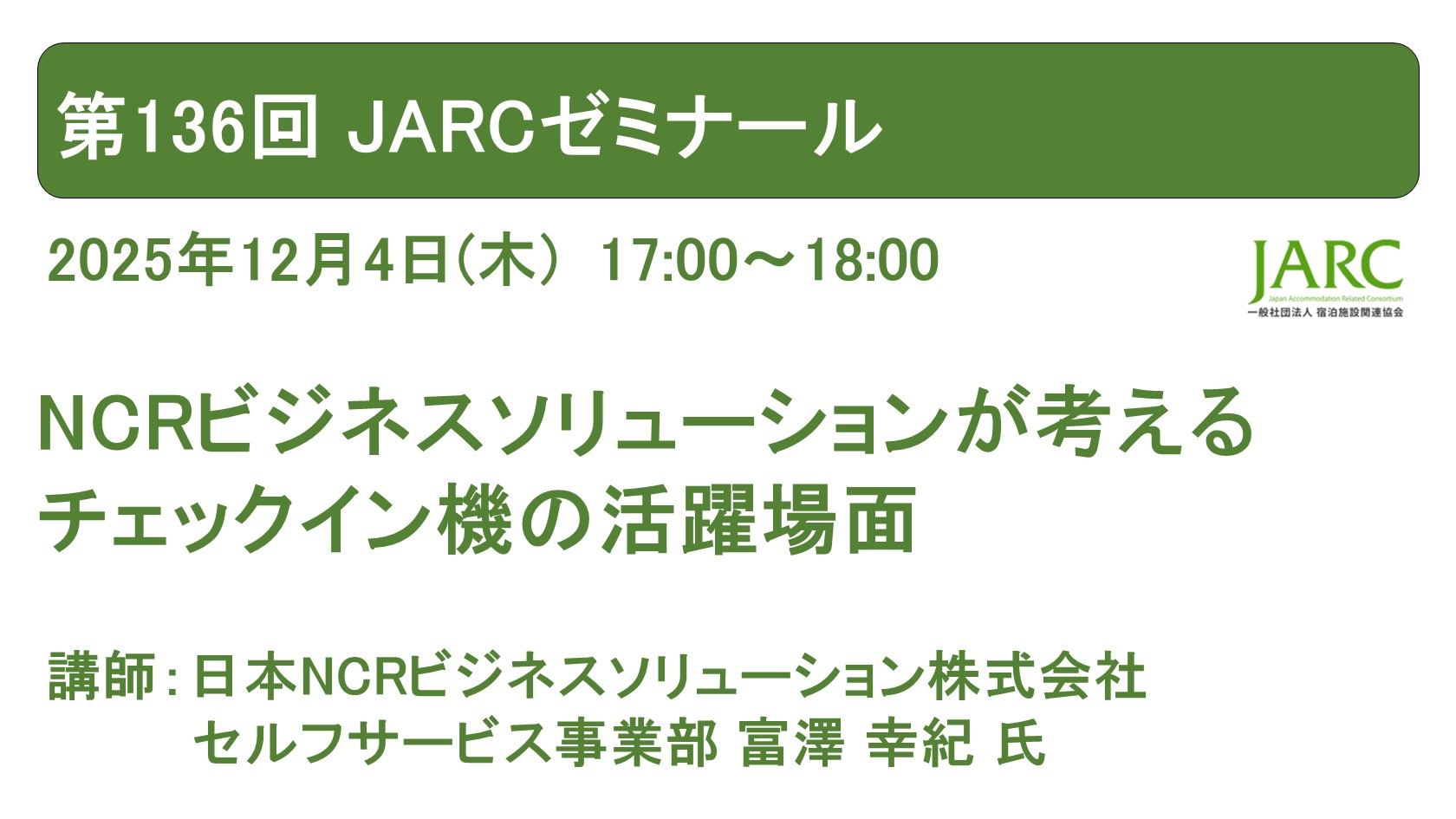相原昌一郎氏
私は旅館が好きではありません――。私はこれまで、多くの場面で幾度となくこの言葉を発してきていますが、そのほとんどの場面で大変驚かれています。なぜなら、私は150年以上の歴史を擁し、敷地内に15棟の文化財建築を有する伝統的日本旅館の経営者であると同時に、日本”旅館”協会に10年以上出向し、政策委員長や労務生産性向上委員長、未来ビジョン委員長、そして、現在ではミライ・リョカン委員長と多くのポストを務めてきた、いわば「旅館という世界」にどっぷりと浸かっているような存在であると思われているからです。
驚いている方々に対して、「正確には、旅館が嫌いなのではなく、今の旅館が置かれている状況が嫌いなんです」と、続けて説明すると、ほとんどの方は安堵とともに納得した表情を浮かべます。「あぁ、そういうことだったらわかるよ」と。ただ、これは私にとっては安堵とはなりません。それは、「多くの人にとってもやっぱり旅館の現状は良くないという認識があるのだ」という確信に結びついてしまうからです。そして、もし、旅館の現状が良くないのなら、いったいなにがそうさせているのか、それは外的要因なのか、内部的な問題なのか。好転させるためにはなにを、どこを、どう変えていく必要があるのか。そもそも旅館は変わることができるのか――。自館の歴史を紡いでいくべき責任と、旅館の未来を提案すべき「ミライ・リョカン委員長」の責務として、今回のこの記念論文を通じて自分自身の考えをまとめてみようと思います。
私は旅館を代々経営してきた一族の元に生まれ、幼いころより館内に自由に出入りし、声を掛けてくれる従業員たちと一緒に食事をし、入浴し、年間行事をともに迎えて成長しました。学生になってからの長期休みには家業を手伝い、それまで家族的に私に接してくれていた従業員と「仕事仲間」という関係性を持つことも経験しました。
働き方改革が進んだ現代では到底考えられませんが、当時は早朝5時過ぎには多くの従業員が出社していました。昼のアイドルタイムを挟んで再び始動し、全体の終業は23時近く。私も時給わずか500円ながら、連日10数時間も働き、アルバイト代をたくさん稼ぎました。その経験は辛かったかと尋ねられれば、確かに肉体的の負担は大きかったと思いますが、仕事という面では辛かった記憶はありません。そして、当時の私の目には、仕事仲間である従業員もまた、同様の感覚でいるように見えました。仕事は激務でしたが、一方、職場には会話が、冗談が、笑い声が絶えず、まるで忙しさを原動力として、皆で多くの来館者を「捌いていく」という一致団結した目標を抱えてるように見えました。そして、その「捌かれている側」である利用客もまた一様に楽しそうに、口々に満足の言葉を述べながら帰っていく――。そこにマーケティングで語られる顧客のニーズやウォンツがあったのか、賞賛されるようなおもてなしがあったのか、と思い返してみても、そういう状況にあったとはとても思えません。それでもそこには間違いなく、訪れる側である利用客と、迎え入れる側である従業員との双方の笑顔、つまり顧客満足と従業員満足とがあったように思います。
時代は高度成長の坂を全力で登り続けている状況であり、そのすべてが正しかったわけではなかったでしょう。ただ、レジャーという名の観光が、旅行が、爆発的に増加していく中で、マイカー渋滞や排ガスが、そして早くもオーバーツーリズムともいうべき社会問題も生じ始めてはいましたが、利用する側と利用される側との間には、お互いに不干渉という明確な線引きが存在していたように思います。施設側は自らに課された業務を殺人的なスケジュールでこなしているわけですが、利用客もまた与えられたフィールドで楽しむことに全力を投入している。野球の選手と観客とに例えるとややわかりはよくなるでしょうか、選手は選手としての最大のパフォーマンスを発揮することに全力を出しているし、観客はその選手のプレーを球場という場所で最大限に楽しんでいる。選手は観客の要望に合わせたプレーはしませんし、観客は選手のプレーに純粋に期待し応援する。勝ち負けがある以上、負ければ選手を野次ることもあるかもしれませんが、それでも野球を楽しみたい、という欲望と、応援する気持ちに変わりはないわけです。結果的に選手と観客が相乗することで楽しみが増幅していく、当時の旅館にはそんな雰囲気があったように感じています。それは、別の表現では「双方が全力で疲れに行くという、同じ方向を向いていた時代」とも言えるのかもしれません。「24時間戦えますか」というCMがあったように、そこにはある意味で「無駄を楽しむ美しさ」もあったように思います。純粋すぎる、貪欲すぎる悩ましいほどの美しさ。そうであったからこそ、その時代の終焉は早かった、そう表現することもできそうです。
バブルがはじけ、観光は、宿泊は、旅館は、長く暗い冬の時代に突入していきます。「美しい時代」が長く続くと考えた経営者らによる過剰投資によって多くの案件が頓挫、多くの施設が倒れていきましたが、バッタバッタと次々にというよりはゆっくりとスローモーションで、そう、まるで沼に沈み込むように消えていった印象を持っています。当時、私は宿泊飲食業の業界誌編集者として国内を俯瞰的に眺めていましたが、そのとき感じていた時代感は、Aでもなく、Bでもなく、だからといってCでもないという感覚。「ファジー」という機能を持った家電製品がヒットしましたが、まさに曖昧であり混沌とした時代であったように記憶しています。
少しずつ変化が見えはじめたのは2000年という大きな世紀の境目が近づきつつあるころ。消費マインドの落ち込みは継続中であったと思いますが、一方で、「どうせ買う(消費する)なら本物を」という時代が到来したように思います。温泉地の表現で言えば、いわゆる源泉掛け流しの神格化です。この流れは食へも波及し、地産地消や天然志向へ。かといって、高額・高級が絶対的に求められたわけではなく、「正しくあること(=騙されたくない)」が絶対的な価値観であったように思います。温泉偽装問題が世間を騒がせたのが2004年ですが、水質検査キットによって各地の温泉水を調査する試みなどもあり、同時に水産物に対する産地偽造や、養殖天然論争なども話題になったように覚えています。これはいったいどういう変化であったと言えるのでしょうか。
私の考えですが、前時代では利用者であったものが、この時代では消費者へと姿を変えた、と言えるのではないでしょうか。野球場を、観光施設を、そして旅館を「利用することに対する利用料」を払っていたものが、「自らの時間や体験を消費することに対する消費代金」を払うことに、つまり、その請求・支払いの主体が相手から自らへ変化したことで、結果に対する査定がはじまった時代です。もう一度重ねます。利用料は、その満足・不満足に関わらず、利用するためには、つまり、足を踏み入れるためには料金を払わなければならないわけです。勝つか負けるかわからなくとも野球を見るためには野球場への入場料を払う必要があり、結果として贔屓のチームが負けたとしても、料金に対する不満は残りません(ふがいない選手に対して「金返せ!」という怒りはあるかもしれませんが)。一方、消費は後追いです。あくまでも消費後の支払いとなるため、そこの満足・不満足は支払い時の感情に大きく影響します。つまり、「時間や体験を無駄に消費させられた=嫌々支払う」が発生しうるわけです。ところが私たち旅館はここになんら意識の変化がありません。つまり、従前から変わらずに予約に従って部屋を支度し、設備を整え、食事を、接客係を用意するわけで、これらは当然に満足・不満足に関わらず、そしてもっと踏み込めば、使う・使わないに関わらず、料金が発生するのです。ここにひとつめの差異による変化があるのではないでしょうか。
ふたつめの差異、それが評価です。それを語るにあたっては「おもてなし」の紐解きが必要です。
おもてなしの語源は明確ではありませんが、私は茶の湯に端を発した「持って(以て)成す(為す)」が有力だと考えています。持つことを意味する「持って」、使うことを意味する「以て」、成果・結果を意味する「成す(為す)」が組み合わされたこの言葉は、「○○を持って(使って)△△をする」ということを意味します。私たちは利用客を迎えるにあたって、部屋を整え、花を活け、季節に合わせて献立を変えるわけですが、本来、「もてなし」とは、こういった物理的な行動による事前準備のこと。同時に語られることの多い「サービス」や「ホスピタリティ」とともにホームパーティで例えてみます。
まず、会場となる部屋を整えること。これは宿主であるホストの役割です。これが「もてなし」だと考えられます。ホームパーティでは食事担当や買い出し担当、片付け担当を決めることがあるでしょう。このそれぞれの役割を担当すること、これが「ホスピタリティ」です。ホスピタリティとは自らが差し出せるものを対価なく積極的・自律的に差し出すこと。ただし、他者からの別の提供もあるため、あくまでもそこに序列はなく同列、主従関係は発生しません。もちろん、もてなし役であるホストも、自らが差し出せるものとして部屋を提供しているという関係性が成立しており、こちらも同列です。他方、「サービス」には明確な主従があります。食べ物を出前で頼んだ場合、この配達者とパーティの参加者との間には絶対的な主従が発生しますが、同時に対価も発生します。依頼を受け配達する行為、これは自律的ではなく他律的です。さて、評価です。この場合、評価の対象となり得るのは唯一、対価が発生しているサービスのみとなるわけで、「対価に見合っていない」「要求が満たされていない」という評価はあって当然です。ですが、それ以外の、もてなしとホスピタリティについては対価も発生せず、主従関係も発生していません。単なる自発的かつ純然たる相手を思いやる気持ちでしかないため、どうやっても評価対象とはなり得ないのです。ただ、現実はどうでしょうか。「おもてなし」は評価の対象とされ、下された悪い評価に対して、施設側は謝罪とともに「さらなるおもてなしの向上に努めて参ります」と表明するに至ります。
私は「もてなし」を否定していませんし、もちろん相手を思いやる気持ちに対しても不理解ではありません。人のみに限らず、いまやChatGPTであっても、思いやりを理解し、言語化可能な時代にあるわけで、思いやりがコミュニケーションの重要な根幹となっていることは十分に承知しています。ですが、こと「おもてなし」に関しては、特に現代の旅館におけるそれは、利用客からの要望に単に応えるものであったり、そのための施設側の気遣い・気配りを指し示しているように感じられ、クレームへの予防線のように見えてしまうのです。コロナ収束以降、未だ多くの飲食店でのマスク着用が認められますが、それが「喫食の場」という感染リスクから従業員を守るためのものであるのか、あるいは飲食業における衛生基準的要素のものなのか。もはや思慮なく繰り返されている日常のようにも感じるわけですが、同様に、思慮なくクレーム対策的に社内ルールに従って発動される「おもてなし」に、悪い評価を防止する効果はあったとしても、行う側、受ける側の双方にそれ以上の心の動きは起こり得ないのではないでしょうか。
これらふたつの差異、つまり「利用者の立ち位置の変化」と、「おもてなしの濫用と評価」、この発生要因は明確です。それは「失われた30年」と称される消費低迷期の行動そのものだからです。
私は「バブル景気」という名付けはすごく上手だったと思っています。一説には1987年、バブルの真っ只中ともいうべきタイミングで経済学者の野口悠紀雄氏が急激な地価高騰を示す表現として使ったと語られていますが、実体なくただ泡が膨れているだけという解釈が、その崩壊後ではなく、最中に出ていたにも関わらず、はじけるまで対処されなかったこと、そして、「やはりバブルであったか」と判明したにも関わらず、その後の対処もまた間違っていたこと、これらがその後の30年を決定づけたのだと思います。つまり、バブルであり、夢であり、盛大な無駄遣い期間であったのだから、どうしたって消費は圧倒的に緊縮されるに決まっているわけです。ところが企業側は、どうやったら消費が元に戻るだろうか、と、まるでバブルの再来を待ち望むかのように、手を替え品を替え、ありとあらゆる企業努力という名の「オマケ」を加え、それでも消費されない状況に至っては、企業努力による低価格化をも推し進めていったわけです。これにより、「安くて良いもの」という消費者優位経済が完成。この流れによって旅館には低価格でありながら高品質の滞在空間が求められ、市場競争が激化、行き倒れた施設を設備投資なしに購入し運用するスキームが誕生して、低価格化に拍車がかかっていきました。私は「おもてなし」はこの時代、このタイミングの産物だと考えています。それ以上の価格引き下げができないなかで顧客満足度を低下させないための人力による「オマケ」です。奇しくもインターネット全盛時代に突入し、近隣だけでない他館の情報も入手しやすくなり、評価の高い「オマケ」を「おもてなし」として導入することが一般化していきます。宿からの誕生日プレゼント、サプライズ協力、無料送迎や無料コーヒー、無料アップグレード。旅行代理店からの「顧客のニーズ」という名の要請であるバラエティに富んだプラン造成にも従うしかありませんでした。他館が提供しているものは自館においても「当然の提供」が約束となり、提供・対応しないことは「おもてなしレベルが低い」というクチコミへ直結していく。なぜ私たち旅館は、自らを貫き通す一流の選手を目指さなかったのか、なぜ、三振しても三振しても応援し続けてくれる熱心なファンを獲得することを選択しなかったのでしょうか。
旅館という名称は明治時代になって一般的に使われ始めたと言われています。それまでの国内宿泊施設は、安価な「木賃宿」、食事付きの「旅籠」、大名や勅使が使用する「本陣」、温泉地にあって湯治を目的とした「湯宿」など、多様な形状で整備されてきたとされます。とりわけ「湯宿」は温泉地毎に湯治ルールが異なるため、短期滞在から長期、食事無しから食事付き、仕切りを持った個室から大部屋滞在と非常にバラエティに富んでいたようです。これらが「旅行商品」として規格化されたことで、多くの宿泊施設は外形を整え、「旅館」化していきます。その後の「旅館業法」(1948年)に関連する「旅館業法施行令」および「旅館業における衛生等管理要領」によって施設設備の内容が、さらに「国際観光ホテル整備法」(1949年)によって、必要とされる基準が明確化され、宿の滞在環境の統一化はさらに進んでいきます。同時に消費者に求められる形で露天風呂や館内バーやスナック、カラオケなどが設置され、合わせて客室内の備品の向上が図られますが、露天風呂付客室など、顧客の要望とされる向上傾向はいまなお続いていると言えるでしょう。
規格化、標準化、消費者の求め――。これらによって、いったいどれだけの旅館の独自性が失われてしまったのでしょうか。そして、果たしてこれらは旅館の地位向上に貢献したのでしょうか。旅館の就業環境は、経営状況は、他業種に匹敵するような誇らしいものとなったのでしょうか。残念ながらそうではない現状において、そして私は、現代の旅館の有り様では、消費者にすら損をさせているのではないか、そう感じます。魅力的・魅惑的な、心躍る旅行体験を私たちが提供できていない、その一点において。
私たちはどのような手順で旅行先、宿泊先を選定しているのでしょうか。何日休めるかという日程確認によって、どこまで足を伸ばせるかというエリアが決定されます。エリア決定後、宿を決めるのに、まず重要なのは予算でしょうか、温泉の有無でしょうか。食事をどこで食べるか、交通手段も重要な項目です。主要駅から遠いのであれば送迎も必要です。そういった多くの取捨選択によってピックアップされた数軒の宿から最終の一軒を決定していないでしょうか。では、海外旅行でも同様の検討過程を辿るのでしょうか。
海外旅行の場合、まず、圧倒的に「ここに行きたい!」が優先されるのではないでしょうか。そこから逆算しての、季節はいつがいいのか、何日くらい必要なのかが決定されるのではないでしょうか。あるいは、「ここ」が「このホテル」という場合もあるかもしれません。そのための下調べをし、場合によっては貯金をし、ようやく迎えた旅行当日は、目に映るものすべてが輝いて――。そういう経験があるのではないでしょうか。私は、旅行はそうあってほしいと思います。自らが欲し、自らが求めたものに辿り着く旅。すべてが万事順調と行かないこともあるでしょうし、自然環境や体調によって影響を受けることもあるでしょう。それでもそれは、あれがない、これをしてほしい、もっとこうだと思った、という不満に繋がるものではないはずですし、それらの不満因子を消すことは私たち宿泊業の役割ではありません。そもそも旅は恋人であれ、友人であれ、家族であれ、同僚であれ、大好きな人と一緒に行くもの。その状況では、どんな思い出も楽しいものとなるのではないでしょうか。冒頭に記した「全力で疲れに行っている」という旅しかり、自らが選択し、自らが振る舞うことで旅の目的が達成されるわけで、これらは能動的な旅と言い換えることができるでしょう。けれども、消費者優位の世の中でいつからか旅は「癒やし・癒され」へと移りかわり、受動的な意味合いが強くなっていきました。私たち事業者にとっては、なにが癒やしとなるのかがわからないため、さらに言えば、なにが不満に繋がるかがわからないため、下手な鉄砲も数打ちゃ当たるとばかりに無駄の多い作業を繰り返す必要がありました。この数打ちゃとばかりに繰り出すもの、それが「おもてなし」と称されているものなのではないでしょうか。この「おもてなし」は人々をスポイルし、「(家と同じような)快適な滞在空間を持ち歩ける」ということを幻想させました。それを全面的にバックアップせざるを得なかったのが私たち宿泊業界の弱さです。ですが、自らも含め、旅行者の記憶に残るのは常に「ここに行きたい!旅」と「大好きな人と行く旅」であったはずです。
これからの日本では「ここに行きたい!旅」が旅行の中心になっていきます。つまり「外客」です。外客は全世界から日本のありとあらゆる場所をめがけて、それもピンポイントで訪れます。先般も当館へ遥か遠く東欧のルーマニアから投宿がありましたが、その理由は「友人が修善寺で働いていたから」でした。では友人に会いに来たのかと聞けば、その就業時期は遙か昔。そのときに友人が送ってくれた修善寺の写真から旅行を計画し、もっとも修善寺らしいという理由で当館を選択してくれたそうです。果たして彼らにとってその選択が正解だったのかはもはやわかりませんが、外客はこのように、それは私たちの海外旅行計画と同様に、直接的に訪れる場所を決定します。そしてまた、その来訪目的も非常に明確です。当館は現状で30%を超える外客比率となっていますが、これは地方旅館としては突出した数字だと思います。なぜ支持を集めるのか。従業員にネイティブスピーカーはいませんし、他国の言語を用いた表示やピクトグラムといった国際対応も行っていません。タブレット等を用いた注文にも対応していませんし、全ての客室は畳敷き、布団による就寝で、料理は魚介だらけの和食、肉料理は出ません。外客を迎えるのならナイトタイムエコノミーは必須!と巷間では伝えられますが、館内は22時には真っ暗です。それでも当館には彼らがイメージしてきた「純日本」が確実に存在しており、それが彼らを引き寄せているのです。そしてそれは、誰かの求めに応じて用意したものではない、当館が百年以上に渡って伝え残してきた、変わらない日本、けれども、誰もが持ちうることができた日本なのです。
私はこれはチャンスだと考えています。当館にとってだけではなく、日本の旅館が自らの得意を発揮することでピンポイントで来訪してもらい、その得意を評価してもらえるチャンスです。ここまで述べてきたように、私たち宿泊業は、これまで多くの独自性を捨ててきました。進化論による進化の枝分かれとは真逆の形で、その系譜にこだわることなく類似性を選択し収斂を行ってきたわけです。そのベクトルを元に戻し、多くの宿が多くの多様性を発揮するようになれば、日本の宿泊産業は魅力溢れる宿屋で埋め尽くされることになるのではないでしょうか。それには「たった一皿の料理」だけでいいのかもしれません。「この窓からのこの景色」で十分なのかもしれません。自らが自信を持って提供できる、唯一無二の特徴を獲得し、広報し、認知されることで、その特徴を目指した旅行者が訪れるのです。極端な例を挙げれば、日本で一番うまいカレーを出す旅館があれば、全国の、世界中のカレー好きが訪れることになるでしょう。カレーと旅館との親和性はともかく、そういう明確な宿作りをすることは、従業員の意識改革にも繋がっていくはずです。どういう宿であるのか、どういう理由で働くのか、その場(施設)で、自らはなにをすればいいのか――。
以前、アイスメーカーの開発担当者が年間に数百種類の新しいフレーバーを考えるというレポートを見たことがあります。この飽食の時代に、もはや新しい味覚の発見は困難だと思いますが、それでもその開発はとても楽しく、やりがいのあるものだと語られていました。旅館は宿泊や入浴など、さまざまな生活商品を提供する場でありますが、木賃宿、旅籠、本陣、湯宿から旅館へという移りかわりにおいて、その系譜も含め、料亭旅館、温泉旅館、観光旅館など、分野が異なる発展を果たした歴史もあります。山の中の一軒宿と、漁港に近い漁師宿では当然に提供できるものも異なりますし、周辺気候が異なれば、もとより姿形も異なるはずです。なぜそこで宿を興したのか、その本質をあらためて考え直し、それも料亭旅館だからといって、料理全般に注力するのではなく、もっともっと限られた分野にリソースの選択と集中を行い、たとえば日替わりで「究極のお椀」を出す宿として極めを目指していくという戦い方もあるのではないでしょうか。それは、その他の料理が仮に通年一緒だったとしても、年に何度も、月に何度も通いたくなる旅館になるのではないでしょうか。
私たちはこれまで「受け入れ」に対しては非常に積極的でした。これからの、未来の旅館に求められるのはアウトプットです。なんのために存在し、どういう宿にしたいのか。私たちにはこれまで培ってきた過去がありますし、時代に合わせて変容を重ねてきた器用さも身についています。それらの能力を整理し、自らの価値を一点突破で極め、なりたい自分を積極的に求めていく。そのことで私たち旅館は自ら目的地になることができるのです。その旅館に行きたいから旅に出る。この世がそんな旅館で溢れたとき、私の旅館への屈折した思いは姿を変え、私は自信を持って旅館が好きだと発言することになるのだと、そんな未来を期待したいですし、その未来に向かって自ら歩みを進めていきたいと思っています。

相原昌一郎氏
【筆者略歴】1971年静岡県生まれ。東京YMCA国際ホテル専門学校、株式会社オータパブリケイションズ(業界誌出版社)を経てデザイン事務所設立。ホテル・旅館のパンフレットや冊子、料理書籍のデザイン・編集・アートディレクションを行う。2011年、家業である新井旅館の6代目として代表取締役就任。一般社団法人日本旅館協会において観光立国副委員長、政策委員長、労務生産性向上委員長、未来ビジョン委員長を経て、2024年からミライ・リョカン委員長および同協会中部支部連合会副会長。ほか、修善寺温泉事業協同組合副理事長など。