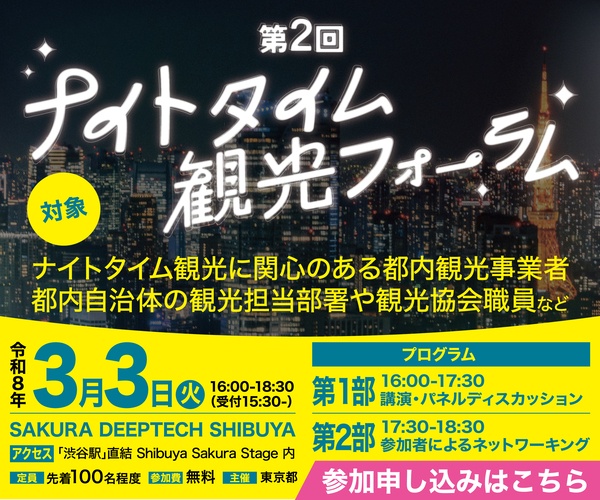福島氏
建築やアートの世界では「神は細部に宿る」という表現がよく使われる。
「真の美しさや価値は細部に宿る。細部を丁寧に作ることこそが完成度を高める」という意味である。そこには職人的思想や美学がある。翻って対人接客サービスのあり方に目を向けると、ここにも細部に宿った神がサービス提供者に誇りを与え、顧客に、もてなしの美学を提示している様が見えてくる。
そのディテールのひとつが「指先」である。すっと柔らかく伸びた指先は品格をたたえ、顧客に安心感と信頼を与える。ホテルには、顧客自身に大切な客として扱われていると実感させる「接客の基本マナー」が存在する。
たとえば、地図上で目的地への道順を説明する際、手のひらを上に向け指をまっすぐにそろえて道順をなぞっていくのが、接客の基本である。この時、顧客の眼前でボールペンでくねくねと道路に線を引いたり、ペン先で地図上をコツコツと叩いたりしながら案内するのはNG。道順が分かりにくい場合は、あらかじめ道順にマーカーで色を付けてから、地図上を手のひらで指し示しながら案内するのが望ましい。
ホテルマンが常に手のひらを見せるようにするのは、顧客に対して安心感、誠実さ、礼儀を示すためといわれているが、これは、日本だけではなく世界中のホスピタリティ業界で共有されている非言語的マナーでもある。
よって、世界中のホテルマンはパブリックやトイレの位置を知らせる時も、客室へ案内する時も手のひらを上にして指し示し、誘導していく。荷物を預かる時もしかり。手のひらを見せながら両手を差し出すことで「安心してお預けください」という無言のメッセージを示す。そして、この時、重要なのが、すっとまっすぐ奇麗に伸びた「指先」なのである。
ところで、チラシなどの紙を手渡す時には所作を美しく見せる配慮の極意がある。
手渡す用紙がA4版縦長の場合、相手が右手で受け取りやすいよう、差し出す側は、右手で長辺の下3分の1を持ち、左手を短辺の左端もしくは中央辺りに添える。次に、相手が読みやすいよう斜めに傾けて差し出し、相手が右手でチラシの長辺を持ったら、すかさず短辺の左手を外し、その後、右手を離す。この一連の動作を流れるように、相手に気付かれることなく行うことで、「何となくいい」を醸し出す高度なサービスの提供が可能になる。言うまでもなく、指先を奇麗にそろえておくことは必須だ。
前回のコラムでも紹介した生田久美子氏は「わざ言語」理論の中で、「技が身体に定着し、意識せずとも自然に発現する状態」をアチーブメント状態と称している。このアチーブメント状態の成立には、(1)技能の身体化、(2)感覚的に再現可能、(3)他者に言語化して伝えられる、(4)自分の中で達成感・納得感があることの四つの条件が必要であると生田氏は説く。この理論を援用すれば、まさに美しい所作とはサービス提供者がアチーブメント状態になることであり、この状態を究めるのが、もてなしのディテール、いわゆる「指先」と言えよう。
冒頭の言を借りれば、「所作の真の美しさや価値は指先に宿る。指先を丁寧にそろえることこそが所作の完成度を高める」とも表現できる。
福島 規子(ふくしま・のりこ)九州国際大学教授・博士(観光学)、オフィスヴァルト・サービスコンサルタント。