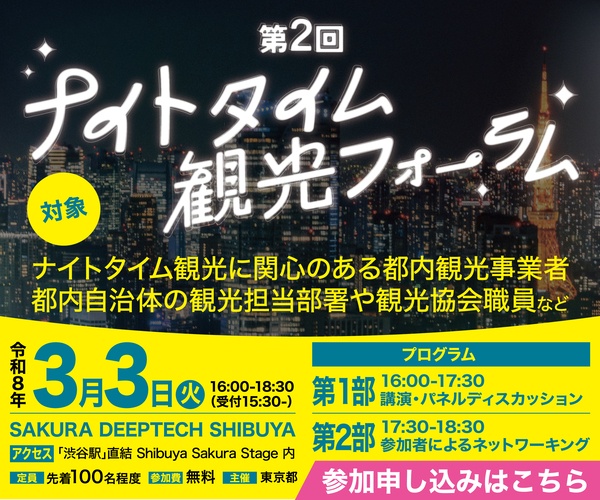台湾観光庁の陳長官(=左)と山下教授
台湾観光庁(交通部観光署)は10月3日、台北の国立政治大学において「構築観光新未来フォーラム」を開催した。同フォーラムには、招聘講演者として日本から帝京大学経済学部観光経営学科の山下晋一教授が登壇。「観光立国政策と持続可能な観光地づくり」をテーマとした基調講演を行い、日本の観光政策の成功事例と台湾観光の発展に向けた提言を行った。新たな観光の未来構築に向けた台湾政府の取り組み。日台両国の観光戦略から見えてくる課題と可能性。

あいさつする台湾観光庁の陳玉秀長官
「量の回復」から「質の飛躍」へ—台湾観光の変革点
「構築観光新未来フォーラム」では会場となった国立政治大学の講堂に約90名の来賓と観光庁幹部が集まり、観光庁長官の挨拶に続いて山下教授による基調講演が行われた。
陳玉秀長官は冒頭の挨拶で、台湾観光が「量の回復」から「質の飛躍」への移行期にあると指摘。「パンデミック以前の賑わいを取り戻すだけでなく、革新と持続可能性を核として、『旅行者を感動させ、地域を潤し、産業を持続可能にする』観光エコシステムを構築し、台湾を世界中の旅行者から選ばれる旅行先にする必要がある」と述べた。
フォーラム全体のテーマは「観光の新たな未来を構築:地域深化×デジタル変革×国際誘客」。山下教授の講演に続き、オーストラリアのECO Tourism AustraliaのCEO Elissa Keenan氏による台湾におけるエコツーリズムをテーマとした基調講演も行われ、その後参加者は3つのグループに分かれてワークショップを実施した。
台湾の「デジタル変革力」と「持続可能な変革力」が強み

山下教授による基調講演
山下教授は講演冒頭、バックキャスティングの観点から持続可能な観光地域づくりの目的について語り始めた。教授によれば、その目的は「住民の幸福度の達成」であり、それを実現するための手段が「デジタル変革(DX)」と「SDGsの達成」だという。
山下教授は具体的な数値を示しながら、台湾と日本の各種世界ランキングを比較。世界幸福度(台湾27位/日本55位)、世界デジタル競争力(台湾9位/日本31位)、スマートシティインデックス(台北23位/東京108位/大阪99位)、SDGs達成度(4位相当/日本19位)など、ほとんどの指標で台湾が日本を上回っていることを指摘。これらの指標の高い相関性と台湾の優位性を示しつつ、すべての指標で上位を占めているデンマーク・フィンランド・スウェーデンが台湾・日本両国の目指すべきモデルであると述べた。
この指標確認により「デジタル変革力(DX)」と「持続可能な変革力」における台湾の優位性を示し、台湾としてすでに取り組んでいるデジタル変革(DX)と持続可能な変革を基盤として観光戦略を推進することの有効性について説明した。
コロナ前水準を超えた日本、回復途上の台湾

山下教授はインバウンド実績の日台比較にも言及。日本がコロナ禍前の水準をインバウンド数(115.6%)・消費額(169.4%)ともに大きく超えているのに対し、台湾のインバウンド数が2019年比66.2%程度に止まり回復できていない状況を共有した。この状況は観光庁のプレスリリースでも「台湾への入境者数はパンデミック前と比べて依然として約400万人少ない状況」と指摘されている。
国際的な観光競争力を示す国際観光開発指標ランキングについても言及し、日本が2011年の22位から2021年には1位へと急上昇した背景には、2016年に安倍内閣が策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」があったと説明。日本が観光後進国としての謙虚な認識から出発し、「やられていない当たり前のこと」を整備するとともに、観光商品・サービスの高付加価値化を進めてきた経緯を説明した。
持続可能な観光地域づくりの要は「地域住民」
山下教授は持続可能な観光地域づくりについて、「地域住民がその中核となり、その地域がどうありたいか(Vision)を明確化し、ビジョンを共有しながらその実現に向け具体的に施策を策定していくことがとても大切」と強調した。
この考え方はスウェーデン発祥のバックキャスティング手法に基づくものであり、「経験と勘に頼るだけではなく、客観的な数値指標・データ分析を重視したEBPM(証拠に基づく政策立案)に基づく戦略を策定することが激変する外部環境の中でより重要になってきている」と指摘。また、ビジョンを共有した戦略推進が「地域に対する誇り・愛着となりCivic Pride(市民の誇り)に繋がる」とし、地域の歓迎力・おもてなし力の強化につながるとの考えを示した。
持続可能な観光地域づくりのモデルとしては、英国ニューフォレスト市発祥の「VICEモデル」を紹介。これは訪問客(V)・地域産業(I)・コミュニティ(C)・環境(E)のバランスを考慮した「四方よし」のモデルであり、「環境に偏るのではなく、それぞれがバランスよく配慮され、次世代に繋げていくもの」と説明した。
欧米豪富裕層誘致と高付加価値化の重要性
円安・台湾元高の状況下で日本からの訪台インバウンド増加の難しさを指摘する一方、山下教授は欧米豪の富裕層をターゲットとした戦略の有効性を提言。日本が欧米豪富裕層の厳しい顧客ニーズに対応するために行った「徹底した受け入れ環境整備と高付加価値化」の事例として、黒川温泉の再生と富山県の楽土庵の取り組みを紹介した。
さらに、日本が強みとしてきた気候・自然・文化・食の「重要4要素」が台湾でも通用することを示しつつ、日本が積極的に進めてきたアドベンチャーツーリズムの高付加価値化が果たす役割や、高い地域経済波及効果、国立公園との親和性を具体的に説明。台湾でのアドベンチャーツーリズム推進を推奨した。
オーバーツーリズム対策と「台湾プロミス」の提言
講演の後半では、台湾の阿里山や九份で発生しているオーバーツーリズムへの対応策として、「レスポンシブルツーリズム(責任ある観光)」の推進を提言。観光客が観光地の自然・文化・人を尊重し責任を持つことの重要性を説明した。
具体例として、フィンランドの「サスティナブルフィンランド」やニュージーランドの「ティアキプロミス」の取り組みを紹介。台湾も観光客の観光地における行動規範を約束事として「台湾プロミス」を世界に打ち出すことの重要性を強調し、その推進を推奨した。
産官学連携で観光の未来図を描く
このフォーラムには山下教授とKeenan氏の2名の国際講演者に加え、台湾のメディア、景勝地、宿泊施設、旅行会社、デザインなど多岐にわたる分野から13名の代表者も参加。地域文化、デジタル技術、国際マーケティングといったテーマについて専門的な見解を提供し、分野を超えた連携と革新的な思考の促進を図った。
フォーラムの締めくくりに陳玉秀長官は、「今日が会議の終わりではなく、台湾観光の新たな未来へのスタート地点」であると述べ、観光庁が今回の収穫を胸に、台湾観光の明日に向けて努力していくとの決意を表明した。
山下教授も最後に「今後の日本の課題も示しつつ、今後の台湾の持続可能な観光戦略の成功を期待」して基調講演を締めくくった。