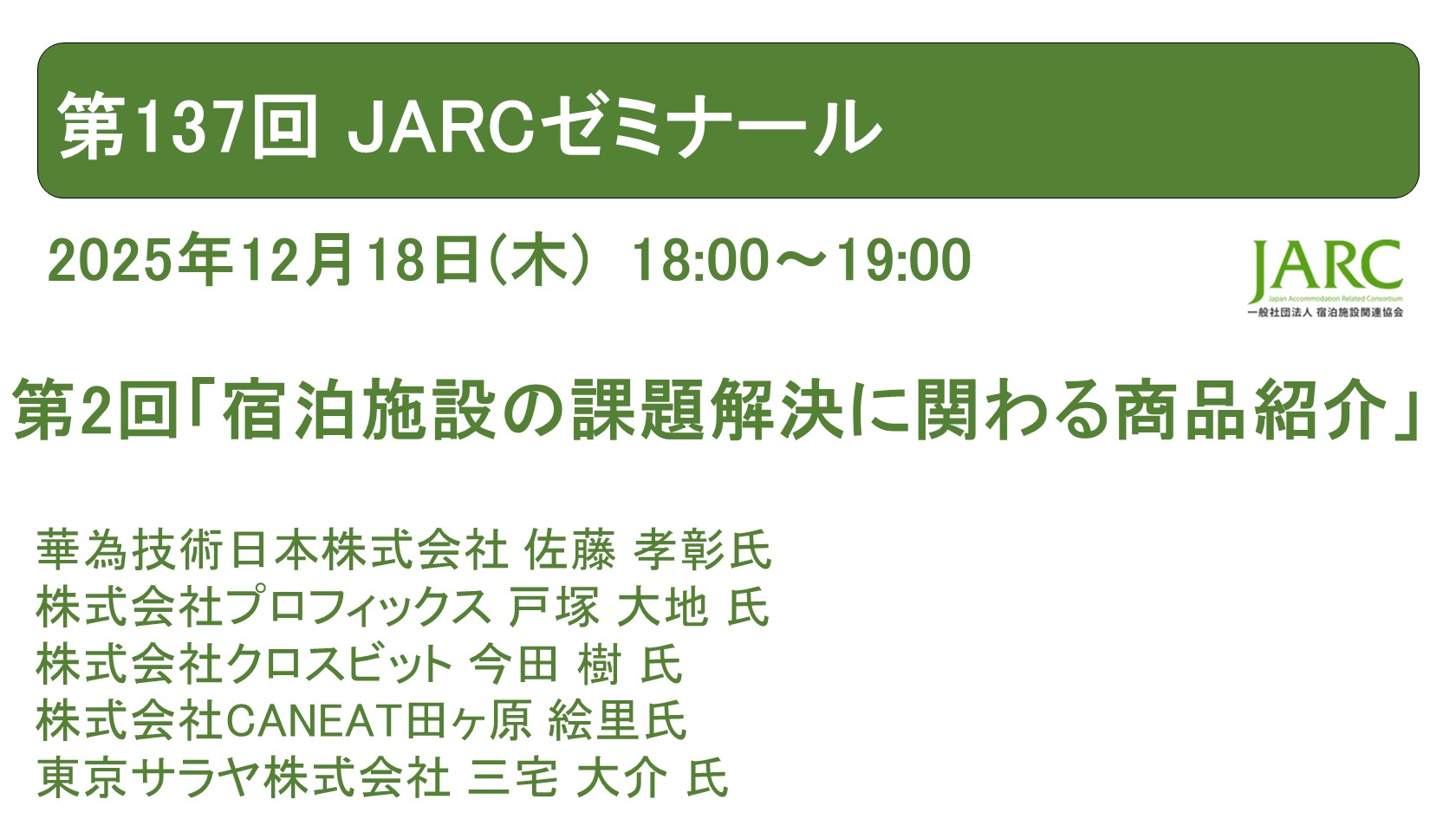竹内美樹の口福のおすそわけ
前号で、北九州のうどんについて書いていたら、他のうどんも食べたくなってしまった。筆者はそば派だが、稲庭うどんは好き♪ 舌触りが滑らかで、つるんとした喉越しなのに、コシがある。コシが生まれるのは、その製法が「手延べ」だから。製法の詳細については別の機会に譲るが、3~4日もかけて作り上げる麺は中心部に芯が通り、しっかりと強く仕上がる。稲庭一辺倒だった筆者だが、香川県で本場の讃岐うどんを食して考えを改めた。讃岐は「手打ち」だから麺を切るのだが、エッジが立ってるじゃないか! 麺の角が感じられるほど切り口が鋭く、驚きの歯応え。
さて、そんな筆者に新たなうどんとの出会いが。江戸時代の町並みを再現し、「鬼平犯科帳」の世界観が楽しめると話題の、東北自動車道上り線にある「羽生パーキングエリア」に立ち寄った際購入した「鬼ひも川」を食してビックリ! 明治27(1894)年創業、群馬県の「花山うどん」2代目が大正時代に考案した、鬼のように幅が広いうどんだ。実は昭和30年代まで販売されていたが、その後製造中止に。それを現5代目が復刻させたのだという。
乾麺の状態で幅3センチメートル。くっつき防止のため、ゆでる際は鍋に1枚ずつ入れなければいけない。ゆで上がりの幅は何と5センチメートル! だが、ゆで時間は意外と短い。つまり薄いのだ。ベストな食感を生み出せるよう、1.52~1.55ミリメートルの薄さに製麺しているという。ちゅるちゅる、もっちり、シコシコの全てがそろい、ベリウマ♪
同社のある館林市は、水はけの良い肥沃(ひよく)な大地と赤城山の伏流水に恵まれ、「上州空っ風」とも呼ばれる赤城颪(あかぎおろし)が吹くことで小麦の穂が強くなるため、昔から小麦の名産地だった。そんな地域性だけでなく、例えば天日干しと同じ環境を再現すべく20年もかけて研究したり、乾燥させては生麺に戻すという特殊な工程を何度も繰り返すなど、独自の製法を追求してきたからこそ、全国のご当地うどんが集結した大イベント「うどん天下一決定戦」で、2013年から3連覇を果たせたのだろう。
先日、日本橋店を訪れてみた。決定戦で提供された看板メニューの「鬼釜」と、日本橋店限定の「海老(えび)天ぷら小釜飯」とざるのセットをシェア。「鬼釜」は冷たい鬼ひも川の上に、群馬県産上州麦豚や温泉玉子などが盛られ、濃い目のタレをかけていただく。館林が発祥地とされる昔話「分福(ぶんぶく)茶釜」にちなみ、タヌキの器で提供されるのがユニーク。ざるは奇麗に折り畳んだ鬼ひも川に、カツオ節とサバ節のハーモニーが絶妙な「伝承つゆ」と、やや甘めで濃厚な「胡麻(ごま)みそつゆ」がつく。うどん屋ならではのだしで、一つずつ釜で炊いたご飯に、えび天や、水分量を減らし天ぷら専用に育てたマイタケの天ぷらなどがのる。
お食事処は群馬2店舗、東京4店舗。おいしいうどんを提供し続けるために、これ以上多店舗展開はしないようだ。こだわりのうどんを求める人々で、また行列が増えるに違いない。
※宿泊料飲施設ジャーナリスト。数多くの取材経験を生かし、旅館・ホテル、レストランのプロデュースやメニュー開発、ホスピタリティ研修なども手掛ける。