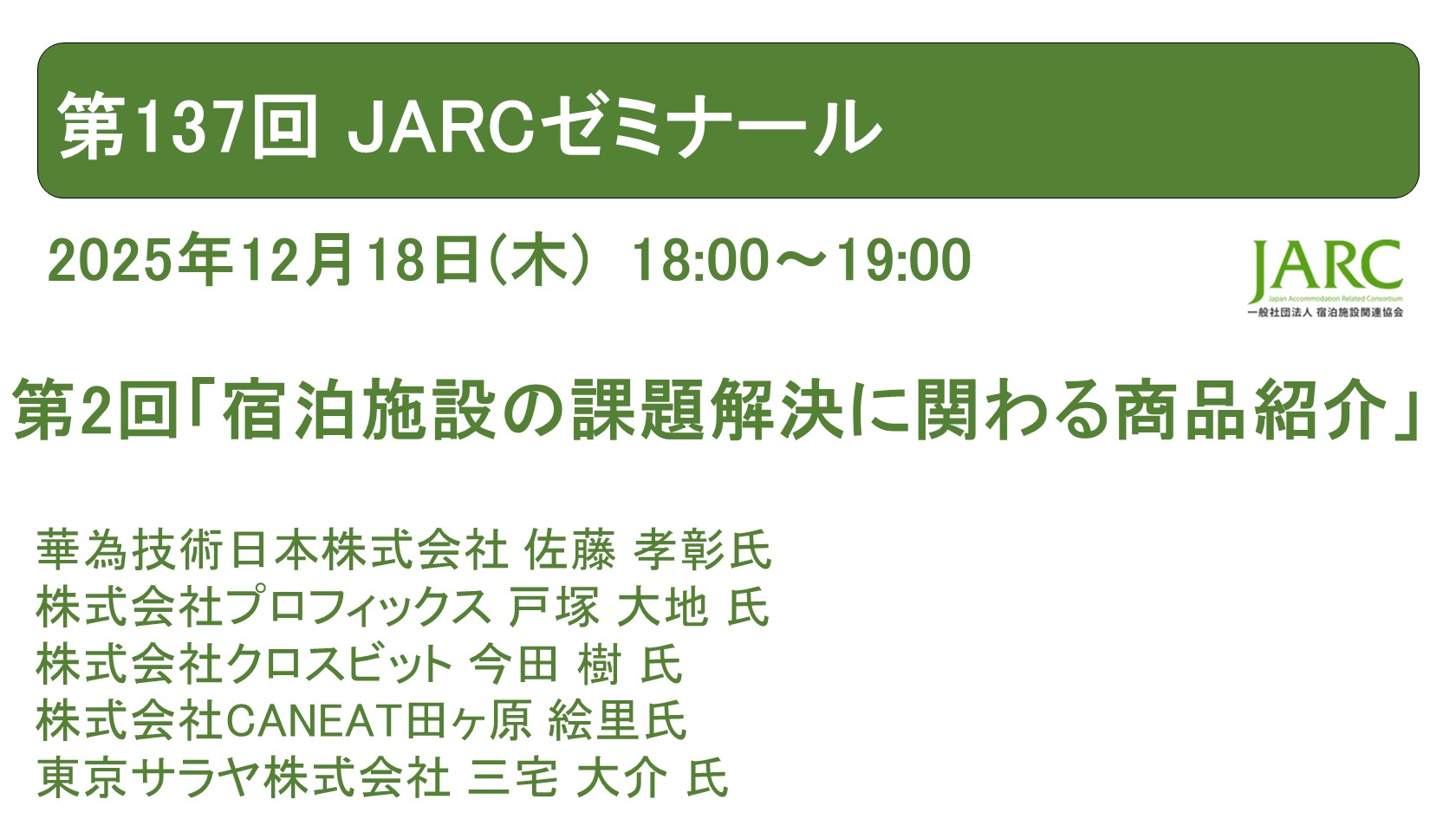竹内美樹の口福のおすそわけ
先日名古屋で、名物の「ひつまぶし」をいただくことに。妹から「あつた蓬莱軒」がおいしいと聞いた。諸説ある中、ひつまぶし発祥の店とされる人気店だ。スケジュールがタイトだから、予約せねばとトライしたが、あえなく撃沈。他を探して最終的に選んだのが「ひつまぶし稲生(いのう) 一号線豊明前後店」。名古屋の安くておいしいひつまぶしランキングで、常に上位に入っている系列店だ。
ここでちょっとうんちく。昔は天然ウナギを使っていたが、太くて大きいウナギは硬いためお客さまには出せず、焼いて刻んで賄いにしたという、ひつまぶし発祥説もある。
明治6年創業蓬莱軒発祥説では、うな丼の出前が増え、陶器の丼が割れることが多く困っていたが、女中頭が割れない木のおひつを使うことを思いついたのがキッカケだという。数人分をおひつに詰めたところ、今度はウナギだけが先になくなってしまう事例が増えたため、ウナギを細かく刻んでおひつの中でご飯に混ぜる「櫃(ひつ)まぶし」が誕生、締めの食事として所望されだし茶漬けにしたという説だ。
ちなみに、「ひつまぶし」は「あつた蓬莱軒」の登録商標だが、後発的に料理を指す一般名称となっており、料理を提供する際に使用しても商標権の侵害とはならないそうだ。2005年の「愛・地球博」の際、ひつまぶしが名古屋メシとして話題に上ると、4代目女将が「広まってくれれば」と、皆が名称を使うのを快諾したという逸話も残る。
さて、「稲生」に話を戻そう。大の白焼き好きな筆者、久々に「地焼き」の白焼きで一杯♪ 外カリッカリの中ふわっトロ、じんわり染み出た脂と相まって、衝撃的なうまさにひっくり返りそう! 江戸っ子だから、ウナギは蒸すのが当たり前と思ってきたが、炭火で焼くだけの地焼きって、こんなにおいしかったっけ?
この際だからと、ひつまぶしは全員「上」を注文。違いを店員さんに伺ったところ、並が半匹、上が4分の3、特上が1匹分という量の違いとのこと。…そういえば、ここまでひつまぶしの食べ方に触れていなかった。ひつまぶしは、3度おいしいといわれる。しゃもじがついていて、おひつからお茶碗によそう。1杯目はそのままウナギのおいしさを味わい、2杯目はネギやワサビなど薬味を散らしまぶしていただき、3杯目はだしをかけてお茶漬けとして楽しむのが作法。
木製のおひつのふたを開けると、細く切れたうなぎがビッシリ並んでいる。愛知県を含む東海地方名産「たまり醤油(しょうゆ)」の深い味わいがタレの決め手だ。「食通の方にもご満足いただけるように」と辛口からスタートさせ、試行錯誤を重ねて甘みを追求したという自信作だそう。お茶碗によそって口に運べば、あぁ、口福♪ だしをかければ、タレとうなぎの脂が溶け出した、得も言われぬ美味なスープが、怒涛(どとう)のように押し寄せる。
すっかりとりこになってしまい、東京で地焼きのひつまぶしが食せる店を、血眼になって探し回る今日この頃だ。また食べたい!
※宿泊料飲施設ジャーナリスト。数多くの取材経験を生かし、旅館・ホテル、レストランのプロデュースやメニュー開発、ホスピタリティ研修なども手掛ける。