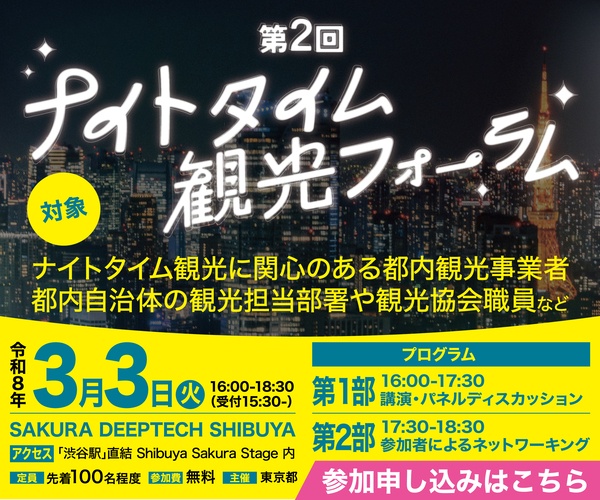2026年版『ミシュランガイド東京』が発表された。総計526軒が掲載され、星を獲得した店舗は三つ星12軒、二つ星26軒、一つ星122軒の合計160軒に達した。さらに、ビブグルマンとして価格以上の満足を提供する店舗が114軒紹介されており、高級からカジュアルまで幅広い層の食体験を網羅している。
今回の特徴として、三つ星が1軒加わり合計12軒となり、新規昇格によって層の厚みがさらに増した。加えて、一つ星の新規掲載11軒や二つ星への昇格3軒など、若手や新興勢力の活躍も目立ち、東京の食文化を一層多彩にしている。日本料理やすしのみならず、フランス料理やイタリア料理、さらには現代的なフュージョン系も評価対象となり、食文化の多様性が「東京らしさ」を示す重要な要素となっている。
世界的に見ても、東京の星付き店舗数は突出している。最新データで都市別に比較すると、パリは三つ星10軒・二つ星17軒・一つ星106軒で計133軒、ニューヨークは三つ星5軒・二つ星13軒・一つ星53軒で計71軒にとどまる。その他、ロンドンや大阪も上位都市に名を連ねるが、総数では東京が群を抜き、世界一の美食都市の地位を揺るぎないものとしている。
2020年から導入された「グリーンスター」の広がりも注目したい。環境負荷の低減や地域食材の活用、持続可能な生産者との共生を評価するこの仕組みでは、東京でも13軒が認定されている。星の有無にかかわらず、環境配慮やサステナビリティへの姿勢を示すことは、世界的な観光トレンドとも合致し、新しい魅力資源になると期待される。
この優位性をいかに観光消費につなげるかが、次の戦略課題となる。従来、東京のミシュラン星付き店は「予約が取れない」ことがブランド価値の一部でもあった。しかし近年は、訪日客の増加に伴い、予約代行やコンシェルジュサービスが隆盛してきている。特に富裕層向け旅行会社やラグジュアリーホテルでは、専用の予約枠や代行サービスを組み込む動きが広がっており、新たな付加価値につながっている。
また、ビブグルマンの掲載が示すように、東京の食は必ずしも高額店だけではない。下町の居酒屋や地域密着型のレストランも観光資源として潜在性がある。こうした中間層向け店舗の国際的発信を強化することで、訪日客の滞在中の食費を底上げし、裾野の広い消費拡大につなげられるはずだ。
今後、(1)星付き店を核とした「美食観光ルート」展開、(2)予約代行や体験型プラットフォームの加速、(3)ビブグルマンやグリーンスターの活用によるサステナブルな食体験の訴求などが進んでいくだろう。東京が世界に誇る食文化の厚みをもっと活用し、観光消費へと転換する仕組みづくりこそが期待される。
世界一の星数を誇る東京のブランディングにおいて「食の都」としてのメッセージ性はまだ弱いように感じる。予約の難しさを克服し、星付きからビブグルマン、そしてグリーンスターまで広がる食体験を有機的に結びつけることが、観光立国日本の強力な武器となるだろう。
(地域ブランディング研究所代表取締役)