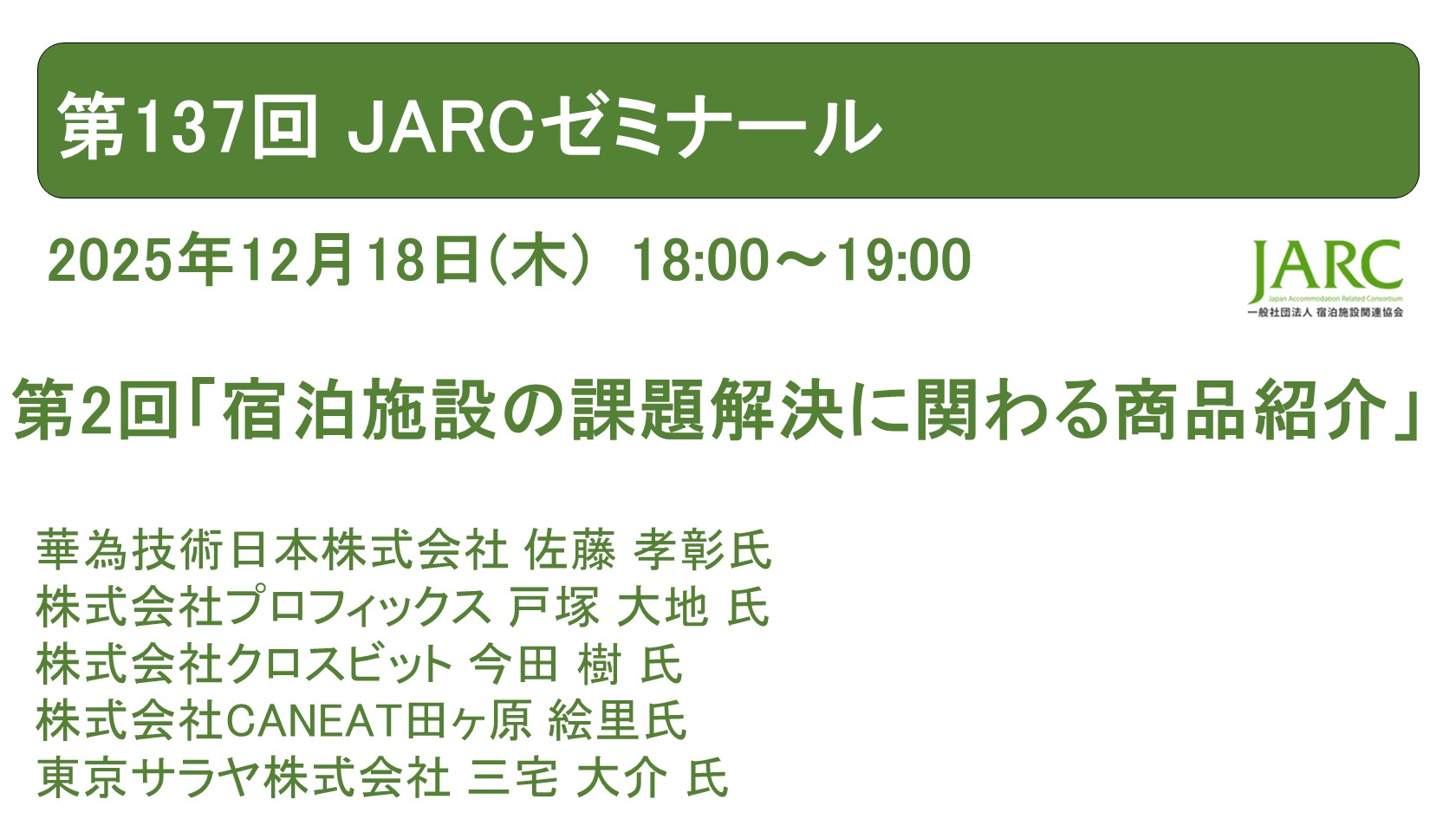会合の様子
宿泊税対応対策協議会(事務局:宿泊施設関連協会=JARC)は9月30日、全国旅館会館2階のJARC事務局で「第1回『宿泊税手引き書』に向けたガイドラインの作成会議」を開いた。USEN-ALMEX、ナバック、バリューコマース、電算インフォメーション、ネットシスジャパン、タップ、新日本コンピューターサービスの各社から担当者が出席。議事進行は、グローバルツーリズム経営研究所の永山久徳氏が務めた。
自治体ごとに異なる宿泊税制度、システム対応に課題山積
会議では、レジャーホテルから旅館まで、様々な宿泊施設に関わるPMS(Property Management System)ベンダー各社から、宿泊税対応の現状と課題について詳細な報告があった。特に自治体ごとに異なる制度設計や曖昧な定義が、システム開発の大きな障壁となっている実態が浮き彫りになった。
レジャーホテルを手掛ける企業からは「レジャーホテル事業では、休憩後や宿泊後の延長利用が一般的です。しかし、これらの『日をまたぐ長時間滞在』を含めた宿泊の定義や課税対象の範囲が自治体によってまちまちで、例えば北海道のように延長利用も課税対象となる場合があります」との報告があった。
さらに「弊社のシステムは自動精算が前提であり、人手を介さないため、課金は自動処理が必須です。正確な課金のためには、『休憩が宿泊に切り替わる瞬間』の厳密なアルゴリズム実装が不可欠です」と指摘。根本的な解決には「行政による『宿泊』の明確な時間基準(例:6時間以上)の設定が必要であり、それが決まればシステムへの実装が可能になります」と訴えた。
複雑な料金判定と二重課税の問題
参加企業からは、宿泊税の課税対象範囲についても多くの課題が指摘された。特に食事付きプランにおける料金区分の曖昧さが問題視された。
「旅館では宿泊料金が食事代込みの場合、宿泊客から見ると、『宿泊税100円の根拠』が不透明になり疑問を抱かれがちです」との声があり、「食事代込みの料金体系では、宿泊客は宿泊代と料理代の内訳がわからず、宿泊税の根拠が不明瞭になります。旅館側が18,000円の総額のうち宿泊代を意図的に免税ライン以下に抑え、料理代を高く設定すれば、宿泊税の課税を逃れることが可能です」と課税の公平性にも疑問が呈された。
また、北海道における宿泊税の二重課税の複雑さも議論された。「北海道では、道税と市町村税が併用課税されていますが、この納付方法が自治体によって大きく異なります」と説明があり、「道と市へ個別に納付を求められるケースがあり、小規模な町村では道へ一括納付といったように、ホテルの所在地によって納税先が異なるのが現状です」と地域ごとの対応の煩雑さが報告された。
「北海道では、道税と市町村税が併用されており、納付先や課税方式が自治体で異なるという複雑な状況です。例えば札幌市のように両税がハイブリッド型になっているほか、市町村が道に代行納付する場合と、施設がそれぞれに納付するよう分けられる場合があります」との説明もあった。
課税免除規定の複雑さと現場の負担
宿泊税の免除規定についても、システム対応と運用の両面から課題が挙げられた。
「旅館では対面で子供の人数やスポーツ団体など、課税対象外の情報を把握できます。しかし、レジャーホテルではフロントでの対面が少なく、居住者確認や利用人数の正確な把握が極めて困難です」との声があり、非対面サービスの増加と免税判断の難しさが指摘された。
また「宿泊税には、『県が後援するスポーツ団体は除外』『民間大会は対象』など、複雑な免除規定が今後導入される可能性があります。納付時の必要書類も自治体ごとに異なるのが実情です」という懸念も示された。
免除規定の複雑化による現場の負担増も問題視された。「宿泊税に地域住民の除外や県外にいる家族といった免除規定が追加されると、システムで個別の除外設定をする手間が増大します。さらに、証明書の提示など対面での確認フローが必要になると、現場の負担が膨らみます」との訴えがあった。
宿泊税のシステム実装に関する提案
会議では、こうした課題を解決するための具体的な提案も多く出された。
「システム対応の簡素化には、『100円未満切り捨てなのか切り上げなのか』のような統一ルールがガイドラインとして示されることが最も有効です」との意見や、「施設側は総額表示(入湯税・宿泊税を含む)であれば税の徴収も効率的になります。現状、別途徴収することで、フロントでの説明や徴収の手間が増え、時間的な無駄が生じています」との声があった。
最も理想的な徴収方法として「OTA(オンライン旅行会社)が宿泊税を一括徴収すること」が挙げられた。「OTAが宿泊施設の所在地や税率を判断し、徴収した税を各自治体に配分すれば、宿泊施設での徴収ミスや手間がなくなります」という提案には、多くの企業が賛同した。
また「宿泊税は、都道府県が一括で徴収すべきです。施設は県にのみ納付し、県内での市町村への配分は県に任せるべきです。また、定額制に複雑な例外ルールを付加するくらいであれば、いっそ定率制にすべきです。これにより、宿泊施設の納付帳票が一本化され、システム対応が大幅に簡素化されます」という、制度設計に関わる提言も示された。
行政の対応改善を求める声
参加企業からは、行政側の対応改善を求める声も相次いだ。特に情報提供や問い合わせ対応に関する課題が多く挙げられた。
「行政への問い合わせでは大きな課題があります。それは担当者によって回答や解釈が異なったり、時間が経つと『言い分が変わる』ケースが頻繁にある点です」との指摘があり、「一度の問い合わせでAという回答を得ても、後日Bに変わったり、電話の最中に担当者間で意見の食い違いが生じることもあります」と行政側の統一見解の欠如に対する不満が表明された。
さらに「自治体の議会で可決されても、総務省の同意を得るプロセスが遅延または停止するケースが複数見られます。例えば京都では、課税額が『高すぎる』と指摘され、最終決定が出ないまま進行が止まった事例があります」と、制度導入プロセスの不透明さによるシステム開発の遅延も課題として挙げられた。
今後の進め方
会議の最後には、今後の取り組みについて議論された。「行政側にはこの非効率性を理解いただき、システム側にとって最も負担の少ない標準的な課税パターンを採用していただくことが重要です」との意見が出され、「複雑な運用は、結果的に宿泊施設様のコストと労力が増大し、納得を得られなくなる原因となります」と訴えた。
具体的なアクションとして、「行政への『統一質問状』を作成し、『PMSの標準対応範囲』を提示した上で、そこから外れる特例を自治体に確認したい」という提案がなされた。
今後の会議は10月15日と28日に予定されており、2回目では「これまでの意見が現場に与える影響や既に発生している事例の明確化」や「理想的な制度設計について検討」、「PMS標準対応範囲の提案」などが議題となる。3回目では提案書の作成が行われる予定だ。
PMSベンダー各社が直面する宿泊税対応の課題は、7月29日に開催された意見交換会でも指摘されていた。当時も「自治体ごとに異なる宿泊税の制度設計が開発の非効率を生み出している」「各自治体から発行される手引き書がフォーマットや記載内容でバラバラであるため、情報が標準化されておらずシステムへの落とし込みが困難だ」など、類似の課題が挙げられていた。
今回の会議では、より具体的な事例や提案が示され、宿泊税制度の標準化に向けた取り組みが本格化している。国内各地で宿泊税導入が検討される中、システム対応の効率化は喫緊の課題となっている。
【kankokeizai.com 編集長 江口英一】