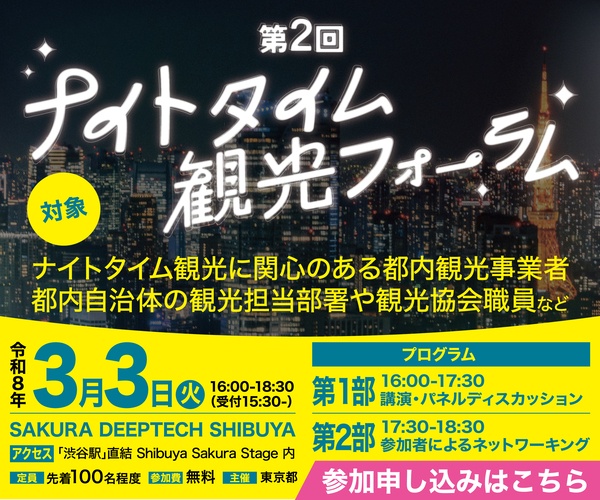有本隆哉氏
0.宮島における高級ホテル誘致構想に見る観光政策の問題点
私は、厳島神社で知られる宮島で、創業400年の宿を営んでいる。ある日、廿日市市が突如、宮島の包ヶ浦自然公園に高級ホテルを誘致する構想を発表した。この話は、宿泊事業者のみならず、土産店をはじめとする観光関連業者や地域住民にとっても、まさに寝耳に水であった。詳細を尋ねても、市から返ってくる回答は「国の方でも『今後はインバウンド富裕層の誘致が大事であり、我が国においてはそのための高級な宿泊施設が足りない』と言っている。こうした中、包ヶ浦自然公園が観光庁の『上質な宿泊施設の開発促進事業』に採択された。これを機に高級ホテルの誘致を図り、インバウンド富裕層を取り込み、宮島、そして廿日市市の発展を図りたい」ということであった。
私たちが懸念を示したのは、高級ホテルの開業により顧客を奪われ、売上や利益が減少するというような狭量な理由ではなかった。むしろ、宮島にふさわしく、世界的にブランド力を有する宿泊施設が開業すれば、宮島全体のブランド価値が高まることは十分に理解していた。しかし私たちが疑問視したのは、オープン以来、子供たちにとっては「遠足といえば包ヶ浦」と言われるほど地域住民に長年親しまれてきた包ヶ浦自然公園を、十分な議論もなく拙速に開発対象としてしまってよいのか、という点であった。本来であれば、「宮島の価値を将来にわたってどう守り続けるか」という大きなビジョンのもとで、包ヶ浦自然公園の活用を位置づけるべきであり、仮にその結果として高級ホテル誘致が選ばれるのであれば、私たちも協力し、地域の発展に取り組む覚悟があった。しかし現実には、そのような段階的かつ慎重な議論は行われず、地域と行政(廿日市市)との認識の齟齬は深まり、最終的には反対運動にまで発展するに至ってしまった。
観光が注目を集めるのは望ましいことであるが、「観光とは何のためにあるのか」という本質的な問いは常に意識されなければならない。観光の名のもとに、かえって地域の価値が損なわれるような事態が生じては、本末転倒である。具体的な事象は異なるものの、観光が目的化してしまっている事例は全国各地で数多く見られる。本稿では、観光政策の問題点を指摘するとともに、「観光を通じた持続可能な地域づくり」のあるべき姿を考察する。
1.観光は「目的」ではなく、持続可能な地域づくりのための「手段」
21世紀に入り、観光は政権の枠を超えて一貫して国の重要施策とされてきた。政府の各種政策に対しては、メディアが批判的な論調を示すことも多いが、観光に関しては、オーバーツーリズムなど一部の論点を除けば、総じて肯定的な姿勢が見られる。現在では、政治、行政、さらには民間に至るまで、広く観光に熱心に取り組んでいる。一つの成果指標である訪日外国人旅行者数は、21世紀初頭には500万人未満であったが、今では4,000万人に迫る勢いであり、こうした成果は官民を挙げた関係者の努力の賜物であることは間違いない。
しかし、ここで立ち止まりたいのは、「我々は何のために観光に取り組むのか」という本質的な問いである。観光が注目を集め始めた当初から、経済成長の新たなエンジン、地域活性化の切り札、ソフトパワーの強化など、さまざまな目的が掲げられてきたが、近年は「地域」という文脈の色合いが一層強まっている。実際、2023年に閣議決定された第4次観光立国推進基本計画においても、「観光による持続可能な地域づくり」が最重要課題として掲げられている。しかし、テレビや新聞など主要メディアにおいては、観光客数の増加といった「量」や、富裕層誘致・消費額といった「質」に関する報道が多い一方で、観光が地域住民を含む地域社会にもたらした恩恵という視点からの報道は、極めて稀である。実際、いわゆる「インバウンドバブル」と称されるほど訪日需要は盛況を呈しているが、その一方で、地方の駅前にはシャッター街が残り、温泉街には廃屋が目立つようになっている。加えて、祭りや伝統芸能、歴史的建造物、街並み、自然といった、これまで地域が大切に守り継いできた固有の価値も、次第に失われつつある。このような現状は、「観光を通じた持続可能な地域づくり」が、いまだ実現の途上にあることを如実に示している。本来は地域課題を解決するための「手段」であったはずの観光、特に誘客活動が、いつしか「目的」そのものと化してしまっている。オーバーツーリズムは、まさにその典型である。プロモーションに偏重した取組ばかりに注力し、観光を地域社会の維持・発展へとつなげる仕組みを築けなければ、観光は地域住民にとって単なる迷惑とすら受け取られかねない。
官民問わず、観光に従事する全ての主体は、「観光は『目的』ではなく『手段』である」ということを改めて認識すべきである。この原理原則は、いかなる状況においても決して忘れてはならない。補助金の設計、宿泊税やふるさと納税の使途といった政策判断において、この視点が欠落すれば、「地域外の事業者に資金が流出し、そのまま消えてしまった」というような、本末転倒な結果を招きかねない。そして、地域には何も残らないという事態が現実のものとなってしまう。
「観光を通じた持続可能な地域づくり」を実現するために、まず何よりも重要なのは、地域社会が抱える課題を的確に把握することである。その上で、観光をいかに活用して課題解決に結びつけるか、その道筋を明確に描く必要がある。なお、地域の課題に対して観光が必ずしも必要でない場合には、無理に観光に取り組むべきではない。現実には、「何の課題を解決するために観光を行うのか」という根本的なビジョンが欠如している地域が、依然として少なくないのではないだろうか。冒頭で紹介した宮島の事例も、まさにその典型である。宮島に暮らし、事業を営む者として、先人から受け継いだ文化財、景観、自然環境を維持・保全し、次世代に引き継いでいくことが重要な課題であると認識している。しかしながら、そうした将来像が地域で共有されることなく、国や世間で富裕層誘致の必要性ばかりが強調されるなかで、いつの間にか「富裕層誘致」が自己目的化してしまった。その結果、「富裕層を呼び込むには高級ホテルが不可欠であり、今はそれがないから誘致しよう」という短絡的な議論へと陥ってしまっている。
話を富裕層の文脈に移すと、現在、観光庁では「地方における高付加価値なインバウンド観光地づくり」という取組が進められている。同庁のアクションプランでは、「持続可能な地域の実現や地域経済の活性化のために高付加価値旅行者(富裕層)を誘致する」と明確に示されている。ところが、選定された全国14のモデル地域のマスタープランを読む限り、多くの地域では、富裕層を顧客とする旅行会社にいかに旅行商品を売ってもらうかが主眼となっており、富裕層向け商談会への出展や、ファムトリップの開催といった施策が中心を占めている。残念ながら、最も重要な「持続可能な地域づくり」に向けて、高付加価値旅行者層の誘致をいかに活かすかという視点が、欠落しているように思えてならない。
話を戻すと、繰り返しになるが、あくまで観光の目的は「持続可能な地域づくり」である。地域ごとに課題は異なるので、一般論で語りつくすには限界があるが、例えば、地域の人口減少の食い止め・人口維持を目的に「稼げる産業」づくりをするために観光に取り組むというのも一つである。また、地域の伝統、文化、自然等の保全・継承のために「活用と保護の好循環」の仕組みづくりを構築するのも一つである。後者は、昨今、環境省や文化庁も積極的に推進していることである。この点、宿泊業界では、極めて示唆に富む取組が始まっている。宿は、歴史的にも地域に支えられ、また地域を支えてきた存在であり、昨今では、宿泊事業者の全国組織である全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会(以下「全旅連」という。)も、「宿を核とした地方創生の実現」を組織の主要方針の一つに掲げている。全旅連は、2025年夏より、全国5つの宿泊施設におい「”宿”サステナブルアクション」と称する新たな取組を開始した。この事業では、宿泊料金とは別に、宿泊客から任意の寄付金を募り、その寄付を地域固有の価値の維持・保全活動(例:自然環境の保護、景観の改善、歴史的建造物の保全、伝統芸能の継承、祭りの存続など)に充当することで、地域社会の持続可能性向上を図るものである。まさに「活用と保護の好循環」を体現する仕組みである。私は、この壮大な社会実験が良き成果を生み、日本各地に広がっていくことを心より期待している。
2.観光において必要なのは、民間ビジネスで行われている「当たり前」を一つ一つ忠実に行っていくこと
地域が抱える課題、そしてその課題解決にあたり観光をどのように活用するかは、それぞれの地域によって異なる。しかし、どの地域にも共通して言えるのは、観光を活用する以上、誘客は不可欠であるという点である。実は、この誘客こそが多くの地域にとって最大の難所であり、その考え方や手法を誤れば、最も重要な目的である「持続可能な地域づくり」には決してつながらない。
観光施策として何をなすべきかを、極めて単純なモデルに落とし込めば、以下のようなプロセスに整理できる。
(1)地域資源の棚卸しに加え、既存顧客や競合地の調査を通じて市場ニーズを把握し、さらに地域としての意思を掛け合わせることで、提供価値(ブランドコンセプト)とターゲットを導出する
(2)提供価値を基に、1)プロダクト(顧客に提供する宿、飲食店、体験コンテンツ、それらを組み合わせた旅行商品等)、2)プライス(顧客への販売価格)、3)プレイス(顧客が購買できる流通チャネル)、4)プロモーション(顧客に認知させ、購買させる活動)(「以下「4P」という。」を設計する
(3)顧客に実際の価値提供を行い、フィードバックを通じて提供価値・ターゲット・4Pの継続的見直しを行う
端的に言えば、これは民間ビジネスの世界で当然とされているプロセスを、一つひとつ丁寧に実行していくだけの話である。しかし、私たち宿泊事業者をはじめとする地域の観光関連事業者、さらには地域そのものが、かつて集客を旅行会社に依存していた歴史的背景もあり、このプロセスを十分に理解しないまま現在に至っているのが実情である。以下、自戒を込めつつ、地域が陥りやすい典型的な誤解について整理しておきたい。
第一の誤解は、「観光政策の主軸はプロモーションであるべき」という考えである。これは多くの地域、さらにはメディアや一般論においても頻繁に見受けられる。しかし、先に示したフレームに照らしても明らかなように、プロモーションは設計プロセスの一部に過ぎず、それ単体では短期的な売上向上には結びついたとしても、中長期的な持続可能な地域づくりに貢献していくような成果は望めない。本来は、提供価値やターゲット、プロダクトなどを正しく設計した上で、初めて有効に機能するものである。仮に地域の提供価値が市場のニーズと乖離していたり、訴求すべきターゲットが誤っていたりすれば、誘客が実現しないのは当然である。「うちの地域は良いものがあるが、宣伝が下手だ」といった声を耳にすることも多いが、実際にはプロモーション以前の設計段階に問題がある場合がほとんどである。
第二の誤解は、「顧客調査や販売戦略は旅行会社を通じて行えばよい」というものである。顧客調査が必要となると、多くの地域や観光事業者は、旅行会社(昨今は、とりわけ富裕層向け専門会社)やOTAにヒアリングを行おうとする。だが、そもそもそれらの事業者が、本当に地域のターゲット顧客を保有しているかどうかは、十分に検証されているだろうか。それを確認しないまま依存すれば、有効な一次情報は得られず、地域戦略そのものを誤るリスクさえ生じる。旅行会社からのヒアリングも一手法ではあるが、なぜ地域や観光関連事業者は、直接顧客の声を聞こうとしないのだろうか。特に、顧客との接点が最も多い宿泊事業者にとっては、その怠慢は大きな機会損失である。マーケティングにおいて最も価値あるのは一次情報であり、顧客の生の声を迅速に吸い上げ、政策や経営判断に反映する仕組みの構築が急務である。
販売戦略においても、旅行会社を前提とした商談会への出展やファムトリップの開催が多く見られるが、現代の消費者の大多数は、自ら情報を収集し、自ら予約を行う時代である。もちろん、BtoB戦略を全否定するものではない。たとえば、地域が設定するターゲット層が旅行会社を通じて予約する傾向にある場合や、大型施設が団体需要を必要とする場合には、旅行会社を活用する販売戦略は大いに意義がある。重要なのは、こうした前提を踏まえた上で、戦略として意図的に旅行会社を選択しているのかどうかである。
第三の誤解は、「ターゲットはインバウンドであるべき」という思い込みである。現在、多くの地域が当然のようにインバウンドを主要ターゲットとしている。しかし、世間でインバウンド需要が注目されているからといって、すべての地域がそれを追従すべき理由はない。観光の目的はあくまで地域の持続可能性を高めることであり、そのために必要な観光のあり方、そして適切なターゲットを、順を追って構想すべきである。そうすると自ずと国内客をターゲットに、さらに言うと、東京や大阪といった全国的な大都市ではなく、近隣の都市の顧客がターゲットになる、ということだって理論上は十分あり得るはずである。
また、ターゲットを「欧米豪」「アジア」「東京」など、地理的な区分だけで捉える例も依然として多く見られるが、これでは不十分である。もちろん地理的視点も重要な要素の一つではあるが、それに加えて、価値観、嗜好、所得、ライフスタイルといった心理・行動的属性も重視すべきである。こうした多面的な要素を考慮することで、4P(プロダクト、プライス、プレイス、プロモーション)の設計は大きく異なるものとなる。
本章ではやや断定的な表現も用いたが、その主張は決して的外れではない。なぜなら、ここで示した内容は、民間ビジネスの世界ではごく「当たり前」とされていることばかりだからである。観光が注目を集める一方で、「観光とは本来、民間事業である」という基本的な認識が、関係者の間で希薄になりつつあるのではないか。地域の持続可能性を高めるためには、観光をビジネスベースで「儲かるかどうか」という視点で捉えることが不可欠である。国や自治体は、この視点を踏まえて政策を構築すべきであり、そして何より、観光事業者一人ひとりが、持続的に利益を生むビジネスの実践者となる必要がある。
3.地域経営の視点の必要性
持続可能な地域づくりの実現には、宿泊事業者をはじめとする地域の観光関連事業者が、収益性のあるビジネスを継続的に行うことが不可欠である。そして、観光関連ビジネスは、地域資源という「資産」があってこそ成立することを忘れてはならない。すなわち、例えば宮島においては、文化財、景観、自然環境といった資源があるからこそ、国内外から多くの来訪者を惹きつけ、それによって観光関連事業者のビジネスが成り立っている。したがって、企業において設備資産への継続的投資が必要であるように、地域においても、価値を生み出す資産に対しては継続的な投資が求められる。
一方で、地域の価値を毀損する「負の資産」の存在にも十分な留意が必要である。例えば、景観を損なう電柱や、海辺に放置されたプレジャーボートなどがその例であるが、なかでも深刻なのは、空き家や、廃業した宿泊施設・飲食店などの廃屋であろう。特に、大型宿泊施設が廃業し、その建物が放置された場合、地域全体に与える負のインパクトは極めて大きい。たとえ周辺の事業者が懸命に経営努力を重ねていたとしても、隣接地に廃屋が生じれば、その努力は無に帰す可能性すらある。廃屋に新たな買い手が現れ、所有者との権利移行が円滑に行われ、再活用されるのが理想ではあるが、現実にはそのようなケースは稀である。また、第三者が撤去を試みても、建物の規模が大きいほど費用が膨らみ、撤去だけを目的とした事業には金融機関が融資に応じにくいのが実情である。このような背景を踏まえれば、廃屋の撤去や再生は、地域全体として取り組むべき課題であることは明らかである。
要するに、持続可能な地域づくりのためには、地域内の資産を適切に把握・評価し、価値を生む資産には継続的な投資を行い、価値を毀損する資産は除去または再生によって地域全体の価値を回復させていく必要がある。これこそが「地域を経営する」ということである。しかし残念ながら、我が国において、こうした本来あるべき地域経営が実践されている地域は、ごくわずかである。例えば、宿泊税は地域経営の有力な財源となり得るが、プロモーションなどに偏重して用いられている現状では、戦略的な経営判断とは言い難い。
4.地域経営の主体は誰であるべきか
前章で論じてきたように、観光をビジネスとして捉え、正の資産には積極的に投資し、負の資産については除去または再生を図るという地域経営の視点が極めて重要である。では、その地域経営の主体は、誰が担うべきなのだろうか。地域経営の必要性については、近年、国全体でも有識者を交えた議論が活発に行われており、「地域経営はDMOが担うべきである」とする声が強くなってきているように見受けられる。しかしながら、自身の拙い見識と、全国各地の宿泊事業者仲間の声に照らすと、こうした見解には一定の危うさがあることも指摘せざるを得ない。もちろん、DMOの中には、地域経営の責任を立派に果たしている組織も存在する。しかし、DMOであるという理由だけで、すべてのDMOに地域経営の能力が備わっていると断ずるのは、あまりにも乱暴な議論である。企業経営と同様、経営能力を欠く主体に運営を委ねれば、その地域は衰退の一途をたどるほかない。
DMOには、構造的に二つの大きな問題点があると考えられる。第一に、DMOの予算や人事は、自治体や地域の有力企業等と深く紐づいている場合が多い。その結果、たとえ優秀な経営者が存在していたとしても、外部のステークホルダーからの意向に翻弄され、結果として第2章で指摘したような罠に陥ってしまう可能性が高い。特に、「観光=プロモーションや商品造成の後、旅行会社を通じて販売するもの」とする短絡的な発想に、DMO自身も影響を受ける例が少なくない。実際、事業内容がプロモーションに偏重する傾向が見られ、仮に外部から専門人材を登用する場合も、旅行会社やOTA、広告代理店等の出身者が中心となっている例が多い。
第二に、DMOの多くは、従来の観光協会から看板を掛け替えるかたちで発足している。一般に、多くの地域における観光協会は、もともと地域内の観光案内所の運営、パンフレットや地図の制作・配布、ポスター掲出、ウェブサイトの運用、地域イベントの主催などが主たる業務であり、DMOに期待されるような地域全体を経営するという高度な戦略性を担うことは想定されていなかった。もちろん、DMOへの移行に際しては、予算面や組織体制の強化が図られることもあるが、それによって組織の本質が容易に変わるものではない。
いずれにせよ、地域経営は、経営能力を備えた主体が担うのが最も望ましく、それが自治体であれ、DMOであれ、あるいは個々の観光関連事業者であれ、主体の形態にはこだわるべきではない。ただ、私自身としては、宿泊事業者による地域経営の可能性を、あえて強調して伝えたい。地域の宿泊事業者は、創業時より当該地域において土地や建物といった大きな資産を有し、そこで事業を営んできた存在である。「宿は地域のショーケース」と言われるように、食、建築様式、設えなどに地域の特色を色濃く反映させており、取引先の多くも地域内に存在することから、地域経済の循環を支える牽引役としての機能も果たしている。このような背景から、宿泊事業者は地域が衰退すれば自らも共に衰退を余儀なくされる立場にあり、ある意味で地域に対する宿命を背負っているとも言える。実際に、一部の地域では、宿泊事業者が地域経営を担うに近い先進的な事例が生まれつつある。
北海道中標津町の市街地から車で約30分の場所に、養老牛温泉という温泉地が存在している。とはいえ、この温泉地には、いわゆる旅館や土産物店が軒を連ねているわけではない。かつては4~5軒の旅館が存在していたものの、その大半が廃業し、現在では「湯宿だいいち」という一軒の旅館のみが残されている。多くの温泉地では、廃業した宿泊施設の建物が放置され、地域の価値を毀損する「負の資産」と化しているのが実情である。これに対して養老牛温泉では、「湯宿だいいち」がそれらの建物をすべて買い取り、再生し、自館の施設として一体的に運営することで、自らの事業と地域価値の向上を両立させることに成功している。また、この地域では、宿泊業に限らず、酪農や林業などの分野においても深刻な人手不足が続いているが、当該旅館は自ら率先して日本語学校を誘致し、外国人留学生の受け入れを促進している。まさに、この一軒の宿が実践している取組こそ、持続可能な地域づくり、ひいては地域経営の一端を担うものと言っても過言ではない。
いずれにせよ、DMOを取り巻く環境には国の補助金が常に存在しており、その結果として、地域に対して何ら責任を負わないプレーヤーまでもが地域経営に参入しようとする事例が後を絶たないのが実情である。このような主体は、地域の持続可能性には関与せず、場当たり的な観光プロモーションやブランディングを繰り返した末に、結果として地域の価値を毀損する事態を招くことも少なくない。宿泊事業者に限らず、地域に根ざした主体を中核とし、地域づくりに責任を持ちうる組織の形成こそが、いま地域社会に強く求められているのではないだろうか。
5.最後に
私自身が宿の経営に携わる立場であることから、本稿の執筆にあたっては、どうしても宿泊事業者に期待を込めた筆致となっていることを自覚している。しかし、それは決して過剰な期待ではない。実際に、それだけのポテンシャルが地域の宿泊事業者には備わっており、言い換えれば、その潜在力を活かす責務が我々にはあると私は考えている。我々宿泊事業者は数年前のコロナ禍においては未曽有の危機に襲われた。その折には、政治・行政・金融機関、そして何より地域の方々の支援を受けることで、辛うじてこの危機を乗り越えることができた。このご恩を忘れることは決して許されず、今後、必ずやその恩に報いていかなければならない。その一つの形こそ、地域経営に対する責任を着実に果たしていくことに他ならないのではないか。
そのためには、各宿泊事業者が経営体力を強化し、宿泊業をより収益性の高い産業へと転換していくことが求められる。各事業者が、その実現に向けて日々最大限の努力を重ねているかと問われれば、依然として課題が残されていることも否定できない。また、宿泊事業者の業界団体である全旅連及び一般社団法人日本旅館協会は、業界の発展にとどまらず、地域全体の持続的な発展に資する活動に尽力すべきであろう。
宮島グランドホテル有もとの経営者として、また、両業界団体において役員を務める立場として、本稿で展開した自論を、まずは私自身が率先して実践していくことを、ここにお約束したい。

有本隆哉氏
【著者略歴】1966年10月21日生。1985年3月修道高等学校卒業。1995年2月有限会社エム・ジー・エイ入社、2024年3月同社代表取締役、有限会社大根屋代表取締役。2016年4月から2024年3月まで宮島旅館組合組合長。2019年5月からJTB協定旅館ホテル連盟広島県支部支部長、同連盟西日本支部連合会副会長、同連盟本部理事。2022年4月から日本旅館協会中国支部連合会会長、広島県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長。同年6月から日本旅館協会本部副会長。2023年4月から全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会副会長。