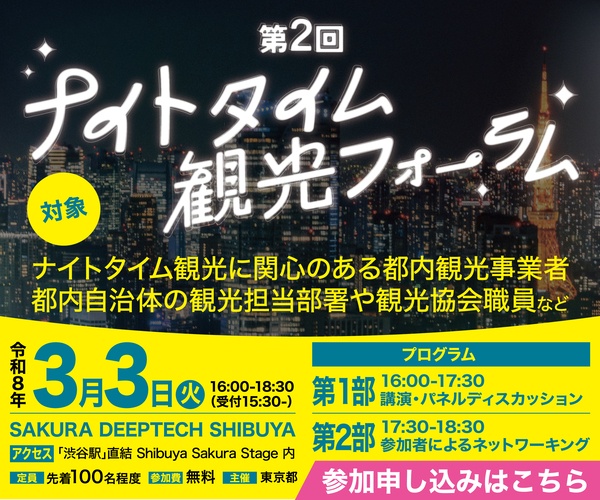福島創生シンポジウム
DCを通じた地域振興の本質を探る 観光プロが語る福島創生への道
日本旅館協会福島支部は9月10日、「ふくしまDCによる福島創生シンポジウム」を喜多方市の熱塩温泉山形屋で開いた。福島県、JR東日本、旅館関係者など100人以上が参加した。JR東日本執行役員東北本部長の高岡崇氏が「観光のチカラ~ふくしまDCと地域の観光振興~」と題して基調講演。続くパネルディスカッション「観光のプロたちがDCによる福島創生を語りつくす90min」では、パネリストとして福島県観光交流局局長の藤城良教氏、福島県観光物産協会理事長の守岡文浩氏、JR東日本東北本部マーケティング部長の新井貴之氏、2005福島県あいづDC推進協議会事務局長の吉田秀一氏、福島県旅館ホテル生活衛生同業組合企画戦略委員長の渡邉利生氏(=土湯温泉山水荘社長)、日本旅館協会福島県支部支部長の瓜生泰弘氏(=熱塩温泉山形屋社長)の6人が登壇。コーディネーターをびゅう會津会会長の平賀茂美氏(=会津東山温泉原瀧・今昔亭総支配人)が、アドバイザーをJR東日本執行役員東北本部長の高岡崇氏が務めた。
「観光は裾野の広い産業」 人口減少時代に挑む高岡本部長

JR東日本執行役員東北本部長の高岡崇氏による基調講演
基調講演では、高岡本部長が観光産業の持つ力や可能性について多角的に論じた。冒頭、東北新幹線全線運転再開を伝えるCMを紹介し、「観光と鉄道は人と人、場所と人をつなぐという点で深い関係がある」と語った。
高岡氏は人口減少時代の現状を直視した上で観光産業の優位性を強調。「人口は2050年までに東北地方では現在の3分の2にまで減少する。これは極めて正確性の高い推計値だ」と指摘し、深浦町のタクシーが町全体で1台しかないという実例を紹介。「定住人口に頼った産業振興には限界がある。発想を切り替えていく必要がある」と語った。
観光産業の強みについて、「定住人口だけでなく交流人口、関係人口を相手にできる」と説明。定住人口1人減少による経済損失(年間約135万円)を補うには、日帰り旅行者71人、宿泊旅行者21人、訪日外国人旅行者7人が必要だとデータを示した。また、観光産業は農業や漁業、製造業、流通業など多くの業種に波及効果をもたらす「裾野の広い産業」だと強調した。
訪日外国人の動向にも言及。2024年の訪日外国人数はすでにコロナ前を上回り、8兆円を超える消費をもたらしている一方で、東北地方への訪問は全体の1~2%にとどまっていると説明した。特に福島県を訪れる外国人観光客の分析では、コロナ前の2019年に5万6千人だった訪問者が2024年には14万人を超え、特に台湾からの観光客が全体の8割を占めていることを紹介した。
「台湾人旅行者の10人中9人は2回目以上の訪日。リピーター率が非常に高い」と説明。東北観光推進機構が毎年12月に台湾で開催している「日本東北游楽日」には10万人が来場し、JR職員の制服が人気を集めていることなども紹介した。
続いて、デスティネーションキャンペーン(DC)について「麻薬のようなものではない」と強調。「素材の磨き上げをするチャンスを作っているのがDC。地方自治体や地元観光関係者とJR6社が連携して観光資源の掘り起こし、磨き上げとJR6社の宣伝媒体を活用した集中宣伝送客を行う国内最大規模の観光キャンペーン」と説明した。
DCはプレDC、DC、アフターDCという3カ年の取り組みを通じてレガシーとして定着させるものであり、「単に口を開けていて観光客が来てくれる」といった考え方ではなく、「地域づくりのきっかけ、皆さんがチャレンジするフィールド」だと強調した。
最後に来年の福島DCについて触れ、「福島県誕生150年、福島第一原発事故から15年という節目の年。復興へのチャレンジをホープツーリズムと絡めて実感していただきたい」と述べた。また、プレDCで実施した取り組みとして、横断列車の運行や首都圏駅での物産展、発酵ツーリズムの推進なども紹介。「新しい観光素材の磨き上げは一朝一夕にできるものではないが、声かけや挨拶運動など今すぐできることもある。地域の機運を高めてほしい」と訴えた。
「一過性のイベントではなく、レガシーを残すDCに」 パネリスト6名が議論

パネルディスカッションでは、コーディネーターの平賀氏が「パネリストの皆様から福島DCに対する思いについてお話を伺いたい」と口火を切った。

最初に発言した吉田氏は、2005年の「あいづDC」について「過去の記録を塗り替える結果となった」と振り返った。「キャッチコピーは大胆に『あいづ』とした。市町村の枠を超えた広域的な資源と多彩な魅力を提供する戦略を打った」と説明。赤べこをモチーフにしたピンバッジやネクタイの作成、全国初となるご当地カラー(赤)の統一、キャンペーンソングの制作などを通じて「心を一つにする作戦」を展開したことを紹介した。
「DCは生半可なことではできない。本気になって本気になってやって初めて一歩前に進める」と強調した吉田氏は、「一人の力は小さくとも力を結集すれば、とんでもない力を発揮する。それが観光だ。子どもたち、孫たちの未来のために我々は今本気で足をかくべきだろう」と熱弁を振るった。

続いて渡邉氏は、2015年の第1回福島DCを振り返り「それをきっかけに福島の観光の流れが変わった」と述べた。当時、若旦那プロジェクトとして情報発信に取り組んだ経験から「口を開けて待っているだけでは絶対に恩恵は来ない。DCという特別な機会に何かチャレンジしてみたいという思いで始めたことが大きく広がった」と説明した。
2015年DCの反省として「終わった後に何か残ったかな、という思いがあった」と述べ、「DCはあくまでもきっかけ。何をブランディングして全国にその魅力を発信し、継続的にお客様が来る仕組みをどう作るか」が重要だと強調した。
また、今回のDCでは浜通りの魅力を全県の魅力として発信することが大事だと指摘。「今回のDCの主役は浜通り。浜通りの魅力を福島県全体の魅力として変換して、福島県の宿泊施設が浜通りの魅力も自分の施設の魅力に変換してお客様に伝えることが一番大事」と述べた。

渡邉氏
瓜生氏は「このDCはあくまできっかけ。レガシー化していくことが重要」と述べた上で、「春来たお客さんに秋もPRする。リピーター化してもらうことによって福島県全体のファン作りをしていく」と提案。また、福島県内の会津、中通り、浜通りの3つのエリアに「横串を刺す」ことの重要性を指摘し、「新幹線で来たお客さんを郡山と福島の乗降客を増やすことが大事。福島を活性化するためには、イベント列車で横串を刺す」と語った。
さらに「思いやり」をキーワードに観光を考える必要性を提案。「おもてなしは有料で一方通行だが、思いやりは無料で双方向。お客様も地域に対して思いやりを持ち、地域の方々も来訪者に思いやりを持って接する」という考え方を紹介した。

守岡氏は「JRがこれだけ力を入れて地元の関係者とともにやっていこうという最大のイベント。これを生かさない手はない」と強調。「準備の差、それぞれの思いの差」がDCの成果を左右すると指摘した。
具体的な取り組みとして、ホープツーリズムと中通り・会津を組み合わせた旅行商品開発や、様々なキャラクターグッズの開発を紹介。「丸っこい赤べこ」や「新幹線のソフビー」、ウルトラマンとコラボした「ウルトラマーカベコラ」など具体的な商品を提示しながら、「福島県のファンをいかに増やすか、再度何度も来てもらうためにはどうしていくか。それを皆様とともに考えていきたい」と述べた。

守岡氏
新井氏は「やはり地域が元気でなければ、当社も成り立っていかない」と述べ、東日本大震災後の列車運転再開時に「地域の皆様に歓迎していただいた」思い出を紹介。「我々の使命は、地域の皆様が元気になる一生懸命やっていただくことのお手伝いをしていくこと」と位置づけた。
JR東日本の取り組みとして、首都圏の駅での「産直市」など地産品紹介の拡大や、首都圏駅への宣伝物の大々的な掲出などを紹介。「やはり何を題材にして、どういった方をターゲットにしていくのか、何を見ればパッと福島だと分かっていただけるのか、そういったところも工夫しながら考えている」と述べた。
また、地域の観光事業者に対しては「来ていただいた方に福島の価値をお伝えしていくことが大事」と強調。「どんなに素晴らしい常磐物のおいしい魚だったとしても、何の説明もなければ『このお魚おいしいね』で終わってしまう。そこで一言添えていただくことで価値が伝わる」と具体的に提案した。

新井氏
藤城氏は「地域の宝を磨き上げて持続可能な観光それをレガシー化に向けて福島県の全員プレーで一致団結して取り組んでいきたい」と述べた。また、震災後の福島空港再建に取り組んだ経験から「皆さんの気持ちを本当にこれからどうさらにこのDCをきっかけに一体となってやっていくのか」という思いを強調した。
県の今後の取り組みとして「プレDCを踏まえて、これまでにない形で情報発信力を高める」「観光資源の掘り起こし、磨き上げのための観光有客促進支援事業補助金の継続」などを紹介。「各事業者が自分ファーストとしてこれを儲けていただきたい」との考えを示しつつ、「プライスダウン競争にしないでいただきたい」と付け加えた。

藤城氏
パネルディスカッションの最後に、アドバイザーの高岡氏は「皆様からお声に出ていた『このDCを一過性のものにしてはいけない』という言葉はとても大事」と評価。「DCはあくまできっかけであってDCが終わりじゃない。DCが目的じゃない。DCがスタートなんです」と強調した。
また「DCをきっかけに新たな魅力を作って需要を生み出して、それをブランド化していく」ことの重要性を指摘し、「単品でイメージを固定化していくことがキラーコンテンツになる秘訣」と助言。「常磐ものや発酵ツーリズムは広すぎるが、その中からキラーコンテンツとなる単品が生まれてくる過程にある。どんどん試行錯誤してみればいい」と述べた。

高岡氏
平賀氏は議論を総括し、「DCはあくまでもスタート。結果でもゴールでもない」「次世代、孫や子供に向けて、未来に向けた仕掛け作りをDCをきっかけにしてやりましょう」と締めくくった。
観光を通じた福島創生を目指す関係者の熱い思いと具体的な行動計画が共有されたシンポジウム。2026年春の本番に向け、地域の機運醸成と観光資源の磨き上げが進められる。

【kankokeizai.com 編集長 江口英一】