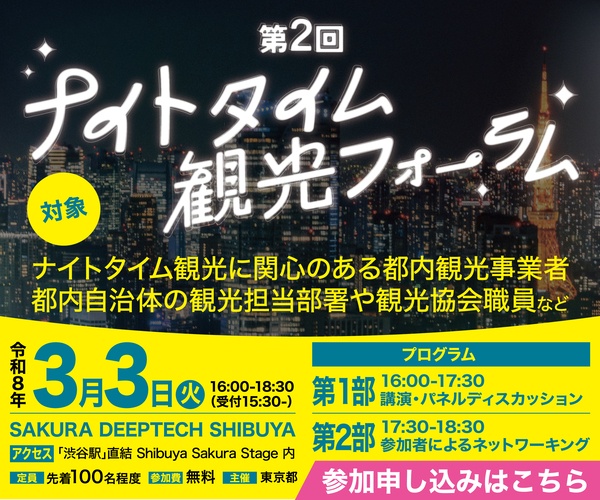被害を最小限に食い止めるため、防災対策は欠かせない(石川県輪島市の黒島地区で)
9月1日は「防災の日」。1923(大正12)年のこの日、マグニチュード(M)7.9の地震が発生、死者・行方不明者が10万人超という犠牲者を出した。いわゆる関東大震災だ。これにちなんで60年に制定され、毎年、各地で防災訓練や防災知識を深めるためのイベントが行われている。
政府も総合防災訓練を行い、今年は和歌山県の沖合でM9.1クラスの南海トラフの巨大地震が発生、西日本と東日本の広範囲で震度7や6強の激しい揺れとなり、太平洋側を中心に大津波警報が発表されたという想定で実施した。
地域でも訓練が行われ、福島県南会津の大内宿ではかやぶき屋根を守るため、火事が起きた際の延焼を防ぐ目的で住民らによる防火訓練が行われた。
地震や台風による被害に加えて、最近では、積乱雲を次々と発生させ、局地的に猛烈な雨を降らせ続ける線状降水帯による記録的な大雨で河川が氾濫したり、土砂災害などが頻発。また、気温が40度を超す地域も出るなど異常な暑さは「災害級」ともいわれる。
地球温暖化の影響か、身近な脅威が増えつつある。過去の経験にとらわれず、危険と思ったら早めに行動することが求められる。
日本気象協会では、普段からできる備えとして、(1)よくいる場所のリスクと避難場所・避難経路を確認しておく(2)日ごろから防災情報を収集する習慣をつけておく(3)非常時に必要なものを普段から準備・備蓄しておく―などを心がけるよう呼び掛けている。
旅館・ホテルにリゾートバイトという形で人材派遣しているグッドマンサービス(東京都千代田区)は昨年末、観光と防災の二面性を持つ「防災観光地」を紹介するサイト「Evacuation Site seeing防災観光地」を公開した。「観光地の魅力を楽しみながら防災の意識を高め、観光振興と防災啓発の両面から地域振興につながれば」という。
その一例として、宮城県の「石巻市複合文化施設」、三重県大紀町の「錦タワー」、静岡県の「磐田市渚の交流館津波避難センター」などを挙げる。
錦タワーは津波災害から命を守る5階建て緊急避難タワーで、1階が消防倉庫、2階が集会所、3階は東南海地震津波被災時の写真や防災資料を展示し、防災意識啓発の提供の場として整備されている。
旅館・ホテルは不特定多数の命を預かっている。自分はもちろん、宿泊客の命を守るため、備えのレベルを上げていきたい。

被害を最小限に食い止めるため、防災対策は欠かせない(石川県輪島市の黒島地区で)