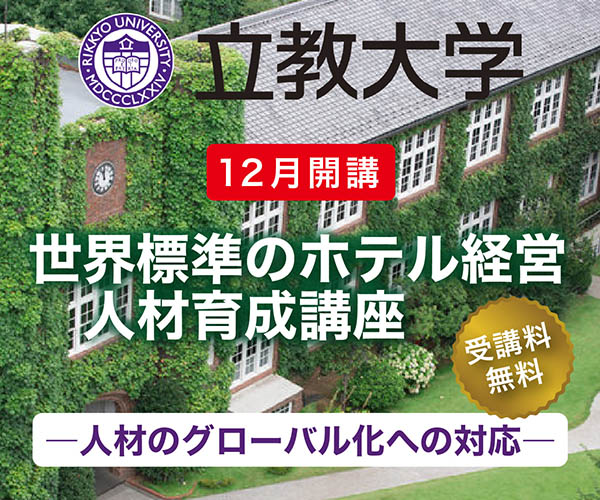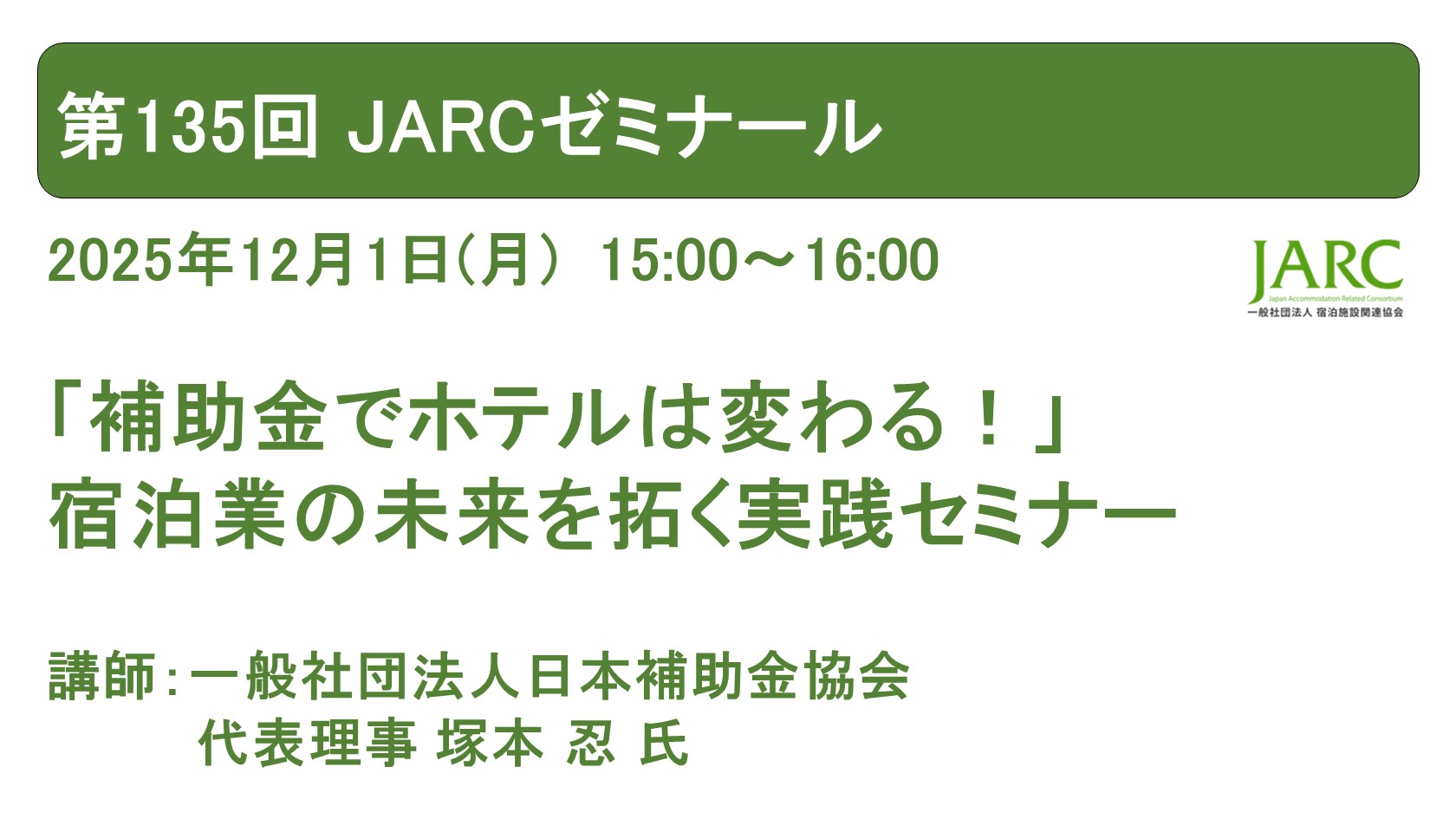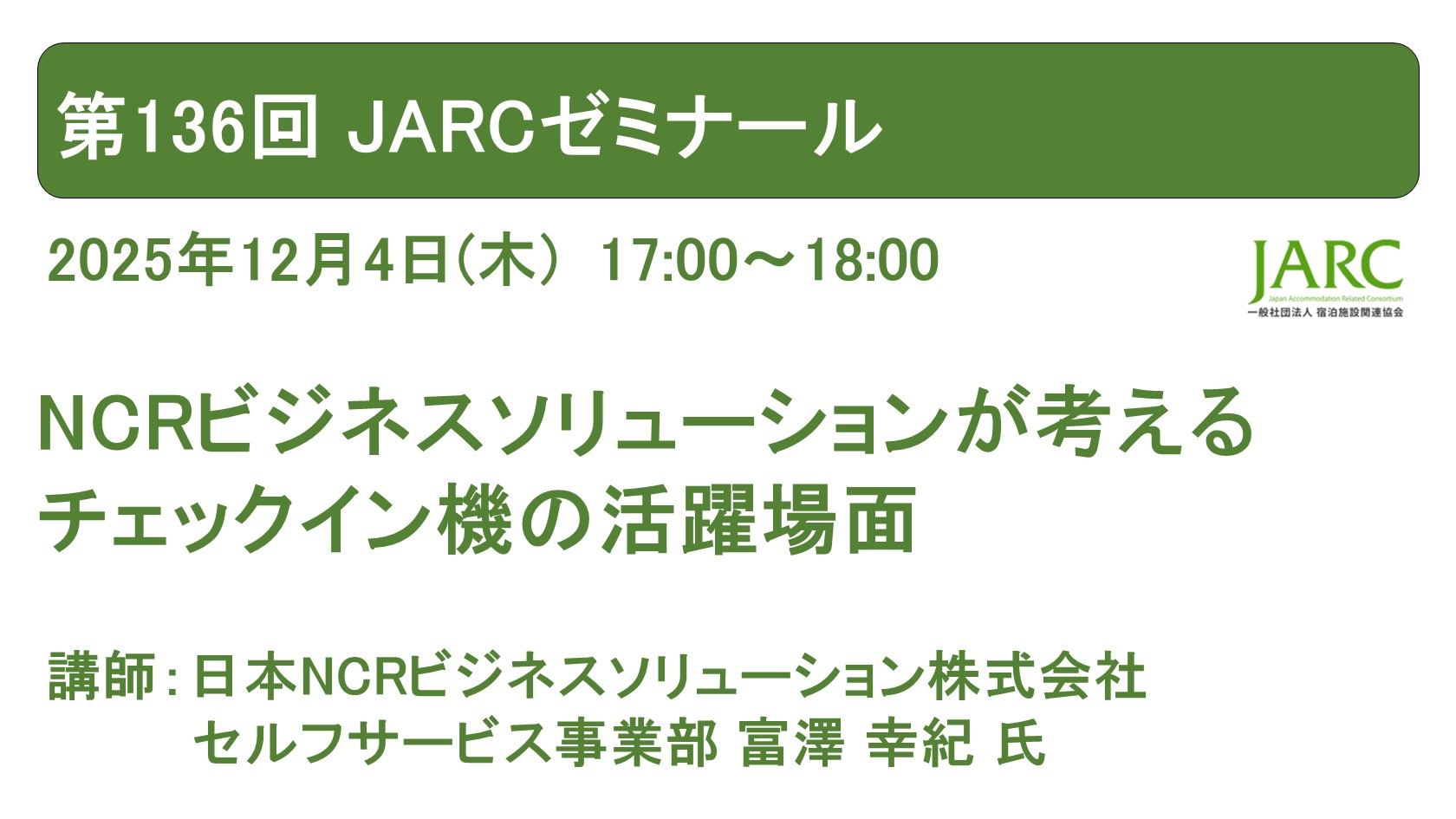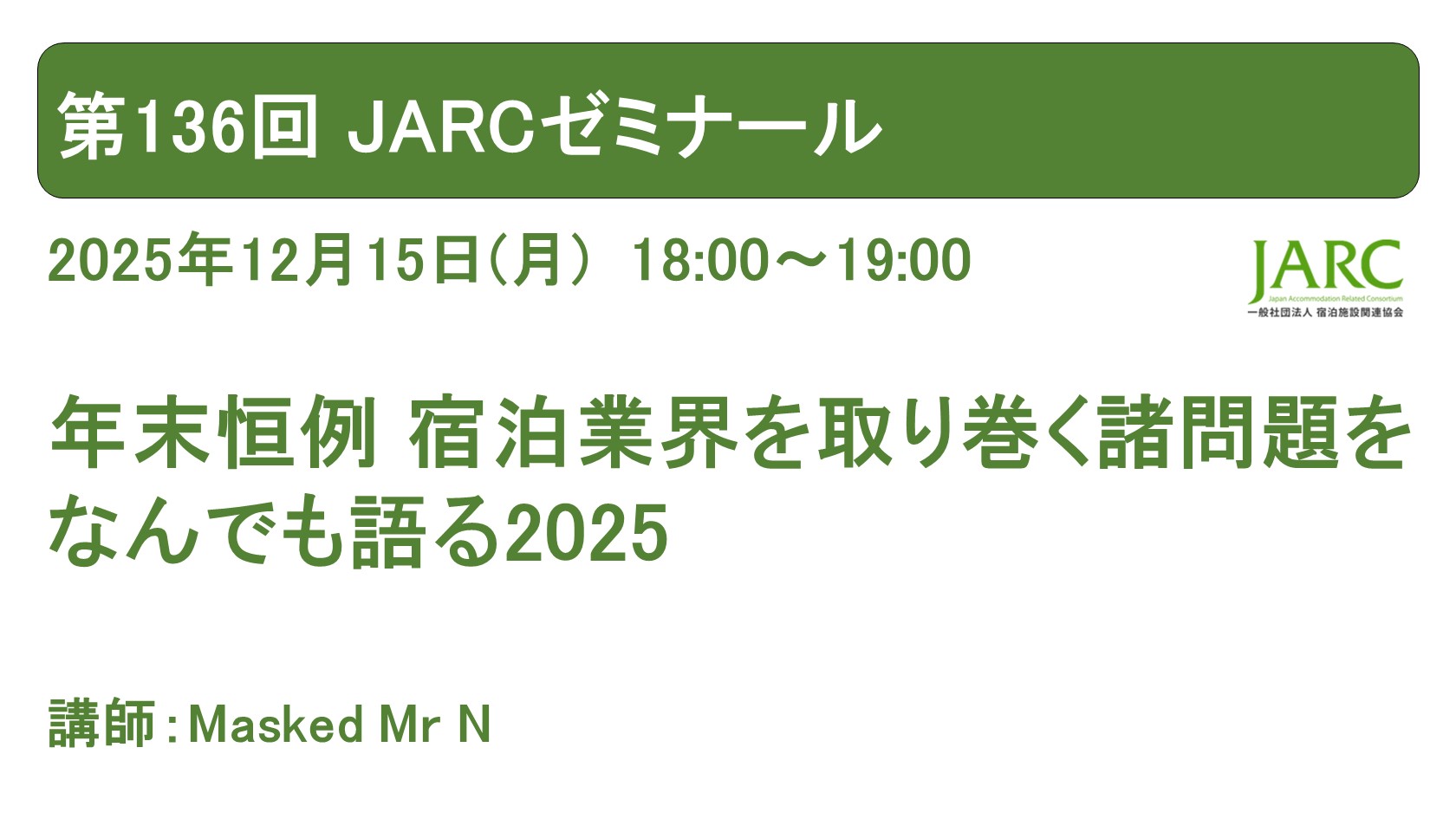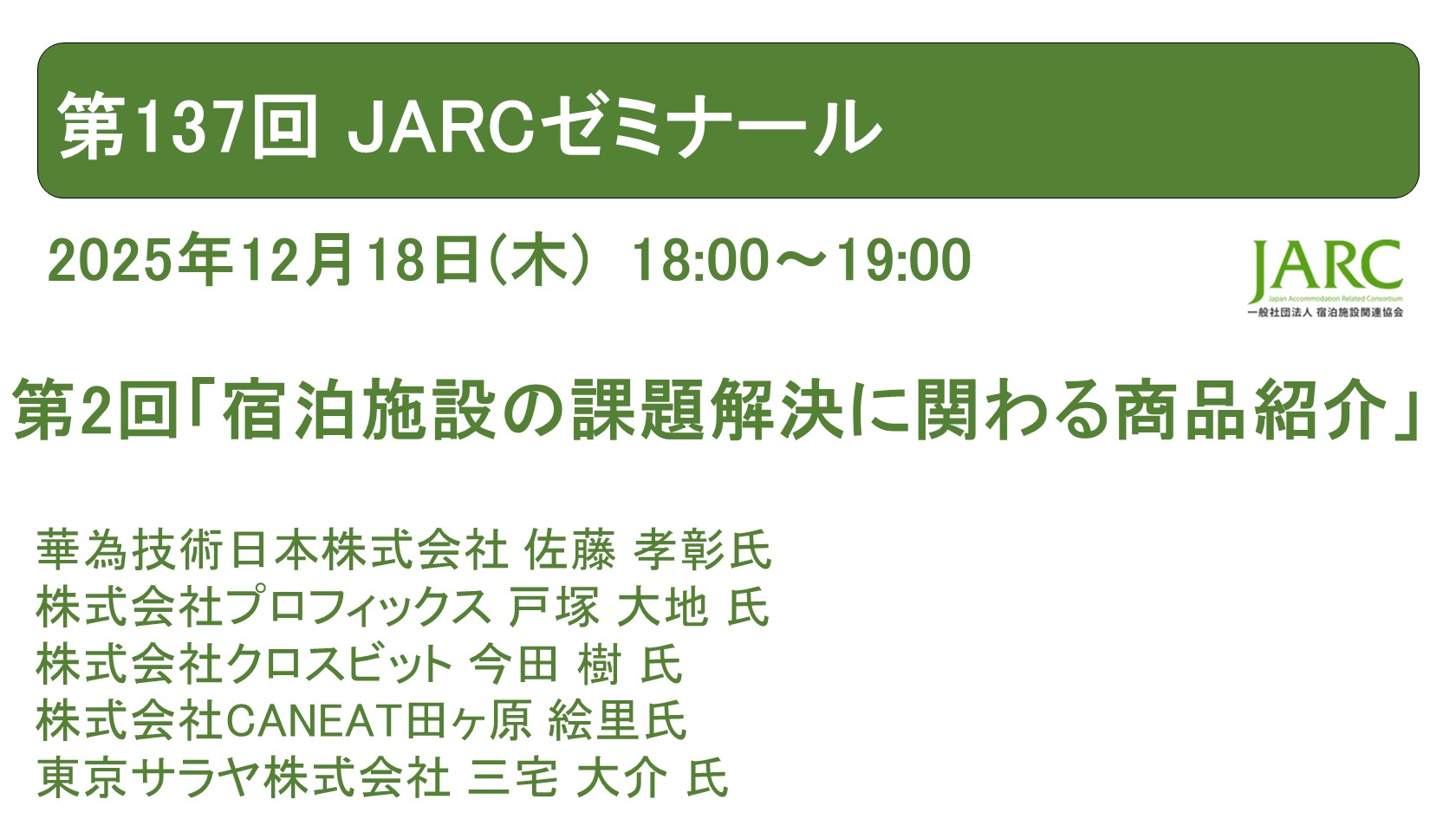石川県志賀町。能登半島の中央部に位置する人口約1万7千人の町だ。2024年元日、震度7の非常に激しい揺れに襲われ、災害関連死を含め20人が死亡、100人以上がけがをした。建物は約2400棟が全壊するなど、合わせて約1万6700棟が損壊した。8月23~24日、復旧復興に取り組む志賀町をメインに、周辺地域の姿を追った。
観光の新たなカギは「太鼓」
志賀町は、電車利用の場合、東京からは北陸新幹線を利用し金沢駅で下車。のと里山海道を車で走れば計3時間半ほどで行ける。レンタカーによる観光が便利なため、町はレンタカーを利用し、町内の宿泊施設に泊まる人を対象に、宿泊代金から最大5千円を割り引く「誘客促進レンタカー利用者宿泊助成金交付事業」を実施している。
志賀町には長い時間をかけて荒波によって岩盤が削られて作られた天然の洞窟「巌門(がんもん)」、映画のロケ地ともなった日本最古の木造灯台「旧福浦灯台」、ギネスブックに掲載されている全長約461メートルの「世界一長いベンチ」、さくら貝などが流れ着く約4キロ続く白砂青松の海岸「増穂浦(ますほがうら)海岸」など、いくつもの観光スポットがある。
また、加能ガニや能登牛、甘えび、滑らかな口当たりと上品な甘さが特長の干し柿「ころ柿」など、特産品も魅力的だ。
毎年8月第4土日に開催されるのが日本遺産である富来地域のキリコ祭り「冨木八朔祭礼(とぎはっさくさいれい)」。初日は約30基のキリコが乱舞する「お旅祭り」、2日目は神輿(みこし)が増穂浦を巡る「浜回り」など、勇壮な伝統行事が繰り広げられる。
今年は2年ぶりの通常開催。23日は11地区のキリコが同町八幡の冨木八幡神社境内に集まり、午後7時ごろから境内に駆け上がり乱舞。法被姿の男衆が「サーセイッ、サーセイッ」の掛け声のもと、キリコを高々と持ち上げた。

23日のお旅祭りで幕を開け、冨木八幡神社前には各地区のキリコが集まった
24日の本祭りでは、富木来領家町の住吉神社に各地の神輿が集まり、浜回りが行われた。

住吉神社に神輿が集結
祭りとセットなのが太鼓。志賀町は能登の中でも太鼓文化が盛んで、能登にある21の保存会のうち、7団体が志賀町にあるという。太鼓を観光資源として生かさない手はない。

住吉神社での太鼓の演奏
志賀町観光協会によると、団体旅行旺盛のころは巌門を中心に多くの観光客で町はにぎわったが、個人旅行化が進み、町は通過点になっていったという。「現在は志賀町がいま行ける能登の北限であるため通過点ではないが、輪島や珠洲が復活すればまた通過点になるかもしれない。いまが町を知ってもらうチャンスであり、そのコンテンツの一つが太鼓であり、太鼓の聖地化を目指したい」と意気込む。
昨年10月にはリレー形式に和太鼓を叩いた最多人数(269人)としてギネス世界記録に認定された。
志賀の太鼓は、2人の打ち手が一つの太鼓を打つのが特徴。今年7月には観光協会主催で「鼓動の頂 トーナメントバトル2025」という新たな大会が開催された。

2人の打ち手が一つの太鼓を打つ「志賀の太鼓」
2人1組が参加条件だが、今回は三味線や鉦(かね)、笛なども加えた3人1組の出場も認めた。太鼓経験がなくても参加できるので、「太鼓を思いっきり叩いて憂さ晴らしを」と呼びかけている。

素人でも打てるよう、打ち方を示す
また、毎年9月第3月曜に小浜神社で行われる「県下太鼓打ち競技大会」は戦前から始まり、90年以上の歴史を誇る。
入賞者は相撲の格付けになぞらえ、優勝は大関、続いて関脇、小結となる。今年は直近、10年間の大関が集まり、10年に一度の横綱大会が開かれる。
福浦(ふくら)港では23日、町の無形民俗文化財「福浦祭り」が2年ぶりに開催された。昨年は地震の影響で神事のみで執り行われたが、今年は巡行ルートを一部短縮して開催。

神輿を載せた神船の海上渡御は勇壮
祭りは港の総鎮守社である猿田彦神社の秋季祭礼。神輿を載せた神船が天狗に先導され海上渡御(ときょ)を繰り広げるさまは勇壮で、住民らによる仮装行列も見もの。

住民らの仮装行列も見もの
能登地方では祭りの日に親戚や友人らを自宅に招いてごちそうでもてなす「ヨバレ」という古い習慣がある。福浦祭りでも一部の家では玄関や窓が開け放たれ、お客さんを迎え入れていた。
観光協会ではヨバレを観光客にまで広げ、地元民との交流の機会にできないか考えている。受け入れ先の問題や、家庭の料理代をどう負担してもらうかなど課題も多いが、いずれは観光商品として売り出したい意向だ。
「志賀町、七尾市、能登島あたりがいま行ける能登の北限ではないか」と観光関係者。能登全体の復興にはまだかなりの時間がかかりそうだ。
被災地のいま
(1)志賀町内のホテル。玄関前の土地が隆起し、段差が生じている

志賀町内のホテル
(2)輪島市門前町を象徴する総持寺祖院も地震で建物が被害を受けた。参道入り口の灯篭は倒れたままだ

総持寺祖院
(3)北前船の船主集落として栄えた輪島市門前町の黒島地区。板張りの壁や窓格子、黒い屋根瓦の家並みが特徴で、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。地震で被害を受け、国指定重要文化財「旧角海家住宅」は倒壊した

輪島市門前町の黒島地区
(4)輪島市の観光名所「トトロ岩」(権現岩)。形状がアニメ映画「となりのトトロ」のキャラクターにそっくりで、観光客に人気だったが、地震で左耳部分がなくなった

トトロ岩
(5)輪島市門前町の海岸を見ると、地震の隆起で黒島漁港の中には海水がなくなった。波は消波ブロック付近まで来ていたが、今は白い砂浜になっている

輪島市門前町の海岸