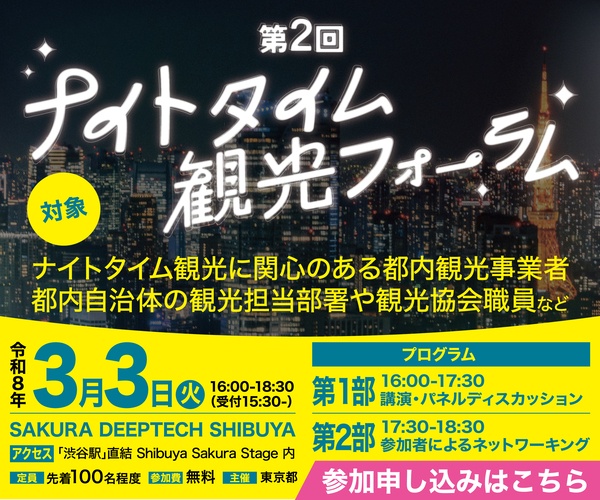地域の共感に必要な要素として物語性が各所で叫ばれるようになってきた。その際、ストーリーとナラティブという二つのキーワードが出てくる。この違いが近年の観光現場で注目されている。どちらも「物語」と訳されることが多いが、その本質は異なる。ストーリーが「起承転結」のある出来事の連なりであり、提供者が一方的に語る完成された物語であるのに対し、ナラティブは「語り合いの中で紡がれていく、開かれた物語」と捉えてもらいたい。観光においては、ガイドや地域住民とゲストが関わり合いながら生まれる”参加型の物語”こそがナラティブといえる。
こうしたナラティブ性は、今後の地域観光の中核となる力である。とりわけ地域ガイドに求められるのは「一方的な解説者」から「共感の触媒」としての変化だ。歴史や文化を語るだけでなく、その土地で暮らす自身の想い、体験、葛藤までも交えて語り、ゲストの感情と重なり合う瞬間を生み出す。そのような関係性が旅の本質的な価値を高める。
ナラティブ型ガイドの好例としては、南イタリアのアルベロベッロが挙げられる。ここにはトゥルッリと呼ばれる世界遺産があり、独特な家屋が並ぶ。このまちでは、観光ガイドが「自分の祖父母がこの家を建てた話」や「幼少期にここで育った記憶」など、極めて個人的な物語を語りながらまちを案内する。ゲストはただ建築様式を知るのではなく、ガイドの人生と土地が重なった”物語の時間”の共有を受けるのだ。
グリーンランドでは、先住民族イヌイットによる取り組みが注目されている。犬ぞり体験や釣り体験の中で、彼らは「祖父の時代の狩猟法」や「氷の変化が生活に与える影響」といったリアルな暮らしの話を語る。それは単なる文化紹介にとどまらず、気候変動の最前線に立つ”当事者の声”として深く心に響く。まさに、土地と生きる人々が観光の主役となる瞬間だ。
ナラティブが注目される背景には、観光の”コモディティ化”への危機感がある。多くの観光地が、似通ったコンテンツや体験を提供する中で、真に差別化できる要素は「人の語り」や「関係性の深さ」に移ってきている。AIが情報提供を担う時代だからこそ、ガイドに求められるのは「生きた主観」であり、ナラティブ的対話力ではないだろうか。
今後、ナラティブ型の地域ガイドを育成する仕組みが各地で求められるだろう。そのためには、ガイド自身の「自分史の棚卸し」や「感情を言葉にするトレーニング」、さらにはゲストとの「対話の設計技法」といった、新たな研修体系が必要になる。また、評価軸も「正確な知識量」ではなく「共感の深さ」や「気づきの質」へと移行していくはずだ。
選ばれて、また「帰ってきたくなる」地域になるには、人と人とが出会い、交わり、変容していくプロセスが大事である。ナラティブとは、その旅の中でしか生まれない「一度限りの物語」だ。今こそ地域ガイドは語りの担い手として、単なる”案内人”から”共感の推進役”へと進化する時だろう。
(地域ブランディング研究所代表取締役)