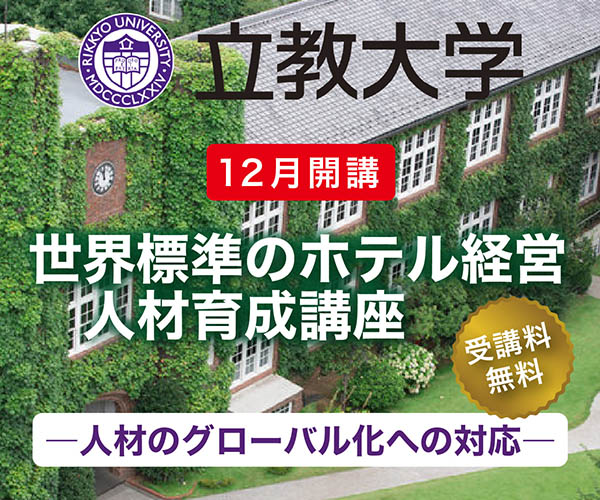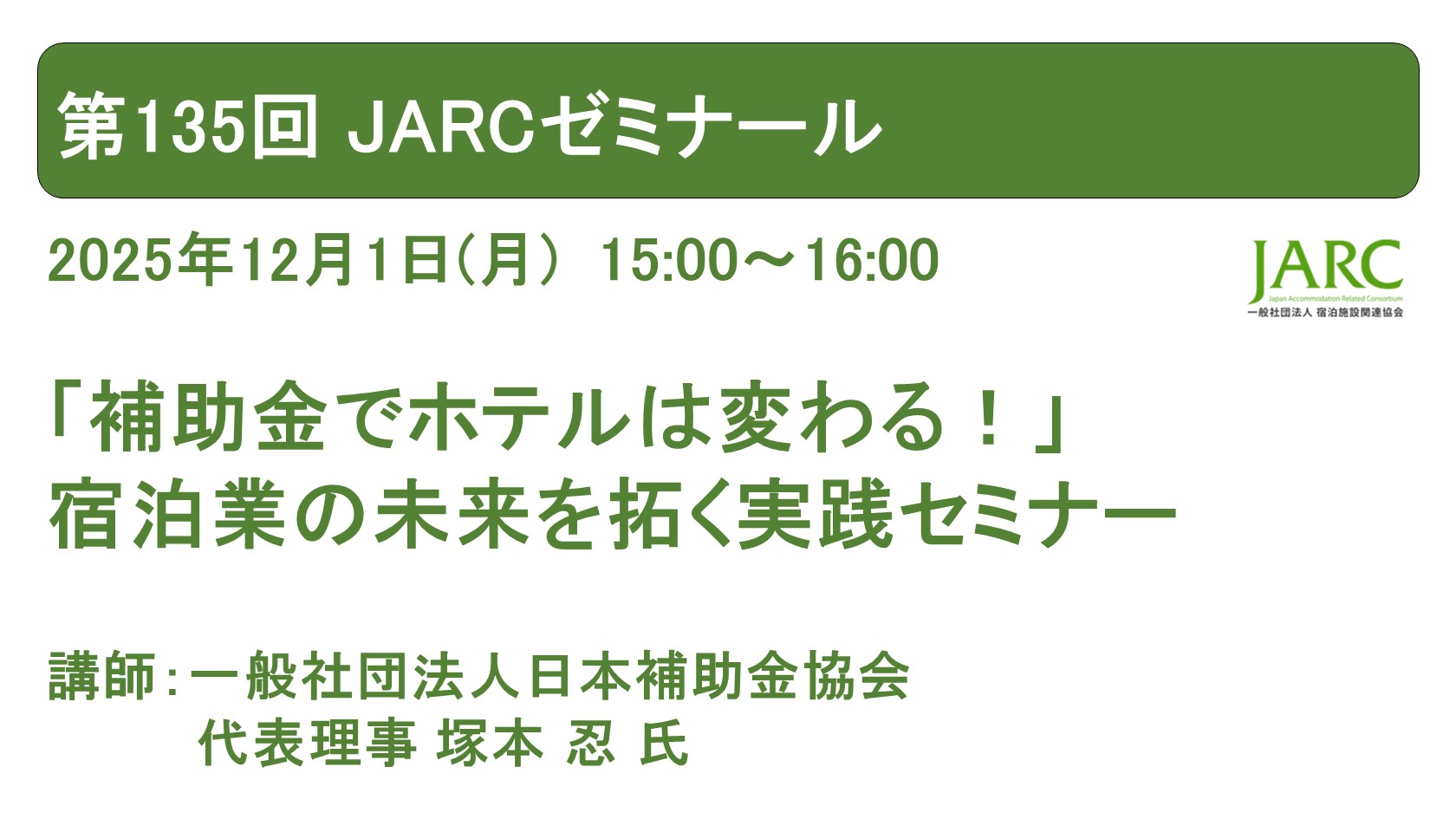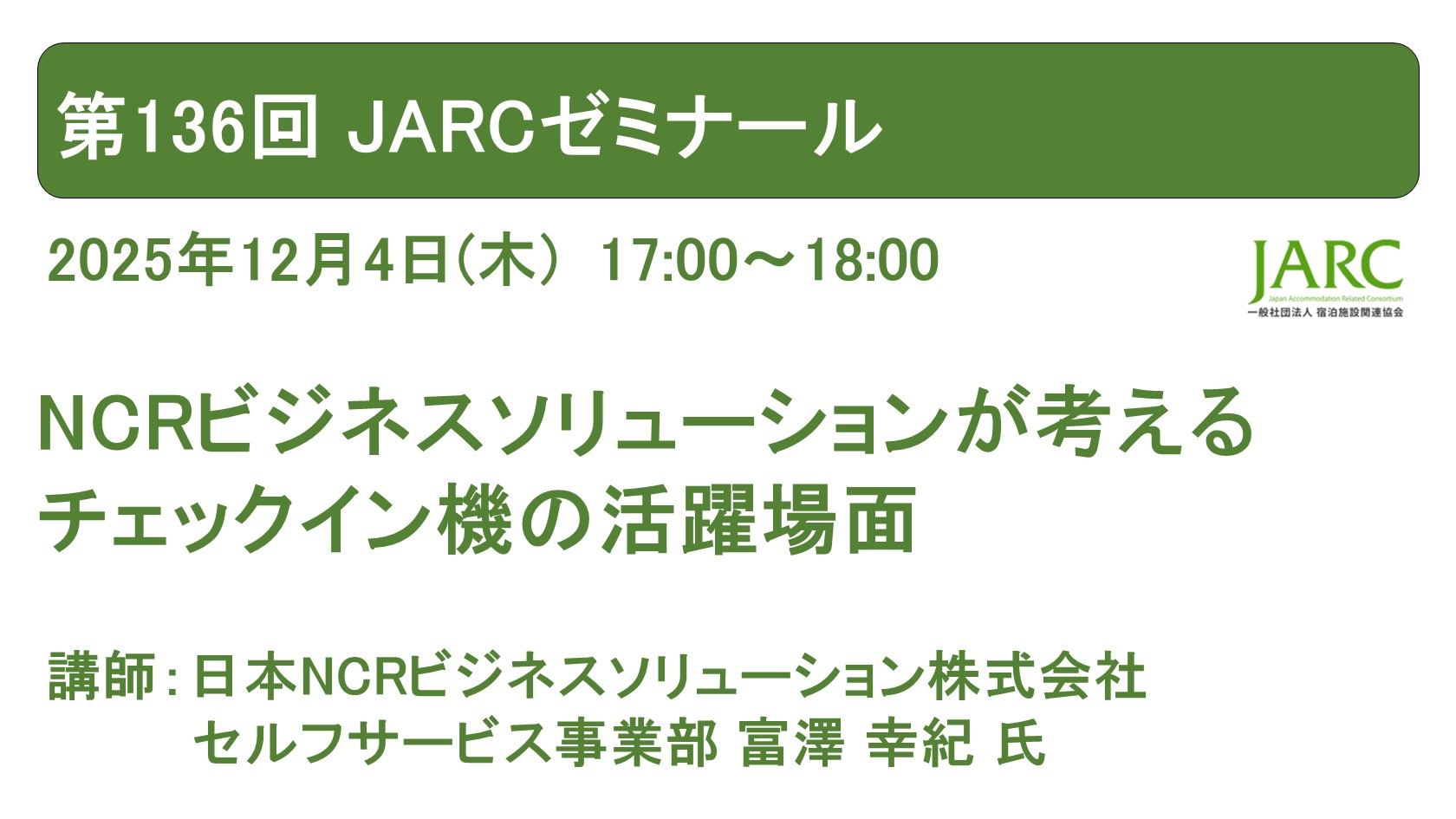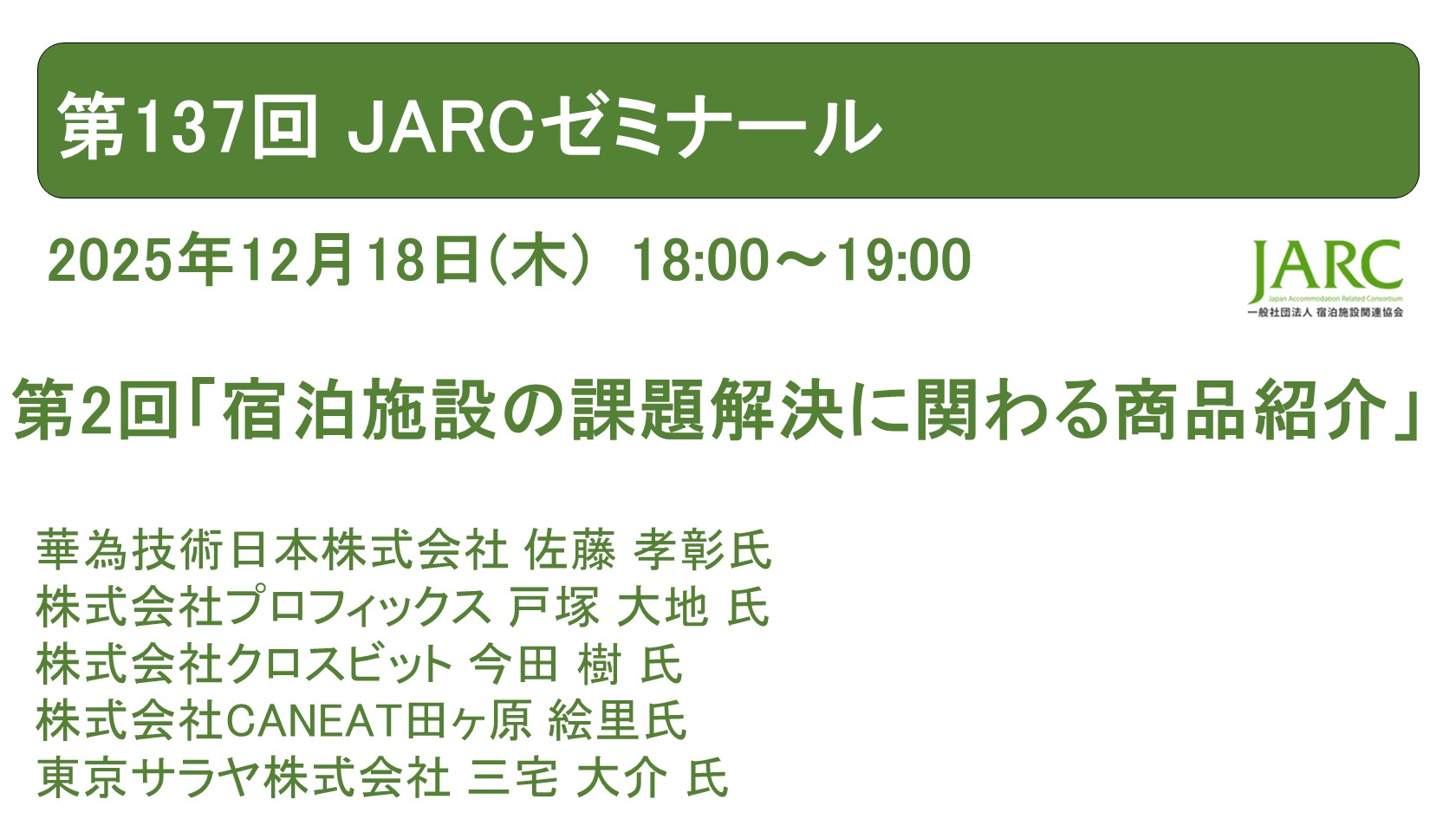ビール酒造組合と発泡酒の税制を考える会は9月1日、2023年度の「ビール・発泡酒・新ジャンル商品の飲用動向と税金に関する調査」の結果を発表した。調査は月1回以上お酒を飲む1,200人を対象に実施。消費者の購買行動や価格変動への反応を明らかにした。
価格に敏感な消費者、節約意識高まる
家庭でビール系飲料を飲んでいる割合は、ビールが59.5%、発泡酒・新ジャンルが37.4%。週平均の消費量はビールが4.2缶、発泡酒・新ジャンルが4.5缶だった。
調査によると、家庭でお酒に使う1カ月の平均金額は5,459円で、前回より214円増加。しかし2025年4月の値上げ後、飲酒量が「減った」と回答した人は16.7%に達している。昨今の物価高騰を受け、節約意識が「高まった」と答えた人は約6割(59.0%)を占めた。
消費者が飲料を選ぶ理由にも価格の影響が表れている。ビールを飲む理由として81.8%が「おいしいから」を挙げ、「品質が良いから」(28.7%)も上位だった。一方、発泡酒・新ジャンルでは「価格が手頃だから」が64.4%と最多で、「おいしいから」は50.6%だった。
料の価格変動に対する消費者の反応も明らかになった。ビール350ml6缶パックが50円程度安くなった場合、飲む量が「増える」と答えた人は10.6%にとどまった。一方、発泡酒・新ジャンル350ml6缶パックが50円程度高くなると、17.8%が飲む量は「減る」と回答。発泡酒・新ジャンルの代わりに他のお酒を飲むか尋ねたところ、28.8%が「他のお酒の量は増えない」と答え、価格上昇に伴い飲酒量自体が減る傾向が示された。
また、平成29年度税制改正により、2026年10月にビール・発泡酒・新ジャンル商品の酒税率が1㎘あたり155,000円に統一される予定だ。その時点での税負担(酒税+消費税)が小売価格の33%程度と想定されることに対し、約6割(60.2%)が「高い」と回答。「安い」(3.4%)、「適正」(11.8%)を大きく上回った。
この調査は2002年から毎年実施されており、ビール系飲料を巡る消費者行動と税金に関する貴重なデータを提供している。調査結果は、飲料メーカーや流通業界が価格戦略を考える上での重要な参考資料となる。同時に、消費者の生活防衛意識の高まりを反映し、価格上昇が消費停滞につながる可能性を示唆している。