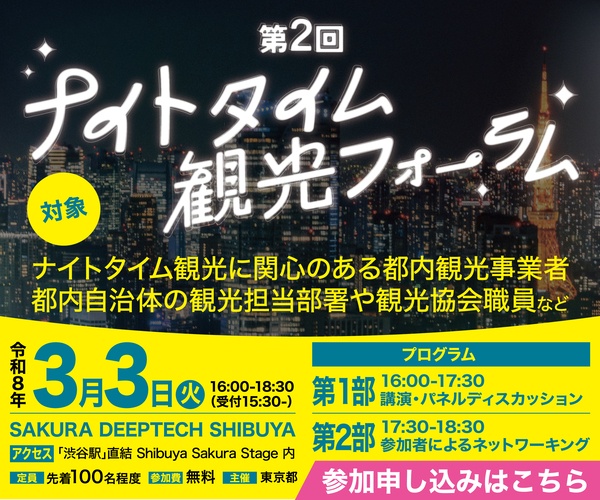前回、重要無形文化財保持者(通称人間国宝)に関して言及した。今回は国宝そのものに関して掘り下げてみたい。文化財は過去の遺産であると同時に、未来の観光・教育・経済に資する「生きた資源」である。文化庁の最新データ(令和7年6月時点)によれば全国の国宝は1144件、このうち美術工芸品が912件、建造物が298棟232件に及ぶ。美術工芸品を見ると、絵画166件、彫刻141件、工芸品254件、書跡・典籍235件、古文書63件、考古資料50件、歴史資料3件となっている。
都道府県別に見ると、国宝の集中度には明確な地域差がある。第1位は東京都で292件。次いで、京都府(239件)、奈良県(208件)、大阪府(62件)、滋賀県(56件)と続く。二つの県を除いてほぼ全ての都道府県に国宝が存在している。
さて、こうした背景がある中で、皆さんは自身の地域の国宝はどの程度ご存じだろうか。そして実際に見たことがあるだろうか。私の出身である広島県には26件の国宝があり、建造物は嚴島神社や不動院金堂、浄土寺本堂等7棟、美術工芸品は19件あり、そのうち11件が嚴島神社宝物館に保存されている。正直、私も調べるまでこれほどの件数が広島にあることを知らなかった。学校教育においてもシビックプライドの一環としてその価値を学習してきたかというと、意外と知らない人が多いのではないだろうか。
令和3年に文化財保護法が改正され「指定文化財」の保存を中心とした制度設計から「登録文化財」や「文化財保存活用地域計画」といった制度が強化され、市町村レベルでの文化財登録が促進され、地域主体での利活用が進めやすくなっている。「守る文化財」から「活かす文化財」へ、法制度の側面からも明確に転換が図られている。
文化財の保存と活用は二律背反ではなく、活用こそが保存の原動力となりうる時代である。入場料やガイドツアーの収益を修復費に回す仕組みや、ガイド養成を通じた地域雇用の創出等、文化財が地域の経済循環に組み込まれていくモデルが求められている。文化庁認定のものだけでも5種、(1)国宝・重要文化財、(2)史跡名勝天然記念物、(3)重要無形文化財、(4)重要有形民俗文化財、(5)重要無形民俗文化財がある。選定や登録するものも数多く存在し、都道府県・市町村単位のものを含めると相当数になる。
あらためてなぜ、これらが生まれたのかという風土・歴史背景やその類まれな技術の価値を正しく理解していけるようになることが期待される。昨今、コンテンツ造成等において新しい価値を作ろうとする傾向もあるが、こうした歴史的価値があるエリアではこれらの価値を再認識し、きちんと伝えていく仕組みが加速すると、来訪者の満足度も向上し、その保存・活用といったサイクルもより良い流れになると考えている。ぜひ皆さんも自身の地域の国宝等文化財の現状を調べて、活用の展望を模索してみてほしい。
(地域ブランディング研究所代表取締役)