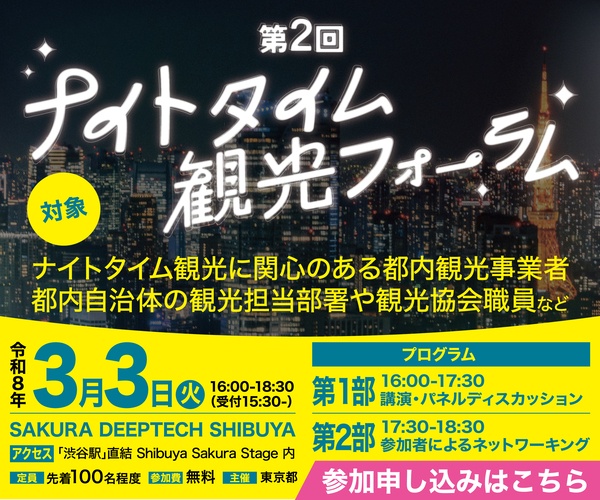「地域の物語」の必要性は各所で語られてきた。昨今、環境省が主導する「インタープリテーション(以下、IP)全体計画」の全国的な展開は、地域内の合意形成を通じた物語の可視化という点で、注目すべき取り組みだ。
IP計画は、国立公園や国定公園等自然地域を中心に、令和5年度までに全国20地域以上で策定されている。地域資源を「伝える」意義を再整理し、その手法や視点を体系化した点は、各地の観光や環境教育において大きなヒントとなっている。
IPとは、自然や文化、歴史といった地域固有の価値を、訪れる人が「自分ごと」として理解・共感できるように伝える手法であり、単なる説明や情報提供ではなく、地域と訪れる人の心をつなぐ「翻訳者」であり「橋渡し役」である。
例えば、沖縄県石垣島最北端の平久保地区では、これまで観光化が進んでいなかった。美しい自然や伝統的な暮らしが残る集落に、近年SNSの影響等から急激に観光客が流入し、地域資源の乱用やマナー違反が大きな課題となっていた。環境省・石垣市・地元住民が連携し、IP全体計画を策定。自然保護だけでなく「地域をどう見せたいか」「何を伝えるべきか」といった住民自身の視点を丁寧に言語化するプロセスが重視された。外部目線ではなく、内側から掘り起こされた”内なる物語”が特徴だ。ワークショップ等を通じて住民の想いを「地域として大切にしたい価値観」として、明文・ビジュアル化していった。これは単なるプランを超えた「地域の憲章」として機能している。その他、鹿児島県霧島地域や富士山麓地域でのIP計画も好事例として注目されている。
一方で、課題も残されている。第一に、制度的な支援体制がいまだ整っていない点だ。アメリカの国立公園には「インタープリター制度」が整備され、専門職が常駐しているが、日本ではそうした人材育成や配置の制度は確立されていない。現場の多くがボランティアや民間委託に頼っており、持続可能性に不安が残る。
第二に、計画は策定されたものの現場で活用されていない、いわゆる”絵に描いた餅”となってしまっているケースもある。IPの本質が地域の日常の中に根づいてこそ、その力が発揮される。観光施設や地域事業者と連動し、実行・浸透こそ必要不可欠だ。
今後は、IPを地域全体のコアバリューとして位置づけ、シビックプライドとして育むことも重要である。IP計画を総合学習の副教材として活用し、小さなころから地域資源に愛着を持ち、それらを守ることが当たり前という感覚が育まれる社会が、真に持続可能な観光地を支えるだろう。
観光・教育・文化・環境保全の連携が進み、IPの価値が各地で再評価されることで、日本の地域は、世界の旅行者にとって「意味のある旅」の目的地となるだろう。訪れる人の心に残る”意味”をどのように設計するか。その鍵は、地域の物語の再発見と、その丁寧な「翻訳」にある。IPによる地域価値の再編集の流れが、今後さらに広がることを期待したい。
(地域ブランディング研究所代表取締役)