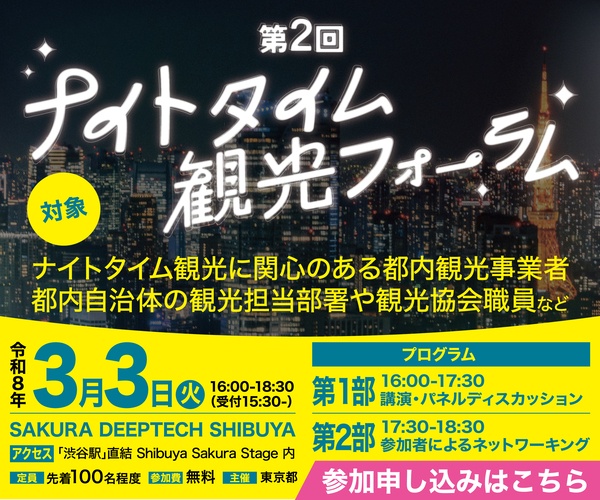昨今の富裕層観光は一過性のラグジュアリーブームではない。背後にある”旅の動機”を深く掘り下げるには、心理学的アプローチも期待されている。その中で改めてマズローの「欲求段階説」を見直したい。
マズローは1943年に、人間の欲求を5段階に分類し、下位の欲求が満たされるとより高次の欲求へと人は動機づけられると説いた。(1)生理的欲求(空腹、睡眠など生命維持に関わる基本欲求)(2)安全欲求(身の安全、経済的安定など)(3)社会的欲求(愛情や帰属、仲間とのつながり)(4)承認欲求(他者からの尊敬、自己の有能感)(5)自己実現欲求(自らの可能性を最大限に発揮したいという欲求)だ。
そして晩年、さらにその上位にある第6段階「自己超越欲求(Self―Transcendence)」の存在を提示した。これは「自我の枠を超えて、より大きな存在や目的に自己を捧げたい」というスピリチュアルかつ超個人的な動機である。今、富裕層観光が求めているのはまさにこの”第6段階”の欲求だと私は感じている。単なるぜいたくでも自己実現でもない「自分という存在を超えて、世界や他者とより深く関わりたい」という欲求である。それが行動として”旅”に現れていると考える。
たとえば、レスポンシブルツーリズムや、リジェネラティブツーリズムの文脈はこれらから起こっていると考えていいだろう。自然再生プロジェクトに参加する滞在型ツーリズム、地域の文化継承者と共に体験をつくるパーソナルツアー、あるいは無名の土地にある祈りの場での内省的な滞在などである。そこには「自分を高める」のではなく、「自分を空にして、何か大きなものとつながりたい」という深い動機が働いている。
この「自己超越欲求」は、安易な情報や金銭では動かない富裕層をも突き動かす”究極の動機”ともいえる。実際、欧米の超富裕層が訪れる旅先では「誰でも行ける」場所よりも「選ばれた者だけが体験できる精神的な場」が重視される傾向がある。
一方で、私たちが地域観光を設計する際、つい「何を見せるか」「どこに泊まってもらうか」といった物理的・表層的なレイヤーに終始しがちだ。しかし、これからの観光には、”旅人の変容”を支える物語と文脈が不可欠である。自己超越は偶然起こるものではなく、意味づけの設計=観光体験の哲学的編集があってこそ発生する。
だからこそ、地域がめざすべきは「豪華なものを用意する」ことではなく「旅人が自己を超える場」を提供することにある。地域資源とは、単に見せるものではなく、共に意味をつくる素材である。地元ならではの祈りや営みにふれることで、自分の存在や人生を見つめ直す。そんな旅を設計できたとき、より深い関係が築かれるだろう。そこに至るには、この世界観をしっかりと導ける達観した先達のような存在も求められている。
観光を、単なる移動や消費ではなく、”精神の交差点”と考え、今こそ「自己超越する観光」を日本の各地に眠る精神性や風習からひも解き、再定義できれば、日本はその先進地になれると確信している。
(地域ブランディング研究所代表取締役)