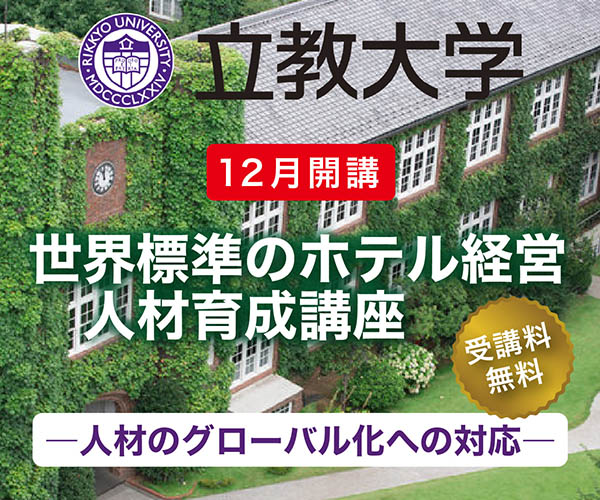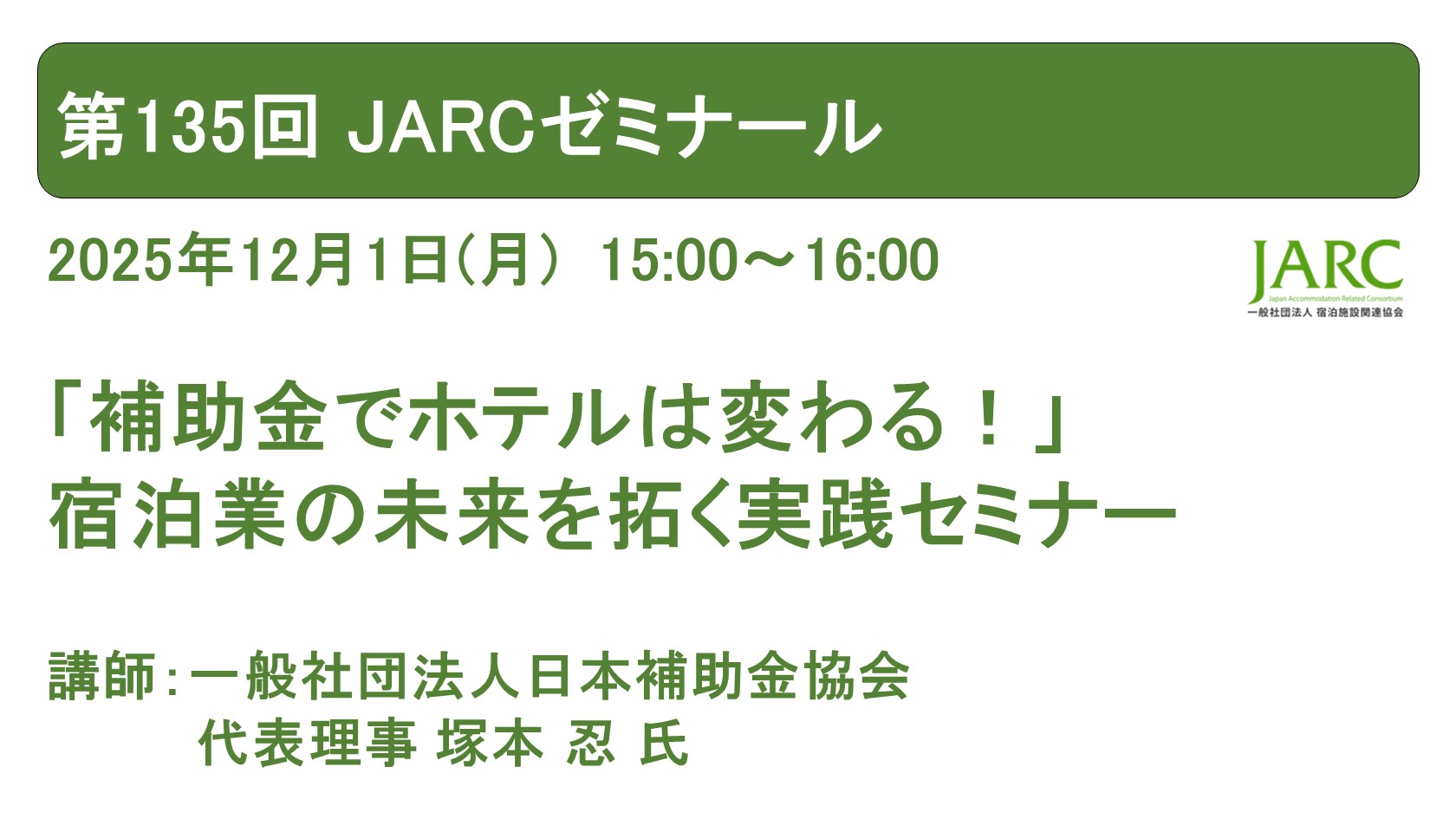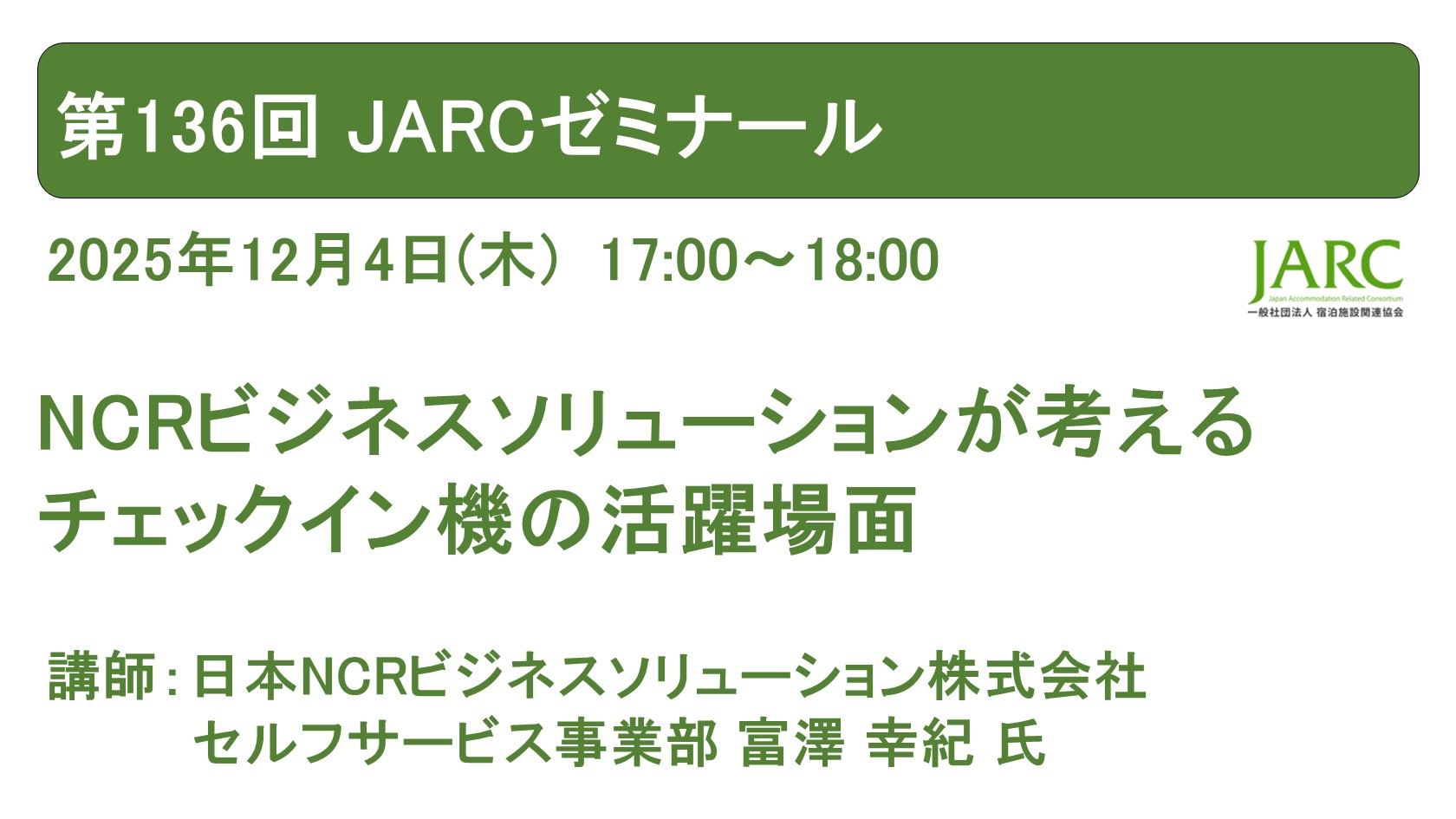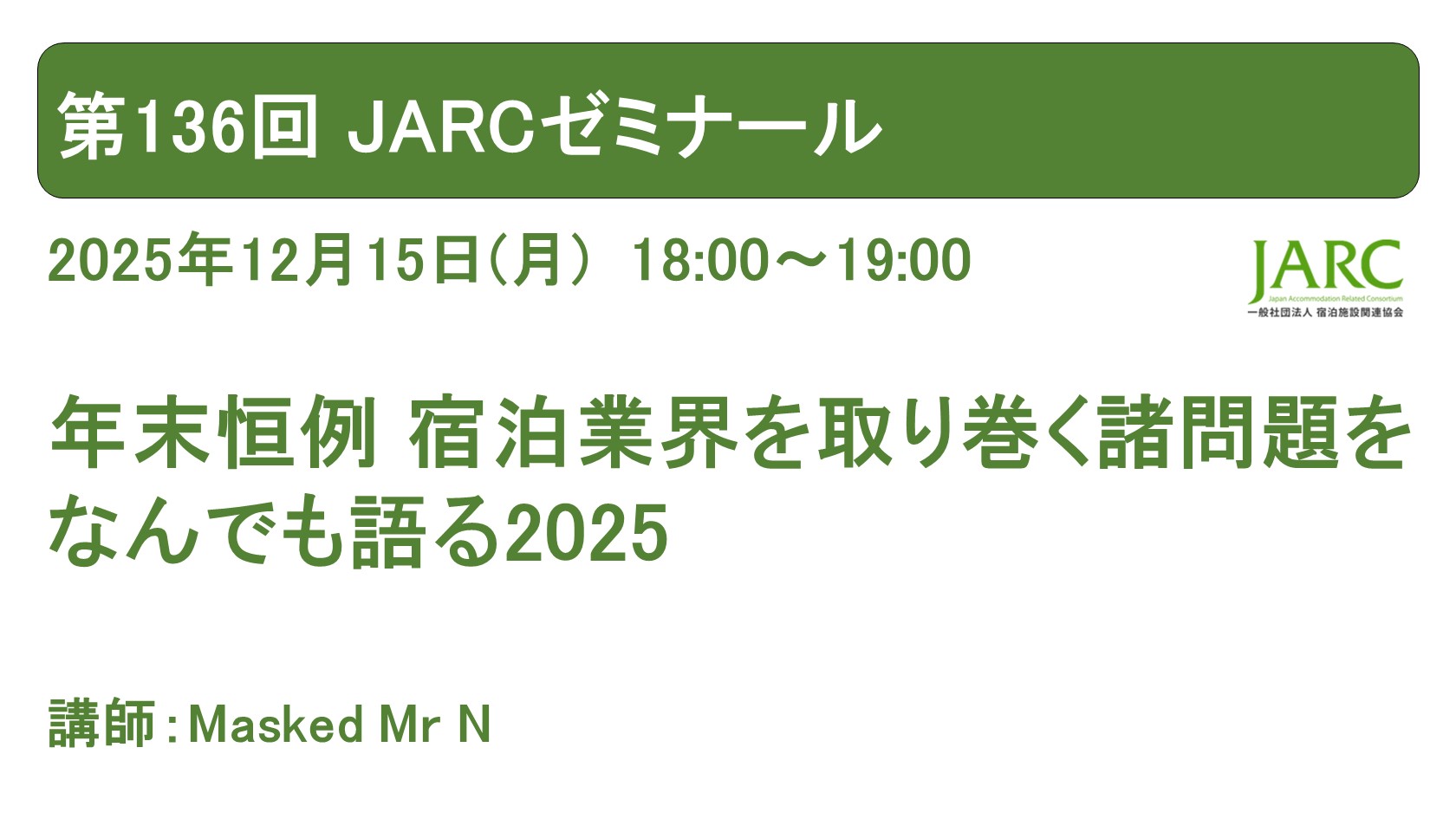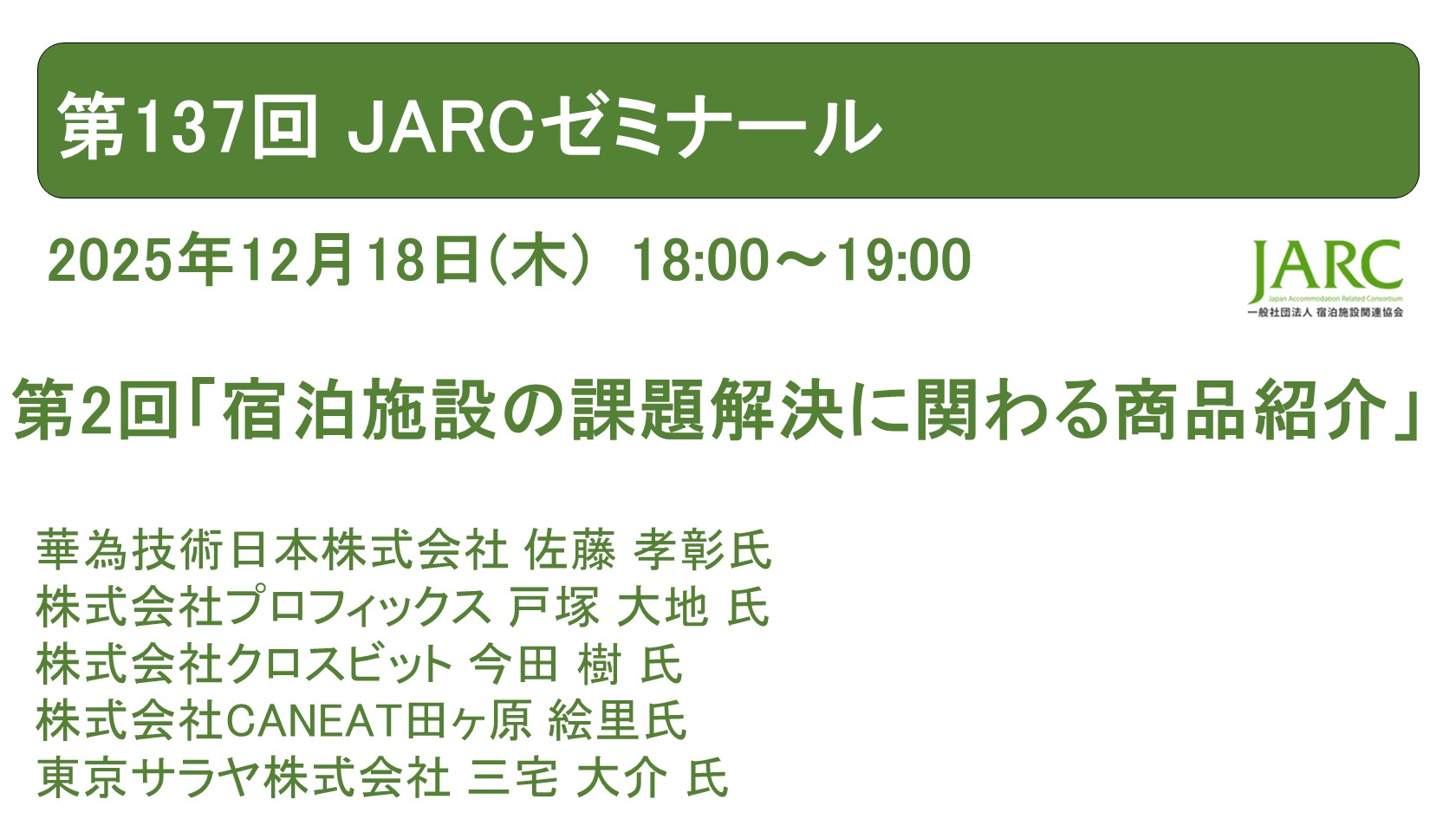映画の魅力と本質を語る三浦友和さん
2025年8月、夏の終わりの陽光がまだ残る大分県由布市湯布院町が、映画を愛する人々の特別な熱気に包まれた。今年で50回目という大きな節目を迎えた「湯布院映画祭」。そのメイン会場である「ゆふいんラックホール」には、俳優の三浦友和氏をゲストに迎えたトークショーを一目見ようと、全国から多くのファンが詰めかけた。大ホールの300席は瞬く間に満席となり、通路や後方は立ち見客で埋め尽くされる。この光景こそ、半世紀にわたり映画ファンと地域に深く愛され、共に歩んできた映画祭の歴史の厚みを物語っていた。

現存する日本の映画祭としては草分け的存在であり、「夏の湯布院といえば映画祭」と称されるほどのブランドを確立している。今年は7月に由布院の玄関口であるJR由布院駅が開業100周年を迎えたこともあり、町全体が二重の喜びに沸いている。単なる映画の上映イベントに留まらず、いかにして湯布院という土地の文化とブランドを醸成してきたのか。50年の節目に、その軌跡と未来を探った。

2025年7月29日に開業100周年を迎えたJR由布院駅
本稿では、湯布院映画祭3日目、8月23日の模様をレポートする。
始まりは「災害からの復興」― 純粋な映画愛が原動力に
「私たちが50年も続けてこられた秘訣を問われれば、それは収益を第一に考えず、関わった誰もが心の底から『面白かった』と思える場であり続けたこと。観客も、ゲストも、そして我々スタッフも。その満足感の積み重ねがすべてです」。第37回から実行委員長を務める三宮康裕氏は、穏やかな表情でそう語る。その言葉に、この映画祭の本質が凝縮されている。

湯布院映画祭実行委員長の三宮康裕さん
湯布院映画祭の端緒は、1975年にまで遡る。同年4月に発生した大分県中部地震により、名湯・由布院は深刻な風評被害に見舞われ、観光客の足がぱったりと途絶えた。この苦境を打破しようと立ち上がったのが、元東宝の助監督で、老舗旅館「亀の井別荘」の若き経営者でもあった中谷健太郎氏だった。
歴史の歯車が大きく動き出したのは、中谷氏と大分合同新聞社の記者であった故・伊藤雄氏との出会いがきっかけだ。当初は「大分良い映画を見る会」という自主上映会として大分市で産声を上げた活動が、復興を目指す湯布院に根を下ろすことになる。
特筆すべきは、これが観光業者の主導するイベントではなかったという点だ。純粋に映画を愛する人々が、本当に良いと信じる映画を、作り手と観客が同じ目線で語り合える場を作りたい。その一心で始まった」。実行委員であり、旅館「山城屋」の代表を務める二宮謙児氏は、その成り立ちをそう強調する。地域おこしや観光振興が第一目的ではなかった。この「文化への純粋な情熱」こそが、映画祭の揺るぎない背骨となった。

第一回と第二回、貴重な映画祭ポスター
発起人である中谷氏は、助監督時代の仲間たちが、後に日本映画界を牽引する監督となっていた。その強固な人脈は、映画祭の大きな武器となった。中谷氏の電話一本で、名だたる監督や俳優が手弁当で湯布院に駆けつける。作り手と観客の間に垣根がなく、温泉に浸かり、酒を酌み交わしながら夜通し映画を語り明かす。アットホームで濃密なコミュニケーションのスタイルは、初回から現在に至るまで、湯布院映画祭の代名詞として受け継がれている。
初代実行委員長の中谷氏から、第4回で伊藤氏へ、そして現在の三宮氏へと、情熱のバトンは着実に繋がれてきた。結果として、映画祭は湯布院に単なる観光地ではない文化的な深みを与え、唯一無二の魅力を放つ温泉地としての「由布院ブランド」を形作る、極めて重要な礎となったのである。
三浦友和氏が語る映画の本質―「信頼関係」と「想像力への問いかけ」

トークショー者(左から):俳優三浦友和さん、諏訪敦彦監督、三宅唱監督
23日のトークショーは、今年の映画祭の熱気を象’徴する時間となった。俳優の三浦友和氏、そして現代日本映画を牽引する諏訪敦彦監督、三宅唱監督が登壇すると、満員の会場から万雷の拍手が送られた。
映画業界に入り54年。数々の名監督と仕事をしてきた三浦氏は、映画作りにおける核心を、自身の経験を交えながら静かに、しかし力強く語った。 「監督から俳優への最大の演出とは、結局のところ、俳優が演技をしやすい環境を整えてくれることに尽きます。小手先の技術指導ではなく、その人間の内面そのものを撮ろうとしてくれる誠実な姿勢。それが何よりも大切なのです」。

映画の魅力と本質を語る三浦友和さん
今や撮影現場では最年長になることがほとんどだという。「監督も共演者も、自分より年下ばかり。しかし、年齢差があるからこそ、お互いにとって貴重な学びが生まれる。世代を超えたプロフェッショナル同士が敬意を払い、真摯に作品と向き合う。その根底にあるのは、いつの時代も変わらぬ『信頼関係』です」と三浦氏は断言する。
「限られた予算と時間の中で、どれだけ良質な作品を生み出せるか。現場では常に工夫と効率化、そして何より協力が求められます。監督と俳優、スタッフの間に深い信頼がなければ、良い作品など生まれるはずがないのです」。
さらに三浦氏は、映画という表現の本質にも言及した。「映画には上映時間という制約があります。その短い尺の中ですべてを説明し尽くすのではなく、いかに観客の皆様の頭の中で想像を膨らませてもらうか。作り手が描かなかった余白に、何をメッセージとして込められるか。それが作品の深さを決めるのだと思います」。
作り手の哲学と、観客の想像力が交差する場所。それこそが、湯布院映画祭が半世紀にわたり大切に育んできた空間そのものであるように感じられた。
文化が紡ぐ地方創生の未来
近年、映画やアニメの舞台となった地を訪れる「聖地巡礼」は、地方に大きな経済効果をもたらす観光コンテンツとして注目されている。また、映画製作そのものを誘致し、地域活性化を図る自治体も増えている。しかし、湯布院映画祭の半世紀にわたる歩みは、それらとは少し異なる示唆を与えてくれる。
彼らは最初から経済効果を狙ったわけではない。「映画が好き」という純粋な情熱から始まり、その熱が人を呼び、共感を呼び、50年という歳月をかけて、いつしか地域にとってかけがえのない文化的財産となった。そして、その文化が結果として地域に活気とブランド力をもたらしている。
三宮実行委員長は、「才能ある若い監督も次々と出てきている。我々実行委員会も若返りを図り、新しい感性を取り入れていきたい」と未来を語る。文化は一朝一夕には育たない。湯布院映画祭が半世紀かけて証明してきたように、地域に根差した本物の文化こそが、持続可能な地方創生の鍵を握っているのではないだろうか。邦画界、そして日本の地方が持つ、その底知れぬ可能性に期待したい。

観客との距離が近いのも湯布院映画祭の面白さ
【九州支局長 後田大輔】