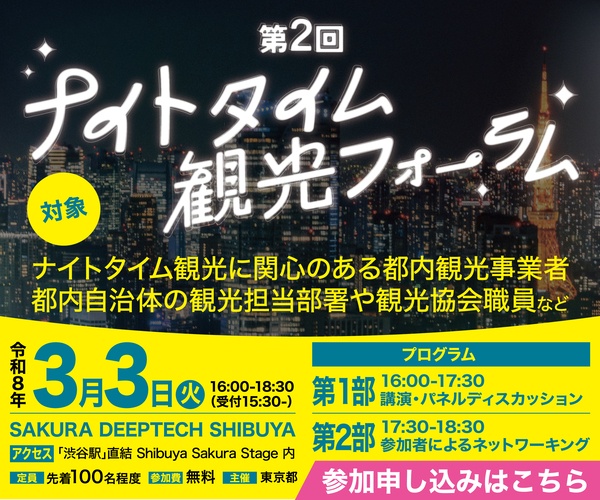本年度の跡見学園女子大学「観光温泉学(温泉と保養)」の授業も終盤に入り、温泉による地域づくりをテーマにした回を迎えました。
そこで2018年から観光協会長として福島県岳温泉を率いている、旅館「花かんざし」の女将の二瓶明子さんからお話をしていただきました。二瓶さんは跡見の卒業生。拙著『女将見た 温泉旅館の表と裏』(文春文庫)のカバーも飾っていただいた深いご縁があります。
本連載でもたびたびつづってきましたが、私は「地域の歴史・文化・風習の伝承者は地域に根を張る宿である」を持論にしていますので、授業の最後に二瓶さんが語ってくれた「地域で一番の宿よりも、地域を輝かせる宿」というお言葉に強く胸を打たれました。
二瓶さんのお話の内容は、まさにこの言葉に帰結する地域づくりについてでした。
開湯1200年の岳温泉の歴史は、時に山津波にのまれ、戊辰戦争では焼き払われ、また旅館からの出火による温泉街の全焼といった受難の繰り返しでした。そのたびに温泉街を移し、乗り越えてきました。
岳温泉といえば、標高1700メートルの安達太良山(あだたらやま)の山頂すぐ下に湧く源泉地帯から、標高600メートルに位置する岳温泉街まで8キロの遠距離引き湯していることで知られています。約40分間も山肌を伝う「引き湯」は日本一の長さだそう。
温泉街の位置を変えながら、「引き湯」をしてきた歴史は、湯守が継承してきました。
湯守の役割も解説してくれました。硫黄成分が多い源泉は空気に触れると湯花が発生し、引き湯する際にはパイプが詰まってしまう。よって「湯花流し」という作業をする必要がある。東日本大震災による土砂崩れで3分の1が埋もれてしまった源泉の復旧作業も続いています。さらに源泉管理をするために冬でも厳しい雪道を行くなど、全てベテラン湯守でないとできない仕事です。硫化水素のガスが伴う源泉での作業は危険と隣り合わせ、といった非常にリアルな実情を「温泉という生き物を扱う危うさ」という印象的な言葉で表現していました。
こうした苦労こそが岳温泉のホンモノを示す価値なのだと、「源泉探訪ツアー」を造成。温泉の尊さを身をもって知る山旅トレッキングです。山頂ではなく、源泉地がゴールというのも納得。
このような岳温泉ならではの引き湯や湯守などの「温泉文化」を伝える取り組みをしている一方で、岳温泉が抱える課題は「岳温泉で生まれ育った事業者が少なくなってきていること」と語ります。
企業が宿泊施設に参入することにより、もちろん大きなメリットはあるが、地域の一体感が失われてしまう。経済効果の域外流失や、歴史ある温泉地だからこそ本質を追求すべき本質が損なわれてしまうことも二瓶さんは危惧していました。
そこで二瓶さんは、宿「花かんざし」の理念として「地域の一番店を目指すのではなく、地域を輝かせる宿になる」を掲げます。
例えば、車で1時間半ほどの浪江町の請戸漁港から魚を仕入れ、浪江町の鮮魚の安全性をお客さまに伝えること。火山灰で浄化された安達太良山のおいしい伏流水で醸された日本酒を提供すること。そして先の大戦中に作られた和菓子「玉ようかん」を出すこと。
これら食材の背景や物語をお客に提供することの重要性を説き、スタッフも日々、学んでいるのだと話します。
この授業を受けた学生さんからは、「単なる宿泊施設としてではなく、地域の魅力や人々のつながりを大切にする場として『花かんざし』を運営されている姿勢から、観光の新しい形や地方における持続可能な暮らしの可能性を強く感じました」と感想が寄せられました。二瓶さんの取り組みはきちんと後輩に届けられました。
(温泉エッセイスト)