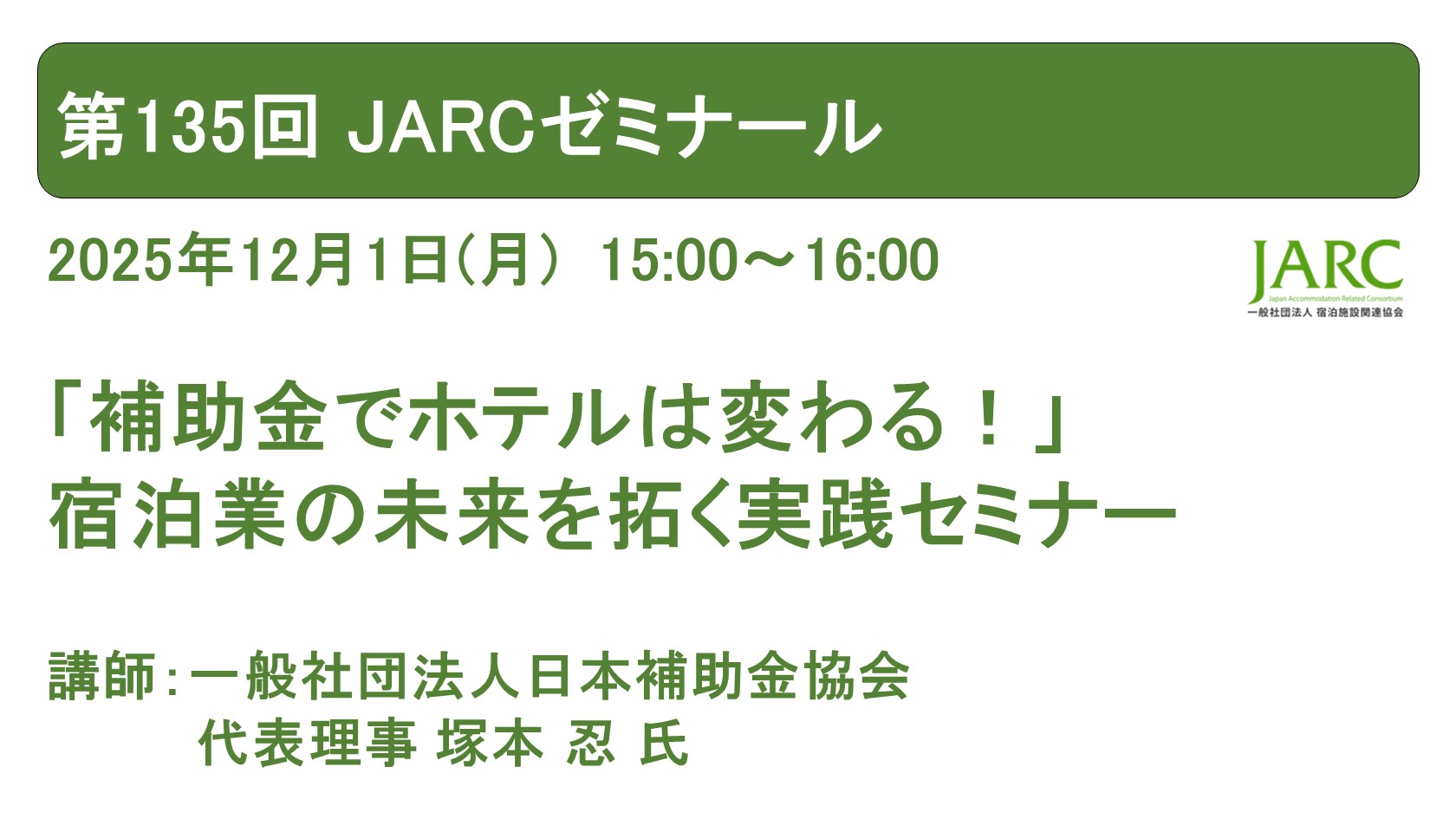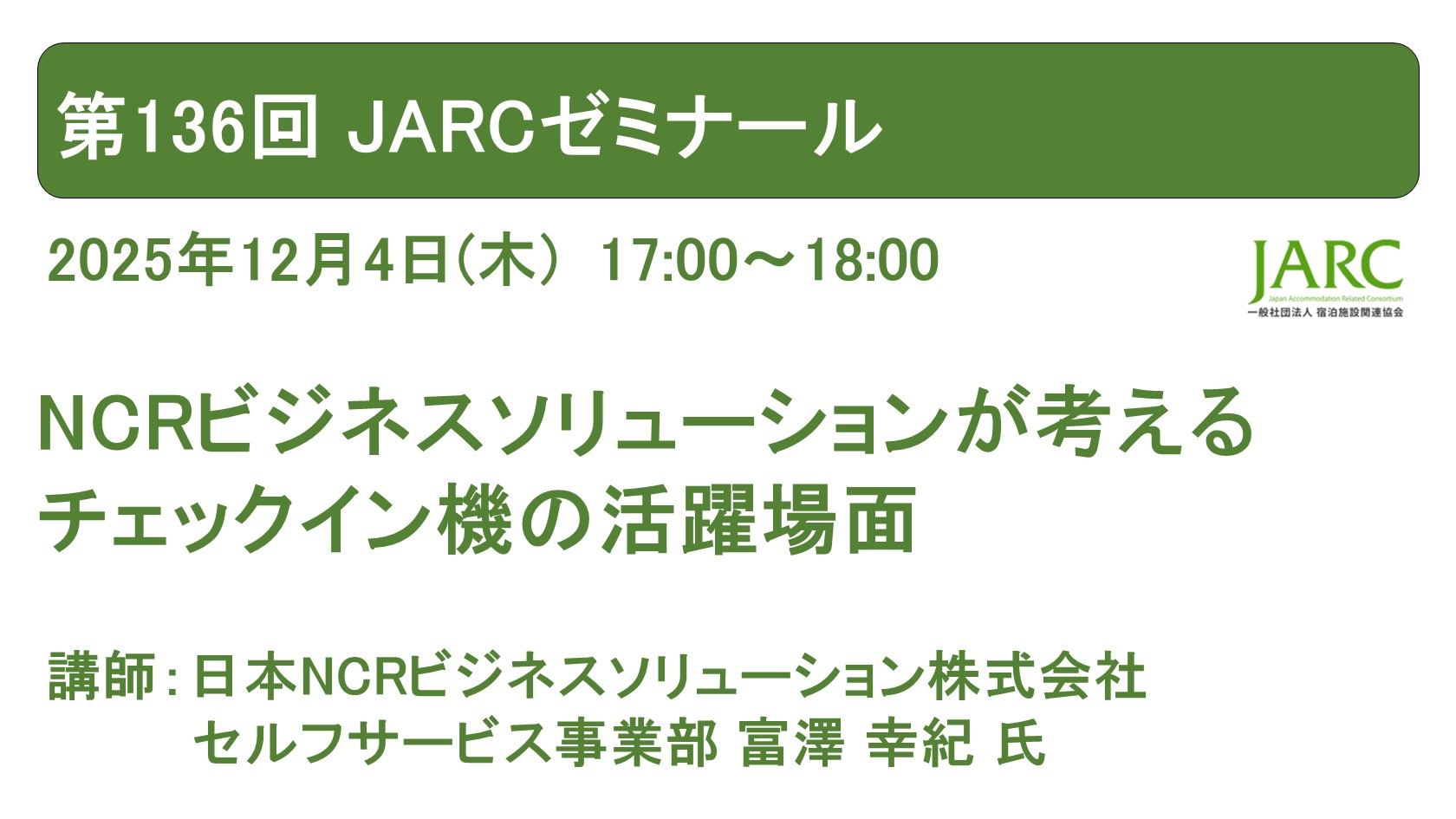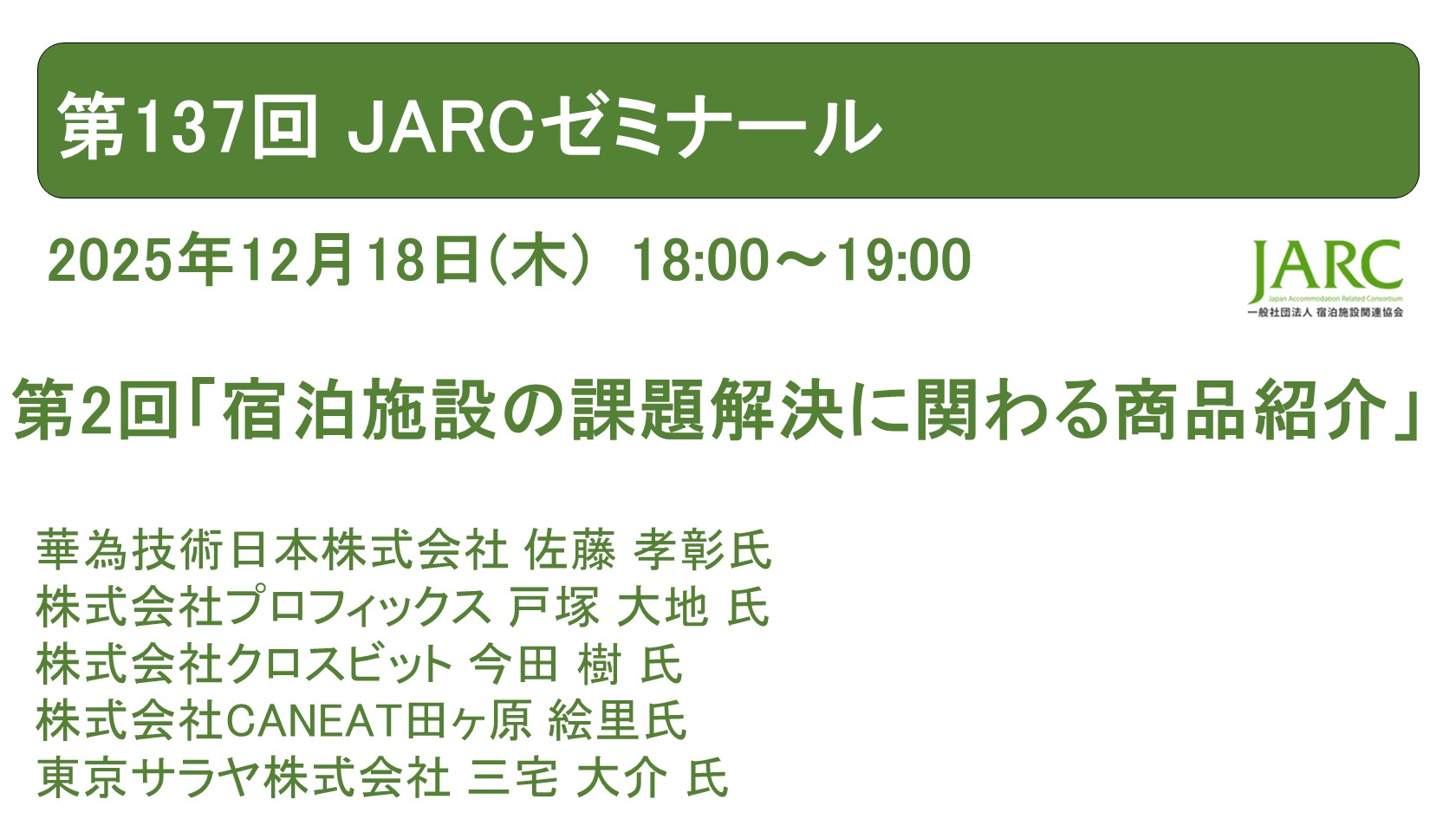宿泊産業を中心とするホスピタリティ産業の経営を、理論的かつ実践的に学ぶための講座です。マーケティング、人事、デザイン、法規、地域振興、投資計画、アセットマネジメントなど多岐に渡る内容から業界の最新動向まで、各分野の専門家や業界を代表する経営陣をお迎えして講義を展開。観光・レジャー産業で働く方々はもちろん、就職活動にのぞむ学生にとっても有益な学びの機会を提供しています。

▷ホスピタリティマネジメント講座
ホスピタリティマネジメント講座パンフレット
【講義内容】
「未来を見据えた持続可能な地域観光戦略とじゃらん(OTA)戦略について」
講師:沢登 次彦(株式会社リクルート じゃらんリサーチセンター長、『とーりまかし』 編集長)
内容:観光産業は国にとって、地域にとって、成長を期待される希望の産業です。コロナ禍以降、予想以上に早く訪日外国人が戻ってきています。国内観光を維持しつつ、訪日外国人増による成長を創る持続可能な観光戦略とは? 未来を見据え、地域は何をしていくべきか?を、じゃらんリサーチセンターの調査及び研究内容を活用してお話しいたします。また、国内OTAじゃらんの戦略も同時にお話しいたします。
「旅館マーケティングの視点」
講師:井門 隆夫(國學院大學 観光まちづくり学部教授)
内容:中小企業の生産性向上が求められていますが、課題解決にはオペレーションだけではなく、資本のあり方まで注視する必要があります。1万年間の定住社会、200年間の余暇経済、50年間の観光バブルがリセットされた今、都市住民の遊動社会を支える社会資本としての地方宿泊業の新しい役割が見えてきています。宿泊業の多様な役割を活かし、資本性資金を調達するためには、観光=レジャーという狭い視野を広げるマーケティングの視点が求められています。
「本質から考える『ホテルの意義の再定義』」
講師:近藤 寛和(宿屋大学 代表)
内容:2020年に発生した新型コロナウィルス感染症により、「宿泊」という需要が大きく縮小しました。その結果、ホテルの本質は「宿泊する場所」ですが、宿泊だけに頼れなくなりました。新たなホテルの価値創造や、ホテルの在り方を模索していかねばならなくなりました。ポストコロナのホテルは、もはや非日常空間でもなければ、単なる寝床でもないと考え、新しい「体験」や「ライフスタイル」を共創する場所としてのホテルを目指すべきフェーズです。では、どのように新たなホテルの価値創造や在り方を考えたらよいか、講義で考察していきます。
「ショッピングツーリズムとは」
講師:新津 研一(一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会 代表理事/事務局長)
内容:世界のインバウンド市場は新たな変化と機会に直面しています。本講義では、市場規模や特徴、競合状況などの基礎知識を学ぶとともに、実際に外国人観光客に来店していただくために必要な考え方や取り組みを具体例を交えながらお話いたします。市場は完全回復しましたが、コロナ禍以前とは、外国人観光客の動向も競争環境も大きく変化しました。その変化に対応するため、具体的なアプローチや取り組みについても学びます。日本と世界のインバウンド市場を理解し、新たなビジネスチャンスを見極めるための知識を身につけましょう。
「ホスピタリティ空間」
講師:山口 有次(桜美林大学ビジネスマネジメント学群 教授)
内容:ホテルや観光・レジャー施設の経営者や担当者において、人をもてなし楽しませ、その魅力を集客につなげる「ホスピタリティ空間」の作り方に関する知識は不可欠である。空間の作り方に関する知見を持たず、計画を外部に委ねる場合でも、顧客満足度や従業員満足度が高く、かつ運営効率や収益性の高い空間とするためには、空間の作り方にも戦略が必要であり、そのための基礎的な考え方を習得しておくことが望まれる。ここでは、レジャー産業界における先進事例の考え方を読み解きながら、利用者の満足度を向上する集客戦略の方向性を、利用者行動からみた時間量・心理量・コミュニケーションの視点から考察する。
「ホテルの人材育成と人的資源管理論」
講師:飯田 広行(株式会社帝国ホテル 人事部人事課マネジャー)
内容:ホテルにとって上質な商品やサービスが成立する条件は、ハードウェア、ソフトウェア、ヒューマンウェアの3つが高品位にバランスよく調和することにあります。とりわけヒューマンウェア=人材の活用がその大きな鍵を握っています。日本の迎賓館の役割を担って誕生し、2025年に開業135周年を迎える帝国ホテルの事例を中心に、ホテル業における人材管理・人材活用について考察します。
「ホスピタリティ産業の環境経営」
講師:丹治 朋子(宮城大学食産業学群 准教授)
内容:地球環境問題がグローバルに深刻化する中で、企業は環境面でも持続可能な経営への移行が強く求められています。日本を含む多くの国が「2050年カーボンニュートラル」を掲げ、脱炭素社会の実現に向けた政策・制度が加速度的に展開されています。また、SDGsやESG投資の観点からも、企業の環境対応は競争力や信頼性を左右する重要な要素となっています。本講義では、ホスピタリティ産業が直面する環境対応の局面を概観した上で、この産業がどのように環境負荷の低減に取り組んでいるのか、具体的な事例とともに紹介し、課題等についても解説します。
「ホテルインテリアデザイン・観光デザイン」
講師:マーク 伊東(Mark Ito Design, Inc. 代表)
内容:ホテル及びそれを取り巻く観光産業のデザインや世界の潮流などを幅広く議論したいと思います。アメリカ・カリフォルニアに25年在住し、アメリカ屈指のホテルデザイン会社にてデザインの仕事を経験し、その後カリフォルニアにてデザイン事務所を運営した経験から、海外からの視点に立ち講義を進めます。まず、日本は世界から見ると非常に小さな国。そして人口も世界から比べれば2パーセント。言語も特殊。文化も特殊。これらを総合的に外国からの目線で俯瞰して日本を見た場合、日本の観光産業が何をするべきか、又は何が出来るかを議論したいと考えています。同時に、日本に住んでいると海外が見えないことを再度理解して頂きたいとも思います。日本の特殊性を理解すれば将来のHorizonは広がると確信しています。
「ライフスタイルホテルのコンテンツと成功のためのエッセンス」
講師:細野 康英(いちご地所株式会社 代表取締役社長)
内容:日本のホテルマーケットにおけるライフスタイルホテルをご紹介いたします。
既存のホテルとは異なるレストラン、ラウンジ、パブリックエリアに宿泊ゲストと地元のゲストが一緒に集まる場所を創り、文化と流行の発信地とする手法と出店戦略についてKNOTのブランドを具体例に話をしていきます。
「新たな旅館経営とDX化について」
講師:宮﨑 知子(株式会社陣屋 代表取締役女将)
内容:神奈川県にある創業106年の旅館を2009年に継承し、経営改善の為、クラウド型宿泊基幹システムを自社開発。2012年より同業他社へのライセンス販売と陣屋での運営ノウハウを他社へも提供を始める。現在は地域連携DXシステムの提供も始め、湯村温泉(兵庫)、別所温泉(⻑野)で別ブランドの旅館を新たに開業。実際に自分達で事例を作りながら地域連携に邁進している。
「ファミリービジネスのホテル運営」
講師:山下 智司(株式会社呉竹荘 取締役会長)
内容:昭和二十三年、静岡県浜松市にて和食料亭としてはじまった「呉竹荘」は、ホテル、結婚式場、レストランとサービスを多様化しながらも、観光事業への注力を行っています。
この講義では、前半においては呉竹荘グループの経営について、その発展の歴史とその中で直面した様々な課題とその克服、ファミリービジネスとしての経営の実態をお話しします。
また、後半では、呉竹荘グループのホテルである「蒲郡クラシックホテル」についてご紹介し、クラシックホテルの意義と運営の実態についてお話しします。
「ホスピタリティ産業のデータ活用-テーマパークを中心に-」
講師:河田 浩昭(東洋大学 国際観光学部)
内容:デジタル化の進展に伴い、スマートテクノロジー(webサイト、アプリ、ソーシャルメディアなど)が観光行動において利用されるようになっています。スマートテクノロジーは観光者に利便性を提供するだけでなく、事業者にとって位置情報や購買履歴、予約情報などの行動履歴データの取得に役立ち、取得したデータを分析することでマーケティング等の意思決定に活用することができます。本講義ではホスピタリティ産業のうち、テーマパークを題材として、データ活用の考え方と活用方法について事例を交えて考察していきます。
「世界のガストロノミーツーリズムの潮流『食文化振興による地域づくりと生態系回復』」
講師:齋藤 由佳子(イタリア土と生態系回復コンソーシアムJINOWA代表)
内容:世界的に関心が高まる環境課題を前に、観光を通して持続可能な地域づくりを行うことは、観光事業者の社会的ミッションです。特に食・ガストロノミーツーリズムは環境配慮型が求められる観光領域であり、旅先での食は美味しさだけでなく、地域にどのような付加価値をもたらすべきかを、イタリアやスペインの先進事例を交えながら考えていきます。
「リゾート、ホテルと地方創生」
講師:澤田 裕一(株式会社リゾートプラス 代表取締役)
内容:リゾートやホテルの開業、運営について大切なことは何か、どのようにして競争力のある施設を創っていくのか。そして、その施設が、いかにして地方の魅力を価値に変えていくことができるのか。沖縄を中心にして、地域振興に宿泊産業がどのような貢献ができるのか、お話しします。
「地方での観光業の起業について」
講師: 石坂 大輔(株式会社ヤドロク 代表取締役社長)
内容:東京・金融業界出身の若者が地方に移住していかに旅館を立ち上げたのか、江戸時代から続く老舗の旅館が多い温泉街でどのように他の旅館と差別化を図って顧客を増やしていったのかを実例を挙げながら講義をします。昨今「地域活性化」や「SDGs」という文脈において地方での生き方を模索する人々が増えてきていますが、一方で地方の観光業においては今なお人材不足が続いている状況です。地方経済においては「観光」が基幹産業として大きな影響を与えることが多く、観光業の盛衰が地域の発展を左右します。旅館経営と同時に人材紹介や旅行業を通して地方に人材を供給する「新しい宿のカタチ」を作り続ける講師の地域づくりモデルをお話しします。
「雪国文化を軸とした新たな観光ブランディング戦略」
講師:井口 智裕(株式会社いせん ISEN corp.代表取締役)
内容: Eastern Washington University経営学部マーケティング科卒業。大学を卒業後、温泉旅館の4代目として家業を継ぐ。2005年に社長に就任し、「湯沢ビューホテルいせん」を「越後湯澤HATAGO井仙」として大幅リニューアル。2008年には周辺7市町村で構成する「雪国観光圏」をプランナーとして立ち上げ、その後15年間にわたり地元の事業者と共に地域独自の暮らしや文化を観光資源に変える取組を実践。2019年には南魚沼市にある老舗旅館の経営を引き続き、雪国を感じる古民家ホテルryugonとして大規模にリニューアル。地域での体験を軸とした新しい旅館づくりを進める。2023年には来訪者に宿の仕事を体験してもらうことで、地域により関わってもらう「さかとケ」という取組を開始。旅館経営者と地域づくり法人の代表という二つの視点から、持続可能な新たな旅行の形を模索している。
「都市マネジメントとしてのホテル開発」
講師:足立 充(立教大学大学院ビジネスデザイン研究科特任教授、元三井不動産ホテルマネジメント取締役会長)
昨今、新規開発ホテルの主流となっている「宿泊主体型ホテル」。事業開始40年余りの歴史の中で、その先達としていち早く宿泊主体型ホテルに舵を切った三井ガーデンホテルズの経緯を日本の宿泊・観光の発展におけるポジションと共に紹介する。また、本来、イベントリスクに耐性のあるホテル運営カテゴリーではあるものの、未曾有の新型コロナ禍におけるその対処を通じて次世代のホテルを展望する。
一方、機能としてのホテルに加え、街づくりを 標榜するデベロッパーを母体とするホテル運営会社にとっての都市マネジメントにおけるホテルの在り様にも触れる。
「外食産業の持続的成長に向けて」
講師:菊地 唯夫(ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役会長)
内容:日本経済はいま大きな転換点を迎えております。デフレからインフレ、過去にない賃上げラッシュ、金利上昇など、久しく見ていなかった景色が広がっております。サービス産業がこの転換期を乗り越え、深刻化する人手不足を克服するためには、過去の延長線上にはない、解を求めていく必要があります。サービス産業におけるデジタル化の本質は何か、人が価値創造を行うホスピタリティにおけるマルチステークホルダーマネジメントはどうあるべきかなど、各種経営テーマを皆さんと考える機会にしたいと思います。
「宿泊施設におけるレベニューマネジメント」
講師:平佐多 彬(IDeaS Revenue Solutions シニアリージョナルディレクター,セールス APAC)
内容:宿泊施設を経営・運営し、継続的に売り上げを上げていくために欠かせない手法であるレベニューマネジメント。この手法が宿泊業界に紹介されて既に数十年が経ちますが、その役割は時代の流れに合わせて変化してきています。講義ではレベニューマネジメントの手法に焦点をあて、そのセオリーをいくつかご紹介することで、聴講者の方が自ら実践に移していくためのきっかけを提供いたします。内容は、宿泊施設で実際に販売活動に携わっている方、宿泊施設を運営されている方、経営されている方に、より適しています。レベニューマネジメントの知識は必ずしも必要とされません。
「ホテル資産投資の概要」
講師:沢柳 知彦(立教大学観光学部 特任教授、株式会社ブレインピックス 代表取締役)
内容:ホテル事業は労働集約的であると同時に資本集約的な産業である。ホテル経営論では触れられる機会の少ないホテル資産投資について概説するとともに、オペレーターとオーナーの契約関係をわかりやすく解説する。また、ホテルの収益構造やアセットマネジメントといったホテル事業全般の基礎知識を広めることを企図する。
「国際ホテル経営論」
講師:阿部 博秀(立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 特任教授、H. A. Advisors, Limited 代表取締役(元日本ハイアット代表))
内容: 外資系ホテルオペレーターは凄まじい勢いで新たなプロジェクトをすすめています。スーパーラグジュアリー、ライフスタイル、ブランデッドレジデンスからオールインクルーシブや旅館、さらに宿泊主体型ホテルのリブランド、コンバージョンまで拡大しています。一方で国内系ホテルオペレーターも静かに着実に大きな変革をすすめています。これらの外資系ホテルオペレーターの経営戦略、開発戦略、競合状況について考えるとともに、日本のホテルオペレーターがどう対抗していくかについても議論します。
「シティホテルの運営について ホテルマネジメント契約の現在地と求められる総支配人像」
講師:後藤 克洋(アーク&カンパニー 代表)
内容:日本のホテル市場は今、ラグジュアリーセグメント及びセレクトサービスやライフスタイルセグメントを中心に外資系ホテルチェーンの戦略的展開が相次ぎ、その訴求市場は旅館あるいは道の駅にも、また、首都圏のみならず地方都市やリゾート地にまで拡大している。その進出形態の多くは所有と運営の主体の分化が前提となるホテルマネジメント契約方式によるもの。本講義では、このホテルマネジメント契約が規定するオーナーとオペレーターの義務と権利の現状を理解するとともに、この契約下で運営を差配する役割を担う総支配人に求められる像をその資質、技術、経験、知識等の観点から明らかにする。
「ホスピタリティアセットマネジメント」
講師:池尾 健(一般社団法人Intellectual Innovations 代表理事)
内容:ホテルはゲストに客室やサービスを提供する施設であることはもちろん、その施設を使って事業を行い収益を生み出す「不動産」でもあります。ホテルを収益不動産と捉え、そのホテルへ投資するとはどういうことか、そしてホテルの価値をどのように捉え、どのようにその価値を上げていくのか、改めてそれぞれの言葉の意味を拓きながら紹介していきます。
「ホテル業とキャピタルマーケット」
講師:平 浩一郎(一般社団法人日本宿泊産業マネジメント技能協会 副理事長)
内容:装置産業であるホテル業は、施設の市場性とは別要因であるキャピタルマーケットにその成否がより大きく左右される業態であり、90年代のバブル崩壊、リーマンショック等の業界への多大な影響を顧みれば明らかである。一方で国内のホテル経営者の多くはこの視点が欠けており、キャピタルマーケットに主戦場をもつ金融プレーヤーに受動的に翻弄されている状況が続いている。コロナ収束後の急速な市場回復が続く一方で労働者不足やトランプショックにより、今後国内ホテル業にどのような影響を与えるのかを過去のケースを参考に検証する。
「ホテル旅館の法規」
講師:小池 修司(畑法律事務所 弁護士)
内容:ホテル・旅館事業を営むにあたっては旅館業法の許可が必要であり、許可を受けた事業者は法の定める様々な事項を遵守しなければなりません。このような公法上の規制が何のためにあるのかを概説し、住宅宿泊事業法(民泊法)の制度設計との比較もしてみたいと思います。また、宿泊客との関係性においては、宿泊約款に基づく契約の内容を理解する必要があり、これに付随して、宿泊客の荷物に関する寄託契約の成否や、宿泊客に対する事業者の安全配慮義務なども問題になります。公法と私法、それぞれの視点からホテル・旅館業の実像を見ていきます。
「ホスピタリティ産業の課題と展望-ホテル事業を中心として-」
講師:藤崎 斉(日本ホテル株式会社 常務取締役 東京ステーションホテル 総支配人)
内容:世界を覆ったコロナ禍の中、国内需要はもちろん、消失したインバウンドビジネスの影響で未曽有の打撃を受けた業界ではあるが、2022年10月に水際対策が緩和され、その後日本人気も有り一挙にインバウンドツーリストによるビジネスが回復した。また円安の影響も含む外部環境を受け、昨今大都市圏を中心に価格高騰も叫ばれる。その状況下であらためてホテル業の形態や、リーダーシップ論等も含めて、観光立国を支えるべきホテル業の課題と展望を考察する。
▷観光地経営専門家育成プログラム
【講義内容】
オリエンテーション
講師:橋本 俊哉
本プログラムの円滑な受講に向けて、プログラムの趣旨、注意事項、スケジュールの説明に続き、本プログラムをより深く理解するための「オリエンテーション講義」を行う。
「観光地における価値の創造」
講師:安島 博幸
観光地に外部から人が訪れるのはなぜか。それは、地域に人を惹きつける魅力があるからである。その魅力を地域の観光的価値と呼ぶ。価値が高まれば、多くの観光客が訪れて観光地は発展し、価値が減少すれば訪れる人が減って、観光地は衰退してしまう。では価値は、どのような要因で増えたり減ったりするのだろうか。観光的価値にはいくつかのタイプがあり、タイプ毎に固有のさまざまな特徴、性質について考える。
「未来を見据えた持続可能な地域観光戦略とじゃらん(OTA)戦略について」
講師:沢登 次彦
観光産業は国にとって、地域にとって、成長を期待される希望の産業です。コロナ禍以降、予想以上に早く訪日外国人が戻ってきています。国内観光を維持しつつ、訪日外国人増による成長を創る持続可能な観光戦略とは?未来を見据え、地域は何をしていくべきか?を、じゃらんリサーチセンターの調査及び研究内容を活用してお話しいたします。また、国内OTAじゃらんの戦略も同時にお話しいたします。
「観光地からの情報発信」
講師:抜井 ゆかり
SNS時代となり、観光地側からの情報発信に、より戦略的な施策が必要となっている。その基礎となる観光情報の流れやSNS各々の特徴を把握し、「観光者のファンマーケティング」、「観光地とメディアの関係構築」の方法を解説する。また、インバウンド観光に関しては、国ごとに異なる事情を基礎とした「各国別のインバウンド対策」に対する留意点を概説。さらに、フィールドワークを活かし、マーケティング分析を伴う課題の提案も行う。
「観光地の調査分析方法1:経済学」
講師:野原 克仁
昨年5月、世界気象機関(WMO)のターラス事務局長が、「今後、地球の気温は未知の領域に入る」と述べた。気候変動問題の深刻化は、地域の自然環境を劣化させ、観光産業にも大きな影響を及ぼす可能性がある。地域の自然環境を維持し、観光産業の衰退を防ぐには経済学による分析が必要不可欠である。本講義では、実際の環境保全・観光政策にも用いられている、自然環境の価値を評価する経済モデルとデータ収集および分析方法を実例と共に紹介する。
「町並み観光地の経営」・フィールドワーク1(川越)
講師:溝尾 良隆
川越が観光地として発展したのは1970年代半ばからである。現在、観光の中心は、蔵造りの建物が集中する一番街と菓子屋横丁である。一番街は江戸時代、1650年前後に、職人町・商人町として整備されてから、1960年代前半まで、ずっと中心商店街として機能してきた。しかし、多くの大型店が川越駅方面に進出して以降、その機能は低下して寂れてしまった。外部の専門家たちから指摘をされて、しだいに蔵造りをいかした町並みの整備が始まり、観光客で賑わうこととなった。いくつかのあたらしい観光対象が付加されている一方で、オーバーツーリズム、観光の質の低下、観光協会の役割、観光のデータ、一番街の車など、問題は山積している。
「サービスデザインで考える観光のソーシャルイノベーション」
講師:柴田 吉隆
サービスデザインは、「デザイン思考」とも呼ばれるデザインの考え方を応用してサービスの発想や計画を行う活動である。このプログラムでは、皆さんが事前に行った観光地に関するリサーチをもとに、ワークショップ形式で当該観光地における新しいサービスの可能性について考える。当該地域と住民や来訪者との関わり方にサービスを通じて変化をもたらし、地域社会や観光に対する人々の認識を変えるようなソーシャルイノベーション指向の提案をしてもらう。
「温泉観光地の経営」・フィールドワーク2(湯河原)
講師:梅川 智也
コロナ禍を経て温泉観光地が目指すべき方向性を履修者とともに考えていくことを目的とする。初日の講義である「温泉観光地の経営」では、『観光地経営の視点と実践』(丸善出版)を参考図書として、温泉観光地の経営にとって重要なポイントについていくつかの視点から学んでいく。翌日の湯河原温泉でのフィールドワークでは、現地の行政担当者、もしくは観光協会担当者の案内により、万葉公園(Park-PFI事業による)をはじめ湯河原温泉の主要エリアを視察し、温泉地再生の具体的な事例を学ぶこととする。その日の最後には行政担当者も交えて総括的なディスカッションを行う予定である。
「温泉観光地の経営事例分析」
講師:桑野 和泉
保養温泉地「由布院」を題材に、地域経営をマクロの視点で考察する。講義では、由布院の持続可能性、環境保護、観光と社会的変化などのテーマについて学ぶ。100年の時間軸で捉え、現在の課題を明確にし、未来ビジョンを共有することで、持続可能な観光地としての魅力を一層高める地域経営の可能性、観光まちづくりを探求する。
「観光地の調査分析方法2:地域の見方/歩き方」
講師:西川 亮
本講義では、都市計画やまちづくりの視点から地域を捉える視点や観光地の特徴を把握する方法を学ぶ。都市は地理的・地形的な条件の上に、様々な法制度や地域住民によるまちづくり活動の蓄積があり、人々の生活の営みがある。観光のベースとなる地域の見方・歩き方を理解することで、観光を批判的にも見る視点を養いたい。
「観光地の調査分析方法3:地理学」
講師:佐藤 大祐
観光地理学は資源やアクター、動機、情報などの観点から観光に関わる空間を科学する。空間を科学することが、いかにして観光地の資源発掘や魅力作りなどに貢献していくのか。授業では、科学すること、すなわち資料やデータをどのように取得するのか、それらを分析する手法にはどのようなものがあるのか、そして得られた結果を観光地の観光戦略や集客戦略といかに結びつけるのかなどについて検討する。
「地域人材を育てる新たな視点と仕組み」
講師:大西 律子
観光まちづくりの現場では、「結局、それを誰が担うのか、動ける人がいない」との嘆きがよく聞かれ、「人材」を巡る問題が常態化している。そんな中、新しい枠組みから地域人材を捉え直し、人材の確保・育成に奔走している地域も見られ始めている。本講義では、そうした地域の事例や、担当講師が長らく携わってきた地域の担い手育成に関わる各種プロジェクトを手がかりに、「地域人材を育てる新たな視点や仕組み」について考える。
総括
講師:橋本 俊哉
本プログラムで受講した講義・フィールドワークの中から、とくに印象に残った内容を各受講者間で共有することにより、これからの観光地経営に向けた知見を振り返る。