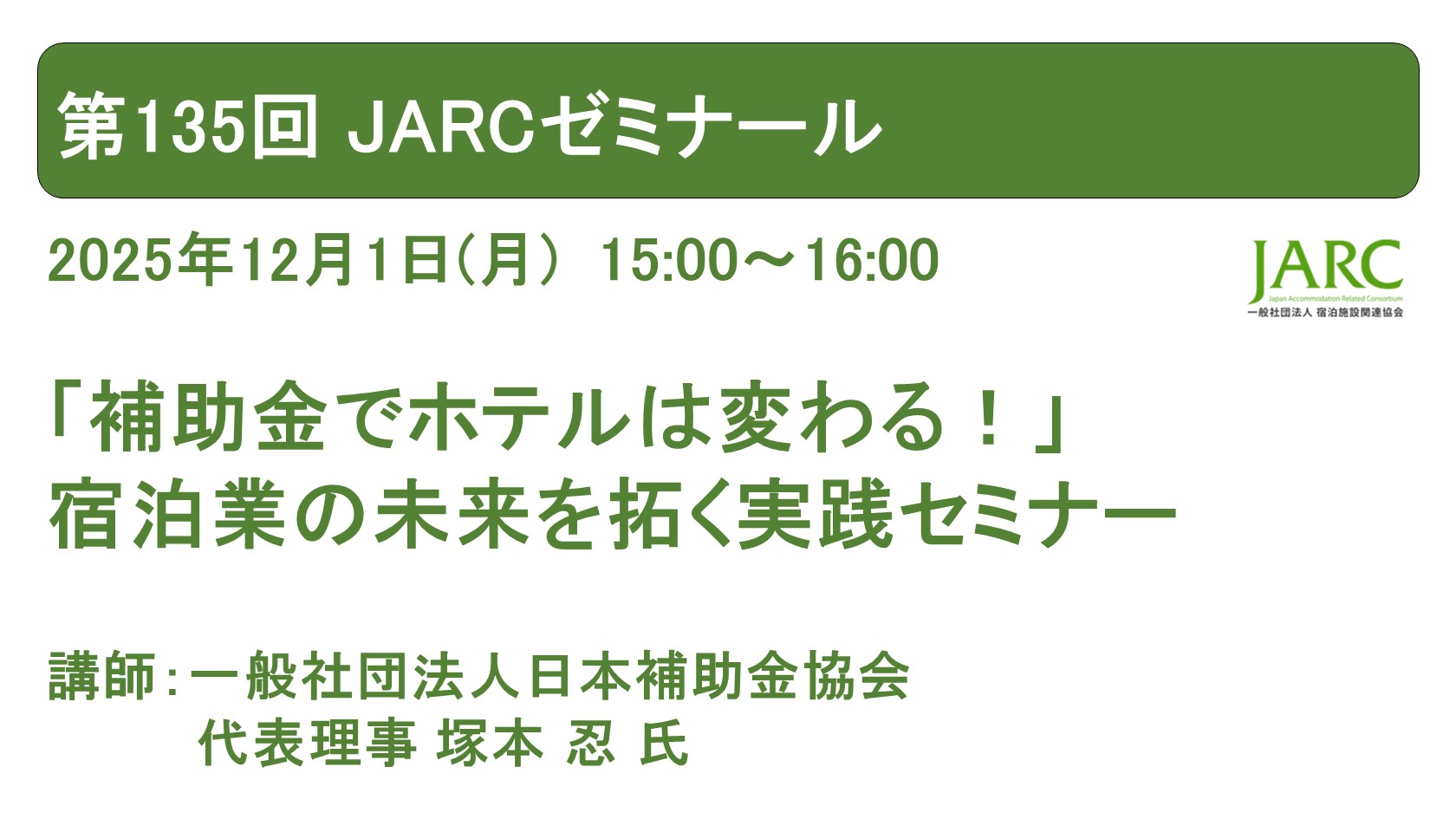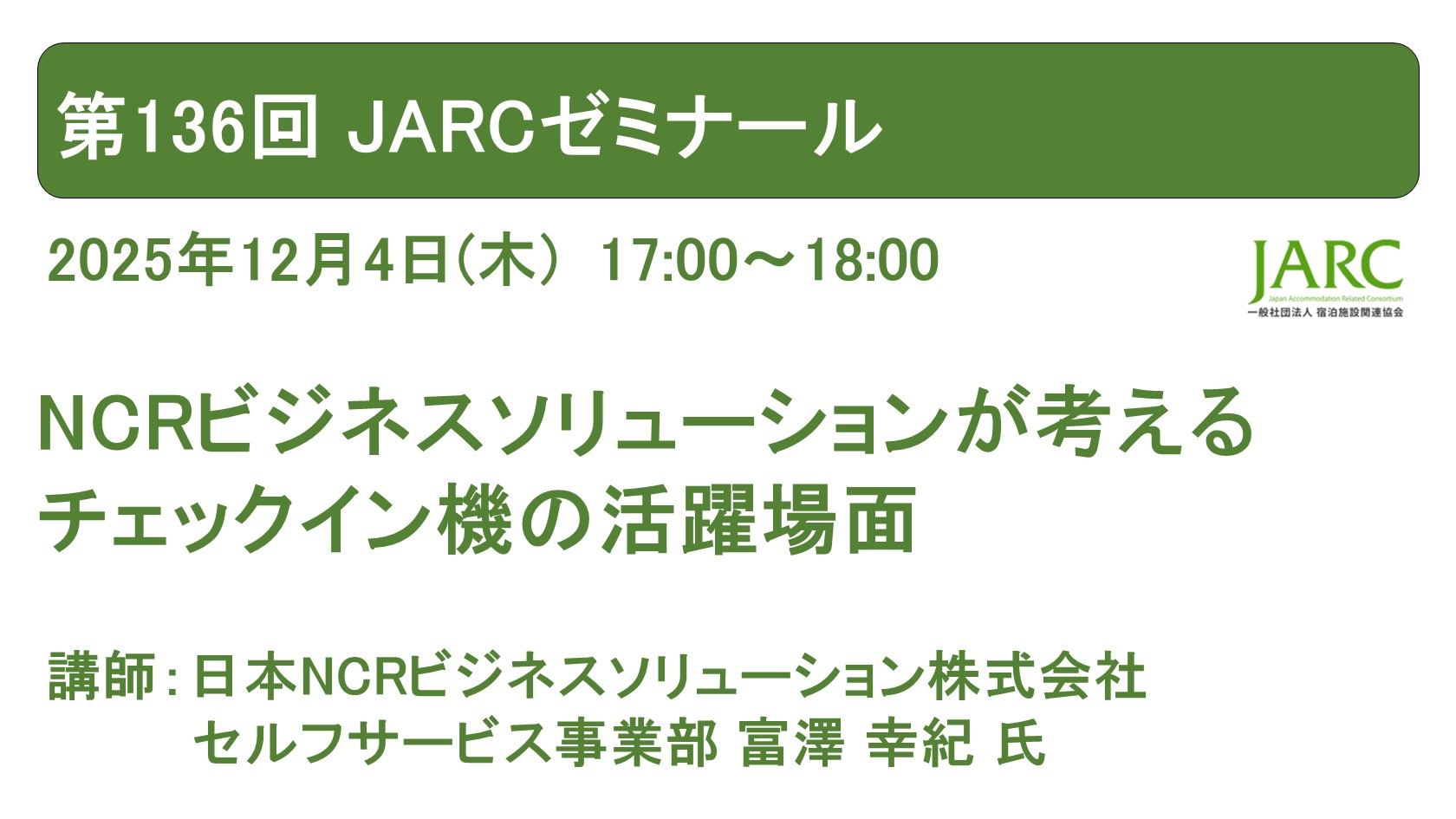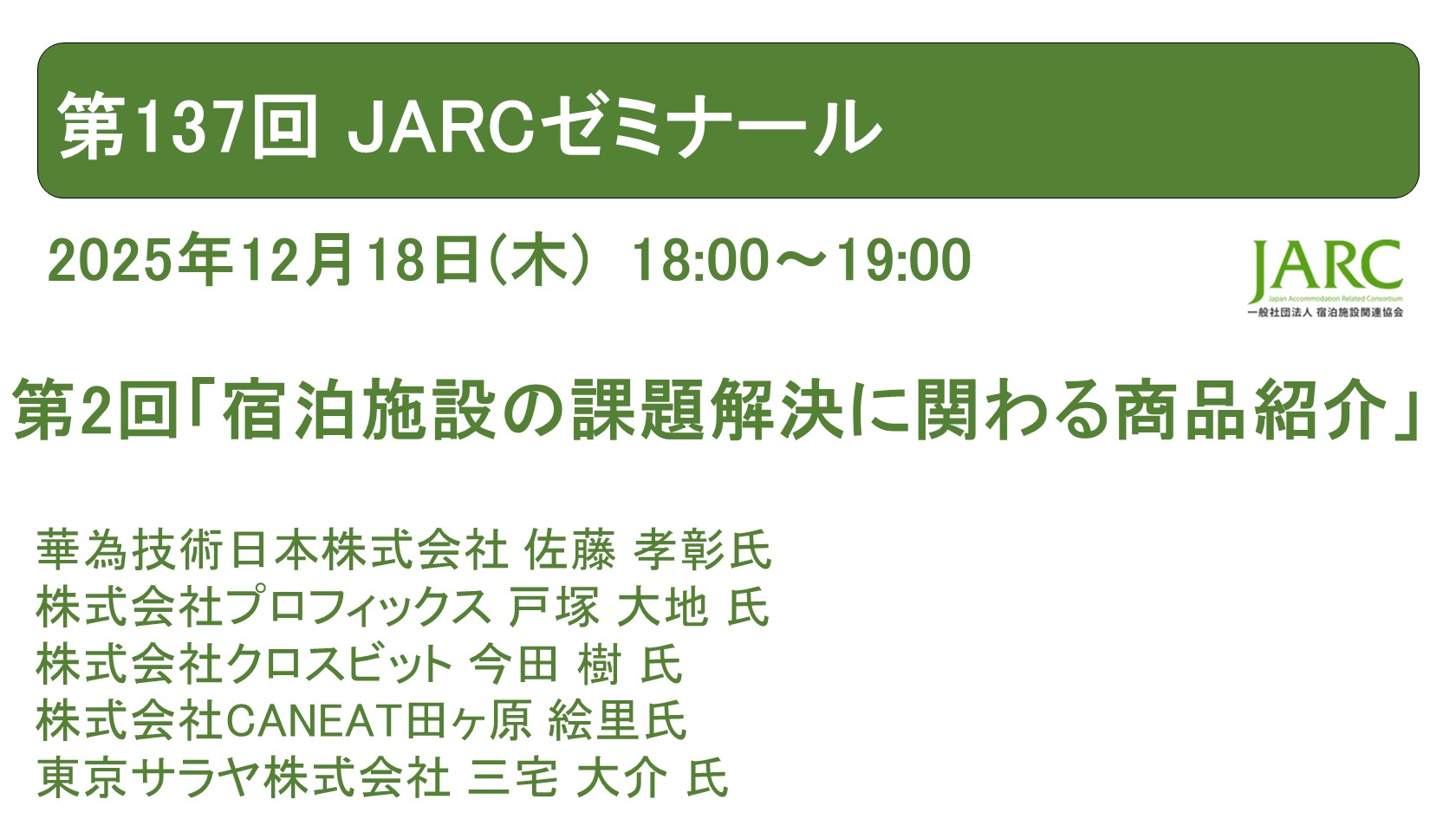一般財団法人運輸総合研究所は6月20日、宿泊事業者向けに『宿泊産業の生産性向上についての手引き』を公表した。観光産業を日本経済を支える基幹産業と位置づけながらも、労働生産性の低さや人手不足という課題に対応するためのガイドラインだ。手引きでは「施設への投資」「業務改革及び人的資本の蓄積」「顧客がサービス等に対して感じる価値及び経営者のプライシング能力の向上」の3つの観点から現場での実践につながる内容を整理している。
宿泊業の労働生産性、全産業平均を大きく下回る現状
手引き作成の背景には、日本の宿泊産業が直面する生産性の課題がある。運輸総研が検討委員会での議論を踏まえてまとめた資料によると、宿泊業と飲食サービス業の労働生産性は全産業平均を下回り、非製造業全体と比較しても低水準にとどまっている。さらに国際比較でも、2020年時点で日本の宿泊・飲食サービスの労働生産性は主要国より低く、日本を100とすると米国やフランスは約3倍の水準だという。
一方で、同じ観光関連産業でもインターネット付随サービス業や旅行業の労働生産性は全産業平均を上回っており、宿泊業に特有の課題があることが明らかになった。また宿泊業内でも資本金規模が小さいほど労働生産性が低い傾向があるという。
運輸総研は「観光産業は世界的にも経済成長を牽引する重要産業」と位置づけ、「日本固有の既存資源を活用し、大きな雇用を吸収しつつ、国内外の需要を取り込み国内経済に裨益する循環で、長期的成長を見込める日本経済を支えるリーディング産業」と評価している。
しかし現状では「労働集約型産業のため、担い手である人手、経営・管理等を適切に行う人材確保が長期成長には必須だが、労働生産性が低く、賃金水準が低いため、一貫して人手不足の状況」と指摘している。
そこで運輸総研では2024年1月に「地域観光産業の見える化に関する検討委員会」を立ち上げ、観光有識者・実務者、経営有識者、事業革新有識者、観光庁を委員とし、宿泊事業者を招聘して議論を重ねてきた。その成果として今回の手引きを作成した。
検討委員会では国内の宿泊事業者にヒアリングを実施し、実態調査も行った。その結果、多くの宿泊事業者において「各帳簿は整備されているが、時価会計ベースのものは作成されておらず、経営状況が正確に把握できていない」「投資計画の作成が実施されていない。もしくは結果の振り返りを実施していない」「労働関係法規の遵守にとどまり、従業員のエンゲージメント向上に向けた取組は不十分」などの課題が明らかになった。
また「顧客ターゲットのセグメントが多くの施設で未設定であり、顧客に向き合ったコンテンツ開発やプライシング、プロモーションが継続的に実施できていない」「リピート率、客室平均単価(ADR)、客室稼働率(OCC)、販売可能な客室1室あたりの収益(RevPAR)等の指標を把握できていない」など、マーケティングやプライシングに関する課題も浮き彫りになった。
一方、海外調査も実施し、特に外国人観光客数世界首位のフランスでの宿泊産業の現状や取り組みについて詳しく調査した。フランスでは、観光客への施設のサービスの質に関する可視化と宿泊施設のサービスの質向上を目的とした格付制度や、デジタル化診断ツールと融資制度の整備、経営や人材管理、リスク管理に関するオンラインガイダンスの提供など、多面的な支援が行われている。
また、地域別に比較可能なデータベースの開発も進んでおり、宿泊施設の占有率、RevPAR、観光客意識調査、観光施設の入場者数や収支、居住者の意識調査、環境リスクマップなどの情報をリアルタイムで提供するシステムも構築されている。
フランスの宿泊事業者へのヒアリングでは「RevPAR」や「売上に占める支出割合」の指標を重視していること、人件費削減よりも顧客満足度を重視する経営姿勢、従業員の就業環境整備やコミュニケーション強化による職場環境改善の取り組みなどが明らかになった。
こうした国内外の調査結果を踏まえ、運輸総研は宿泊産業の生産性向上のためには製造業等と同様に施設への投資や業務改革及び人的資本の蓄積が重要である一方、宿泊産業特有の要素として「雰囲気・ブランド・顧客の知的満足を充足する説明等の『ソフト面の価値』が重要であり、この価値に相応する的確なプライシングが生産性向上の鍵」であると結論づけている。
手引きでは、宿泊事業者の取り組みを3つの観点から整理している。
1. 施設への投資
2. 業務改革及び人的資本の蓄積
3. 顧客がサービス等に対して感じる価値及び経営者のプライシング能力の向上
運輸総研は、宿泊事業者の取り組みに加え、観光協会・DMO、自治体にも本手引きを活用してもらうことで「地域の観光産業の現状理解が進み、地域の観光産業全体の生産性向上に貢献したい」としている。
またフランスでの調査結果を踏まえ、今後の取り組みとして「公的格付制度の導入、管理会計の徹底、DMOの本来機能発揮、DMOとの連携などの取組みや、国の支援に当たっての『手引き』の活用等の要件化などが行われることが必要」と提言している。
日本の宿泊産業は2023年度、インバウンドの増加などによる大幅な需要回復により、生産性上昇率は全産業で最大(前年度比+12.0%)となった。ただし「生産性上昇幅に比べて賃金変化幅は小さい」という課題も指摘されている。
なお、今回の取り組みは「地域観光産業の基盤強化・事業革新に関する提言」(2023年7月)に基づくものであり、「生産性向上の取組の根拠となる観光産業における『付加価値』の創出・分布構造の『見える化』を図ることが必要」「地域観光産業の地域価値や地域経済への貢献に関する『見える化』が必要」という提言を具体化するものとなっている。
『宿泊産業の生産性向上についての手引き』は運輸総合研究所のウェブサイトで公開されており、他にも「地域観光産業の見える化に関する検討委員会とりまとめ」のポイント版、簡略版、本文、補足資料なども公開されている。