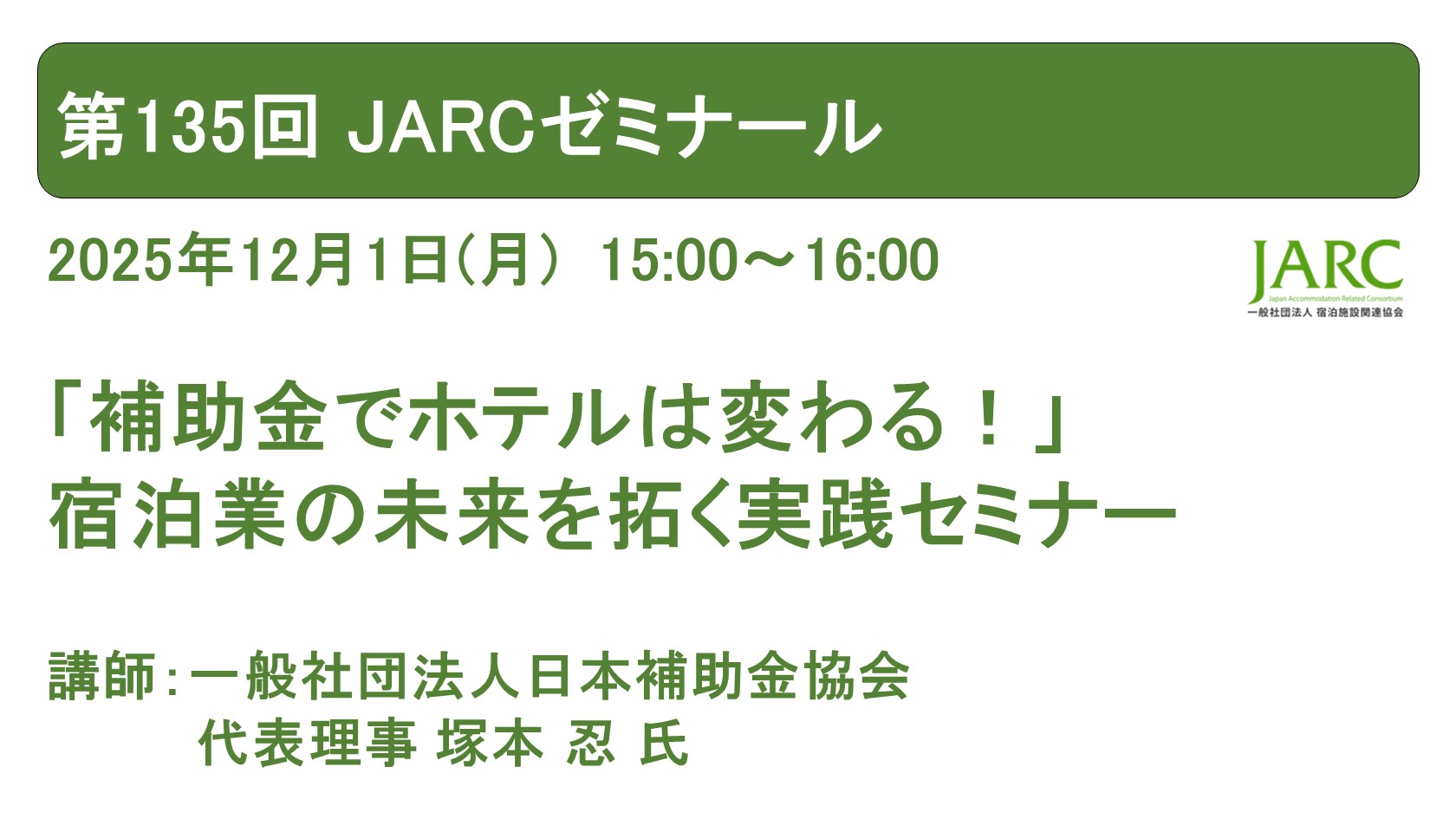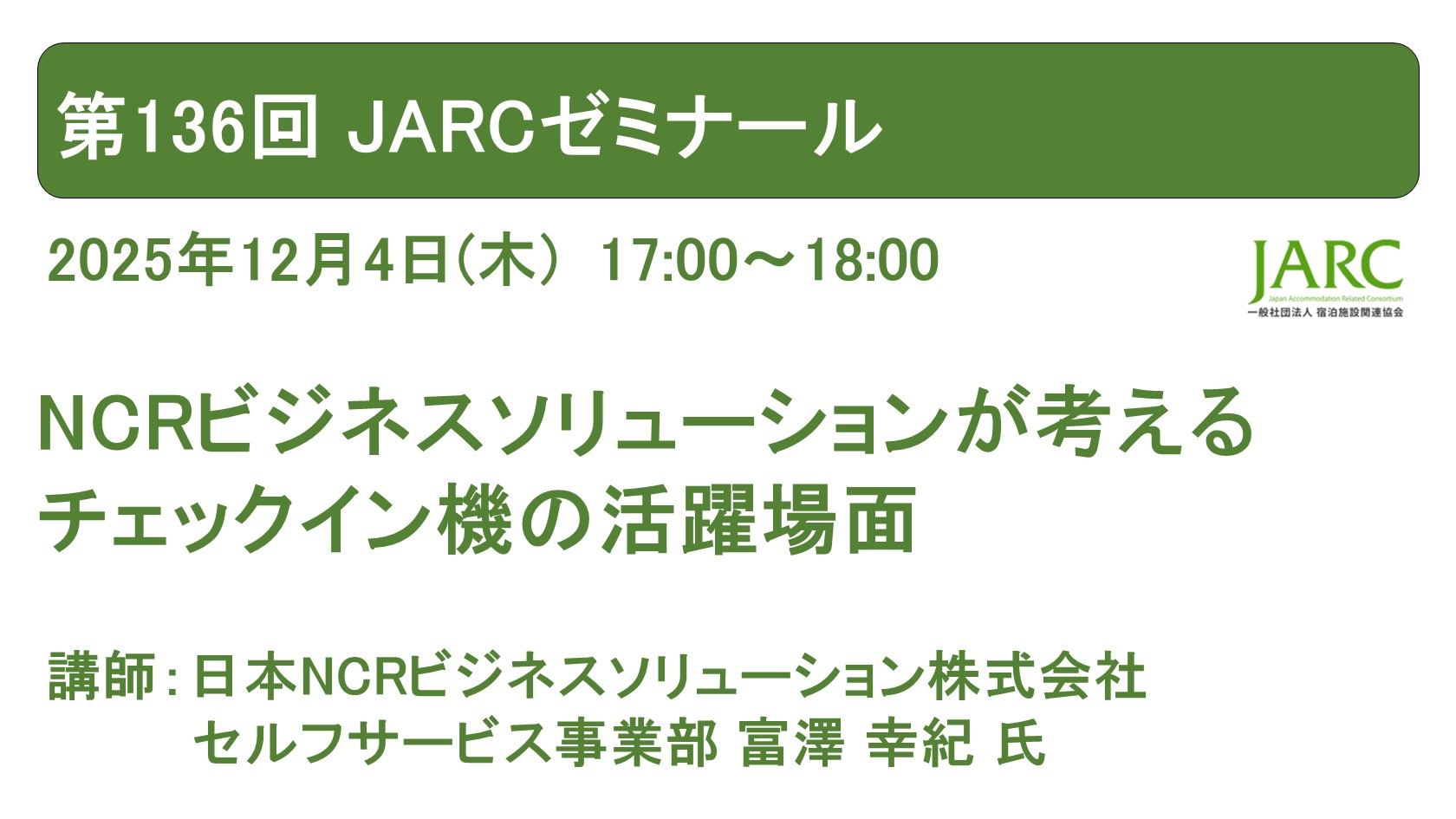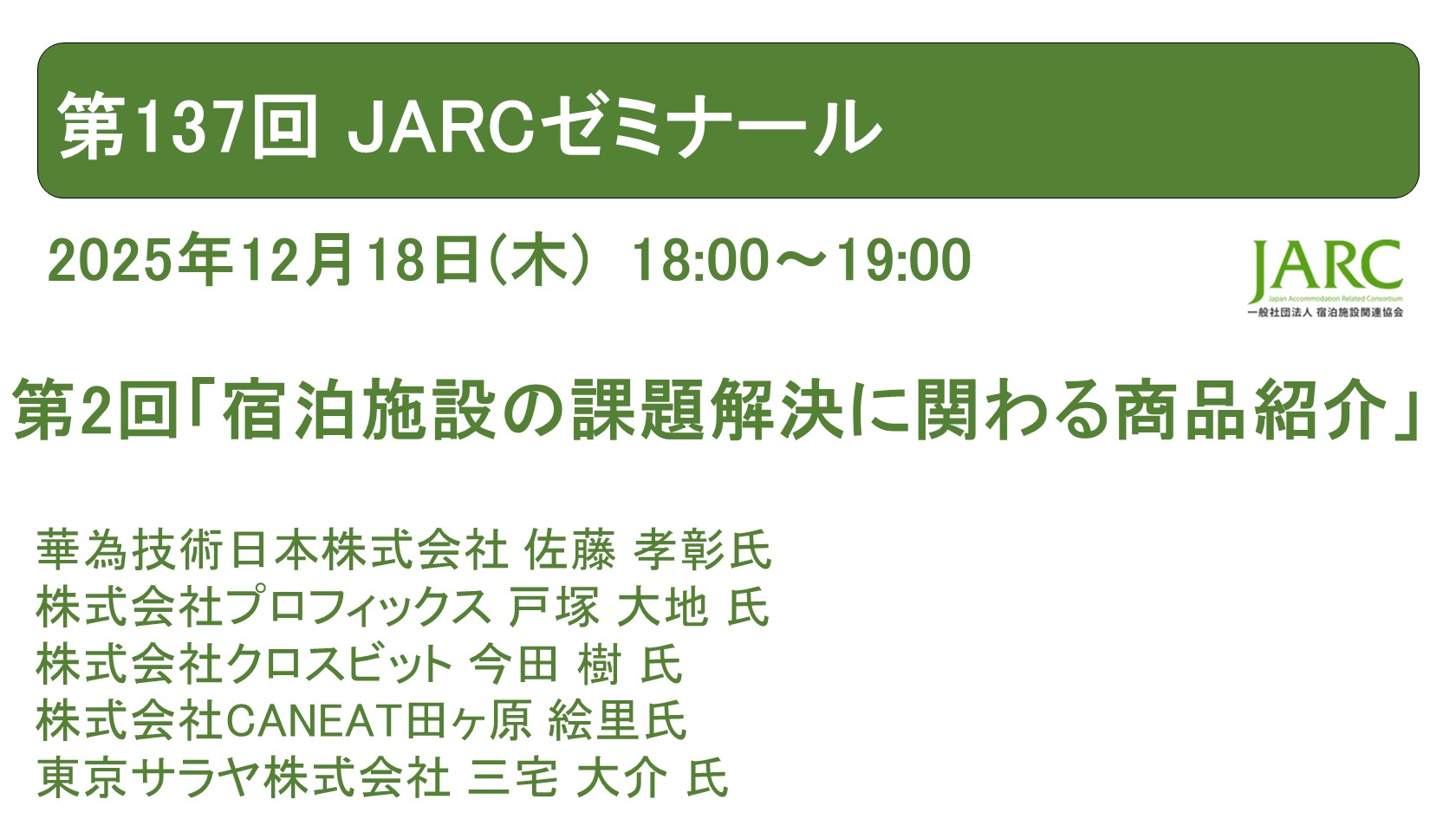自治体の責任主体化と委託制への転換を提案
運輸総合研究所は2025年6月30日、「地域交通制度の革新案」と題した緊急提言を発表した。人口減少や運転士不足で地方だけでなく都市部でも維持が困難になっている地域交通の存続に向け、自治体を責任主体とし、公的負担の根拠を「補助」から「委託への対価」へと転換するなど、抜本的な制度改革を求めている。同研究所は7月7日にシンポジウムを開催し、制度革新の具体案について議論する予定だ。
提言は、地域交通を「公共財」と位置づけ、現行制度では存続が難しくなっている現状を打破するため、道路運送法や地域公共交通活性化・再生法など関連法の改正を含めた27項目の革新案を示した。
運輸総合研究所によると、地域交通の主な担い手である民間企業は厳しい経営状況に加え、運転士などの人手不足が一層深刻化しており、地方部のみならず都市部でもサービスを縮小せざるを得ない危機的状況にあるという。特に「2024年問題」と呼ばれる労働時間規制の厳格化により、運転士不足は今後さらに深刻化すると予測している。
地域交通を国家的・国民的・地域的に必要不可欠な「社会資本」であり「公共財」と位置づけた上で、制度革新の要点として、地域交通確保の責任主体を自治体とすること、公的負担の根拠を支援(補助)ではなく委託への対価とすること、法定協議会の設置および法定計画策定の義務化などを挙げた。
また、現在の「需要」に基づく地域交通政策を転換し、「潜在的な需要も含め、地域住民をはじめとする国民の生活の質(QOL)を向上させ、ウェル・ビーイングによる豊かな生活を実現する」ことを確実に広く社会の共通認識とすることが必要だとしている。
提言では、地域交通制度の革新が「地球環境保全、国土強靭化、地方創生などの国家的課題、そして地域住民をはじめとする国民の生活の質(QOL)を向上させ、ウェル・ビーイングによる将来に向けた豊かな生活の実現などの国民的課題に貢献する」との考えを示した。
地域公共交通総合研究所が今年2月に実施した「公共交通経営実態調査」によると、地域交通事業者の経営を圧迫している主な要因として、燃料高騰問題(22%)、人手不足問題(18%)、人件費高騰問題(12%)、利用者減少問題(12%)などが挙げられた。また、行政の支援や制度改善への期待としては、補助金・補助制度(21%)、制度改善・規制緩和問題全般(18%)、燃料費補助(17%)などが多かった。
運輸総合研究所は7月7日、東京都内でシンポジウム「緊急提言~地域交通制度の革新案~」を開催し、全国各地のバス等の交通事業者が登壇して地域交通の現場の視点から制度革新案について議論する予定だ。同シンポジウムには、会場とオンラインを合わせて1000名を超える参加申し込みがあるという。
「地域交通制度革新に関する検討委員会」の委員長である屋井鉄雄氏(運輸総合研究所所長、東京科学大学特任教授)らが中心となって取りまとめた今回の提言は、昨年9月の「地域交通産業の基盤強化・事業革新に関する検討委員会」提言に基づき、法制度等の革新案をさらに具体化したものだ。地域交通の基盤強化・事業革新のために目指すべき法制度等について、現状では地域交通事業の存在・存立自体が困難となっていることから緊急に提言したとしている。
提言では、地域交通の事業を現在の細分化された制度から、道路を活用した人の輸送に係るサービスを継続提供する事業はすべて「自動車交通事業」(仮称)として再整理するなど、シンプルで明快な事業制度への転換も提案している。無償送迎やシェアサイクル、タクシーアプリなども含まれるという。
また、事業開始の許認可は法定協議会の合意を要件とし、法定協議会の合意により手上げ方式で自治体が行うことも可能にするとした。公的負担については、法定協議会への一元交付化や地方交付税の地域交通充当額の明確化なども提言している。
緊急提言のベースとなった考え方は、1996年に運輸省(当時)が決定した「運輸分野の需給調整規制廃止」から約四半世紀が経過し、「競争により利用者の利益の保護及び利便の増進を図る」という当初の目的から、「競争から協調・共創へ」と社会経済状況が変化したことを踏まえたものだ。
提言では、「単に赤字補填を続けていくだけでは地域交通の確保は困難。現行制度での対応は既に限界」「サービスの縮小等で地域・国民生活(QOL)の質は低下。ウェル・ビーイングによる豊かな生活の実現を困難にすることで持続可能な社会の実現の観点でも危機的状況」と現状を分析している。
運輸総合研究所はこの緊急提言を通じて、法改正を含めた制度革新が早期に実現されるよう、国や自治体などに対して働きかけていくとしている。