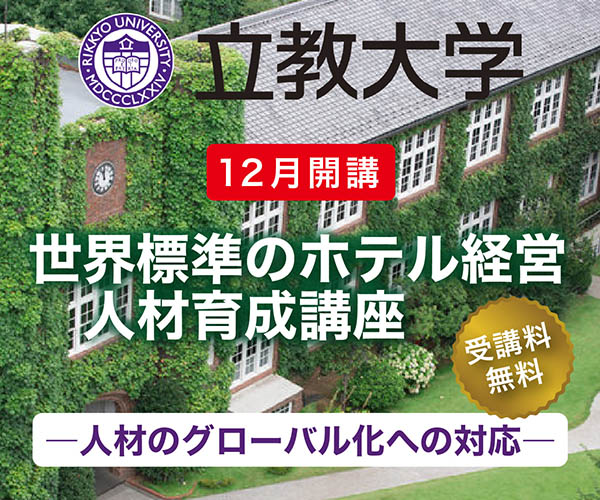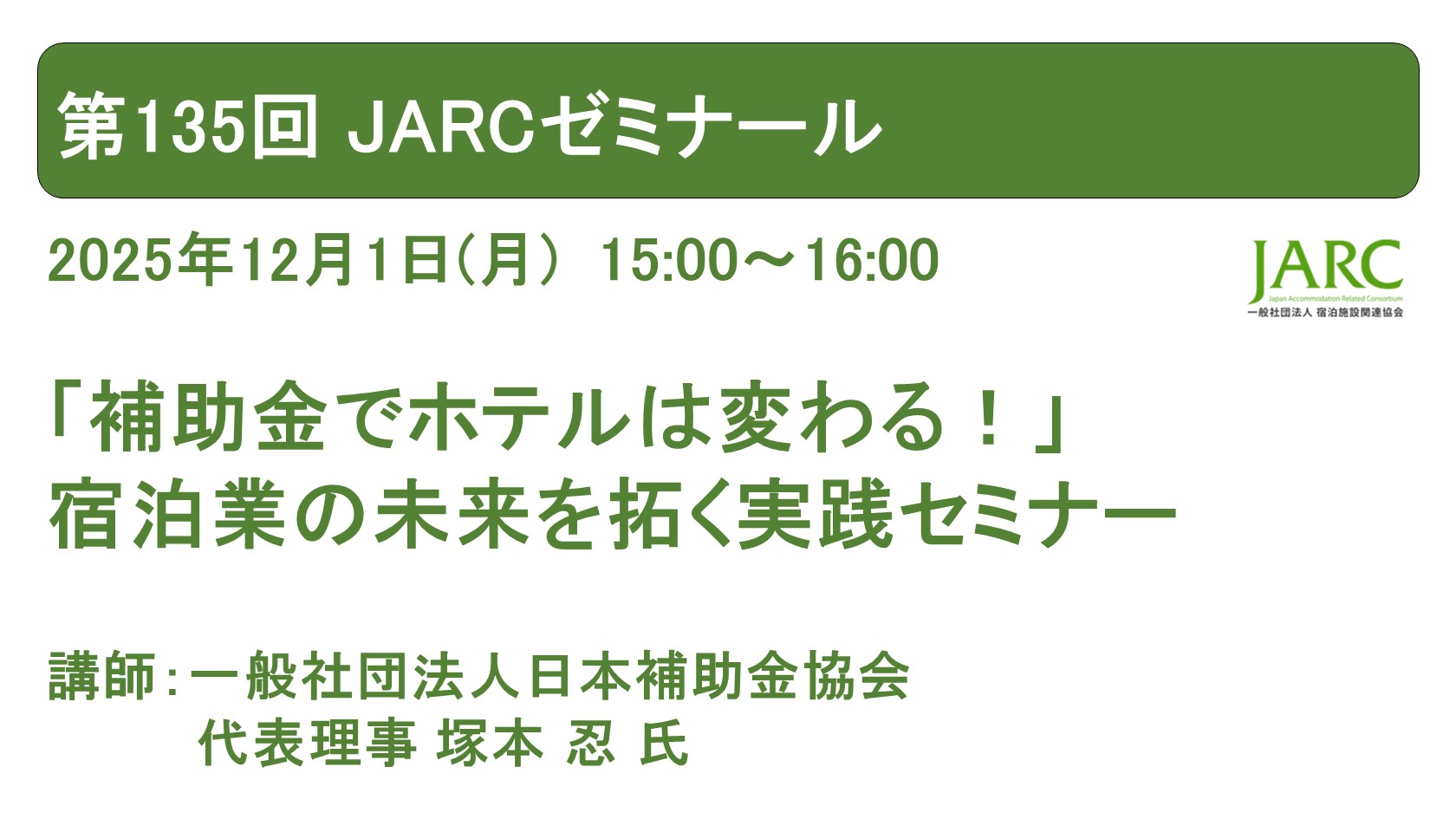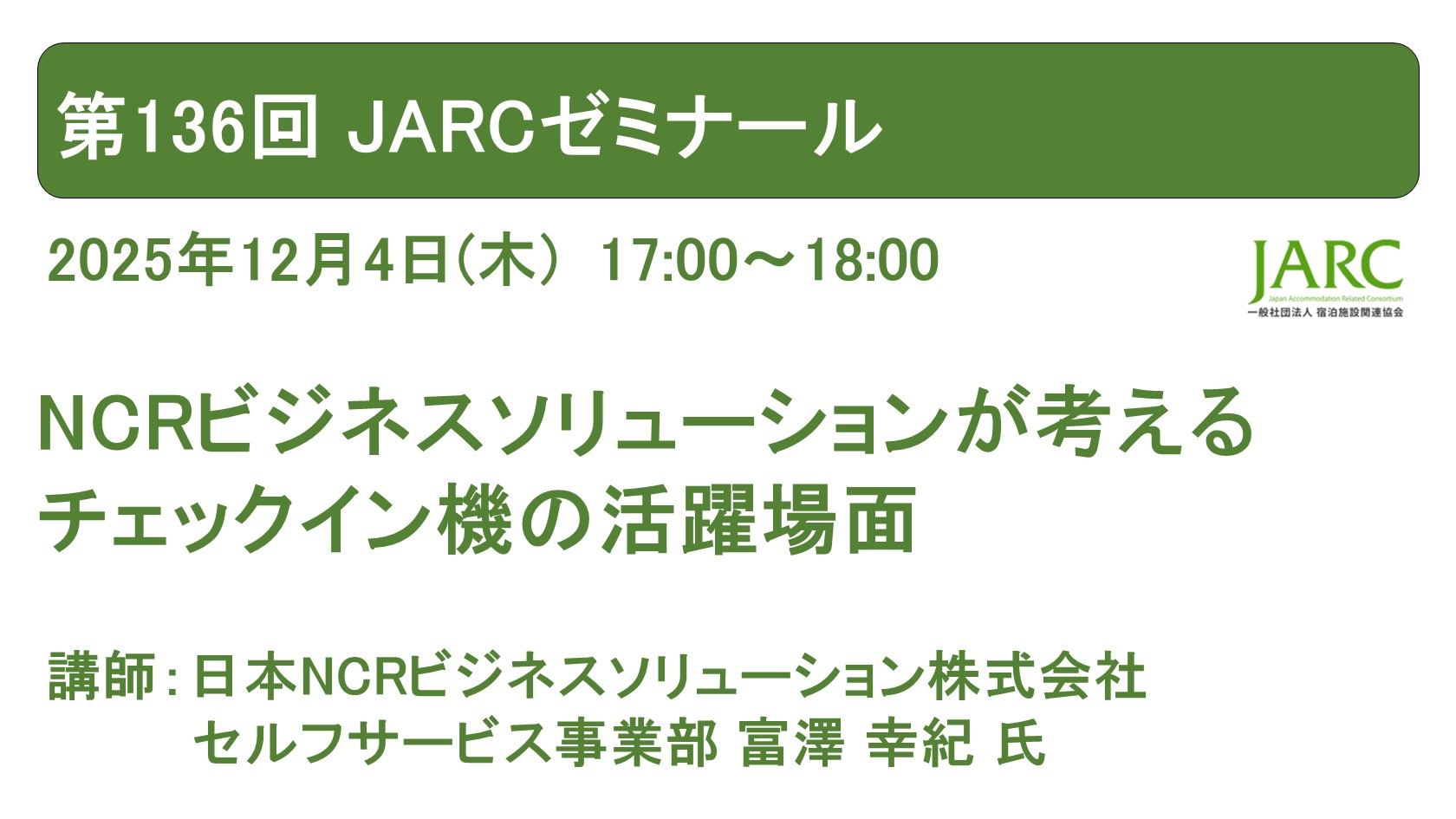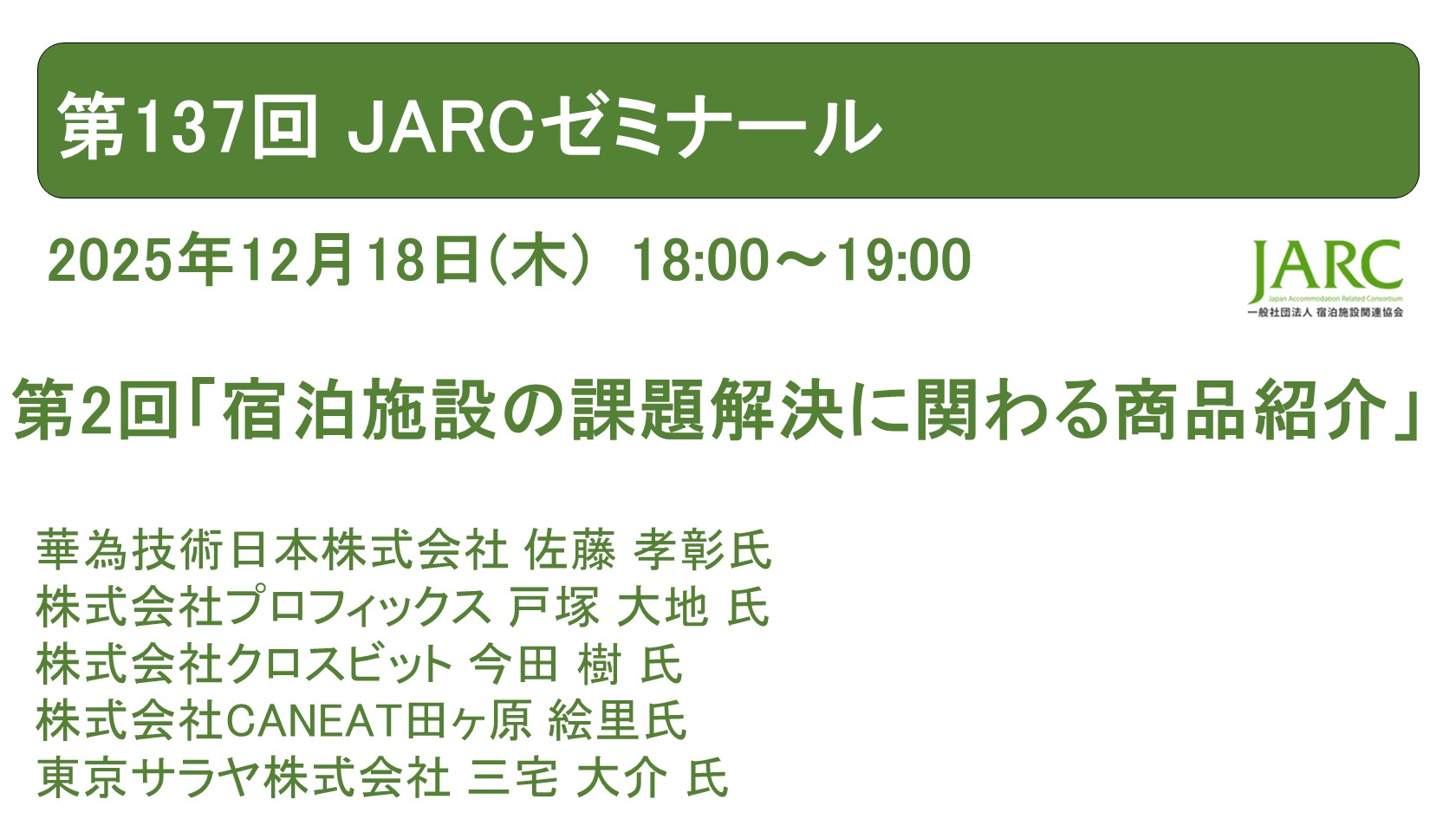武内氏
観光経済新聞社は5月15日、無料オンラインセミナー「第36回観光経済新聞チャンネル」を開催し、株式会社コングレ代表取締役社長の武内紀子氏が登壇した。「未来が生まれる、『場』をつくる。-MICEを通じた国際交流・地域活性化―」をテーマに約1時間の講演を行った。武内氏は経団連観光委員長も務め、「第5次観光立国推進基本計画」策定に関わる交通政策審議会観光分科会の委員でもある。講演では、インバウンドの回復状況やMICEの特徴・効果、G7広島サミットの事例などを通じて、MICEが観光立国実現の戦略的ツールであることを解説した。

武内氏
回復するインバウンドとMICEの可能性
武内氏は最初に訪日外国人旅行者数の動向について説明した。「2024年の訪日外客数は3,687万人で、過去最高だった2019年の3,188万人を約500万人上回りました。2023年比で47.1%増、2019年比では15.6%増となっています」と現状を紹介。増加の要因として「ピークシーズンである桜・紅葉・夏休み時期に、単月過去最高を更新したこと、また東アジアだけでなく東南アジア・欧米豪・中東からも増加していることが挙げられます」と分析した。
訪日外国人旅行消費額も過去最高を更新。「2024年には8兆1,257億円となり、2023年比で53.1%増、2019年比でも68.8%増となっています」と述べた。この数字は輸出品目と比較しても「自動車の17.9兆円に次ぐ規模で、半導体等電子部品の6.1兆円や鉄鋼の4.4兆円を上回り、日本で第2位の輸出産業となっています」と強調した。
一方、日本人の国内旅行も回復傾向にある。「2024年の日本人国内延べ旅行者数は5.4億人で、コロナ前の9割程度まで回復。消費額は25.1兆円と過去最高を記録しました」と説明。2023年比で14.8%増、2019年比でも14.7%増と伸びている。これに訪日外国人旅行消費額8.1兆円と海外旅行(国内分)1.0兆円を合わせると、「日本国内での旅行・観光消費額は34.3兆円に達し、2023年比で21.9%増、2019年比で22.7%増となっています」と市場の大きさを示した。
MICEの定義と観光産業における位置づけ
MICEとは何かについて武内氏は「企業の会議・研修・セミナーを意味するMeeting、企業の報奨・研修旅行であるIncentive Travel、大会・学会・国際会議のConvention、そして展示会・見本市・イベントを表すExhibition/Eventの頭文字を取った言葉です」と説明した。
観光産業における位置づけについては「観光業は宿泊サービス業や旅行業、交通事業者、飲食サービス業、小売業など多岐にわたる業種で構成されていますが、MICEはイベント・コンベンション業として観光業の一角を担っています」と述べた。
武内氏はMICEの特徴として「通年の需要が見込めること、コンベンションは経済不況の影響を受けにくいこと、MICE参加者はクオリティ・ビジターであること、観光のリピーターになることが多いこと、そしてコロナ禍にあってもオンラインで開催されたことなどが挙げられます」と説明した。
また政策面では「2023年3月に閣議決定された『観光立国推進基本計画』では、『持続可能な観光地域づくり戦略』『インバウンド回復戦略』『国内交流拡大戦略』の3つが基本方針として示されており、このうち『インバウンド回復戦略』の施策の一つとしてMICEの推進が挙げられています」と政府の取り組みを紹介した。
国際会議開催に関する目標として「2025年までにアジア最大の開催国(3割以上)にする、2030年までにアジアNo.1の開催国として不動の地位を築き、世界5位以内にすることが掲げられています」と説明。実際、2022年と2023年の国際会議開催件数は、日本はアジアで1位を獲得していることを示した。
MICEがもたらす多様な効果
武内氏はMICEの効果について「①地域への経済効果、②ビジネス・イノベーションの機会の創造、③国・都市の競争力向上、④交流人口の平準化、⑤レガシー」の5つを挙げた。
特に経済効果については、「2023年の国際MICEによる経済波及効果は約8,520億6千万円、新たに生じた雇用創出効果は約8万2,185人分、税収効果は約1,052億6千万円と推計されています」と述べた。さらに「国際会議の外国人参加者1人当たりの平均消費額は約112万2千円で、これは訪日外国人1人当たりの旅行支出額約21万3千円の5.27倍に相当します」とその高い経済効果を強調した。
ビジネス・イノベーションの機会創造については「国際会議・展示会の機会を活用したネットワークや販路の拡大、グローバル企業との共同研究や世界の先端研究者との交流創出、日本の技術力や商品・サービスに対する認知・理解を深め、日本製品の購入や地域の産業振興を推進することができます」と説明した。
国・都市の競争力向上については「世界都市ランキング(国際会議件数など)やMICEを通じたネットワーク構築によって都市の競争力が向上する」とし、交流人口の平準化については「観光が休日型なのに対し、MICEはビジネス用途のため平日にも多く開催されるという特徴があります」と述べた。
「レガシー効果」についても言及し、「MICEの開催は経済波及効果だけでなく、市民の新しい知識能力開発や地元への愛着・誇りの高まり、民間組織やNPO法人の売り上げ拡大や新しいビジネスパートナーとの出会い、行政組織の海外行政組織とのネットワーク構築、教育機関・研究機関の海外研究者との共同研究開始、開催地全体の交通インフラ整備など、中長期的に好影響をもたらします」と幅広い効果を紹介した。
大阪・関西万博による経済効果
武内氏は今年4月13日に開幕し、10月13日まで開催されるの大阪・関西万博についても「2018年から2025年の期間に実施された、または実施される大阪・関西万博関連事業がもたらす経済波及効果は建設投資が8,570億円、運営・イベントが6,808億円、来場者消費が1兆3,777億円で、合計約2.9兆円と試算されています」と説明した。「来場者数は2,820万人、参加国・地域は158を見込んでいます」と付け加えた。
国際会議の現状と日本の戦略
武内氏は日本開催の国際会議統計について「2023年の国際会議開催件数は1,376件で前年比2.5倍、参加者総数は101.6万人で前年比3.1倍、うち外国人参加者は12.9万人で前年比3.8倍となっています」と説明した。
この背景として「2022年10月に入国者数の上限が撤廃され、2023年4月には日本入国時のワクチン証明書または出国前検査証明書の提出措置が撤廃されたことが影響しています」と指摘。中・大型国際会議に絞ると「外国人参加者数50人以上かつ参加者総数300人以上の会議は255件で前年比3倍、外国人参加者数は8.8万人で前年比4.2倍でした。これは2019年と比較すると、開催件数は54.1%、外国人参加者数は67%の水準まで回復しています」と述べた。
開催形態についても「全体の53%にあたる736件が対面開催で、2020年以降初めてハイブリッド形式を上回りました」と、対面開催への回帰傾向を示した。
アジアでの国際会議開催状況については「『アジア主要国における国際会議の開催件数に占める割合』を見ると、2022年・2023年ともに日本がアジア1位となっています」と日本の優位性を説明した。
PCOの役割とコングレの国際ネットワーク
武内氏はMICEのステークホルダーについて「主催者、参加者、協賛者、出展者を中心に、PCO(Professional Congress Organizer)、会議場・展示場・ホテル、旅行代理店、航空・鉄道・運輸、国・政府観光局(JNTO)・自治体・DMO・CB、さらに施工・美術、映像演出、音響照明、IT、印刷、弁当料飲・ケータリング、人材派遣、警備などが関わっています」と説明した。
PCOとしてのコングレの役割については「カタチのないところから主催者と共につくり上げていくのが我々の役割です。具体的には誘致支援、プランニング、事前準備、当日運営、事後業務の5ステップで業務を行います」と述べた。
誘致支援では「情報収集・調査、会場選定、ビッドペーパー作成、募金計画策定・活動サポート、広報対応、ロビー活動補助、誘致プレゼンテーション、PR動画制作など」を、プランニングでは「基本計画策定、準備スケジュール策定、広報戦略策定、コンセプト策定など」を行うと説明。事前準備では「活動戦略策定、予算案策定、会場・機材・備品手配、インフラ・OA手配、宿泊・輸送・旅行手配、社交行事・演出企画・料飲手配、運営スタッフ手配など」を担うという。
当日運営では「財務管理、全体運営管理、演題管理・参加登録管理、招聘者対応、通訳・翻訳、会場設営・装飾、運営スタッフ管理、機材オペレーション、社交行事・演出、警備・動線管理など」を、事後業務では「決算処理・会計報告、広報対応、報告書作成、記録素材制作、礼状作成・発送、事後広報など」を行うと詳細に紹介した。
開催地の魅力発信についても「特産品・名産品の展示やお土産の提供、郷土料理の提供や伝統芸能の演目披露、地域の魅力を舞台演出で表現するなど、開催地の魅力を発信したり、地域活性化やシビックプライドの醸成につなげるため、主催者に様々な提案を行い、共に会議をつくりあげていきます」と説明した。
サステナビリティへの取り組みとして「2024年9月、イベント・MICE業界6団体が運営の立場から制作した『イベント・MICE関係者のための使いやすいサステナビリティガイドブック』が完成しました」と紹介。「コングレ自身も情報セキュリティ管理体制の向上やサステナブルなMICEの推進とそれを通じた社会課題の解決に取り組み、ISO14001(環境マネジメントシステム)やISO20121(イベントサステナビリティ・マネジメントシステム)などの認証を取得しています。両認証を取得した企業は日本で初めてです」と述べた。
また、国際的なネットワークについて「IAPCOという組織には45か国91社180拠点のPCOが加盟しており、ICCAは約100か国の1,100以上の会員を持つ国際機関です。また当社が事務局長を務めるWorld PCO Allianceは世界の18のコンベンション企業によるアライアンスであり、さらに日中韓のBESETO Allianceを通じてアジア発でビジネスを展開しています」と、グローバルな活動基盤を紹介した。
G7広島サミット―MICEの効果を示すケーススタディ
武内氏は2023年5月19日から21日にかけて広島で開催されたG7サミットについて、「当社ではサミットでの会場設営・会議運営全般、政府報道関連のサポート業務、国際メディアセンター(IMC)の会場設営・運営業務を担当しました」と説明した。
サミット開催による経済波及効果は「広島県内が約725億円(うち広島市が約573億円、その他の地域が約152億円)、広島県外が約492億円で、合計約1,217億円と推計されています」と述べた。
サミット開催から1年後の新しい出来事として「2024年5月19日には広島平和記念資料館の北側に『G7広島サミット記念館』がオープンしました。サミットゆかりの品々を展示する施設で、次回日本がサミット議長国になる2030年12月まで開館する予定です」と紹介。また「2024年5月には広島空港にコロナ禍以降初の新路線として広島~ハノイ間が就航しました。これはベトナム・チン首相と岸田首相(当時)が広島サミットで会談したことも背景にあります」と述べた。
観光面での効果も顕著に現れている。「嚴島神社のある宮島への観光客は、2024年は過去最多の来島者数を記録しています。大鳥居を背景に首脳が記念撮影したことで外国人観光客が増加しています」と説明。広島平和記念資料館についても「2023年度は198万1,782人(うち外国人67万757人で約1/3)が訪れ、G7広島サミット開催によって過去最多となりました。さらに2024年度は226万4,543人(うち外国人72万8,385人で約1/3)と過去最多を更新しています」と述べた。
武内氏は「広島県への総観光客数増加に伴う5年間(2027年まで)の経済波及効果は約1,649億円と試算されています」と、MICEがもたらす長期的な効果についても言及した。
MICEを通じたまちづくり
武内氏は最後にMICE施設を活用したまちづくりについて事例を紹介した。「施設の管理運営業務にとどまらず、全国各地で進む再開発などの企画段階からMICEの役割や効果などを提案し、MICE施設を活用したまちづくりに取り組んでいます」と述べた。
具体例として長崎市の「出島メッセ長崎」での取り組みを挙げ、「地域の魅力をビジネスにつなげるため、地元企業への講義などでMICEに関する情報を提供するほか、長崎市、DMO長崎、産学官と一体となったMICE誘致活動、地元の人材育成、活性化に取り組んでいます」と説明した。
また「開業とリンクして大学生と地元企業の人材育成を支援しており、社員による講義や学生による施設のオープニングイベント企画の実施、長崎大学経済学部対象の『MICE人材育成プログラム』、地元の地方銀行ふくおかフィナンシャルグループ主催の『長崎MICEスクール』など、交流人口の拡大施策を展開しています」と具体的な取り組みを紹介した。
武内氏は「MICEは国・地域、企業・団体、産業・学術分野において共創社会の戦略実現ツールであり、MICEビジネスの発展が社会貢献につながる」という言葉で講演を締めくくった。