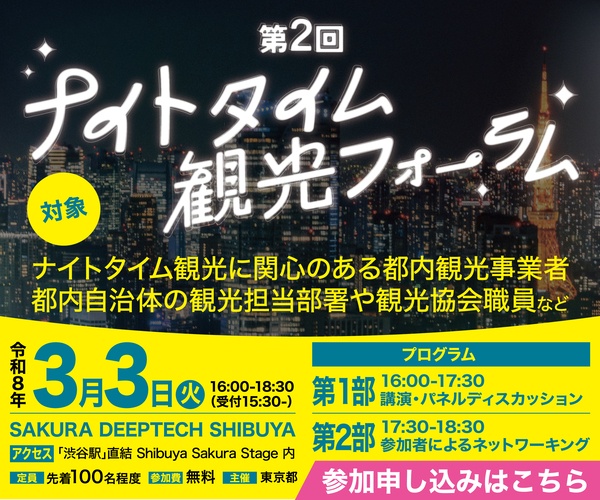大阪・関西万博へは、大阪周辺の駅から九つのシャトルバス路線が設定されています。会場に近いJR桜島駅のほか、大阪駅、新大阪駅、難波駅、天王寺駅などからも便があります。
ただ、運行本数はそれほど多くありません。万博協会の運行計画によりますと、主力となる桜島駅からのシャトルバスは終日5~10分間隔の運転ですが、それ以外の路線はピーク時でも30分から1時間に1本程度です。全便予約制で、席数が少ないため、午前中は予約が難しい状況になっています。
たとえば新大阪駅から万博会場への直行バスは、新幹線から乗り換えて会場に向かうには便利です。遠方からの訪問者は、早朝に自宅を出て、万博を訪問するにはうってつけの路線でしょう。しかし、午前中の運転本数は8本にすぎません。高速バス用車両なので、定員も少なく、新幹線で運ばれてくる大量の万博訪問客をさばくには不足です。実は筆者も利用しようと思い、訪問予定日の2週間くらい前に検索しましたが、午前便は全便満席で諦めました。
万博の当初計画では、各路線とも、もう少し多くの便を設定しようとしていたようです。しかし、運転士不足で、各社とも十分な運行本数を確保するのが難しかったとのこと。万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」ですが、運転士不足はまさに未来社会の課題であり、バスの運行本数不足は、それを体現しているようにも感じます。
限られた運転士を集中投入したのが、桜島駅からのシャトルバスです。この路線だけは運行本数が多いので、予約が比較的取りやすくなっています。筆者もJRの電車で桜島駅まで行き、15分ほどバスに乗って会場を訪れました。桜島駅は大混雑していましたが、誘導はしっかりしていて、万博輸送の主力ルートとして機能している様子がうかがえます。
気になったのは、桜島駅からのバスが、定員70名程度の電気バスで、輸送力のある連節バスが使われていなかったことです。電気バスは循環型社会を象徴し、万博のテーマに沿うのかもしれませんが、運転士不足という現実に即してみれば、日本の未来社会に求められているのは輸送力のある車両ではないでしょうか。
連節バスは調達に時間がかかりますし、今回は難しかったのかもしれませんが、見てみたかった気もします。
(旅行総合研究所タビリス代表)

(観光経済新聞2025年4月28日号掲載コラム)