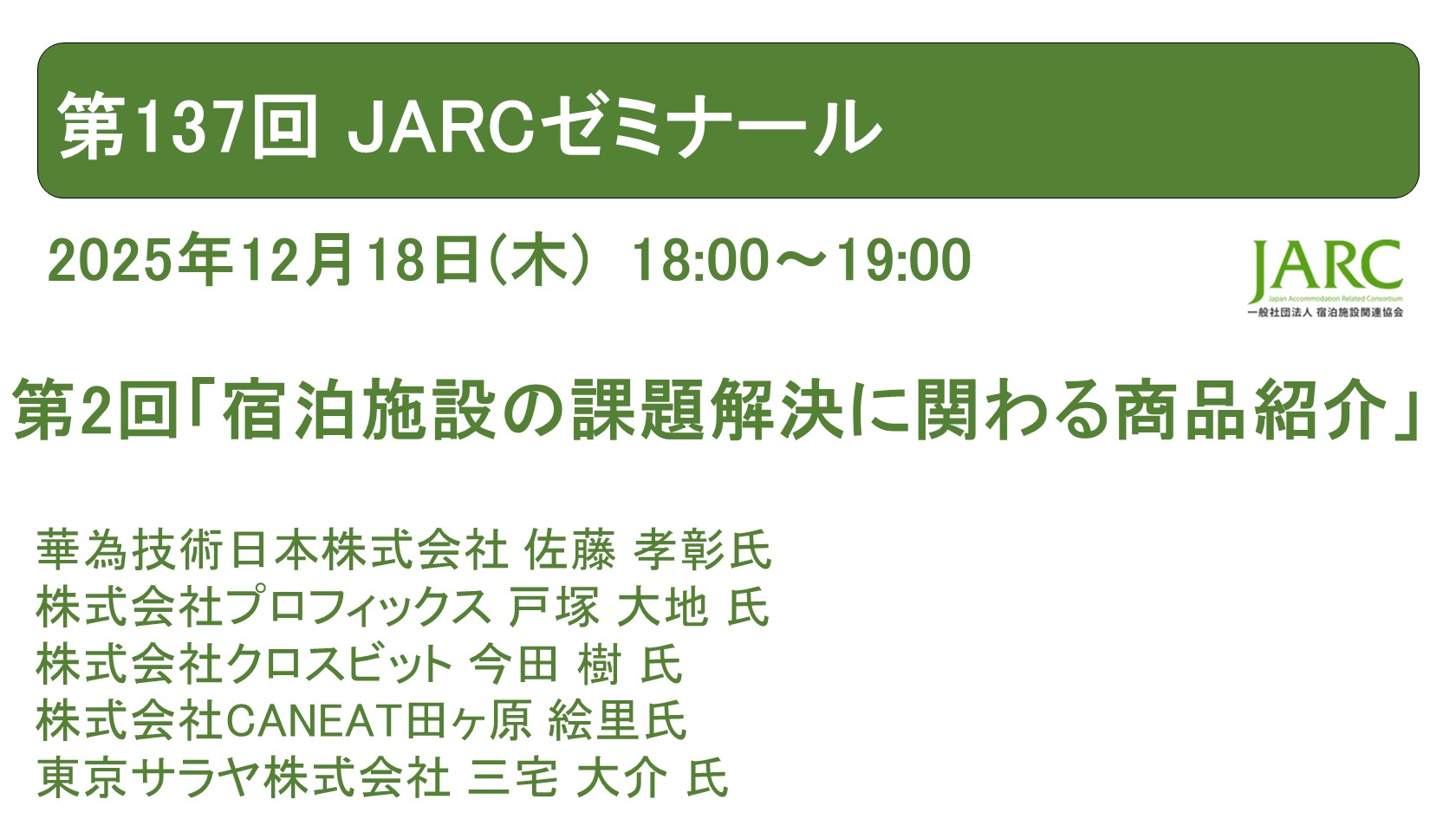日本で唯一の料理の祖神「磐鹿六雁命(イワカムツカリノミコト)」を祭る高家(たかべ)神社(千葉県南房総市)で5月17日、春の例大祭・庖丁(ほうちょう)式奉納が「たかべ庖丁会」により行われる。
磐鹿六雁命は、日本書紀に登場する人物で、日本武尊(ヤマトタケルノミコト)にカツオやハマグリを料理して献上し、朝廷で料理をつくる職に任命された。その子孫が代々朝廷の調理番を担当することとなり、日本料理の原型が形作られていったとされる。
日本料理の基礎ができたのは、平安時代になってから。四条中納言藤原朝臣山蔭卿が光孝天皇の命を受け、さまざまな料理をまとめて後世に伝えていく中で、宮中行事の「庖丁儀式」が定められた。
一般公開される庖丁式では、烏帽子(えぼし)と直垂(ひたたれ)を身にまとい、食材に一切手を触れずに包丁とまな箸を用いて、コイやマダイ、マナガツオなどを調理する。
伝統にのっとり厳かに行われる儀式は、自然に対する畏敬の念や生き物に対する感謝の気持ちを重んじる日本古来の思想が息づいている。