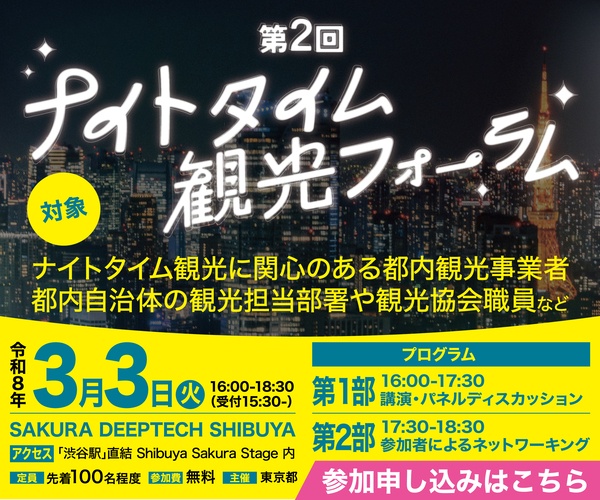日本には、脈々と受け継がれてきた”わざ”がある。そのわざを体現し、伝承する個人に贈られる称号が、いわゆる「人間国宝」だ。正式には「重要無形文化財保持者(各個認定)」とされ、国がその高度な技能と文化的意義を認め、助成を行う制度である。人間国宝という言葉はあくまで認定された個人の通称だが、広く定着しているので、あえてこの称号を使って整理していきたい。
現在、認定の対象は「芸能」と「工芸技術」の大きく二つに分かれ、能楽、歌舞伎、雅楽、文楽などの伝統芸能から、陶芸、染織、漆芸、刀剣、和紙といった工芸まで幅広い。
2025年2月時点で、延べ390名余が認定されており、保持者は約110名。文化審議会による厳格な審査のうえ、文部科学大臣が認定するという構造で、その認定基準には「技術水準の高さ」「文化的意義」「後継者育成への貢献」が含まれる。まさに、日本文化の最高峰ともいえる称号だ。
2025年はこの制度にとって大きな節目となりそうだ。先日文化庁から発表されたのが、実に約50年ぶりに対象分野が拡張され「食や酒などの生活文化」が加わる見通しである。これにより、和食の料理人や杜氏といった、地域の“日常にある伝統”の担い手も、人間国宝として認定される可能性が開かれる。かねてより、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」や「伝統的酒造り」の技法に代表されるように、食文化は世界的にも日本のアイデンティティを象徴する領域となっており、今回の制度改定は時代の要請でもある。
この動きは、地域観光にとって極めて重要な意味を持つ。新たにこれらの分野が人間国宝に認定されることで、文化的価値から地域誘客への大きな触媒となるだろう。ある町に「人間国宝の料理人がいる」と知れば、その地を訪ねて料理を味わいたいと思うのは自然な感情だ。人の営みに根差した“わざ”に触れることは、地域の深層とつながる体験を生む。それが滞在型観光、着地型観光の深化にもつながっていく。
そもそも人間国宝の存在は、地域のブランド力の証にもなり得る。例えば「人間国宝の刀匠がいる町」「蒔絵(まきえ)の達人が工房を開く集落」というように、タイトルがそのまま観光地としての差別化要素となる。さらに重要なのは、その存在が若い世代や外部人材にとっての“憧れ”や“指針”となることだ。後継者不足が深刻な中で、伝統技術の社会的価値を明確に可視化することは、文化の持続性に資する。全国における人間国宝の方々の地域文化伝承への大きな貢献はもっと評価され、各地でもっと敬意を表されるべきものに感じる。
人間国宝とは、その人物の栄誉ではあるが、それ以上に“地域が培ってきた文化の総体”を象徴する存在であるはずだ。今回の制度改定は、その象徴の輪を芸能や工芸だけでなく、食や暮らしへと広げていく歴史的転機だ。地域に根差した“わざ”を守り、伝え、魅せる。その連鎖こそが、真の観光地域づくりを支えるエンジンになるに違いない。
(地域ブランディング研究所代表取締役)