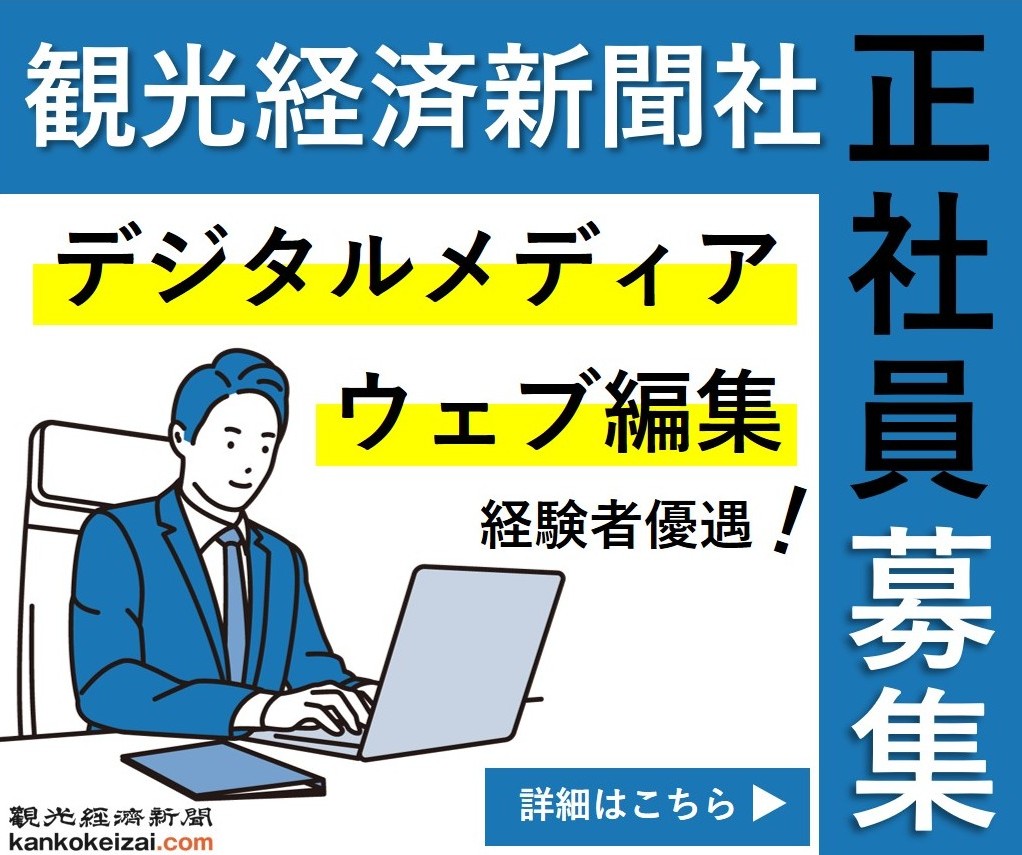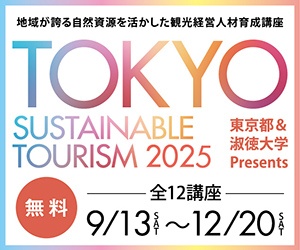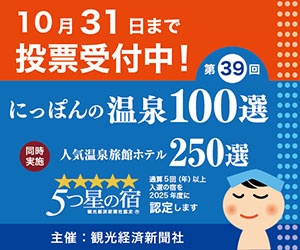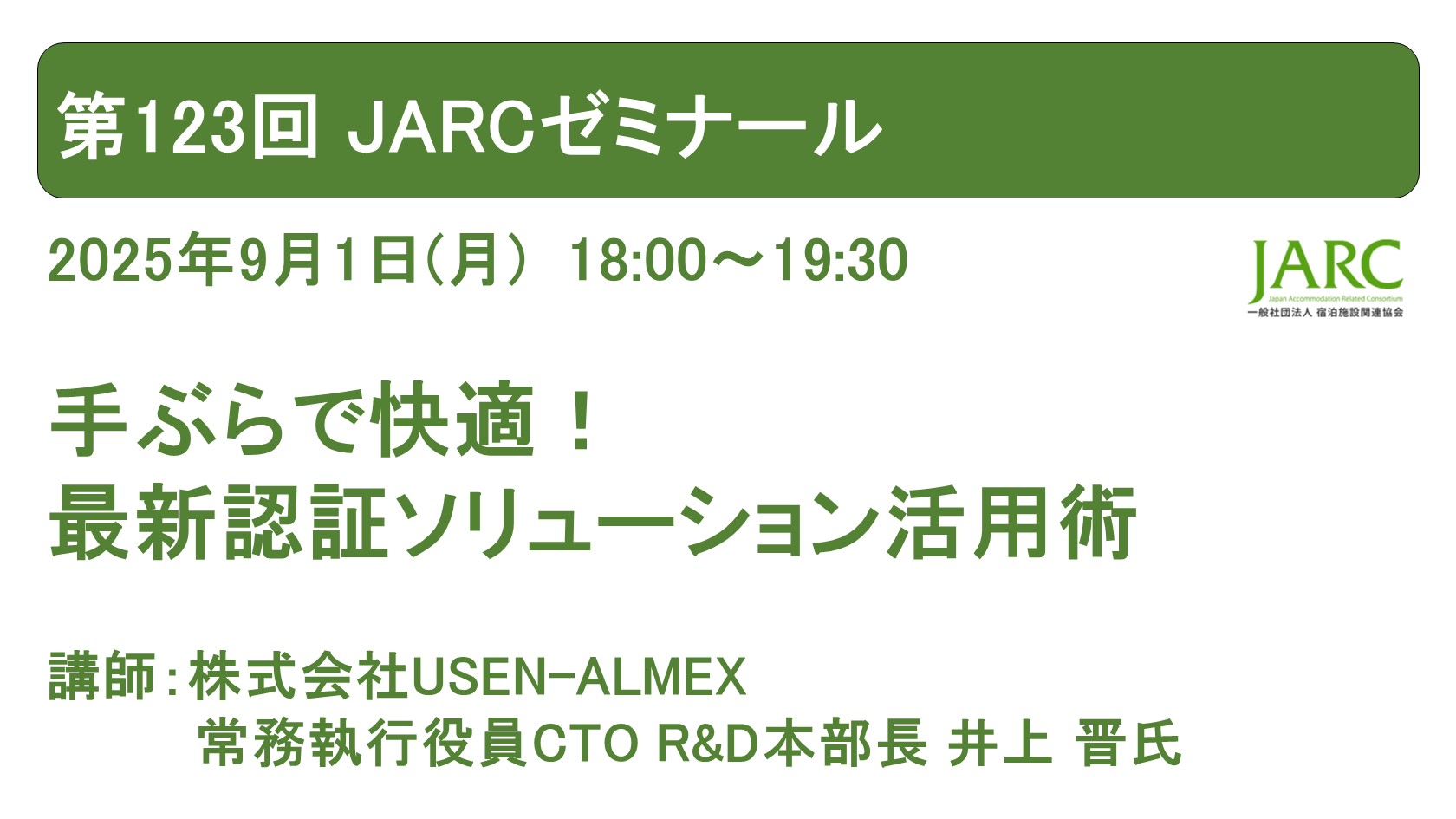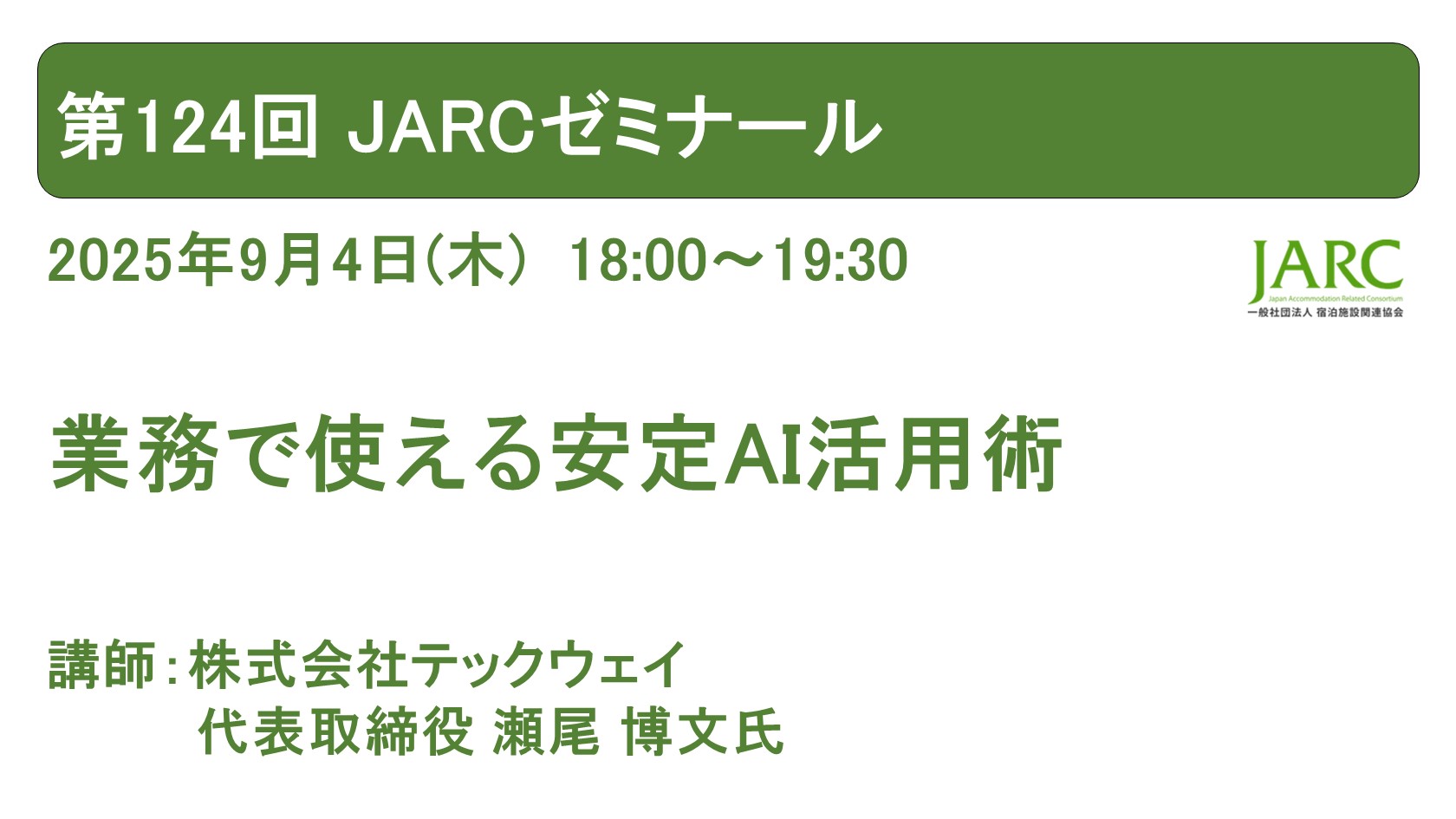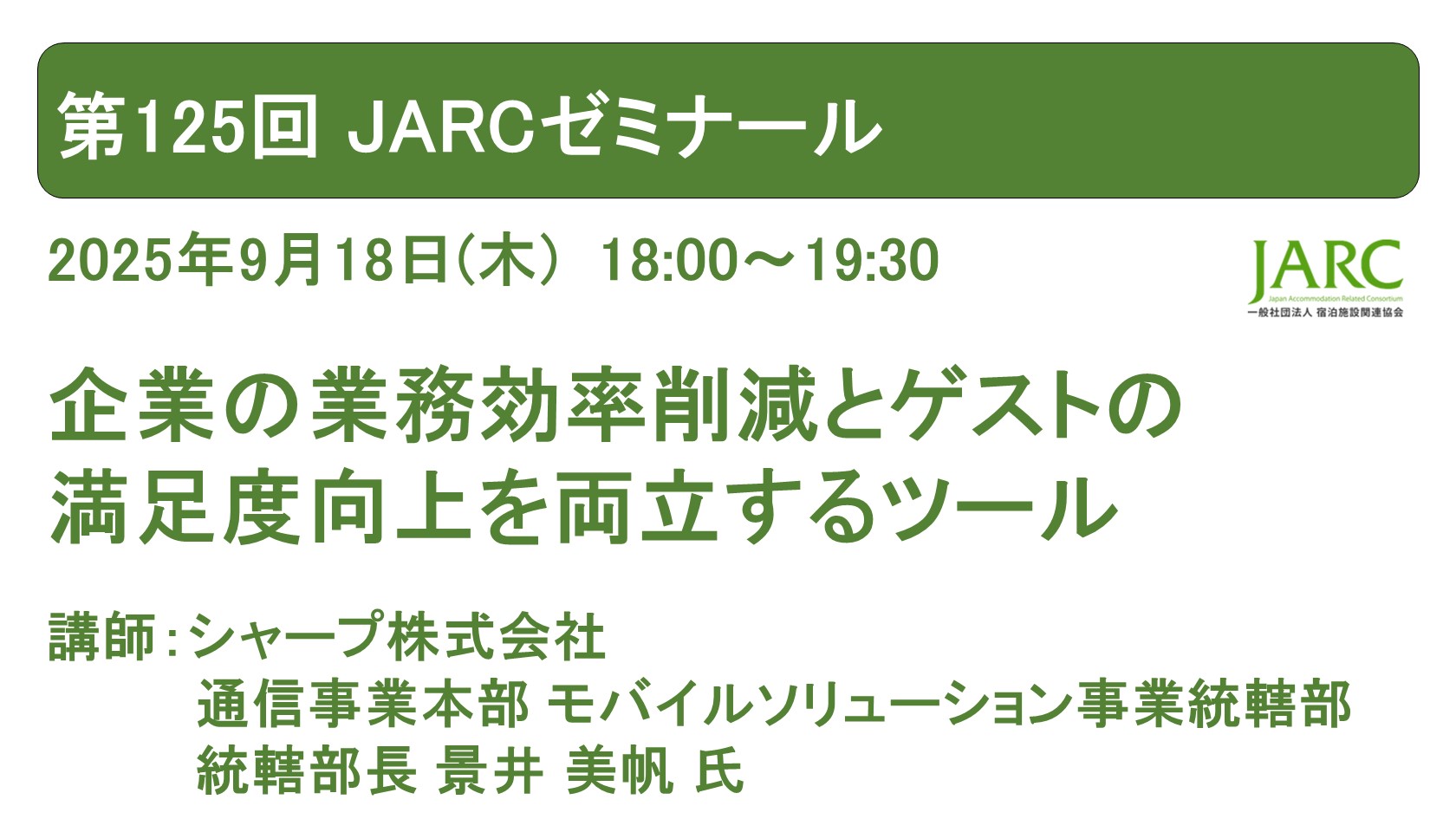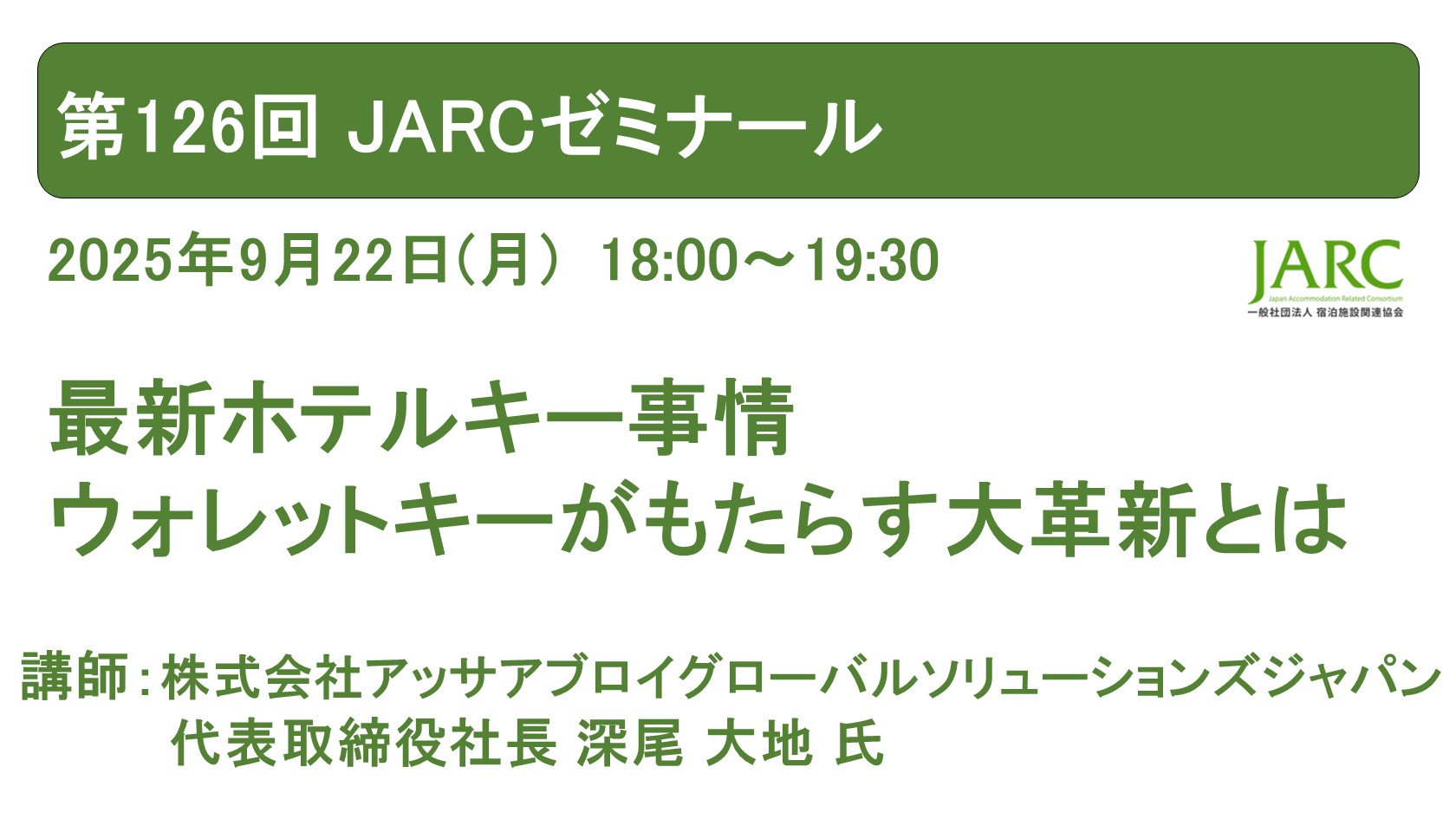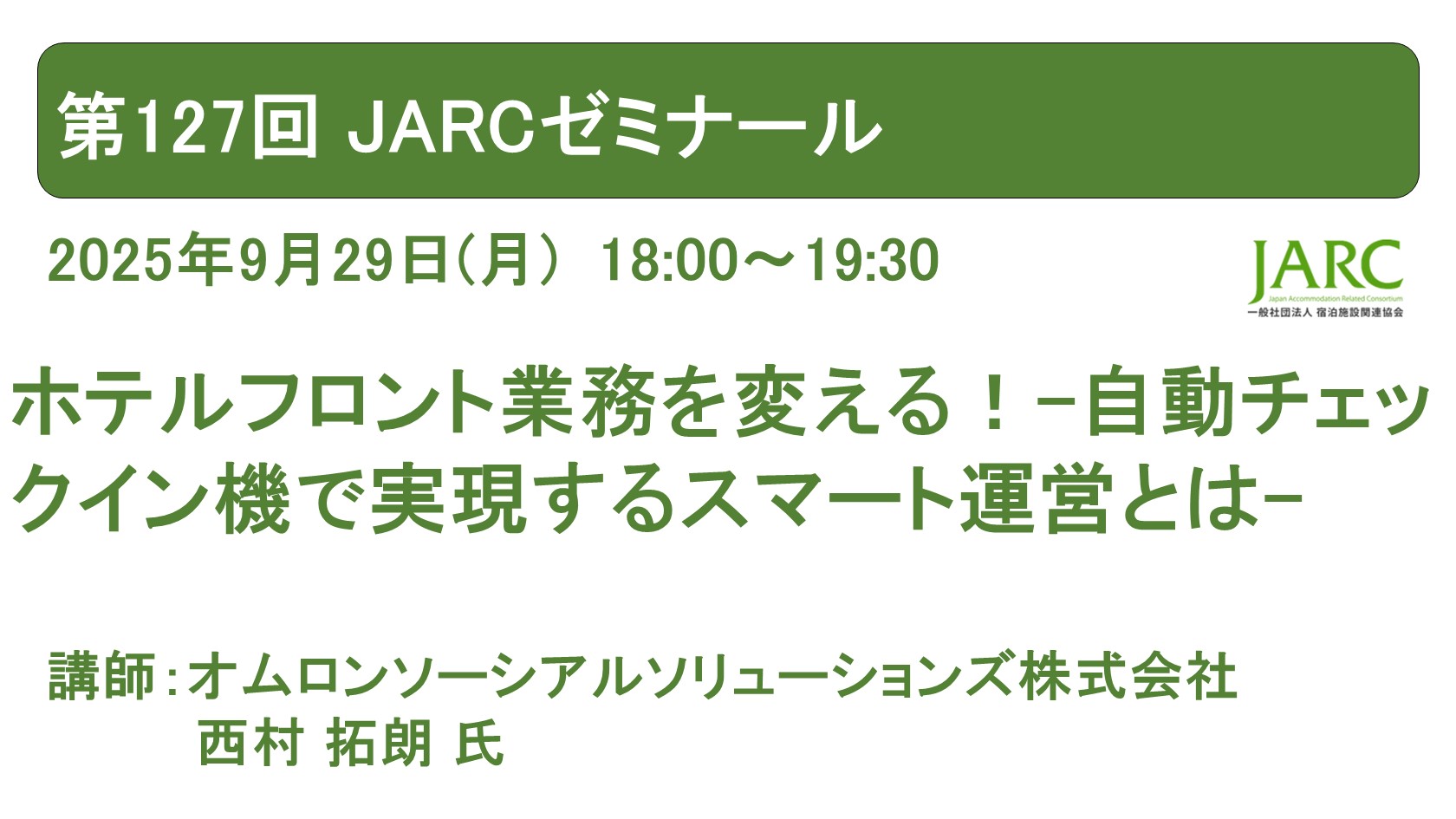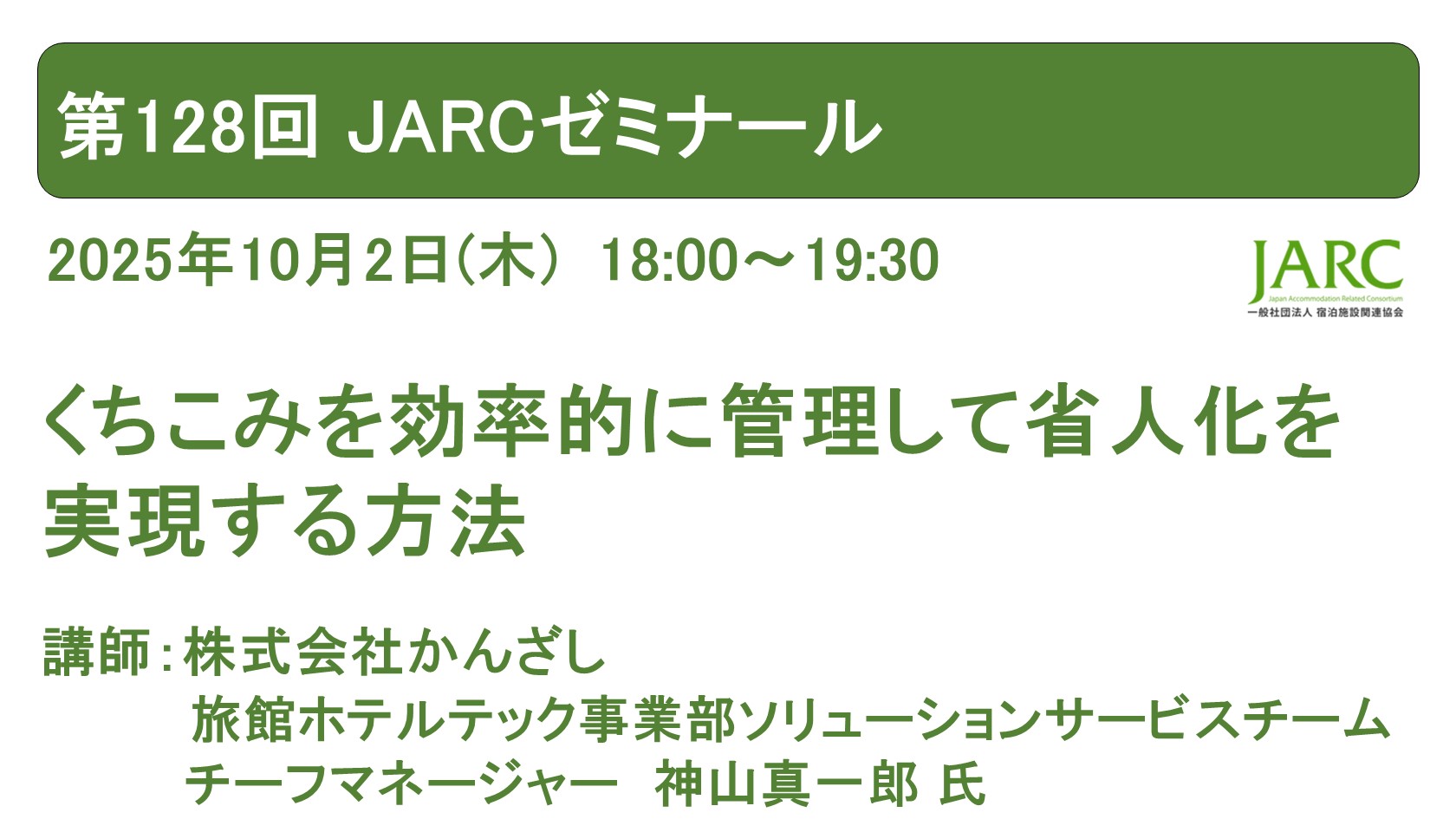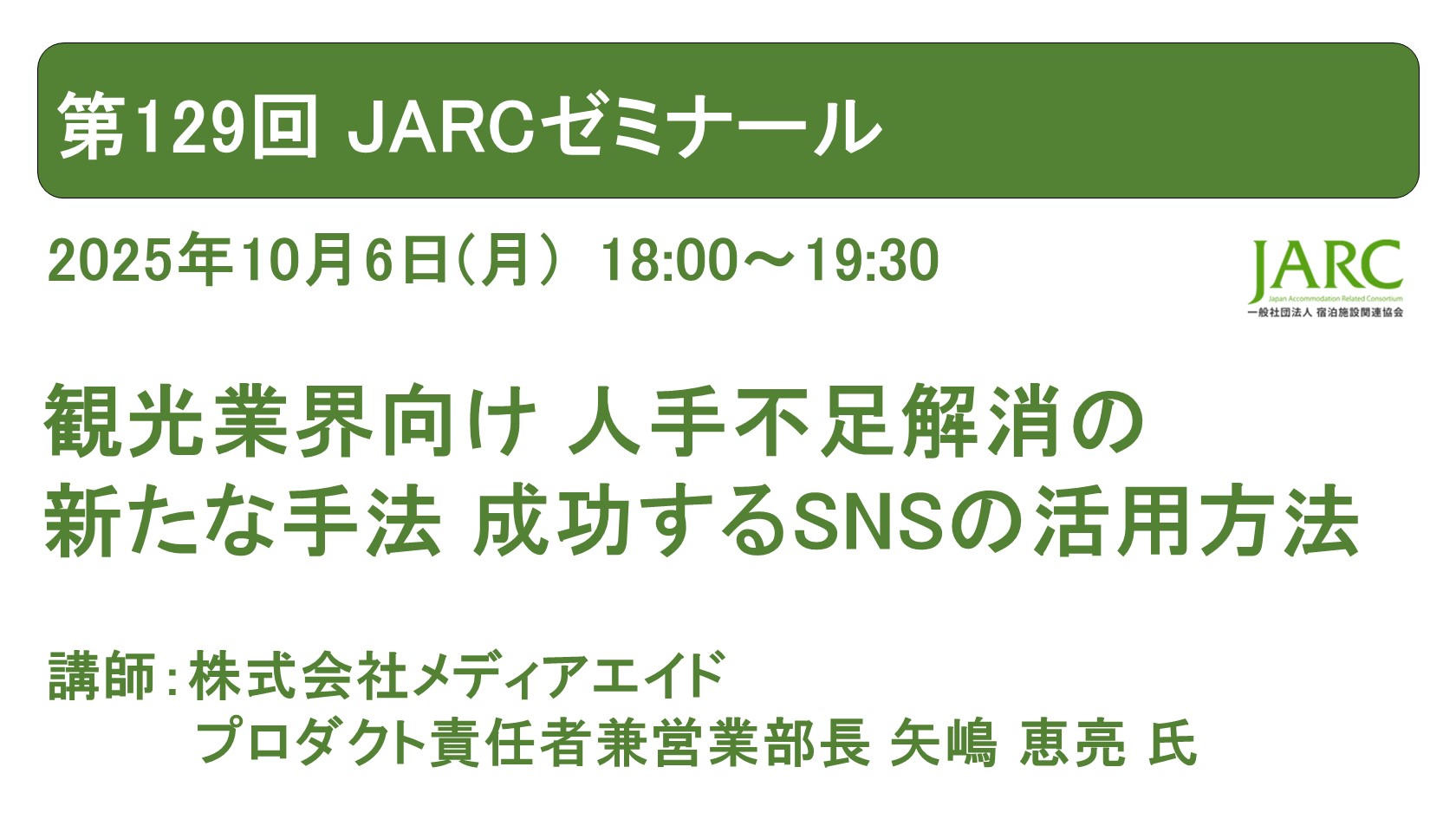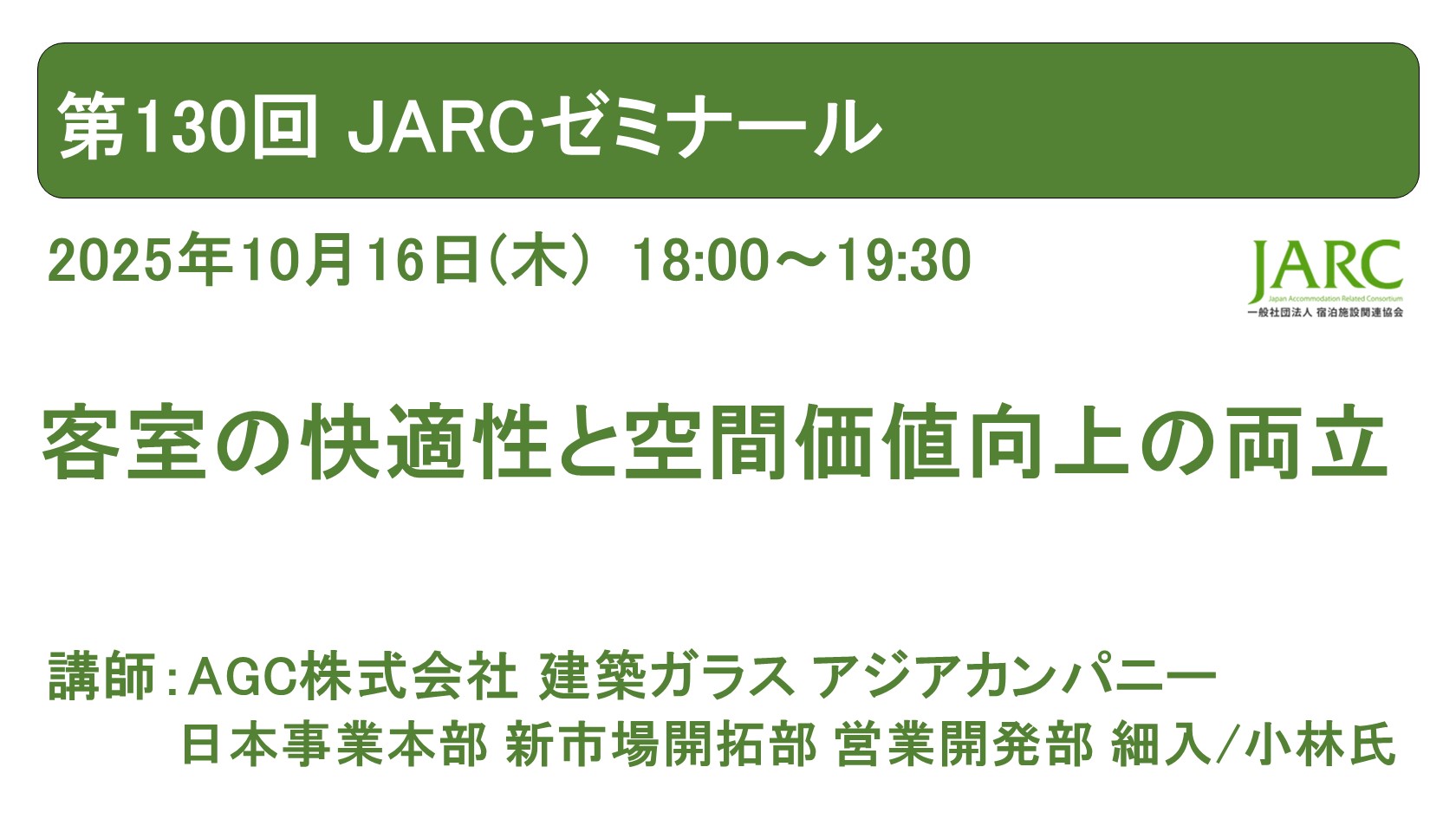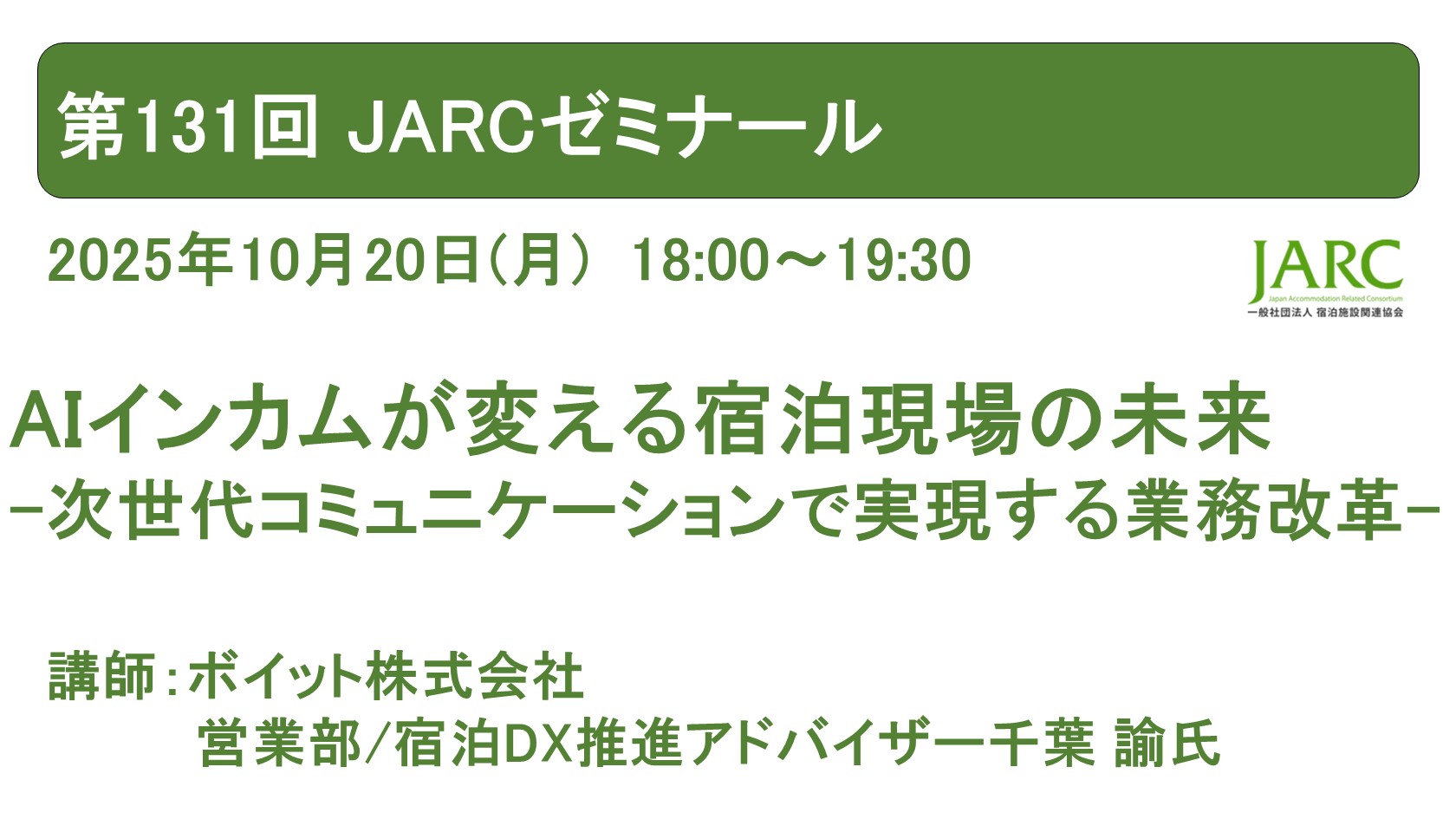日本政策金融公庫はこのほど、半期ごとに行っている食に関する消費者調査の1月実施分を公表した。現在の食の志向について「健康志向」とする人が45.4%で、2010年12月調査から9期連続で最多回答となった。「安全志向」も前期比3.9ポイント上昇と、昨年からの食品異物混入問題を受けて、「食の安全性に対するこだわりが表面化した」(同社)。
調査は1月1〜13日、全国の20〜70代の消費者2千人を対象に、インターネットを利用して行った。
「現在の食の志向」を二つまで回答してもらったところ、「健康志向」が45.4%と最も多く、前期(昨年7月調査)比で0.2ポイント上昇。次に多いのが「経済性志向」の32.4%(同0.8ポイント低下)。
以下、「簡便化志向」(26.0%、同0.1ポイント低下)、「安全志向」(25.4%、同3.9ポイント上昇)、「手作り志向」(18.7%、同0.8ポイント低下)などが続く。
安全志向は前期比で最も大きく上昇した。
食の志向を年代別にみると、健康志向、手作り志向、国産志向が高齢層、経済性志向、簡便化志向が若年層の比率が高い。
安全志向は50代が31.2%、60代が32.0%と、両世代で特に高くなっている。
今後の食の志向(二つまで回答)は、現在の志向と同様、健康志向が46.7%と最多になった。
また現在の食の志向に関する調査結果と比較すると、健康志向と簡便化志向(27.4%)で「今後」の比率が「現在」よりも高くなっている。特に簡便化志向は2008年1月の同設問開始以来、初めて「現在」を上回った。