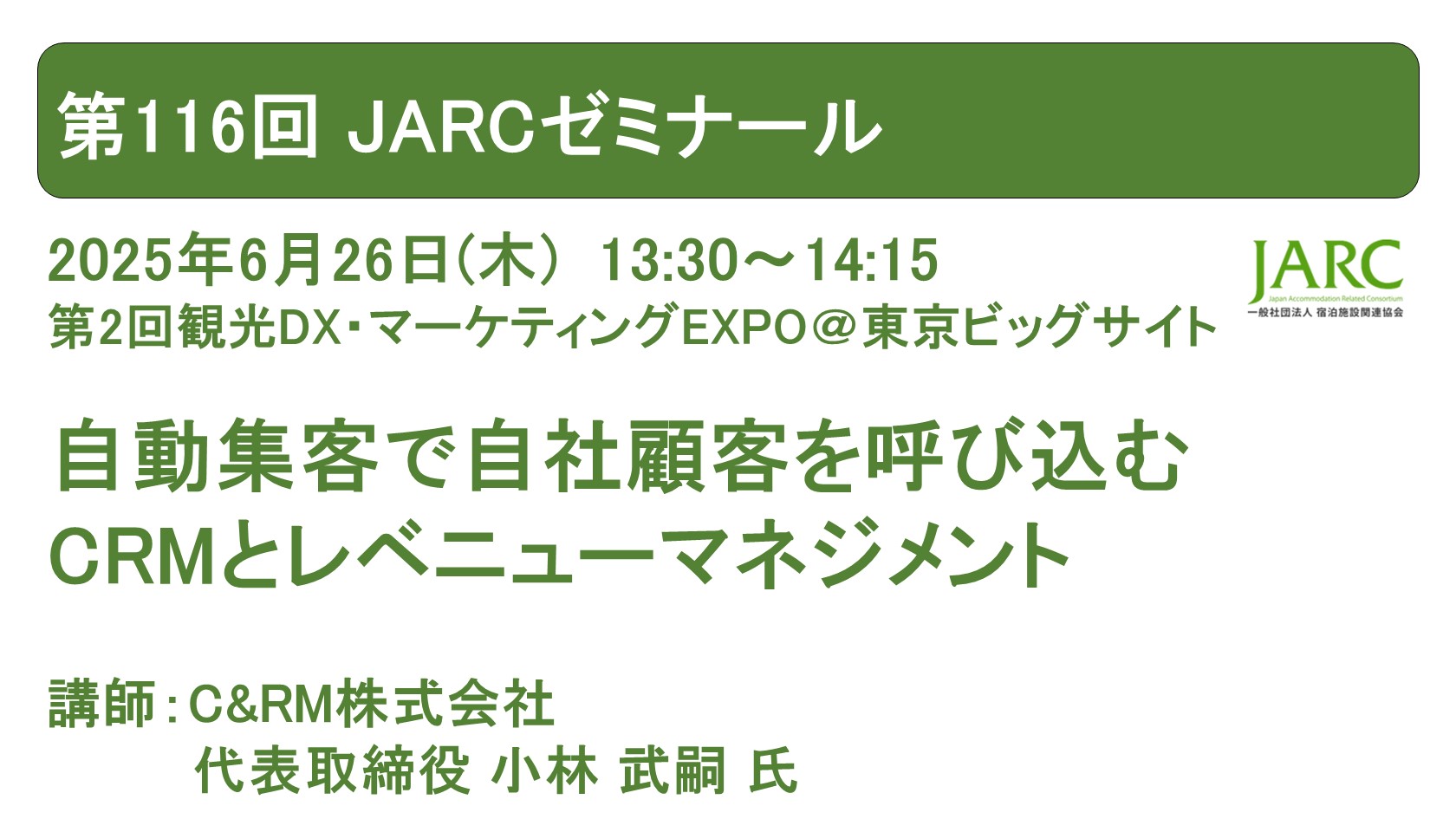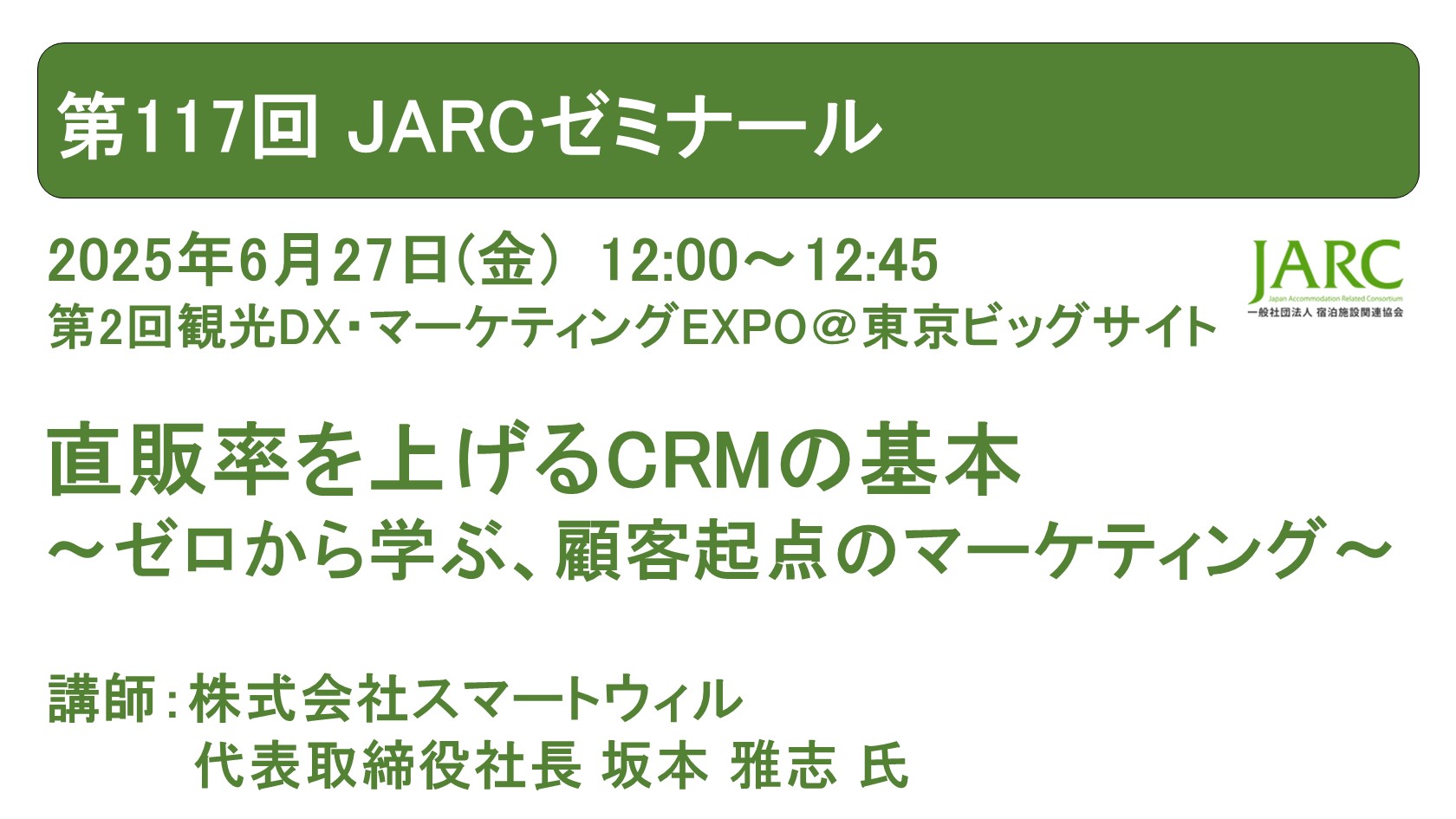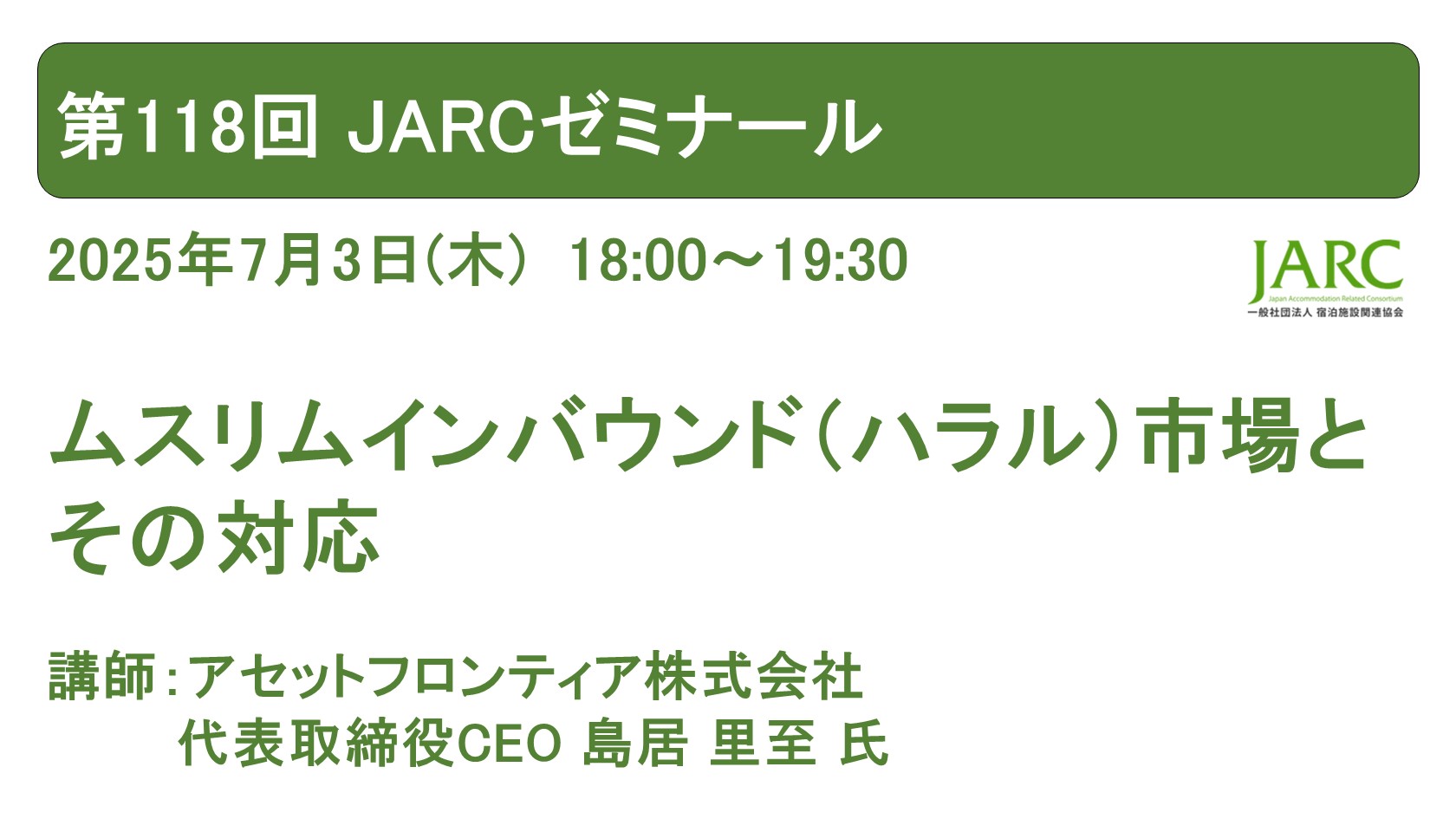飯野氏
おもてなしを利益向上につなげる
「日本の宿おもてなし検定」は2009年に第1回の初級(現3級(基礎))検定試験が実施されて以来、現在は2級(応用)、1級(指導)と併せて三つのレベルで試験が実施されています。3級、2級はウェブ検定で、1級は1次審査(作文)、2次審査(実技および筆記試験、面接)から構成されています。開始以来、3級は約3万人の方が、2級は約6千人の方が受験してくださっています。また、1級は過去5回の試験で計24名の方が合格され、3級、2級と比べて狭き門ではあるものの、例年、受験される方は緊張感を持ち高い意識で臨んでくださっています。
では、この検定をお宿の経営にも生かしていただくためにはどうすれば良いのでしょうか。それはおもてなしを利益向上につなげるために活用することです。日本では、おもてなしとは心から歓待することとして、その行為を金銭で測ることを積極的にやってこなかった背景があると言われています。この精神性は価値観としては素晴らしく維持すべきとは思うものの、一方で料理や施設と並んでおもてなしが宿泊業の商品であることも間違いありません。商品である以上、おもてなしは利益につながるべきだと考えます。そのためには、おもてなしがもたらす利益について今一度確認する必要があると思います。
心を込めておもてなしをした結果、リピーターの来訪回数は増えているか(顧客との関係性の生涯化、永代化)、宴会などで当日発生する飲料などの売り上げは向上しているか(状況判断力、提案力)等々、金銭的価値とおもてなしをつなげることへの抵抗感をなくして売り上げ向上との関係性が明確になれば、人に対する投資、すなわち給与手当などの上昇が可能となり検定合格者を含む働く人たちにとっても一層のやりがいが感じられる仕事となり得るのではないでしょうか。
答えが一つではないと言われている「おもてなし」を検定で測ること自体の是非から議論が始まり運営委員会が発足した07年から数えて15年がたつ今、3級は検定自体もさることながらテキストを新人教育に活用できるなど、一定の評価をいただける検定となってまいりました。今後は検定合格者の方にとってより魅力ある検定となるため、1級合格者が活躍する場の機会を増やしたり、外国人スタッフにとっても基本を覚えるテキストとして使用しやすいものとしたり、そして何よりおもてなし検定を取得した人にとって誇りとやりがい、ひいては待遇面の改善にも生かされることを願っています。

飯野氏