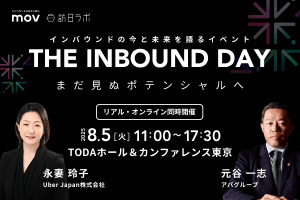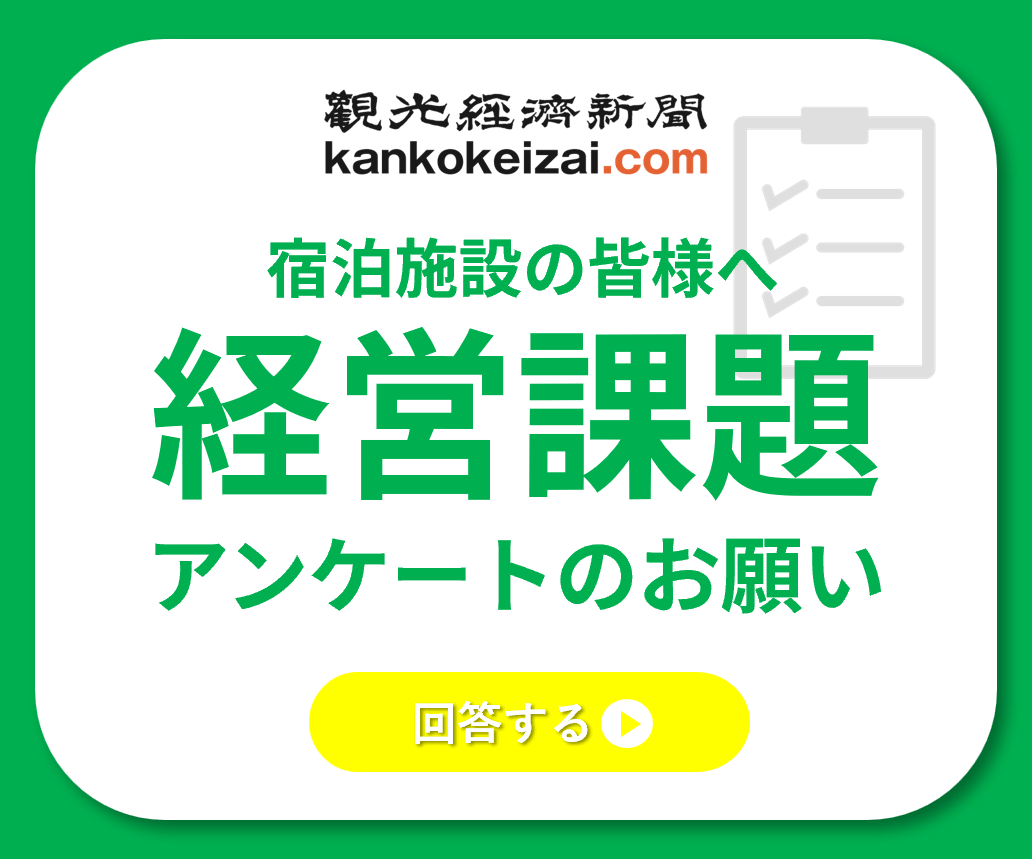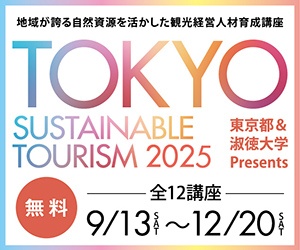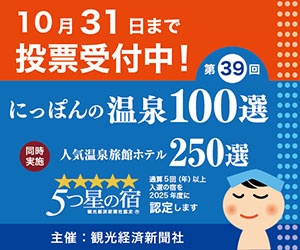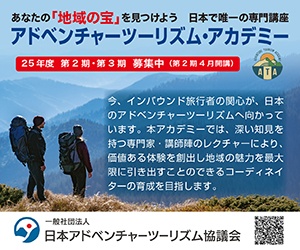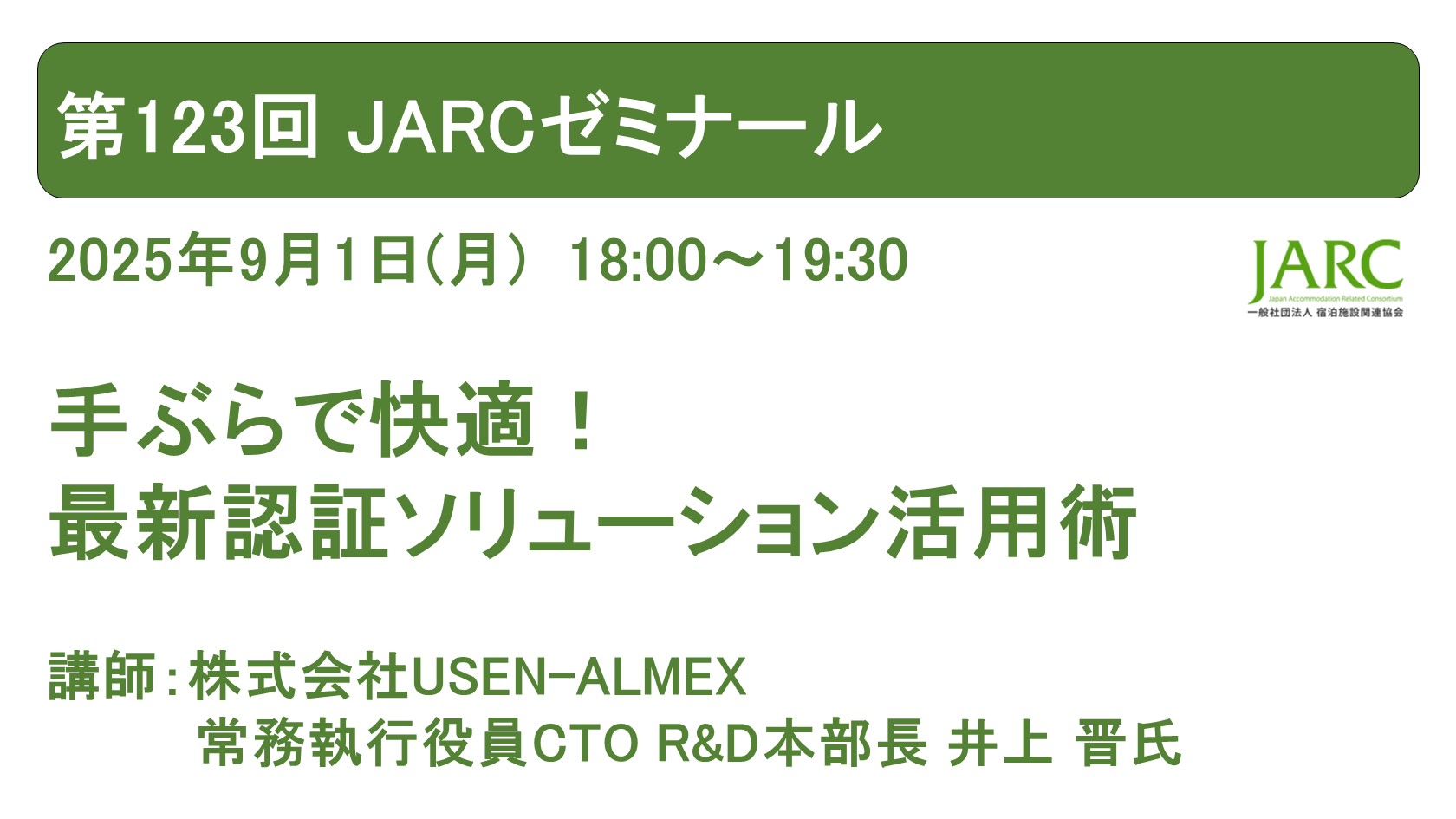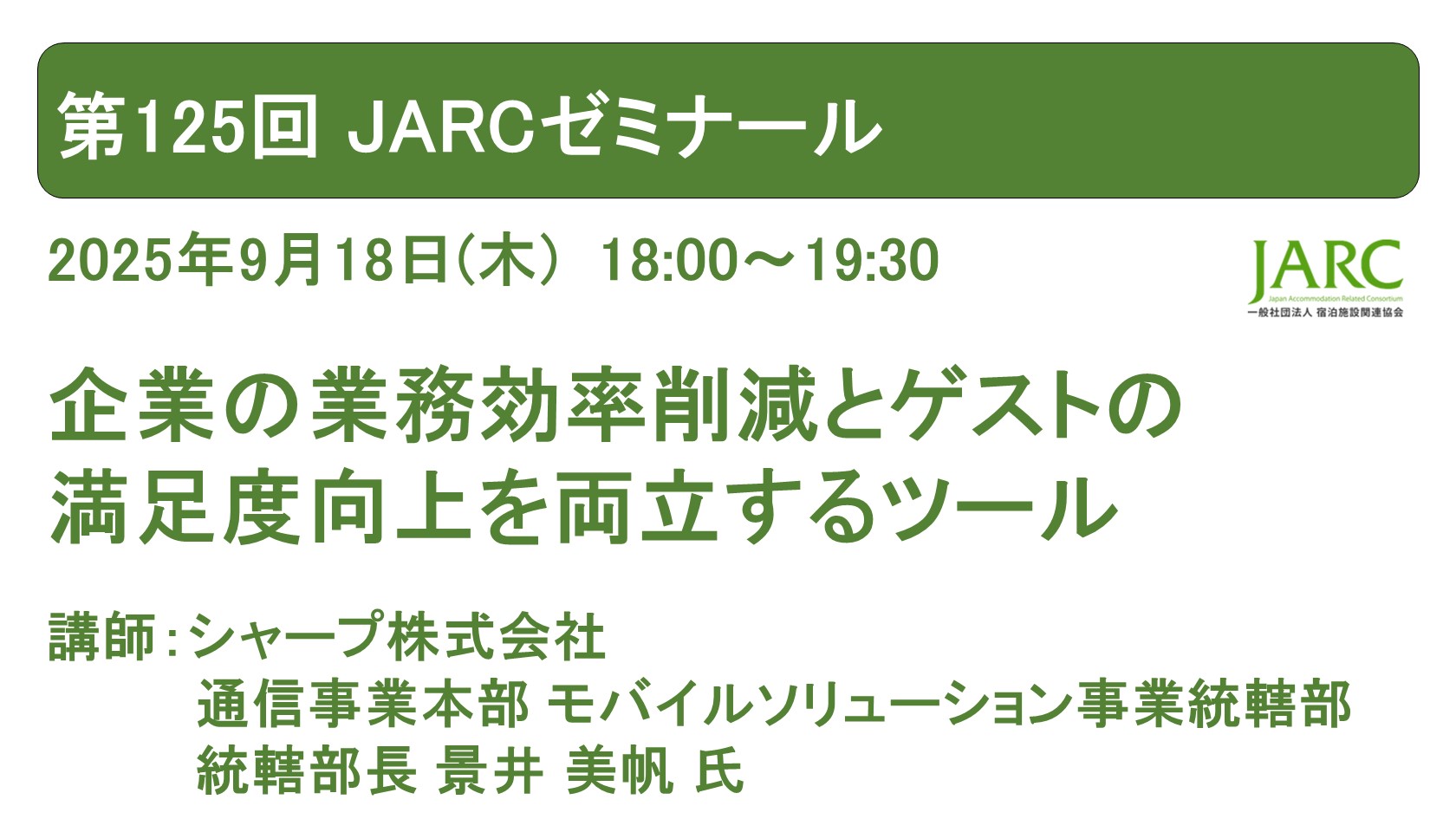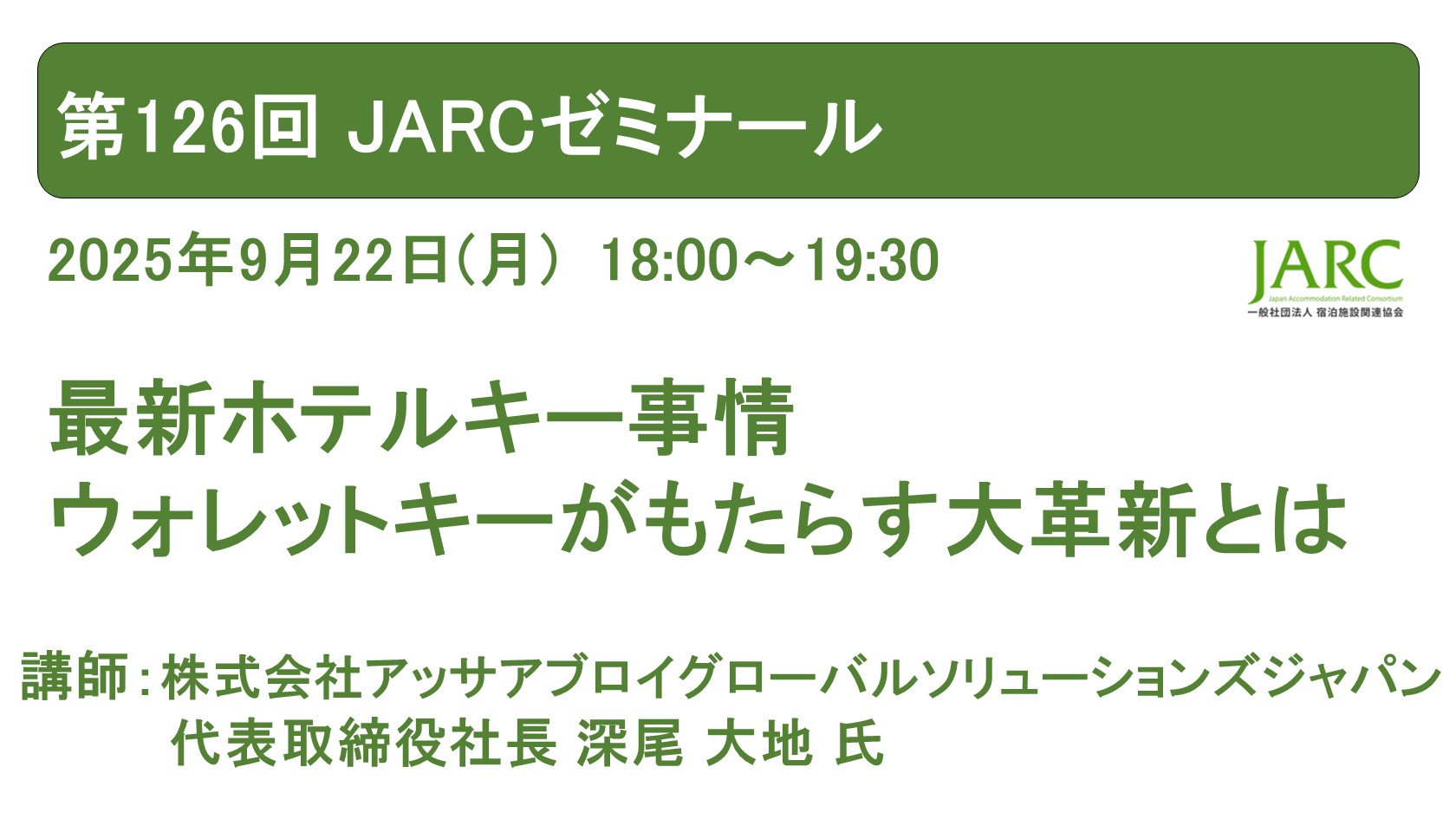1月下旬に米国航空機大手ボーイングのジャンボ機「747」の最後の機体がアトラス航空に引き渡され、半世紀余りの歴史に幕を下ろした。ジャンボ機は1967年から累計1574機製造されたが、脱炭素化が進む中で燃費性能が劣るために需要が低迷していた。
前方2階建てのジャンボ機は69年の初飛行以来、最大乗客数500人超の大量輸送で航空運賃低減を実現し、航空旅行の大衆化に貢献した。日本航空は累計113機のジャンボを保有し、世界の航空会社で最も多くのジャンボを運航していた。全日本空輸も国際線でジャンボを大いに活用し、日本人の海外旅行の激増を促進させた。私もかつて何度もジャンボに搭乗して数多くの国々を訪れた。それだけにジャンボの生産に幕が下ろされた報道に接して哀惜の念に堪えない。
一方、2月下旬の新聞報道では全国各地の人口の少ない七つの村でつくる「小さな村g7」の村長7人が首相官邸を訪れて、岸田文雄首相と面会し、地域活性化や移住促進に向けた支援策を要望したことを知った。g7は各地域で特に人口の少ない北海道音威子府村、福島県檜枝岐村、山梨県丹波山村、和歌山県北山村、岡山県新庄村、高知県大川村、熊本県五木村が参加している。深刻な過疎化や少子化など共通課題の対応策を話し合うために、16年から「g7サミット」を開催し、昨秋までで計5回開催している。今回は首相に要望書を手渡し、(1)ふるさと納税で7村の特産品の詰め合わせなど地域をまたぐ共通返礼品の導入(2)移住に向けた住宅確保の財政支援―などを求めた。
「小さな村g7」の頑張りを知って、エルンスト・シューマッハーが1973年に出版した『Small Is Beautiful』のことを思い出した。シューマッハーはドイツ生まれの英国の経済学者で77年に亡くなっている。この本は半世紀前に出版されているが、物質主義や消費主義を批判し、環境問題に真摯(しんし)に取り組むことを訴えて、世界的ベストセラーになった。シューマッハーは石炭や石油などの化石燃料に依存する産業の今後のエネルギー危機の到来を予測したが、まさに73年に第4次中東戦争をきっかけに第1次オイルショックが始まり、79年にはイラン革命によって第2次オイルショックが世界を襲った。
シューマッハーは55年にビルマ政府の経済顧問として招かれたビルマで仏教徒の生き方に感銘を受けて、66年には「仏教経済学」を提唱している。仏教経済学は簡素と非暴力を基本として、最小資源で最大幸福を得ることを目的としていて、自利だけでなく利他も重視している。「大きければ大きいほどよい」という考え方よりも、「物事の適正な限度を知る」ことの大切さを説いている。
観光庁は現在「観光立国推進基本計画」の次期計画を策定中であるが、世界的に観光をめぐる環境が大きく変化しているので、量的拡大志向だけでなく、質的向上志向やスモール・イズ・ビューティフル志向にも配慮しながら、日本観光の多様性をより良く輝かすことのできる骨太の大計を策定してもらいたい。
(北海道大学観光学高等研究センター特別招聘教授)