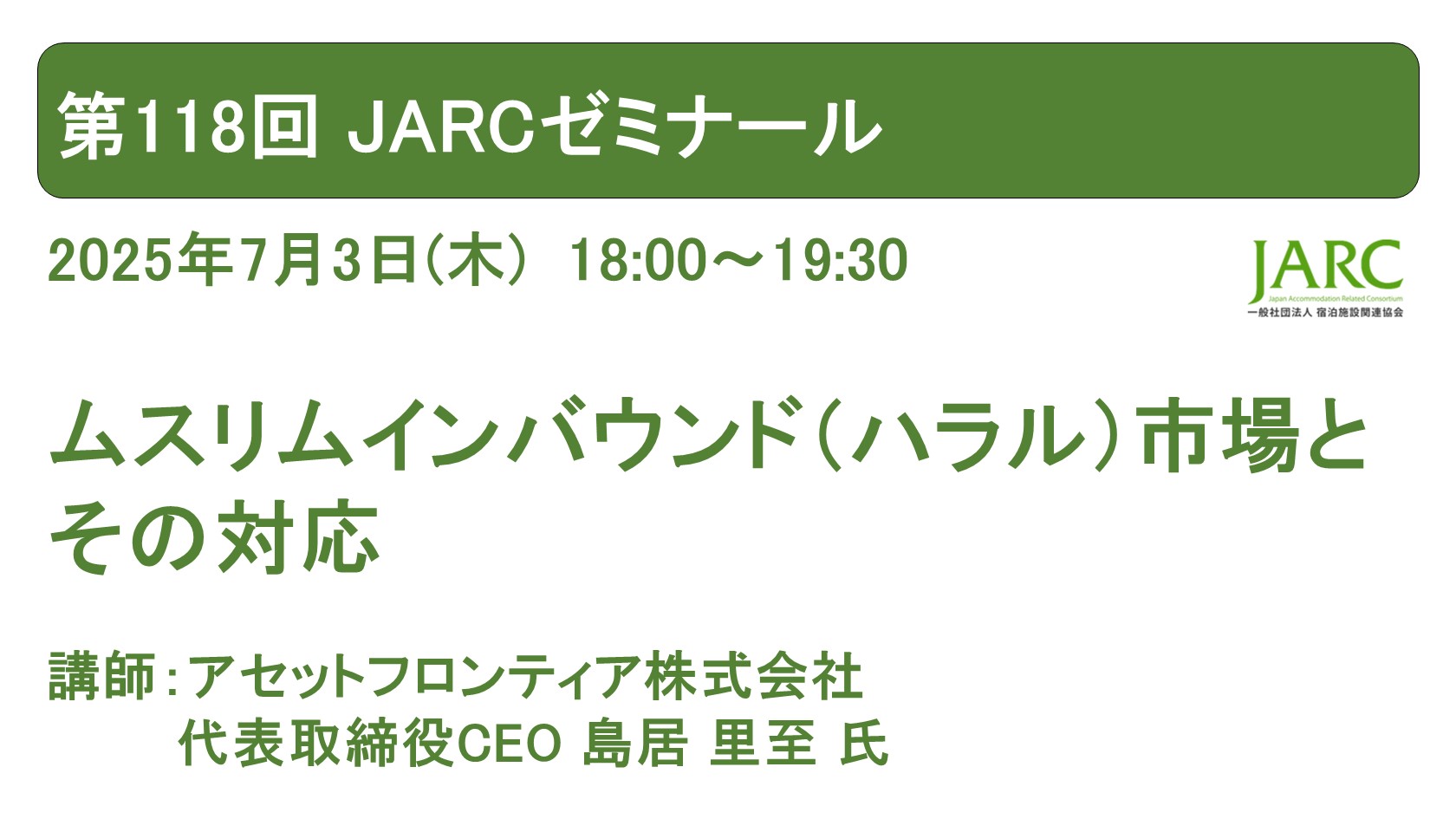古宮社長
HIS×DMMの地方創生戦略
リアルとテクノロジー融合 中立的立場で稼ぐ手段提案
――新会社「地域創生LAB」ではエイチ・アイ・エス(HIS)とDMM.com(DMM)が連携するが、狙いは。
「テクノロジーのDMM、国内外に営業力・ネットワークを持つHISの力を掛け算し、地域、日本を明るく、面白くすることを目指し、7月15日新会社を設立した。私は5年前、HIS内で地方創生の事業を1人で立ち上げた。初年度に黒字化し、4年目には複数人となった組織を単年黒字化した。これまでは、地域の課題を吸い上げ、HISのリソースを最大限生かし、リアルな旅行に関するコンテンツ作成、送客に関する提案を行ってきた。しかし、今はコロナ禍となり、不安定、不透明、不確かな状況となった。これまでに国内、海外の視察を重ねてきたが、今後において人を引き付け、ビジネスの川上を取るには仮想現実、VR、AR、ホログラフィックなどテクノロジーによる付加価値が必要だと確信し、DMMに声を掛けた」
――会社名にHIS、DMMの名前がないが。
「われわれはHIS、DMMのマーケット内だけでビジネスを行うわけでない。例えば、ハウステンボスは、HIS以外の国内外の旅行会社からも客を受け入れ、多く売る会社には大きなリターンを返している。中立的な立場であるわれわれは、他の旅行会社、映像制作会社などと連携することももちろんある」
――事業内容は。
「既存コンテンツとデジタルコンテンツの融合を推進する。まずは、地域にある既存施設にデジタルを加え、価値を付け直す。例えば、地方にある動物園のデジタル化だ。集客をあげるために、ナイトサファリを行う施設もあるだろう。しかし、入場料は昼と夜で変わらない。また、展示は昼も夜も同じで、リピーターを獲得しづらい。そこでデジタルの出番だ。来園者の歩く隣でデジタルのライオンが歩いたり、ライオンに映像を投影して着飾らせることはもちろん、季節に合わせて映像を変化させたり、架空のキャラクターとのコラボレーションも可能になる。入場料は、仮に通常1千円であるものが5千円となったとしても、映像美への需要は必ずある。また、DMMの既存コンテンツも生かせる。刀を擬人化したオンラインゲーム『刀剣乱舞』が老若男女から人気を得ている。地域で映像を使ったコラボイベントを開催することも可能だ。夜や早朝にイベントを行えば、宿泊、飲食の消費につながる」
――販売価格は。
「決まった商品、値付けはない。顧客が求めるものをオーダーメイドで作成する。デジタルは、場所、時間は問わず、二次、三次利用ができることが利点だ。システムを変更すれば、顧客のターゲットエリアに合わせた内容にも簡単に変えることもできる。課題、要望に合わせ、満足できるものを共に作り上げたい」
――施設の運営者となることは。
「直接運営することはない。1社で完結できるものでないし、そういう時代ではない。地方創生では、地域の人が主役であり中心だ。われわれが地域で楽しめるプラットフォームとスキームを提供し、地域の人はその素材を最大限使い、稼げる体制を共栄、共創しながら構築する」
――地域の課題をどう捉えているか。
「人口減少、少子高齢化は今に始まった話ではない。一度外に出た人は、戻りたいと思うものがあれば戻るし、出たくない理由があれば外に出ない。地域に魅力や稼ぐ手段がなくなれば減る一方となる。既存の観光地、道の駅などがあるから大丈夫という意見もあるが、20、30年後でも通用するだろうか。仮に補助金を旅行会社に提供してツアーで集客したとしても、補助金が途絶えれば旅行会社も去っていく。将来を見据え、変幻自在で魅力あるキラーコンテンツを中心とした町づくりは有効なはずだ」
――他社と比べ強みは。
「木を見るか、森を見るかだ。われわれは森を見ている。木はそれぞれの会社の都合や抱える事情で成り立っているが、あえて切り倒す必要はない。しかし、誰かが森を見る管理人として仕事をしなければならない。リアルとテクノロジーが加わり、幅も深さもあるわれわれがその役割を担う。事業のゴールは、売り上げや集客人数で考えていない。大きな森を作り、育てることが先決だと考えている」
――今後の事業計画は。
「コロナ禍の影響もあり、計画を来年に持ち越すなど、練り直している」
――海外展開は。
「日本で作ったコンテンツは、インバウンドプロモーションにも活用できる。海外では日本人がまだ刀を差し、自動車や家電の国だと思っている人がいる。HISの海外拠点のほか、日本企業の海外支店、海外企業とも連携しながら、日本のエッジの効いた魅力の発信に努める。世界には約80億人の人口がいて、世界のドル供給量は約88兆ドルある。可能性は無限大だ」

※こみや・たけし=1996年4月エイチ・アイ・エス入社。大阪No.1Travel支店長、ロンドン支店長、H.I.S.Experience Japan代表取締役などを経て、2017年6月から地方創生・官民連携事業室室長。2020年7月から現職。
【聞き手・長木利通】