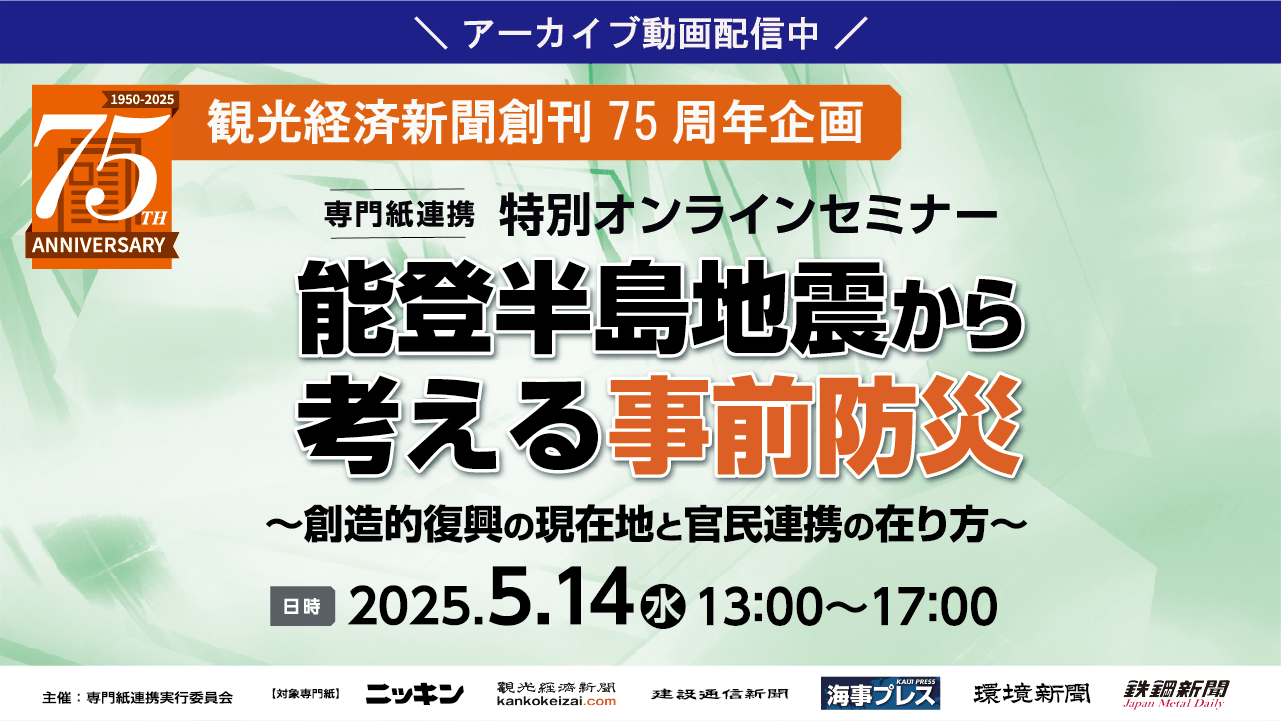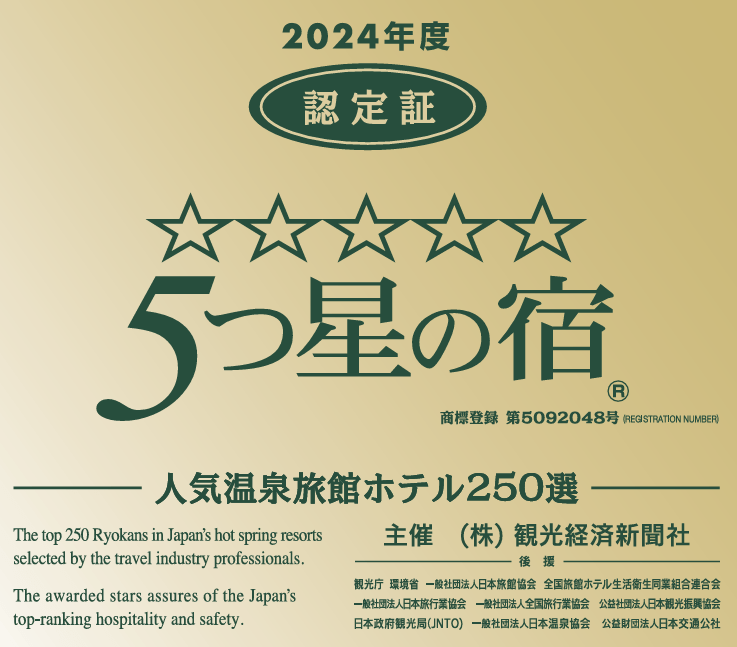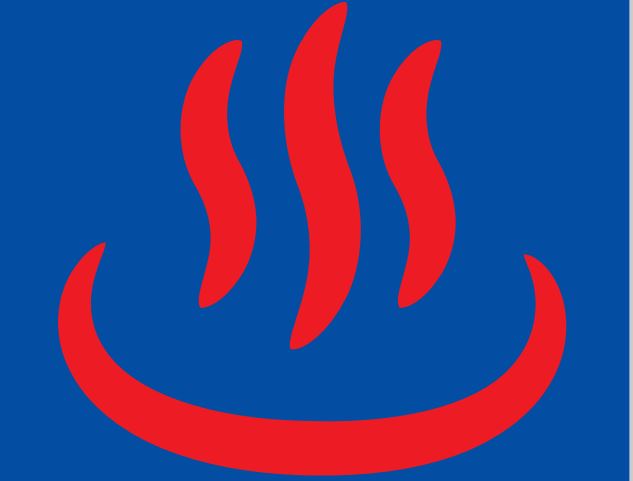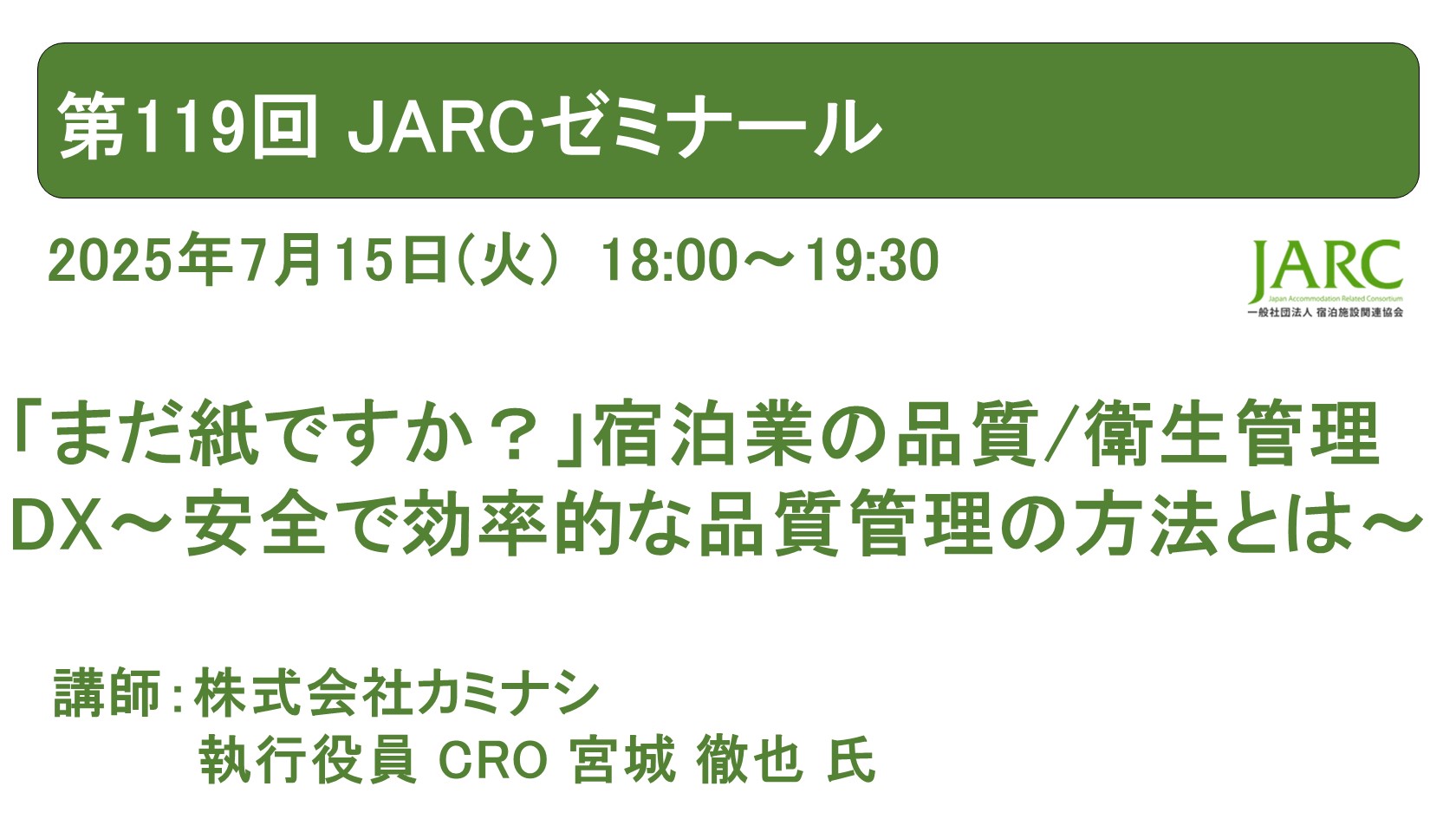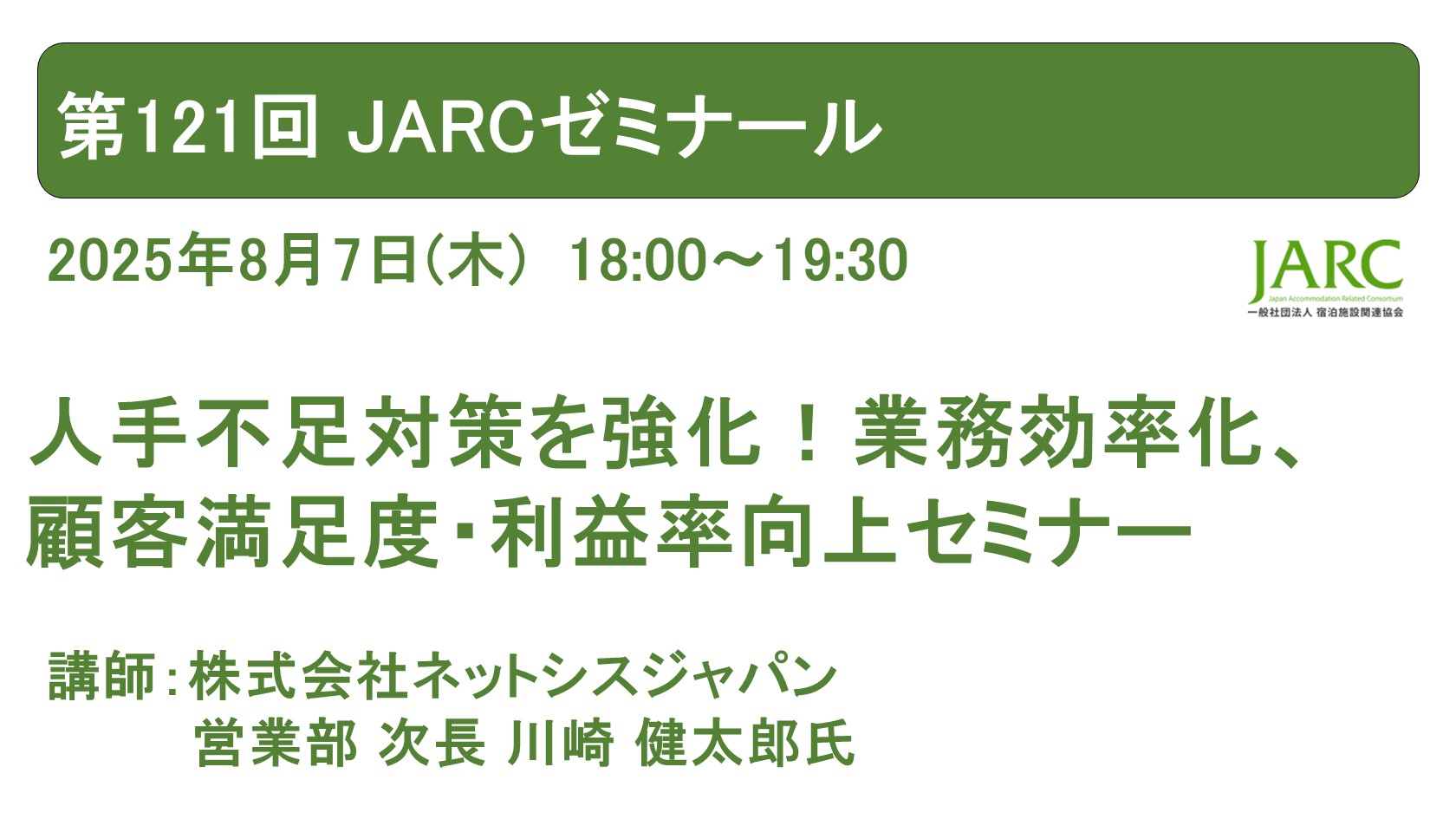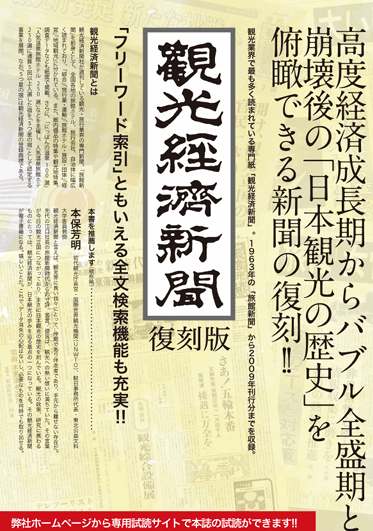シュアリングエコノミー協会代表理事 石山アンジュ氏
地域活性化に大きな役割を果たす
――近年のシェアリングエコノミー市場の変化をどう見ているか。
シェアリングエコノミー市場は黎明期から成長期に移行していると感じている。
シェアリングエコノミー協会を立ち上げた2016年当時、会員はスタートアップを中心としたプラットフォーマーなど40社程度であったが、現在は約360社に増加している。また、大手小売業や自動車メーカーなどがサブスク型のレンタルなどシェアサービス事業に参入し、スタートアップによる新しい産業から大手企業がシェアリングサービスを取り込むような流れが出てきている。
一方で、コロナ禍で働き方や暮らし方の見直しが行われたことが市場に大きな影響を与えた。リモートワークが進んだことで多拠点生活や地方移住を推奨する動きが始まり、暮らし方や働き方が一極集中型から多極分散型へと見直されつつある。その手段としてシェアリングエコノミーが支持されている。業界によっては制度的な課題もあり、それらが解決されることで市場は加速度的に拡大すると考えている。
――地域活性化の取り組みの一つとして自治体によるシェアリングエコノミーの活用に注目が集まっている。
16年に全国5自治体がシェアリングシティ宣言を行い、20年にシェアリングシティ推進協議会が設立された。シェアリングシティは海外の概念で世界150都市以上に広がっているが、海外のモデルの多くは都心部の人口密集、経済格差、サステナビリティなどの領域で注目されている。一方、日本で多くの自治体が抱える問題は人口減少や高齢化だ。シェアがそうした問題を解決し得る可能性があると、政府は17年に「未来投資戦略2017」でシェアリングエコノミー推進を打ち出した。日本は非常に特殊で、世界的に見てまれなケースだ。人口減少や高齢化により公助のモデルの限界が出てきた中で、それを補完する一つの選択肢としてシェアリングエコノミーが期待されている。
例えば、以前は1日10本だったバスが1本になり、高齢者が病院に行くにも苦労している。コミュニティバスの採算が合わなくなり、タクシー会社はどんどん事業撤退していく、ならば市民同士で送り合いしたらどうかということだ。ただ、乗合交通やライドシェアの取り組みが全国一律で語られる面は否めない。交通問題といっても中核都市と過疎地域では課題が全く異なる。本当に深刻な問題である過疎地域においては部分的にライドシェアを認める動きが出てきても良いのではないか。地域の人口規模や交通課題をしっかりと整理した上で、モビリティのシェアサービスを導入しやすくすれば自治体側も助かるのではないかと思っている。
こうした交通問題だけでなく、買い物、子育て、介護などの問題についても同様で、自治会など昔あった地域の共同体がなくなる中、シェアサービスがその機能を補完することに期待が高まっている。
――新たなモデルを作り、広げるための取り組みは。
その課題について、シェアリングエコノミー協会だけでは難しいと行ったのが16年の「シェアリングシティ宣言」で、まず先見性を持つ市長や町長に手を挙げてもらい、それぞれの自治体がモデルを作った。この動きが後のシェアリングシティ推進協議会につながり、自治体同士が先進事例などをシェアして取り組みを広げている。
例えば、佐賀県多久市は、地域に居ながら、シェアリングエコノミーを活用してオンラインで働くモデルを作り、新しい就業支援の形として推進している。多くの自治体が人口流出に悩むがその大きな理由の一つが地域に仕事がないということ。この成功事例がさまざまな自治体に広がっている。また、千葉県千葉市は、空き家や使わなくなった公共施設を活用する遊休資産の循環モデルを考え、こうした空間をシェアサービスで市民に開放している。
それぞれの地域にそれぞれの課題がある中、推進協議会では、関係人口、働き方、子育て、SDGs(サステナビリティ)、防災、観光、遊休資産活用、モビリティという八つのテーマを設定し、モデル創出の支援などを行っている。
実際に協議会を運営して思ったことは、自治体の職員同士、他の自治体との職員同士が交流し、意見交換する場が意外と少ないこと。事例をつくった職員が他自治体の職員と直接情報共有できる場に大きな意義を感じている。
――それらテーマの分野について期待や可能性について伺いたい。観光分野は地域活性の大きな柱となっているが、コロナ禍で大きな打撃を受けた。
コロナ禍でインバウンドが激減し、接触を伴う対面型サービスの民泊などの需要も減退したが、今後は非常に可能性のあるサービス分野だと思っている。
今、インバウンドが戻ってきているが、人の滞留は都市や有名な観光地に集中してしまっている。外国人観光客をもっと増やすためには、ニッチな場所も含めて全国に人が流れていく必要がある。観光資源を持たないと考える自治体は少なくないが、今ある資源ですぐに人を呼べるのがシェアリングエコノミーの大きな特徴だ。
例えば、2022年から北海道の十勝管内清水町は全国で初めて町長の自宅に民泊で泊まれる取り組みを開始した。札幌から1時間半もかかるが、すでに多くの外国人観光客が訪れているようだ。私も泊まったが、町長の自宅で一緒に朝ご飯を食べる体験自体が非常にユニークで、楽しかった。また、清水町は全国初の職員の副業民泊も始めている。例えば移住を担当する職員が、移住希望者を自宅に泊め、実際に移住が決まった例もあると聞いている。
これらは予算を付けて新しい施設を作ったわけではない。民泊だけでなく、地域の人しか知らない、都市部にはない郷土料理や家庭料理などユニークな体験ができることで人が流れていく、非常に大きな意義があることだと思う。
――デジタル田園都市国家構想(以下:デジ田)をシェアリングエコノミーの点からどう捉えているか。
デジ田においてシェアリングエコノミーの活用がしっかりと認知されたことによって、取り組みが進みやすくなったと感じている。
今後の可能性や期待という点からはオープンデータの活用に期待している。デジ田で進めるスーパーアプリ(さまざまなアプリにアクセスできるプラットフォームの役割を果たすアプリ)の中で、シェアサービスがより使いやすくなるようなモデルを作っていただきたいと思っている。
例えば、シェアサイクルのサービス事業者が持つ、いつ、どの道を通ったかというデータを観光政策に生かすというニューヨーク市の事例がある。デジ田の中でデータのオープン化や共有化が進めば、観光政策だけでなく空き家活用などさまざまな取り組みに生かすことができる。もちろん情報の取り扱いはセンシティブな問題だが、官民がデータを連携し互いに生かすような、もう一歩踏み込んだ取り組みに期待している。
一方、個人の生活という視点からは、今後、お金があってもどうしようもないことがどんどん増えていくだろう。交通が不便で簡単に病院に行けない、警察を呼んでもすぐに来ない。私は、子育て世代だが、毎日ベビーシッターを呼ぶのは現実的ではない。かつて地域には誰かが預かってくれたり、皆で子どもを見守るという仕組みがあった。介護も同様だ。人とのつながり、セーフティネット、コミュニティといった視点の個人ニーズが高まっていくと考えている。
そうした時にシェアサービスがあると思い出していただければいいなと考えている。別に「シェア」という言葉でなくともよい。例えば、四国支部では「わかちあい」、沖縄支部では「ゆいまーる(沖縄の方言で『助け合う』の意味)」という言葉を使って浸透させようとしている。人々がわかちあって、つながりの中で助け合って生きる、かつてあった共助のモデルを、デジタルを使って今の時代に合ったものとして作っていけるかが大事だと考えている。

石山 アンジュ氏 1989年生。2012年国際基督教大学卒。リクルート、クラウドワークスを経て現職。シェアリングエコノミーを通じた新しいライフスタイルを提案する活動を行うほか、政府と民間のパイプ役として規制緩和や政策推進にも従事。著書に「シェアライフ―新しい社会の新しい生き方(クロスメディア・パブリッシング)」。デジタル庁シェアリングエコノミー伝道師。大分と東京の2拠点生活。