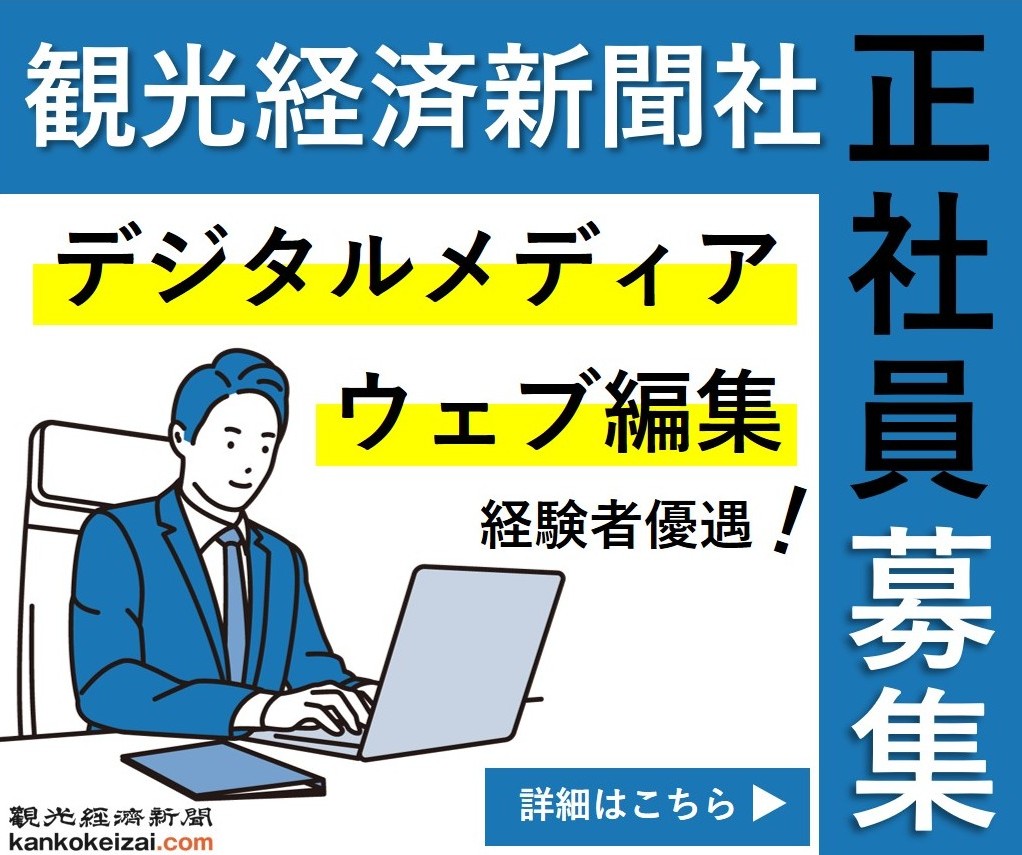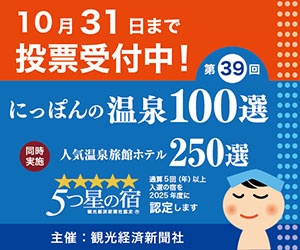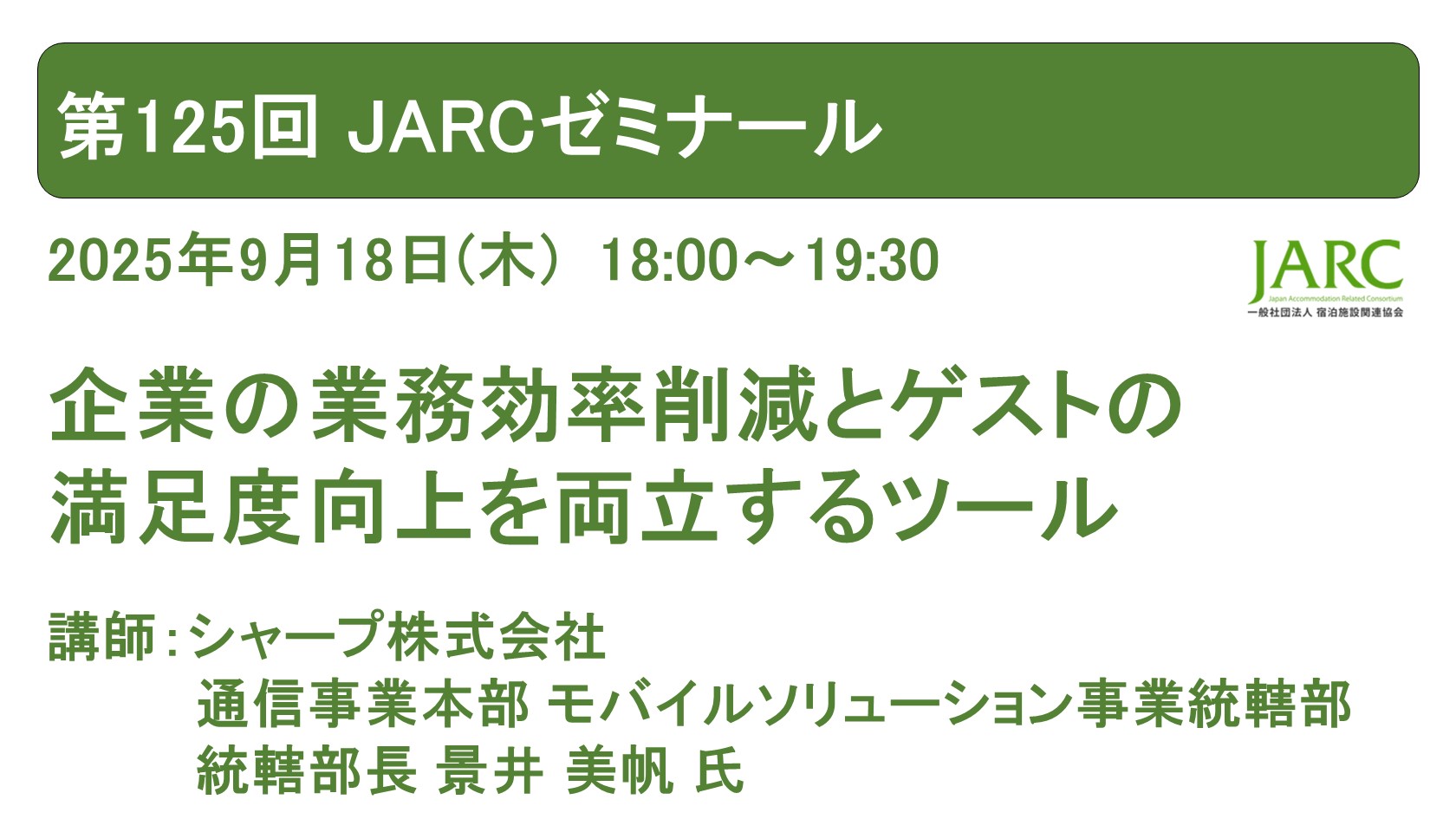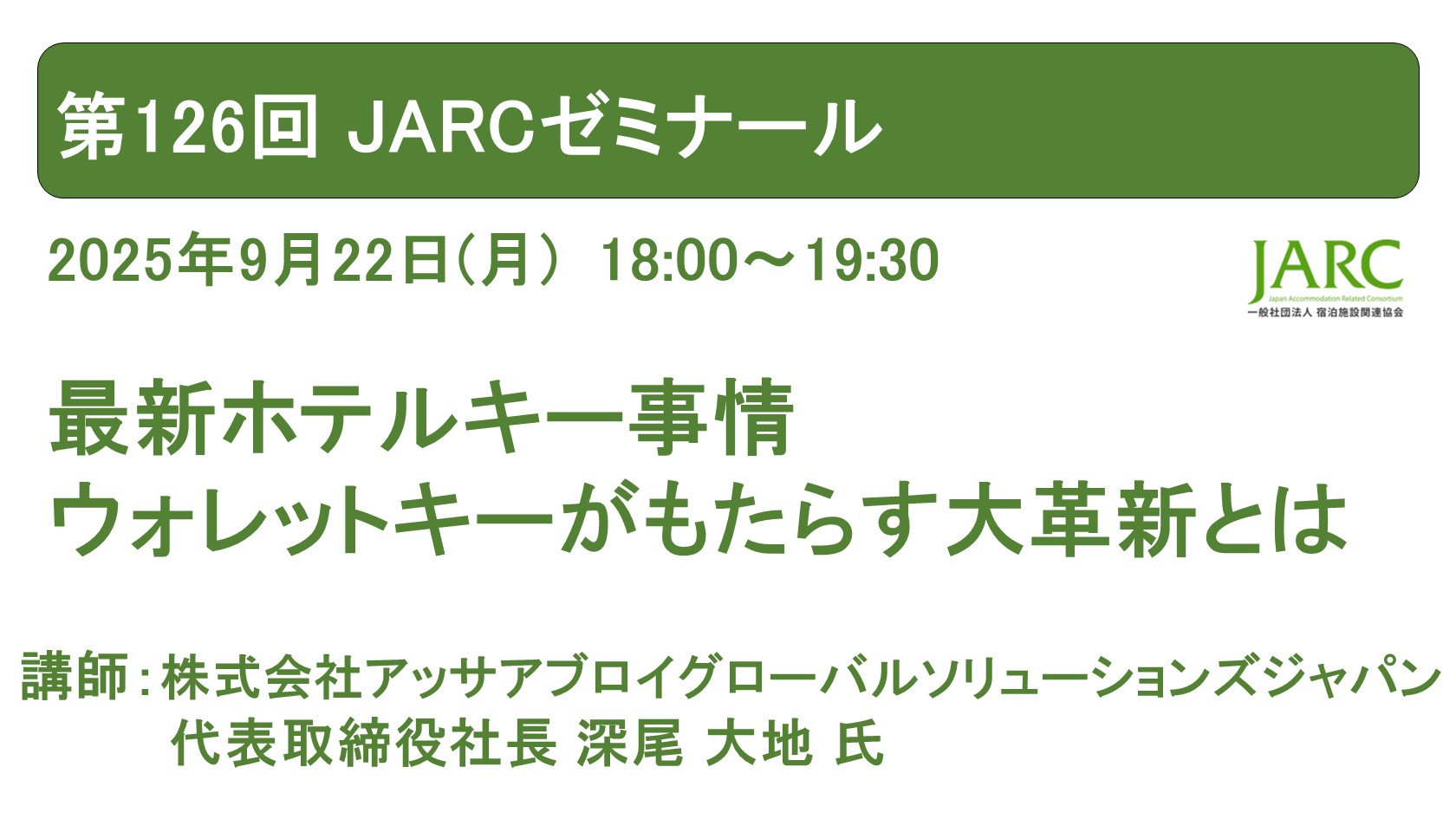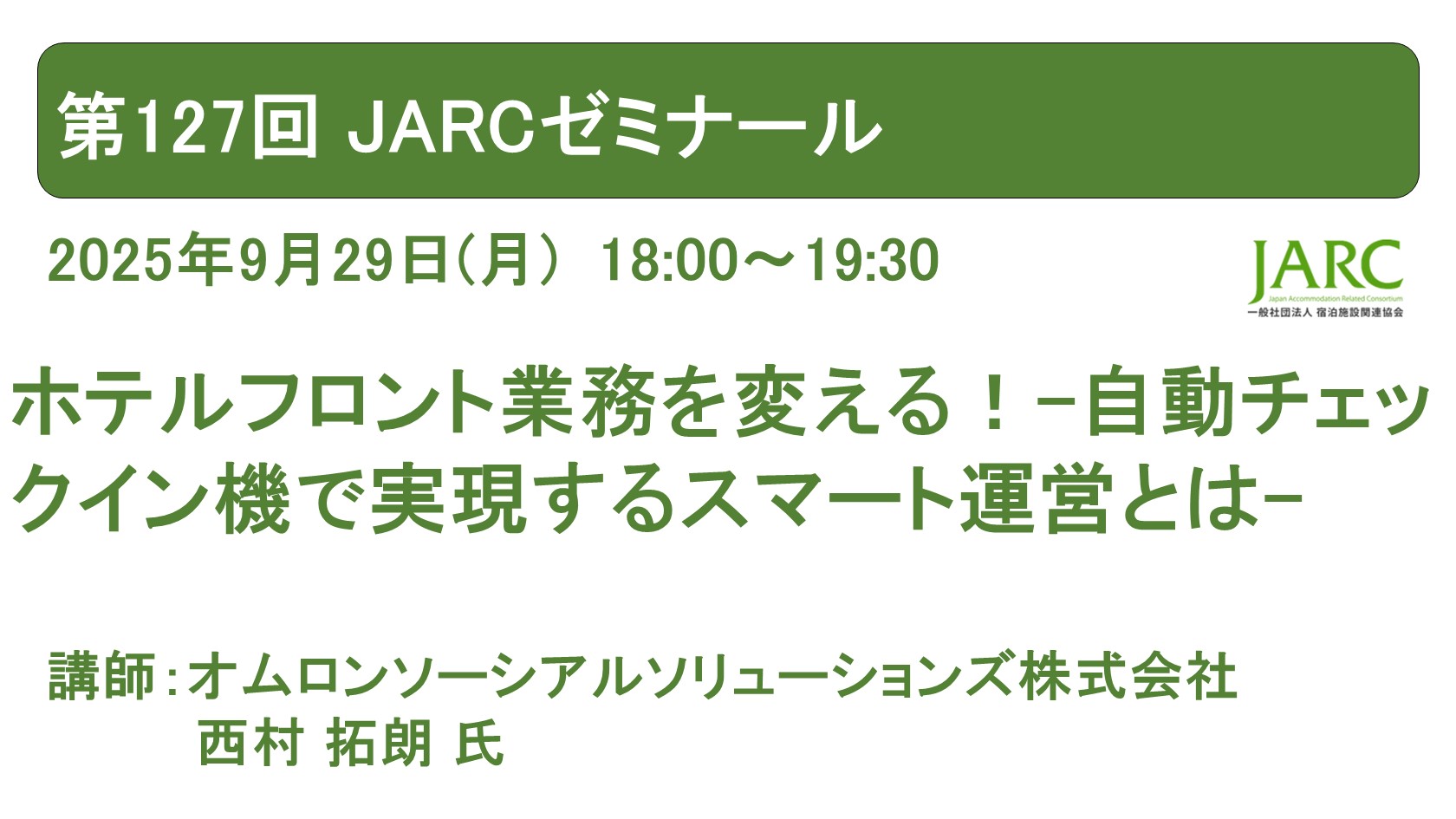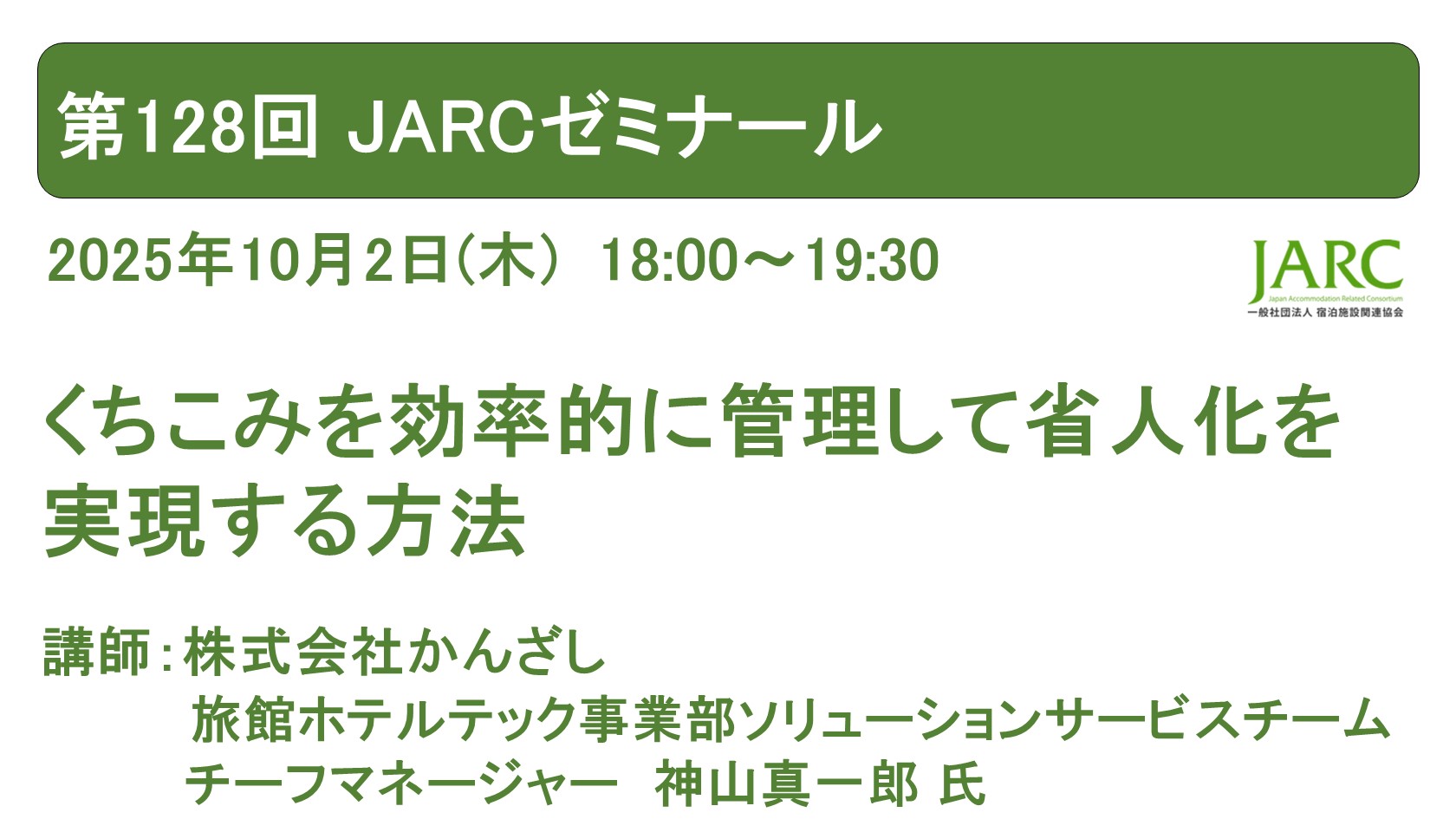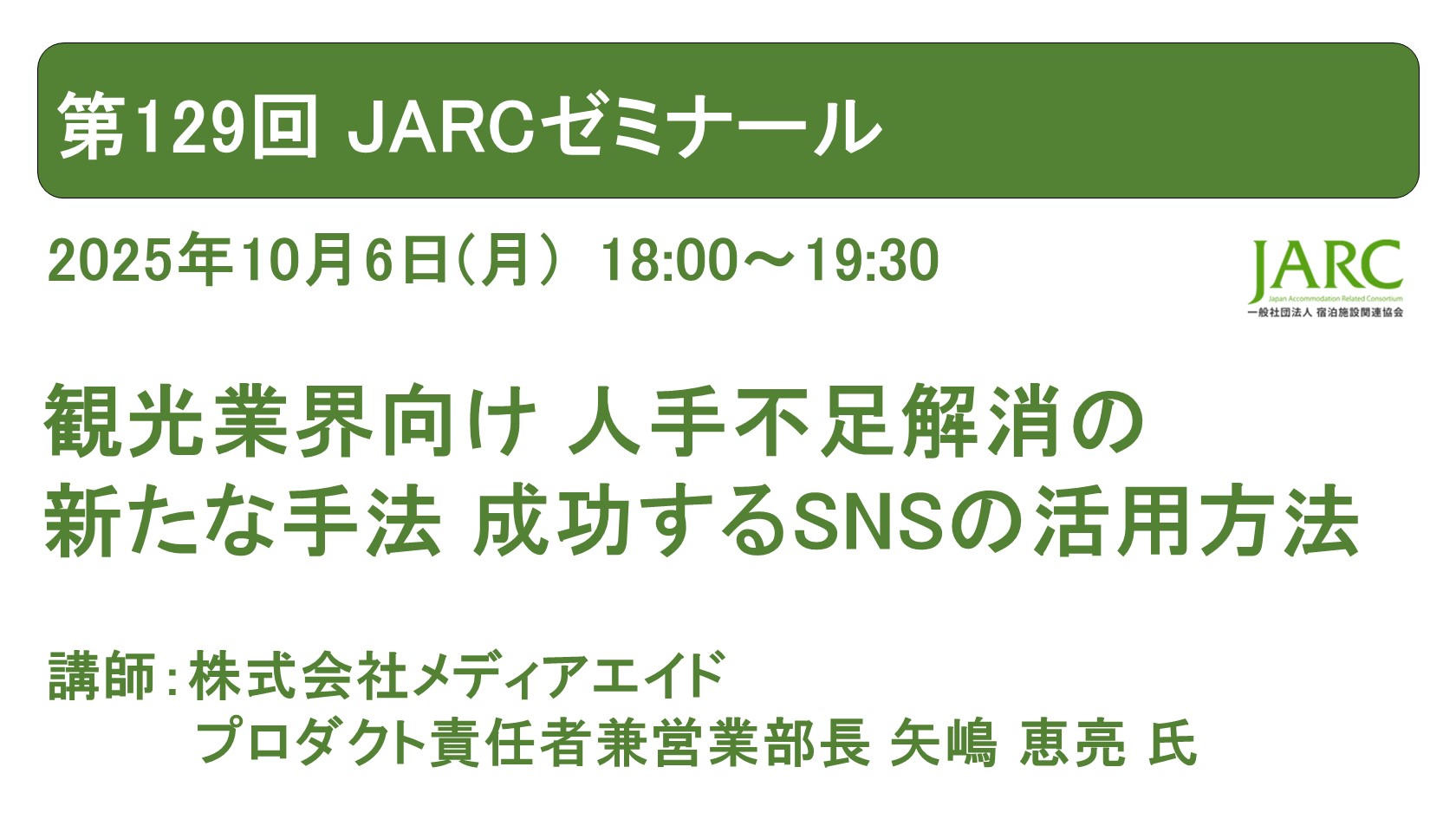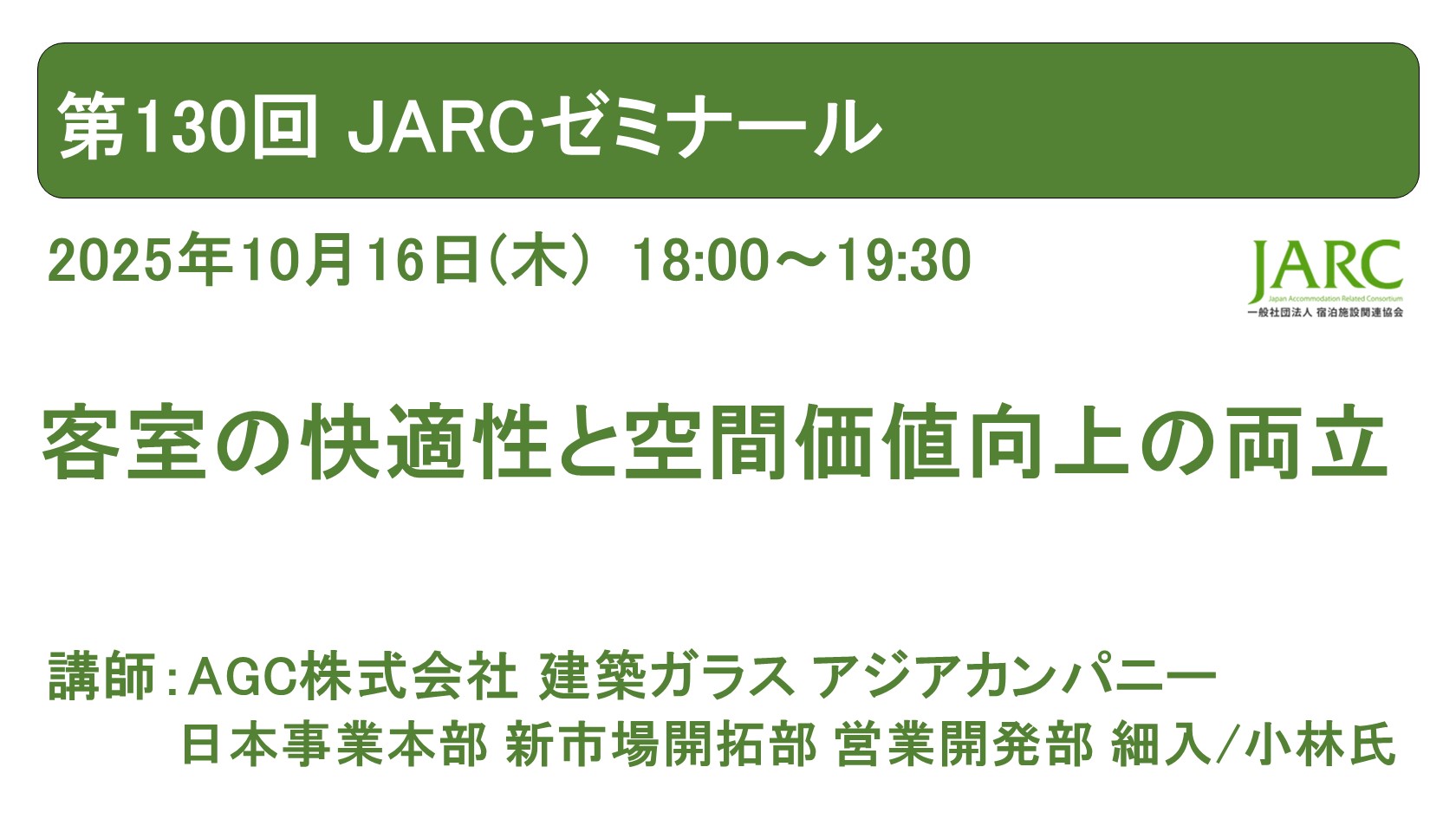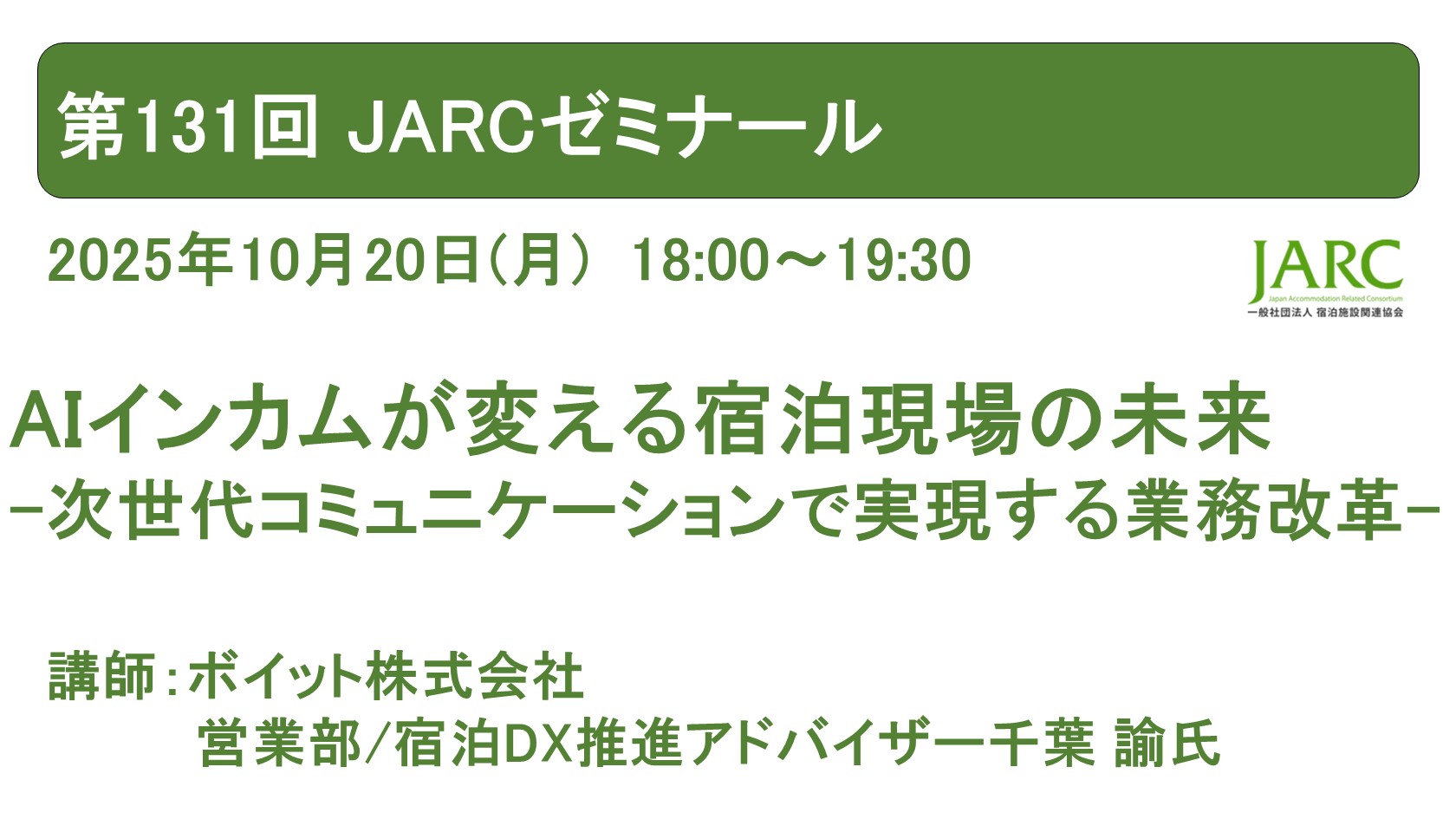観光庁長官 髙橋一郎 氏
総力挙げて地方誘客促進 稼げる産業、基幹産業に
観光庁は、2008年10月1日の発足から15年の節目を迎えた。インバウンドの拡大や国内における旅行消費額の増加に成果を上げたほか、観光産業の生産性向上、観光地域づくりを担うDMOの育成などに注力してきたが、コロナ禍を経て、積み残した課題が顕在化し、新たな問題にも直面している。観光庁の髙橋一郎長官に観光立国復活への取り組みなどについて聞いた。
――発足から15年。観光庁の成果は。(聞き手・観光経済新聞 副編集長 向野悟)
2008年10月に、観光立国の実現に向けた施策を強力に推進することを目的に観光庁が発足した。振り返ると、年間の訪日外国人旅行者数を倍増させて1千万人にするとの目標を立て、2003年にビジット・ジャパンキャンペーンがスタートした。2006年には、観光立国推進基本法の制定によって、観光立国を目指すことを国会の意思として示していただいた。こうした後押しがあり、観光立国の実現に向けた旗振り役として発足したのが観光庁だ。
発足以降、東日本大震災、コロナ禍という厳しい状況を経験するなど、観光を取り巻く状況は目まぐるしく変化してきたが、真っすぐな上り坂を駆け上がるときも、どん底のときも、それぞれの局面に応じて全力で取り組んできた。私自身も、2013年~2016年に観光庁で参事官、課長職を務めたが、その当時は、アジアをはじめとする世界経済の成長力をインバウンドの形で日本に呼び込み、全国津々浦々に消費と交流を生み出そうという時期で、地域のにぎわいを通じて、観光がわが国経済のけん引役、柱となり、かつ地域の発展の礎となるということを実感できた。
2016年には、観光を日本の成長戦略と位置付け、2030年に訪日外国人旅行者数を6千万人にするなどの目標を掲げた「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定し、関係省庁と協力して日本の魅力の発信や受け入れ環境整備、戦略的なビザ緩和、消費税免税制度の拡充に取り組んだ。こうした取り組みの成果として、2019年の訪日外国人旅行者数は3188万人、国内における日本人と訪日外国人を合わせた旅行消費額は約28兆円と飛躍的な拡大を遂げた。
――コロナ禍への対応はどうだった。
2019年に次長として観光庁に戻ったが、ほどなくして、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大し、国内外の人流が一斉に止まってしまった。需要が消滅し、観光産業の事業継続と雇用の維持が危ぶまれる未曽有の状況に直面し、大変な危機感を持った。政府を挙げて支援金や雇用調整助成金の特例措置、実質無利子・無担保融資などの支援に取り組むとともに、Go Toトラベル事業を創設・実施することで、旅行需要の創出に全力を挙げさせていただいた。
――Go Toトラベルには当初、約1.3兆円の予算が計上された。県民割や全国旅行支援に充てた予算を合わせると総額は約2.7兆円に上る。
観光予算としてはかつてない規模だ。それだけ政府全体の認識として、観光の発展の基盤が失われるとの危機感が強かった。観光が国や地域の経済に果たす役割の重要さが改めて認識されたということでもあった。Go Toトラベルや全国旅行支援を実施するとともに、コロナ後の発展の在り方も見据えて、高付加価値化やDXを促進するなど、観光産業の多面的な支援にも取り組んだ。
関係の皆さまの努力の結果、本年7月の訪日外国人旅行者数は232万人、コロナ前の19年同月比で78%、日本行きの海外旅行が制限されていた中国を除いた数字では103%とコロナ前を超えている。訪日外国人旅行消費額も本年4~6月期が1兆2052億円、19年同期比で95%となるなど堅調に回復してきている。
――成果の一方で積み残した課題があり、新たな課題も出てきている。
コロナ禍を経て旅行者の意識に変化が生じたほか、観光産業が以前から抱えてきた課題が一気に顕在化するなど、観光政策を取り巻く環境も大きく変わった。そうした状況を踏まえ、本年3月に新たに策定した観光立国推進基本計画には、「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」の三つのキーワードを掲げ、これに対応する戦略、施策を打ち出した。
国内外の観光需要は、急速な回復と言っていい状況だが、インバウンド・アウトバウンドのバランスの取れた双方向交流の拡大、そして、地方部への誘客、これが極めて重要な課題となっている。宿泊のデータでも、外国人旅行者の7割以上が三大都市圏に集中している。地域の活性化につながる地方誘客は、観光政策の本質であり、総力を挙げてさらに強化していきたい。他方で、一部の観光地では混雑やマナー違反による地域住民の生活への影響、あるいは旅行者の満足度低下への懸念が生じている。こうしたオーバーツーリズムの課題に対しては、関係省庁の協力を得て対策を取りまとめ、有効な施策を講じていく。
いま観光の質が問われている。国内外の旅行者が地域の文化や自然に深く触れるような体験・交流を生み出し、地域や観光産業が経済的に、社会的に持続可能な在り方で発展することが大切だ。その地域でしか体験できない特別な価値を提供し、生産性、収益性を向上させ、稼げる産業へと変革していく。観光を持続可能な在り方で発展させていくことで、地域を次世代に引き継いでいけるようにしたい。
――15周年の節目に観光産業、地域の観光関係者にメッセージを。
観光産業は、コロナ禍の危機的な状況をくぐり抜けてきたが、宿泊業などは依然、債務の返済などで厳しい状況にあると認識している。これに加えて生産性、収益性の低さ、人手不足といった構造的な課題を抱えている。しかし、観光は成長戦略の柱、地域活性化の切り札である大事な産業だ。それらの課題を解決しなければならない。観光庁は、宿泊業などに対して高付加価値化やDXなどの支援策を総合的に講じていく。
観光産業においては、DXの推進がサービスの高度化と旅行者の利便性向上の鍵となることから、その積極活用が極めて重要だ。
宿泊業の人手不足については、足下の事業者の採用活動とともに、人手をかけるべき業務に人材を集中するための業務効率化への設備投資、外国人材の円滑な活用などを支援していきたい。経営者の皆さんは厳しい状況の中、ギリギリの努力をされていると思うが、ぜひ今こそ従業員の方々の待遇改善に取り組んでいただきたい。観光庁も収益性の向上、経営の高度化に向けた取り組みを引き続き支援していく。
旅行業についても、旅行者のニーズを熟知し、さまざまな観光地に精通している強みを生かして、付加価値の高い旅行商品を提供できるよう、さらなるビジネスモデルの変革に期待している。地域の関係者と連携して、その土地ならではの魅力を生かした旅行商品を造成、販売する取り組みなどを今後も支援していく。
観光産業には、持続可能な在り方で生産性、収益性を高め、わが国の基幹産業へと成長してほしい。そのためには、お得なサービスの提供にとどまらず、お買得ニッポンに甘んじることなく、価値あるサービス・体験を相応の対価を得て提供していくことが重要だ。
観光を通じた地方創生、地域活性化は、地域の関係者のお力添えなくしては実現できない。地域の社会、経済に好循環をもたらし、地域に貢献する持続可能な観光地域づくりへの取り組みを強化する。「住んでよし、訪れてよし」の通りだ。地域経営の視点を大事に、自治体やDMOなどを支援し、各地のお手本となるような成功事例をたくさん作っていきたい。観光の意義の一つは、住民の方々が観光客を迎えるということを通して、地域の歴史や文化を再発見、再認識することだ。地域への誇りをさらに深めてもらえるような観光でありたいと願っている。
観光庁には、観光立国実現への旗振り役、司令塔の機能を託していただいているが、観光の主役は、現場を支えている観光産業、地域の方々だ。この国の観光がどうあるべきかのビジョンをお示しし、メッセージをお届けしながら、観光を支えている現場の方々の取り組みがより大きな力となるよう、これからも全力で取り組んでいきたい。
夢と誇りを持てるように 観光産業は人を幸せにする仕事
――髙橋長官は長官就任以前にも観光庁で約5年間仕事をしている。国土交通省、内閣官房でも 観光に関係した仕事が多い。観光政策に臨む上で大事にしていることは。
観光の仕事というのは、人の心に訴え掛ける、人の気持ちに働き掛ける仕事なのではないかと思っている。どうしたら地域の魅力、あるいは日本の素晴らしさを人々の心に深く届けることができるか。観光庁の仕事には、伝統を大切にしながら、知的好奇心を持って新たな価値を育み、人の心に鋭敏に柔らかく寄り添う感覚のようなものが必要だと考えている。
観光には人生を豊かにし、人を幸せにする力がある。人生観や価値観が変わるような旅行があり、日常の暮らしや日々を生きていく上で支えとなるような旅がある。人生の節目にいろいろな気持ちを抱えて旅に出たり、介護が必要な状態で諦めていたけれど家族の支えで温泉旅行に出掛けたり、さまざまな思いを込めた旅というものがある。人生の限られた場面、短い時間のことかもしれないが、忘れられない、魂を揺さぶられるような経験になることもある。
コロナ禍に際し、観光の発展の基盤が失われるとの危機感は強かったが、人々の旅行や観光への欲求、旅へと突き動かされる思いは根源的なものであり、必ずいつか復活すると確信していた。
観光産業は、人々の幸せに深く関わり、人生に彩りを添えることができる素晴らしい仕事だと考えている。これから観光の世界に入ってくる若い方々をはじめ、地域で観光に携わる皆さまが、さらに一層、夢と誇りを持って、前に進んでいけるよう力を尽くしていきたい。

髙橋 一郎氏(たかはし・いちろう) 1988年運輸省(現・国土交通省)入省。2013年観光庁参事官、14年同観光戦略課長、15年同総務課長、17年内閣審議官、18年内閣官房東京オリパラ大会事務局統括官。19年観光庁次長。21年国土交通省海事局長。23年7月から現職。東大法卒。東京都出身。59歳。