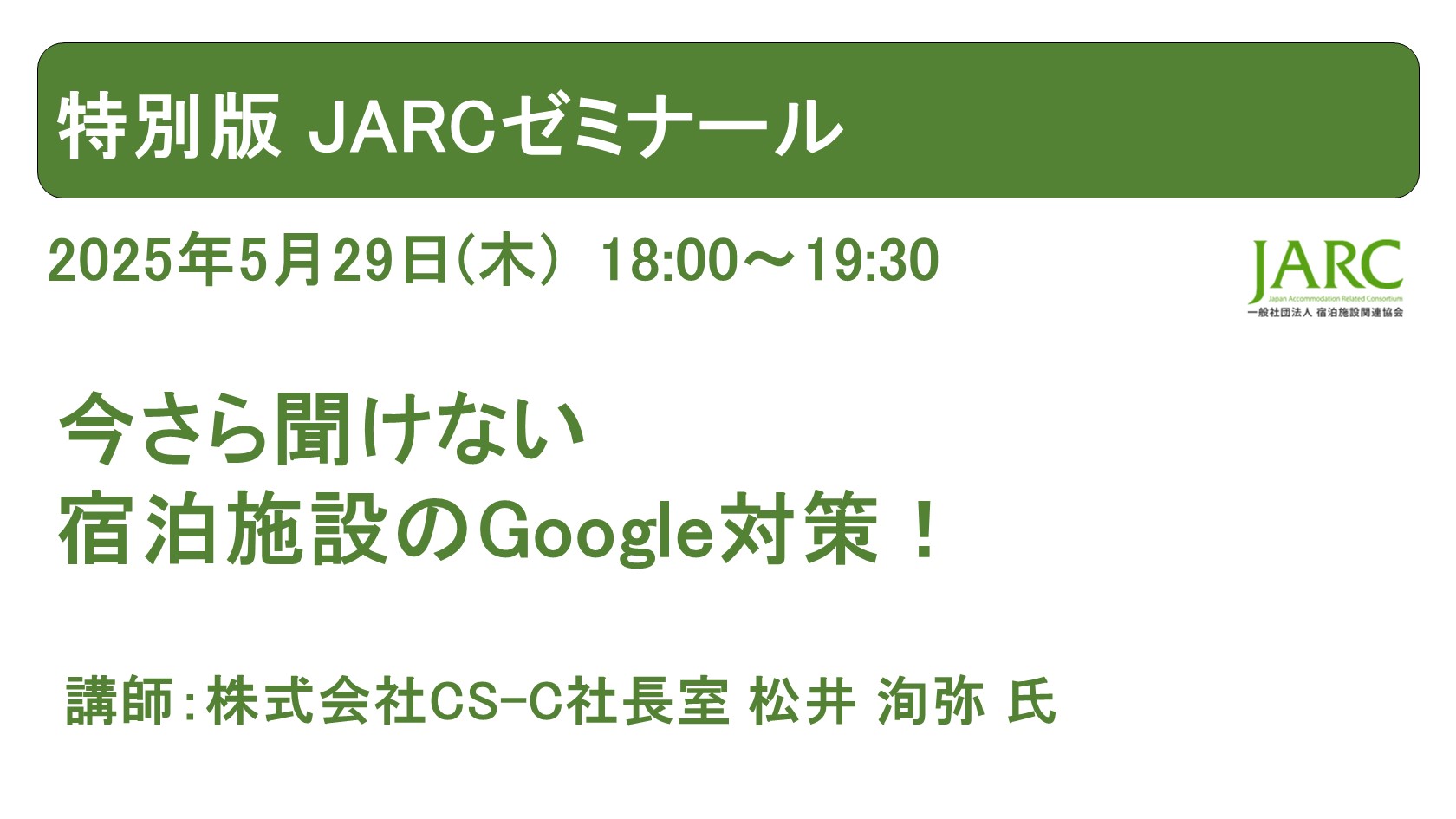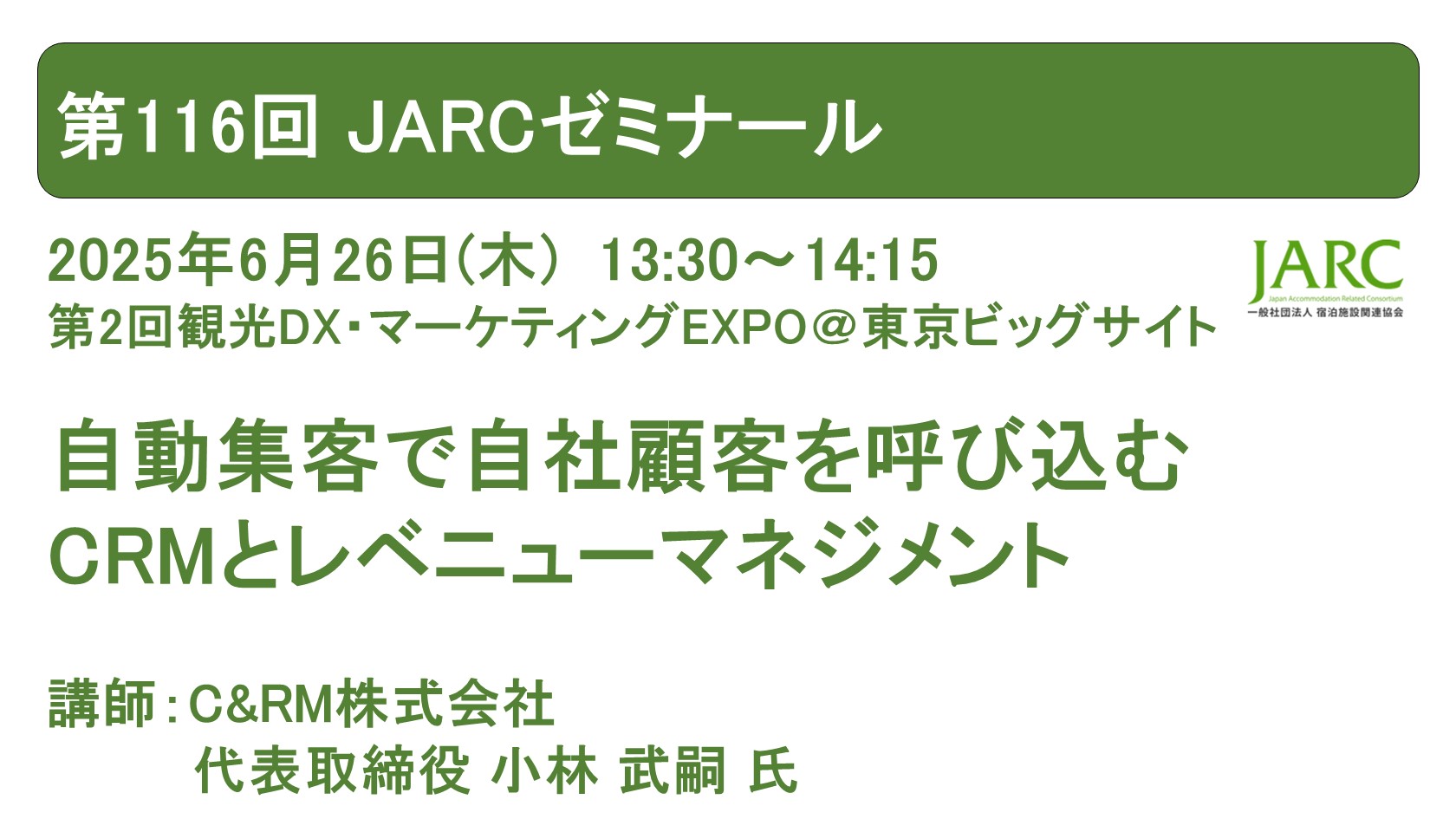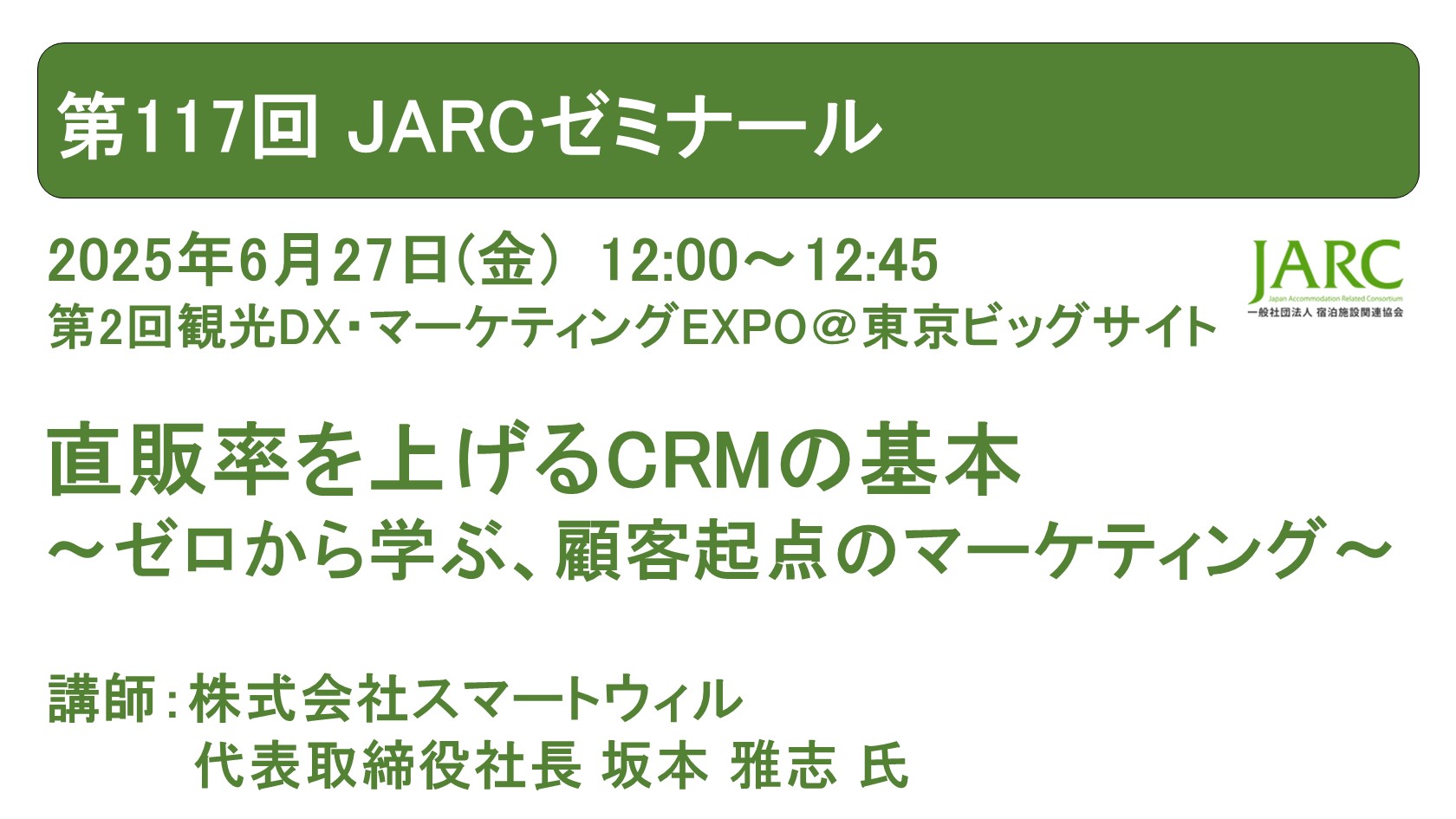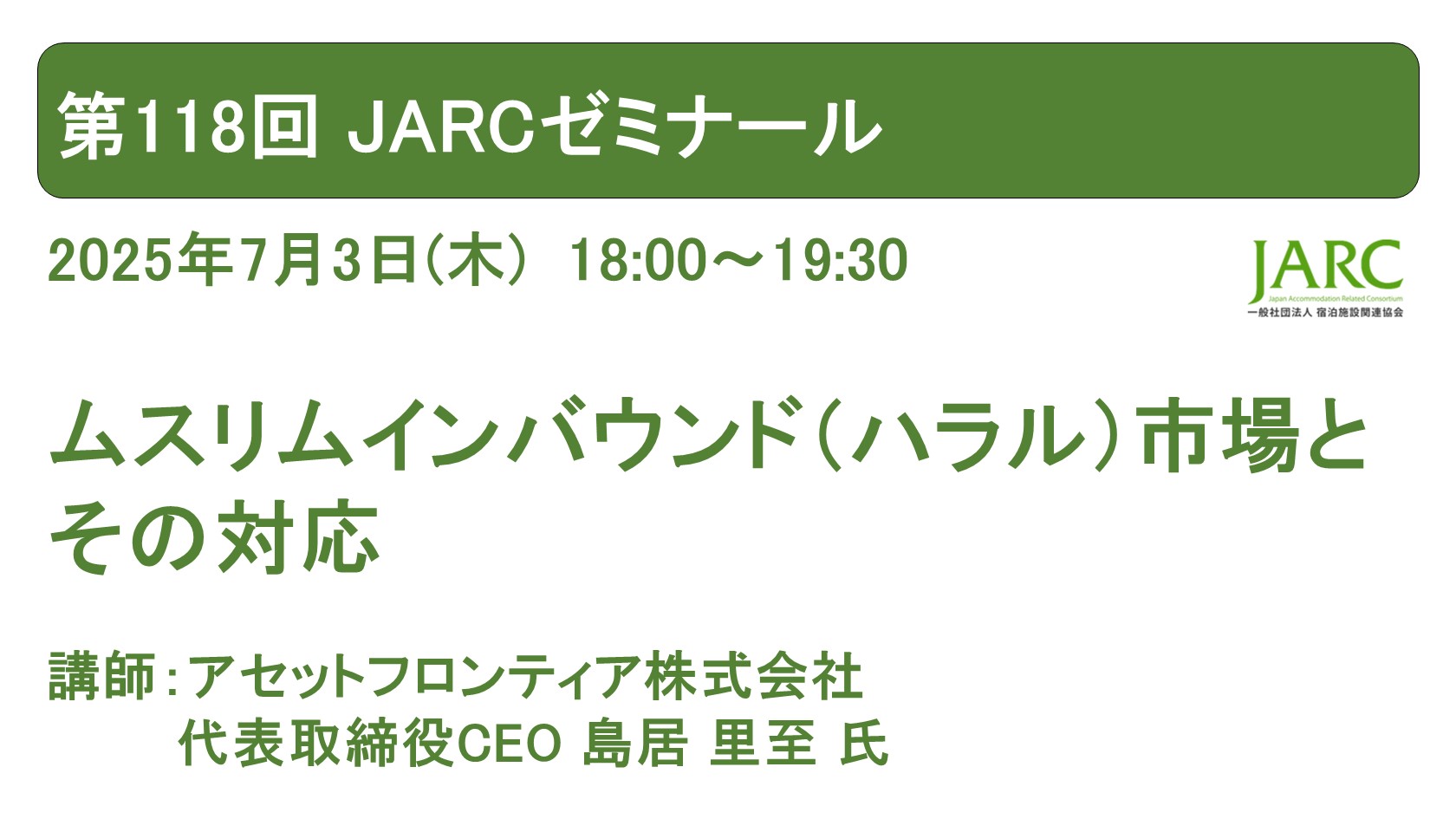北橋室長
温泉の保護と利用
地熱促進で保護指針改訂 温泉事業者の不安払拭へ
温泉行政を所管する環境省は、温泉資源の保護と地熱開発推進の同時達成のため「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」を改訂し、9月30日に発出した。また、利用に関しては、「新・湯治」などを通じた温泉地の活性化を推進している。温泉地保護利用推進室の北橋義明室長に取り組みを聞いた。
――ガイドラインを改訂した背景は。
「『温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)』は、都道府県が地熱開発に係る掘削の許可を判断する際の技術的な助言等のために作成している。政府の規制改革実施計画で地熱開発の促進に向けて温泉法の運用見直しが決まったことから、科学的な知見を踏まえて有識者会議で検討を行った。その結果、大規模な地熱開発では、一定の範囲内で個別の井戸掘削の離隔距離規制や本数制限を設けないことにするなど、規制の在り方を見直し、ガイドラインを改訂した」
――環境省は地熱発電施設数を現在の約60施設から倍増させる「地熱開発加速化プラン」を打ち出した。
「温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルを政府全体で進めており、環境省では『地熱開発加速化プラン』を発表した。地熱開発そのものに予算を投じることは環境省の担務ではないが、温泉法の運用見直しや、温泉への影響を監視する温泉モニタリングの普及などを通じて開発に対する温泉事業者の不安を払拭(ふっしょく)するなどの施策を進めていく」
――地熱開発には、温泉の減水や減温など影響を懸念する温泉事業者もいる。
「改訂したガイドラインでは地熱開発に際し、調査やシミュレーションなど科学的な推定に基づき、資源の持続可能な利用を前提とした『全体計画』を事業者に策定させることにした。全体計画には温泉への影響予測を含めることにしているほか、地熱貯留層と温泉帯水層との距離や位置関係の考え方を示すなど、既存の温泉に影響が及ばないよう求めている。科学的な知見や技術は進歩しているが、地下構造の把握に100%確実ということはないので、さまざまな調査段階で明らかになった最新の情報やデータを地域で共有し対応することが大事だ」
――地域での情報共有や合意形成には「協議会」の役割が重要とされている。
「ガイドラインでは、自治体や温泉事業者など幅広い関係者が参画する協議会をつくるよう求めているが、今回の改訂では『順応的管理』として、全体計画などの各段階における開発計画について協議会で意見交換することや、発電所の運転開始後も各種のデータを基に温泉への影響を協議会で評価することなど新たな管理の考え方を示した。温泉に悪影響が出た場合の対応方針や温泉事業者への補償についても、協議会の中で定めておくことが望ましいと盛り込んだ」
――政府の規制改革実施計画やエネルギー基本計画には、温泉資源、地熱資源の適切な管理に関する新たな制度を検討することが記載されているが。
「環境省としては、今回のガイドライン改訂や、来年4月施行の改正温対法(地球温暖化対策推進法)に基づく再生可能エネルギー促進区域の新設などもあるので、当面はそれらをしっかりと運用していく。資源管理の新たな制度をつくる必要があるかどうかは引き続き動きを見ていくが、今すぐに新法の検討を進めるというわけではない」
――環境省は大規模な地熱発電とは別に、地域における温泉熱の利活用を推進している。
「地域固有の資源をいかに活用するかを地域が主体的に決めていく必要がある。温泉熱はいろいろな使い方ができ、すでに多くの温泉地や温泉事業者が、それぞれにバイナリー発電や熱交換器、ヒートポンプなどを導入している。温水の供給、農産物の生産など、地域の産業振興にも生かされている。浴用などの温泉に影響が出ないことを前提にしながら地域共生型の利活用を支援していく」
――「新・湯治」による温泉地の活性化策は。
「現代のライフスタイルに合った温泉地での過ごし方を提案する事業で、その推進には『チーム新・湯治』として356の自治体、団体、企業などが参加している。この中で温泉地に滞在することのリフレッシュ効果を把握する調査も実施している。入浴だけでなく、温泉地で楽しむ食やアクティビティを含めた効果を探っているので、その成果を温泉地のPRに生かしたい。国民保養温泉地についても、歴史のある制度なので意義を見直してさらなる活用を考えたい。厚生労働省の所管だが、温泉利用と運動に適した施設を『温泉利用型健康増進施設』として認定し、要件を満たすと医療費控除の対象になる制度がある。これと国民保養温泉地を連携させることなども検討している」

北橋 義明氏(きたはし・よしあき)北海道大学院農学修士修了。1998年、環境庁(現・環境省)入庁。国立公園管理や野生生物保護などの担当部署を経て、今年7月から現職。大阪府出身。48歳。
【聞き手・向野悟】