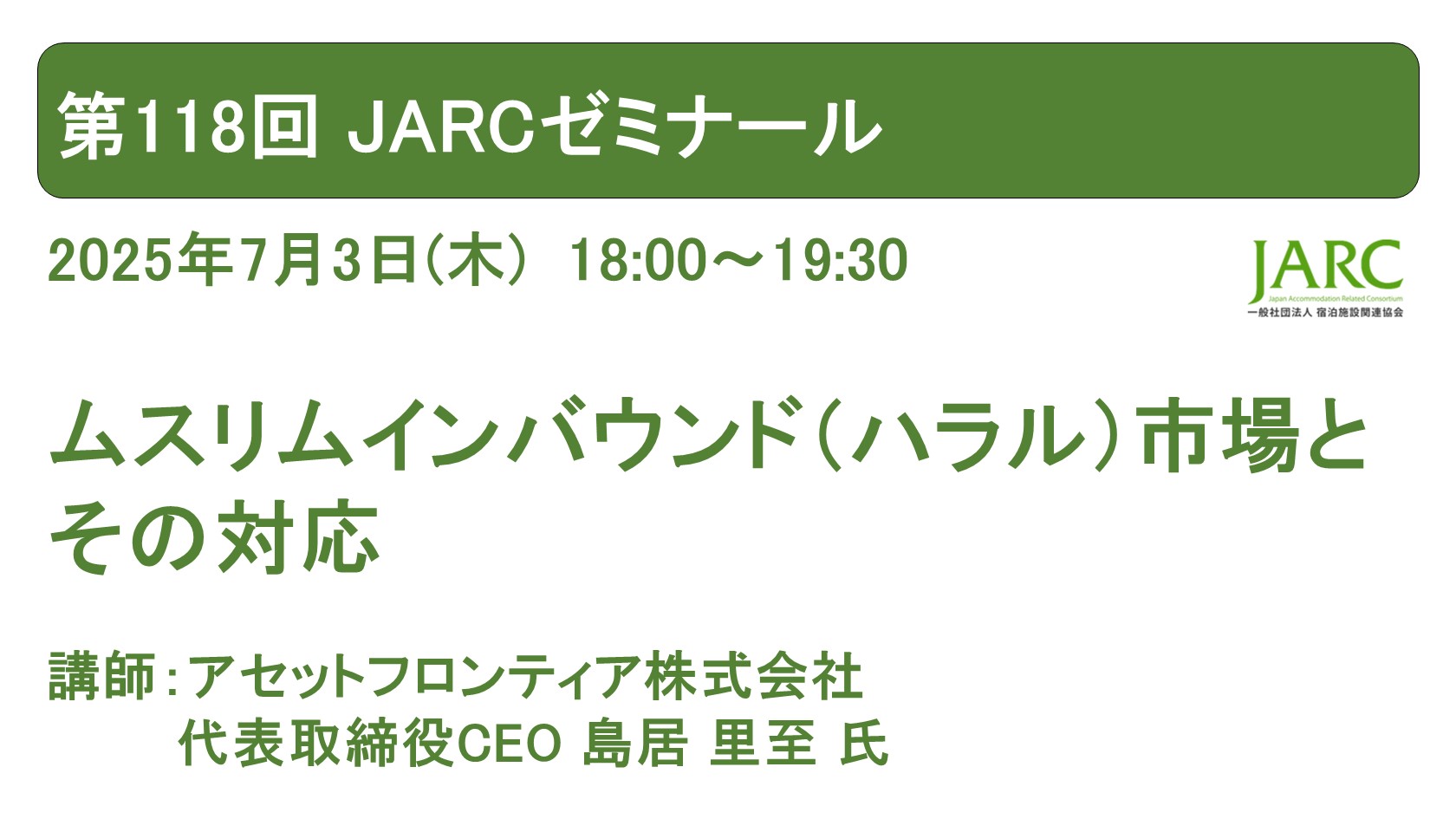足利学校を見学する学生ら
日本学生観光連盟は5、6の両日、群馬、栃木両県にまたがる両毛地域でフィールドワークを実施し、「食」を通じた同地域の活性化策を話し合った。
フィールドワークは、学観連設立の2009年度から毎年1回行われている。6回目となる今回は、11大学から34人の学生が参加。東武鉄道と地域内7市、6商工会議所で組織する「同地域両毛地域東武鉄道沿線活性化協議会」が協力した。
テーマとした「フードツーリズム」はニューツーリズムの一分野。最近では和食やB級グルメ、“デパ地下”の人気が高まり、これらを取り込んだ地域振興に注目が集まっている。
学観連は、今回のフィールドワークのタイトルを「フード×風土」として、同地域の食を取り巻く歴史や地域性などを絡めて学ぶことにした。
具体的には、和食を生かした地域活性化、東武線を利用した同地域への誘客の可能性を検討。ほとんどの学生が同地域を初めて訪れる中、初日は、日清製粉ミュージアム(群馬県館林市)や桐生織物記念館(同桐生市)など同地域の産業や伝統文化を観光資源として生かした施設を視察した。
2日目は跡見学園女子大学(東京都文京区)に会場を移し、フィールドワークを基にした意見交換会が行われた。学生からは「遠方からの観光客を迎え入れる宿泊環境が少ないため、宿泊手形を作成し充実化を図る」「両毛地域オリジナルの粉ものを作る」「両毛地域の学生と連携し、若者目線のニーズを取り入れる」などの意見が出された。
これらの意見は今後、学観連内部でまとめ、同協議会に「両毛地域活性化案」として提言する。

足利学校を見学する学生ら