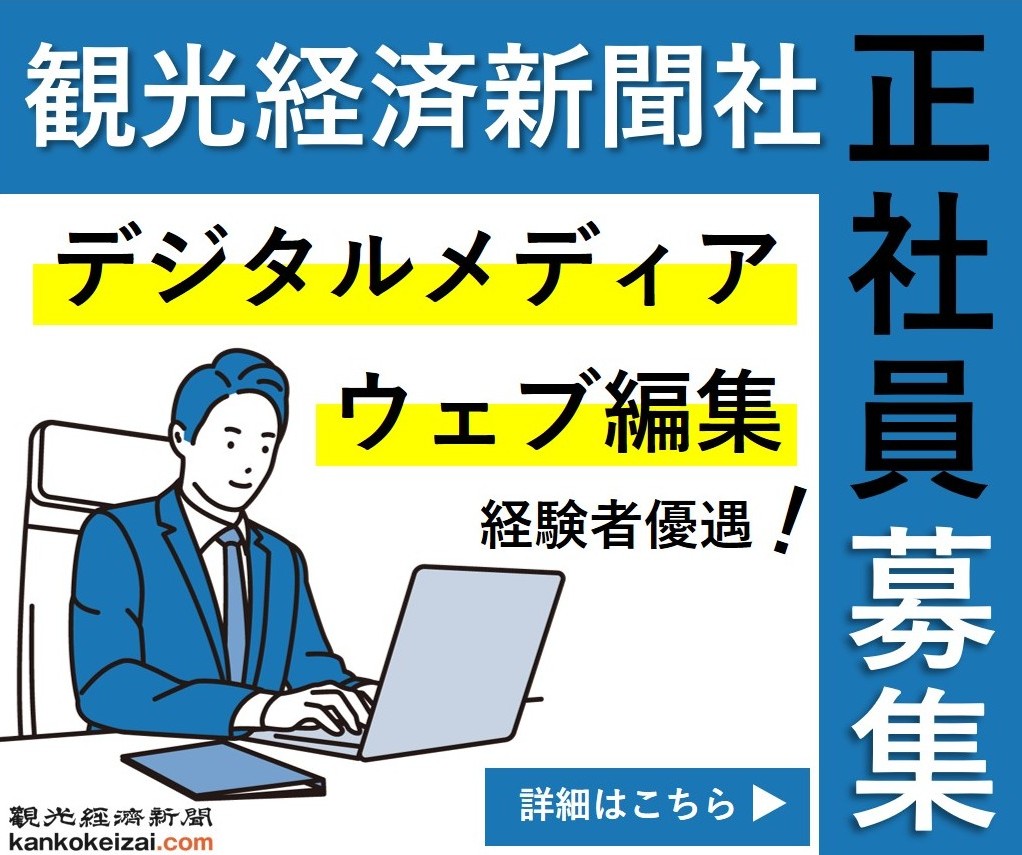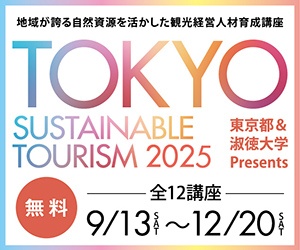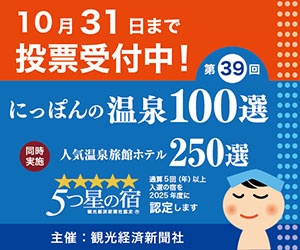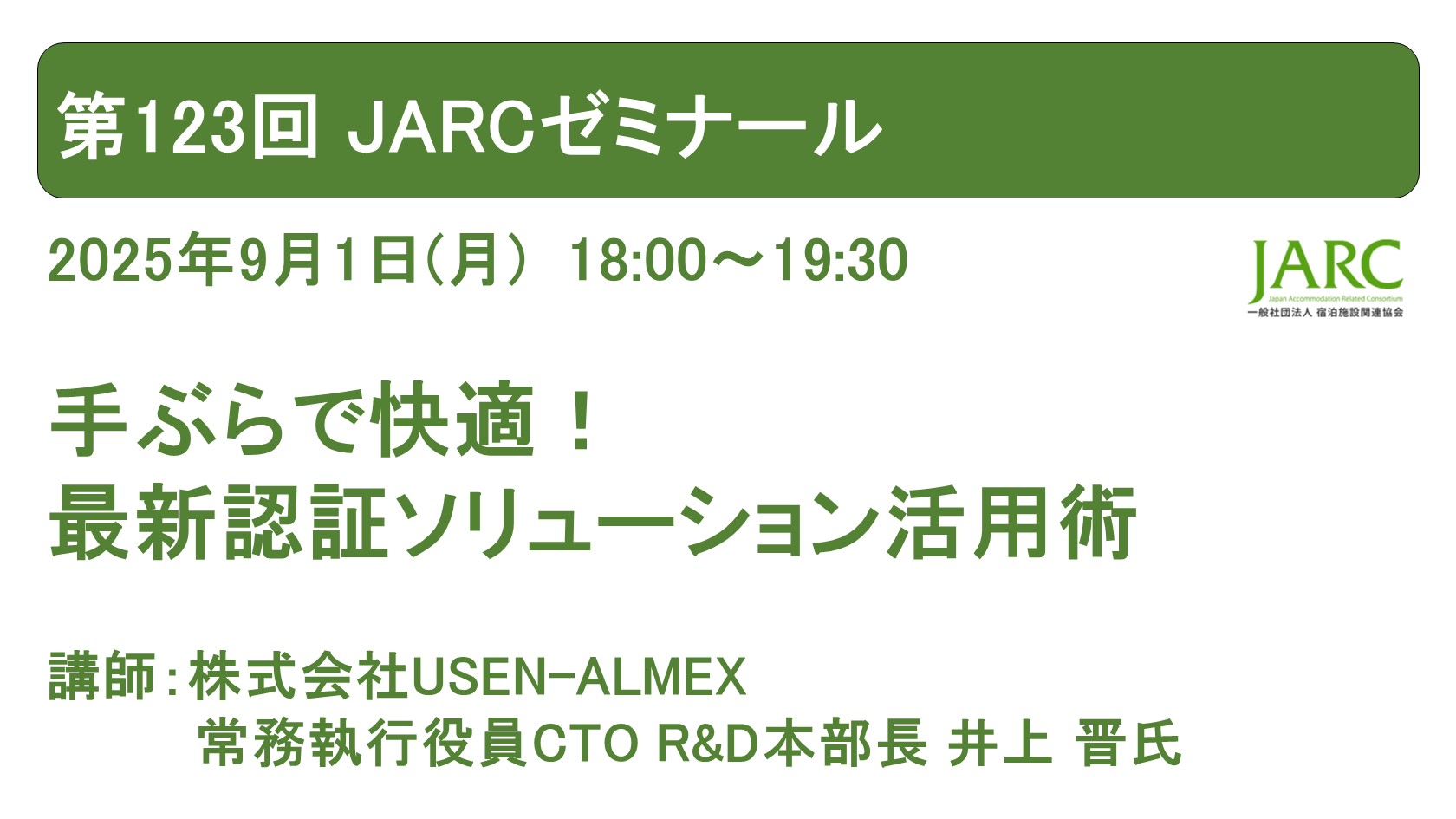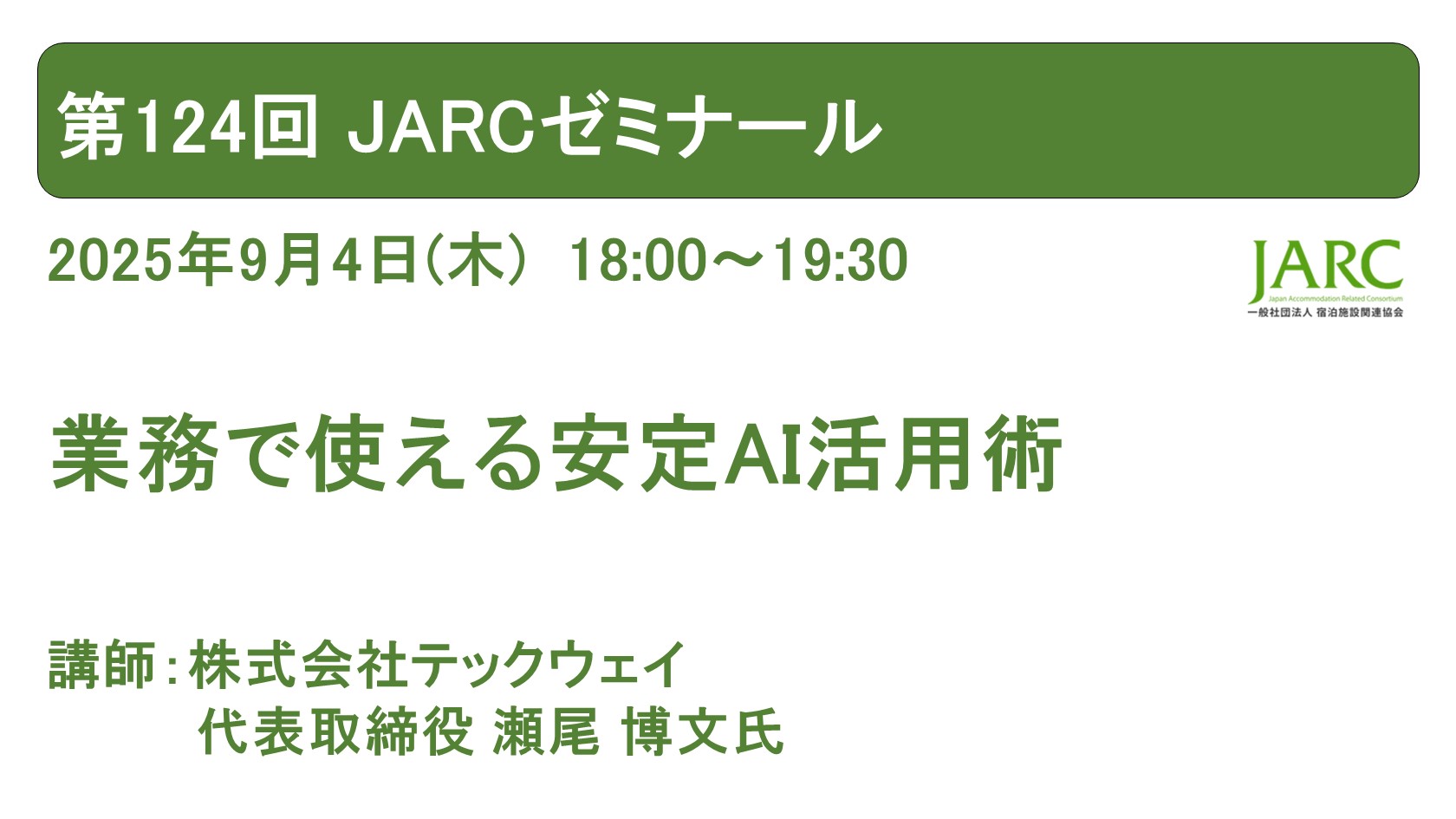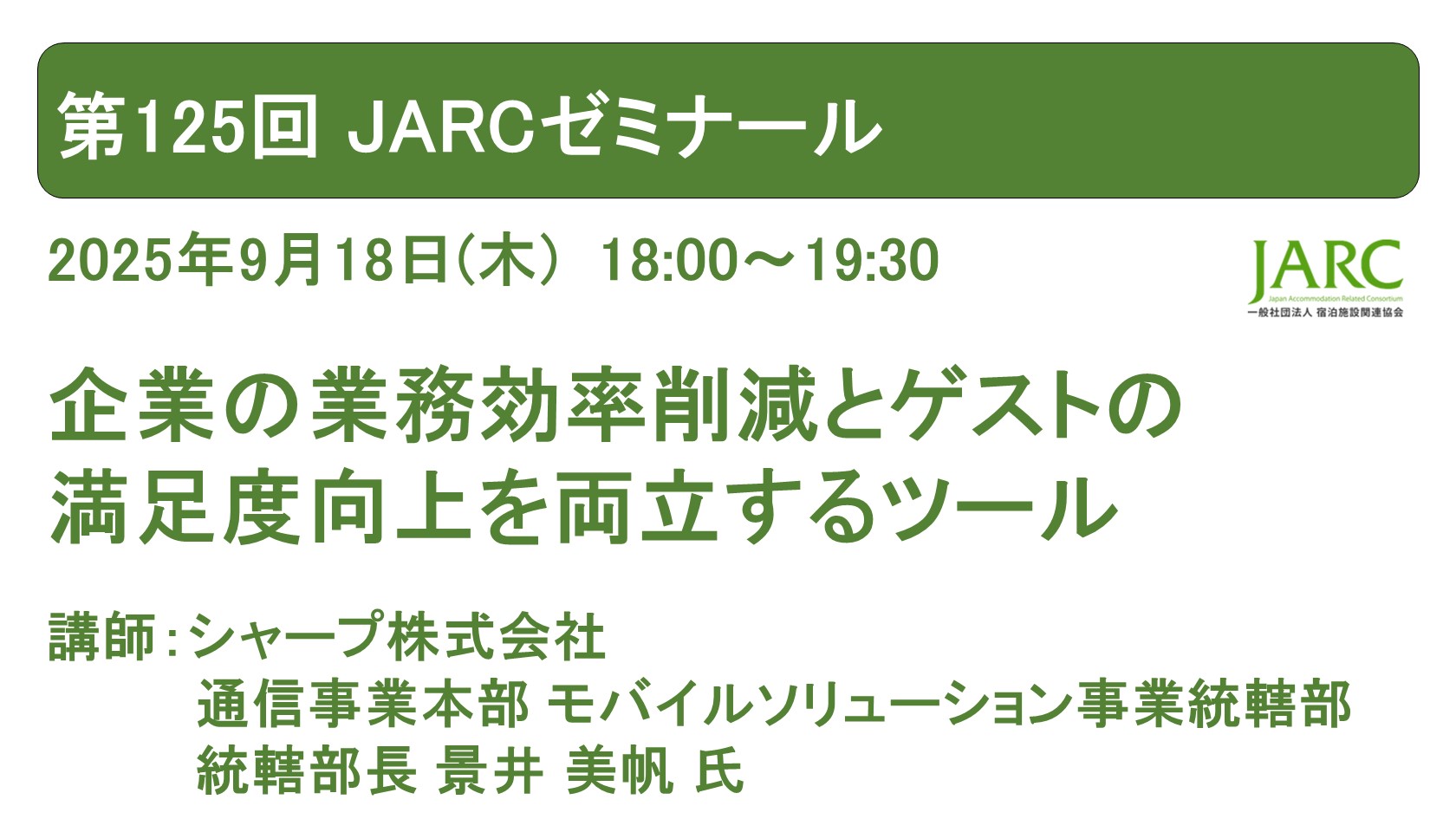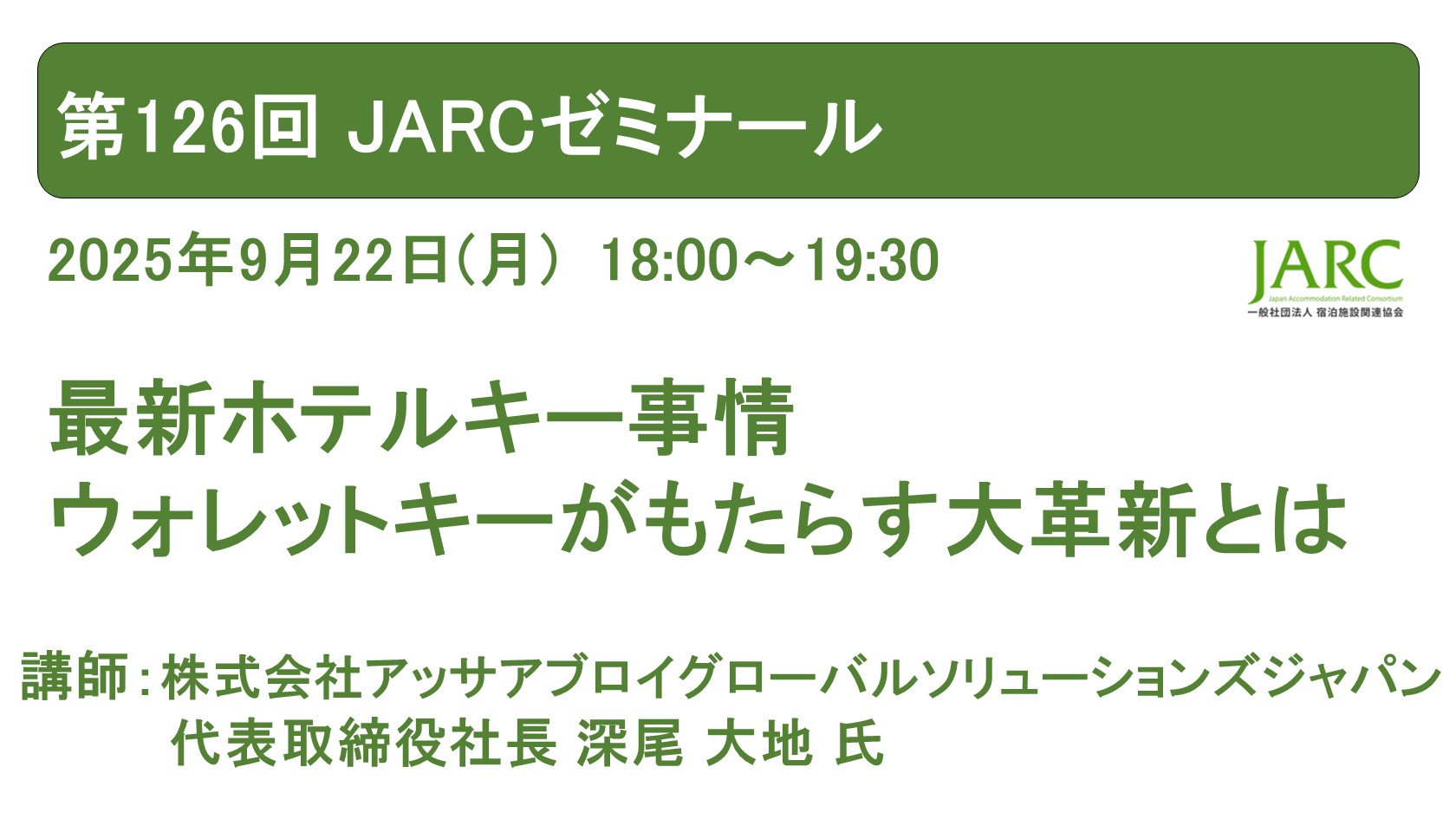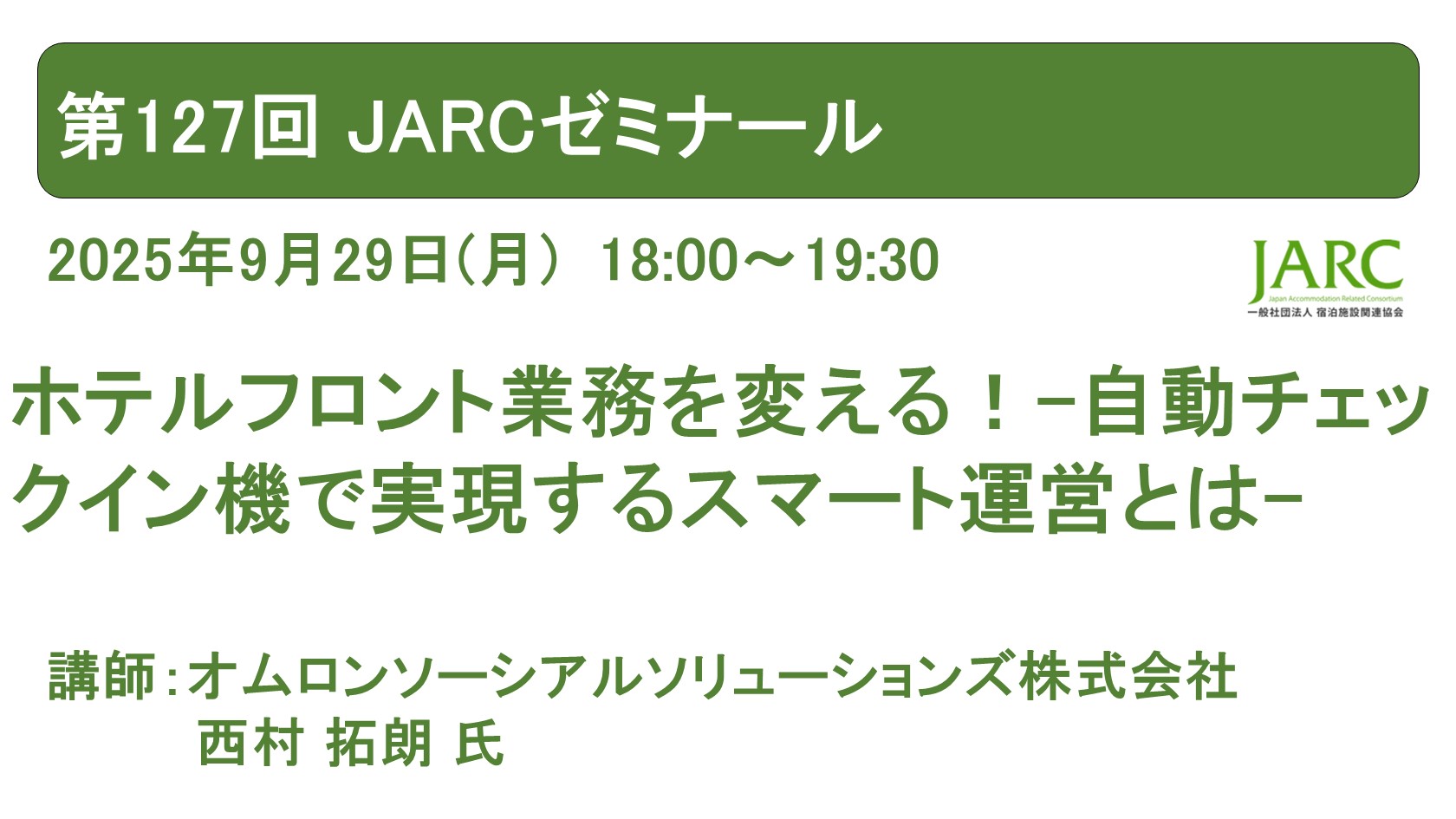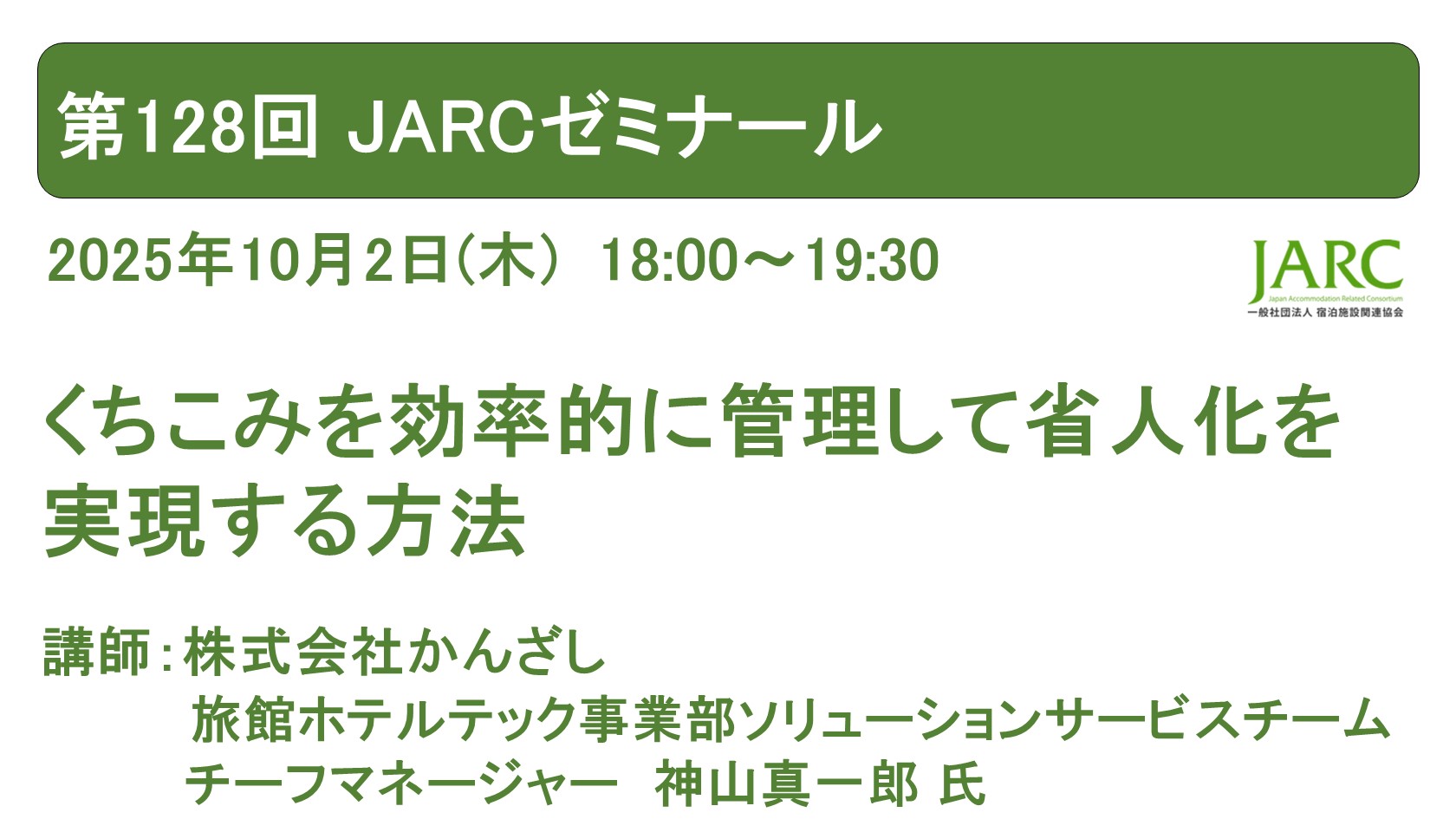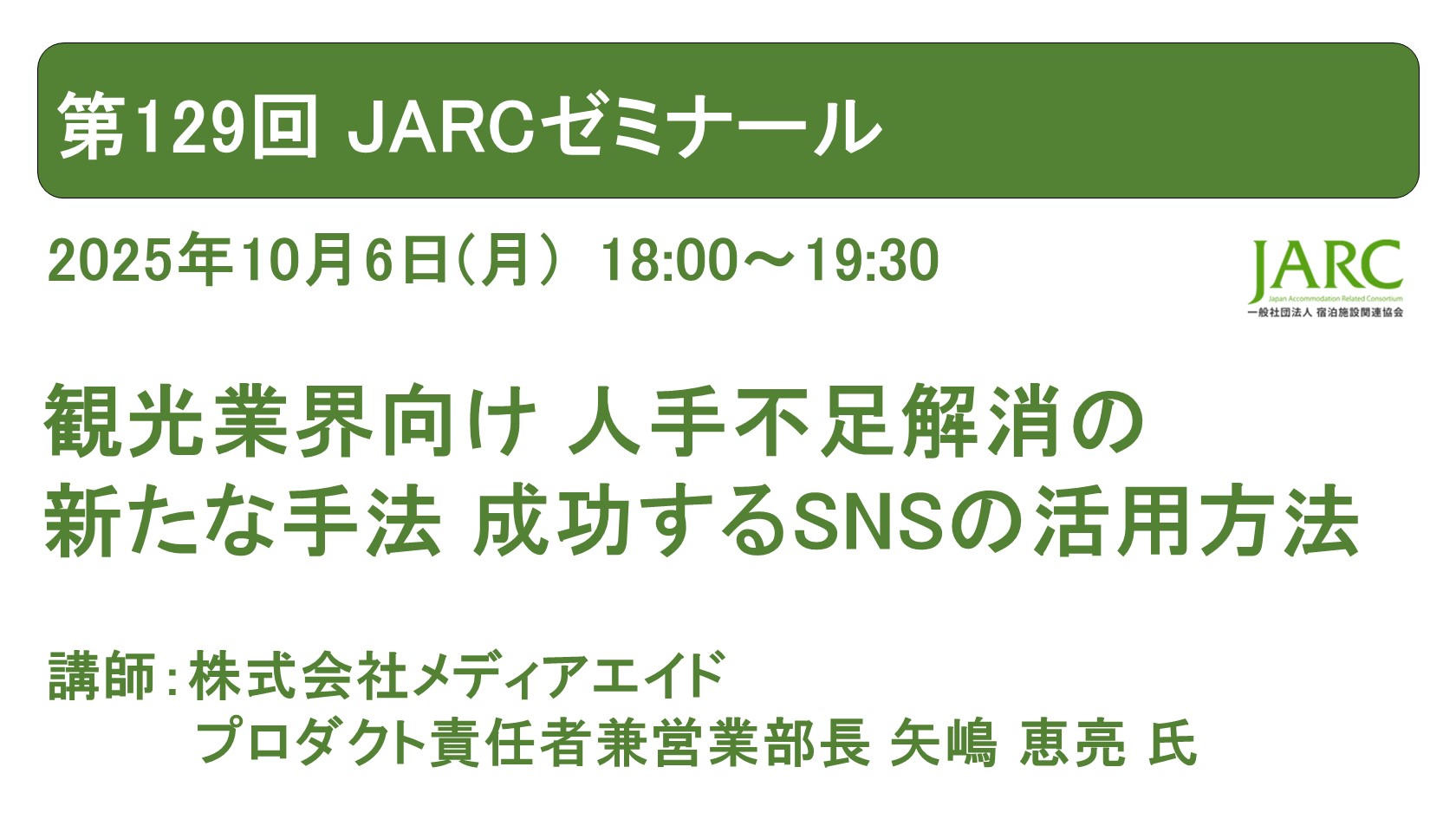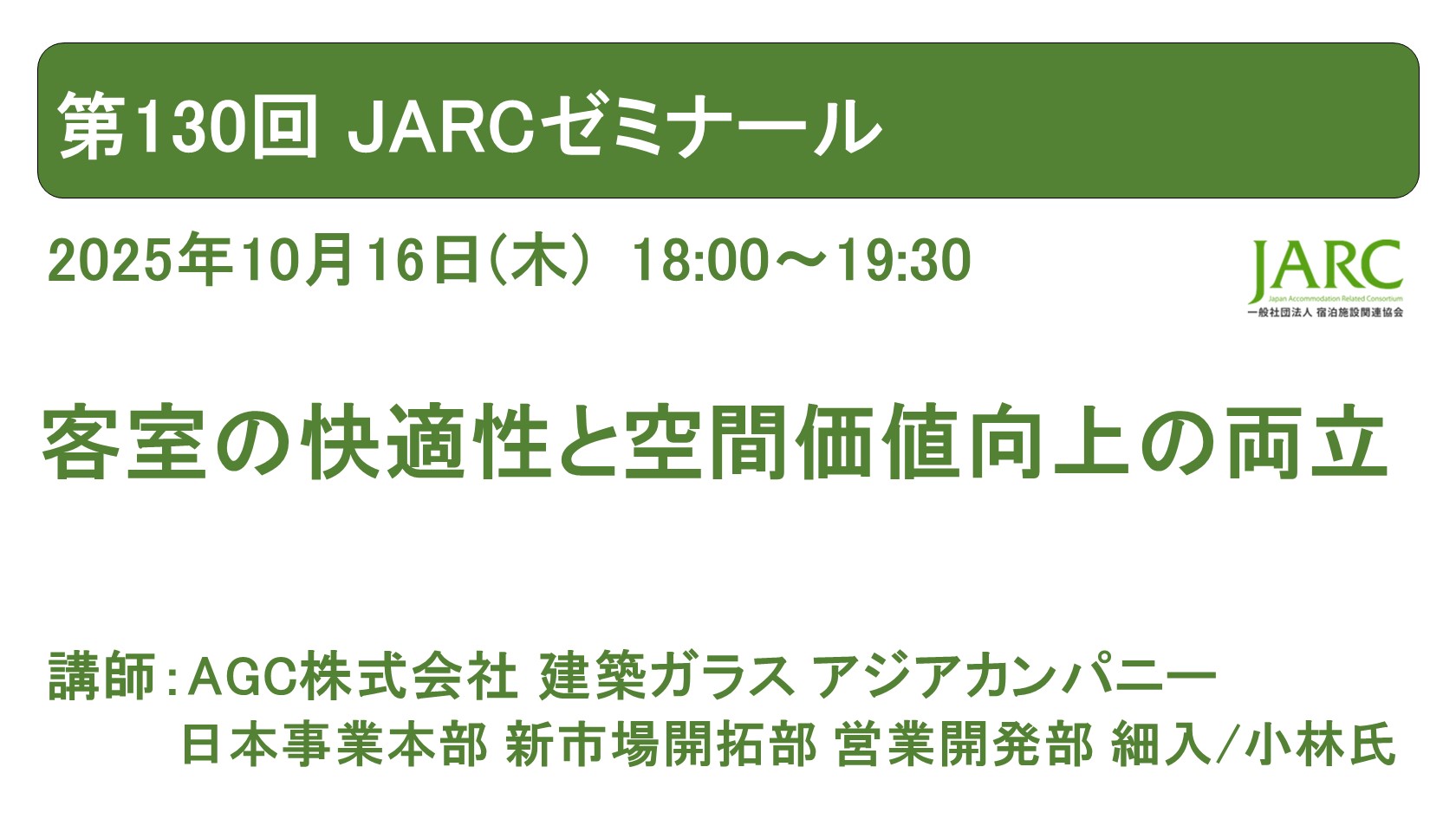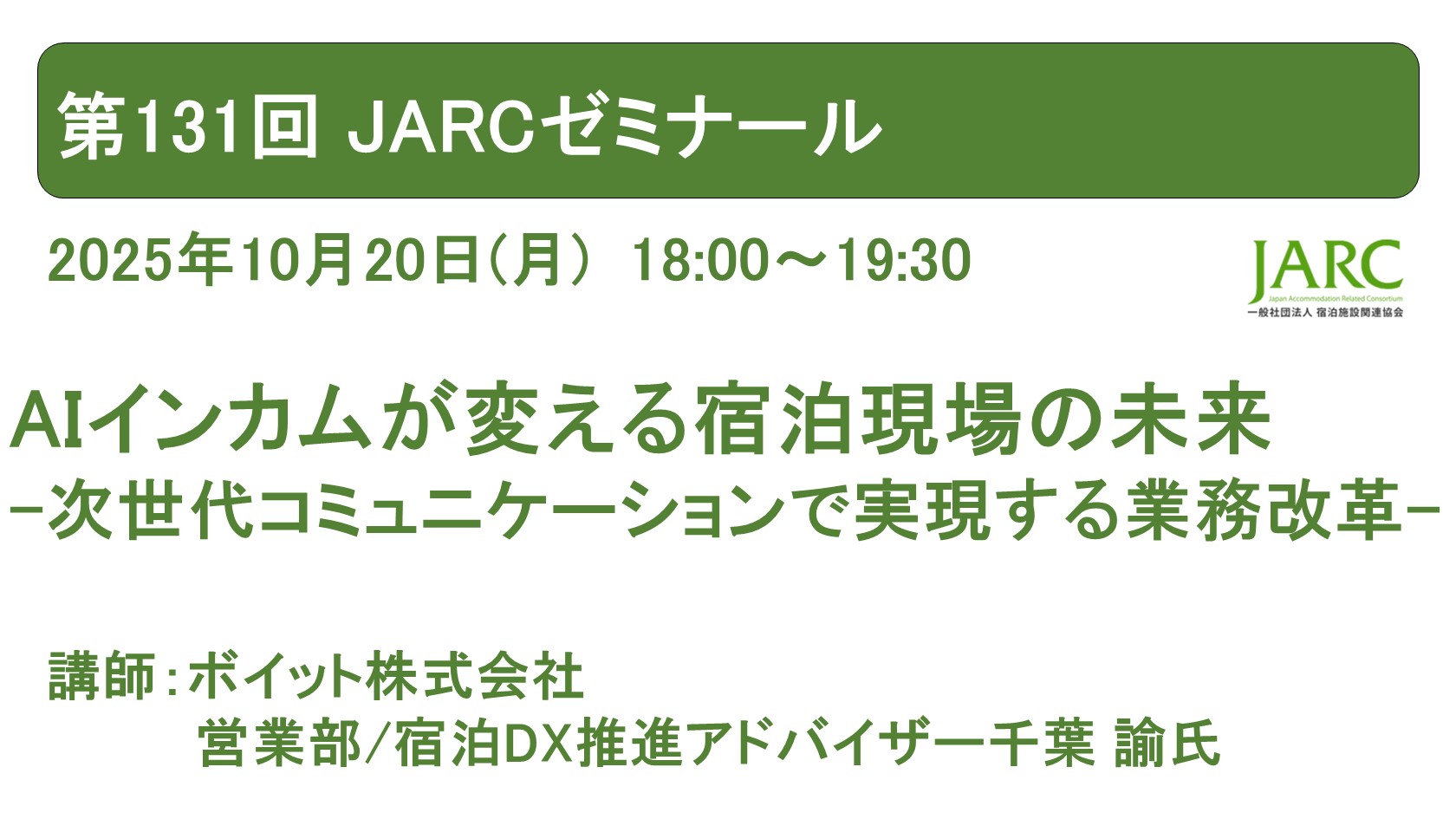政府の観光立国推進本部(本部長=前原誠司国土交通相)が設置している休暇分散化の作業部会は、ゴールデンウイーク(GW)と秋の大型連休を全国5ブロックごとに分散させる具体案を示した。企業の有給休暇取得と学校休業の分散化を組み合わせる方式ではなく、一部の「国民の祝日」のあり方を見直し、地域ごとに休日を割り振る方式だ。この具体案に対し観光業界からは、需要拡大への期待の一方で、効果予測や地域への影響などを踏まえた慎重な制度設計を求める声も挙がっている。具体案の提示で幅広い関心が高まる中、休暇改革の機運を生かす議論が求められている。
■内需の拡大
休暇の分散化は、旅行のピーク需要の分散により観光地や宿泊施設、交通機関の混雑緩和につながり、オンシーズンの旅行費用を低下させるなど、旅行意欲を刺激する効果が期待される。国内観光の振興が地域経済の活性化や雇用の創出をもたらすことから、“財政出動なき内需拡大策”とも言われる。
観光産業にとっては、ピーク期の定員オーバーなどで吸収できなかった需要を分散化で獲得できれば、旅行商品の販売拡大や宿泊施設の客室稼働率の向上につながる。半面、時期の集中に依存した経営は立ち行かなくなり、事業者、観光地の“優勝劣敗”が明確になる可能性もある。
分散化の具体案の提示に先立つ、12月の作業部会では、星野リゾート社長の星野佳路氏が「休暇の分散化で埋蔵する内需を顕在化させるべき」「旅行者の満足度を高めても、高めなくても、休日は客で埋まるという競争環境の甘さが観光産業の国際競争力を低下させている」と意見を述べた。
■具体案への反応
作業部会が提示した具体案に対しては、休暇改革を推進したい観光業界からも慎重な議論を求める声もある。
観光18団体でつくる観光関係団体会長連絡会議(議長=舩山龍二・日本ツーリズム産業団体連合会<TIJ>会長)は昨年12月、「観光立国実現に向けた提言」と題した文書を国交省の辻元清美副大臣、藤本祐司大臣政務官に提出。休暇改革については、祝日の分散化ではなく、年次有給休暇の完全取得と連続休暇取得の法制化、学校休業の多様化などへの施策を要望していた。
作業部会の具体案に関してTIJは、「祝日に焦点が当てられたもので、連絡会議が提言した休暇取得の促進ではない点が残念。祝日3連休化(ハッピーマンデー)の効果などを検証した上で議論した方がいいのでは。観光振興のための案だけに反対しづらいが、慎重な取り扱いが必要だ」としている。
国際観光旅館連盟の佐藤義正会長は、個人的見解とした上で、「地域への影響を十分に考える必要がある。例えば、北東北のGWは八幡平や八甲田の雪の回廊、麓には桜という絶好の観光シーズン。首都圏の休暇時期が外れると影響は大きい。地域によって出るプラス、マイナスをどう考えるか」。秋の大型連休についても「国内観光の振興にとって各月の3連休をなくして大型連休にするのがプラスなのか、検証する必要がある」と指摘した。
日本観光旅館連盟の近兼孝休会長も「他の会員からも意見を聞き、考えをまとめたい」と断った上で、「地域、業種業態によって賛否両論あるだろうが、個人的にもいくつかの問題点は思い浮かぶ」と述べた。
■休暇改革の好機
観光分野だけでなく、生活、経済に与える影響は、プラス、マイナスを含めて計り知れない部分がある。3日の会合で作業部会座長の辻元副大臣は、「1つひとつ問題をクリアし、コンセンサスを得ながら進めることが大事だ」と述べた。半面、休暇改革を実現するには、「最終的には慎重かつ大胆な決断と実行が必要になる」(溝畑宏観光庁長官、2月定例会見で)という側面も否定できない。
観光産業や地域にとっては、不安材料をそのままにしておけないが、休暇改革の好機を逃すことも大きな損失だろう。休暇改革には「ワーク・ライフ・バランス」(仕事と生活の調和)という視点も欠かせず、観光を通じた休暇の過ごし方が、旅行消費や雇用の効果以外にも、業務の能率アップなどの生産性向上、国民の心身の健康増進などにつながるとアピールしていく必要もある。国を挙げた議論が活発になる中、観光業界や地域がどのように休暇改革の議論に向き合うのか、重要な場面だ。