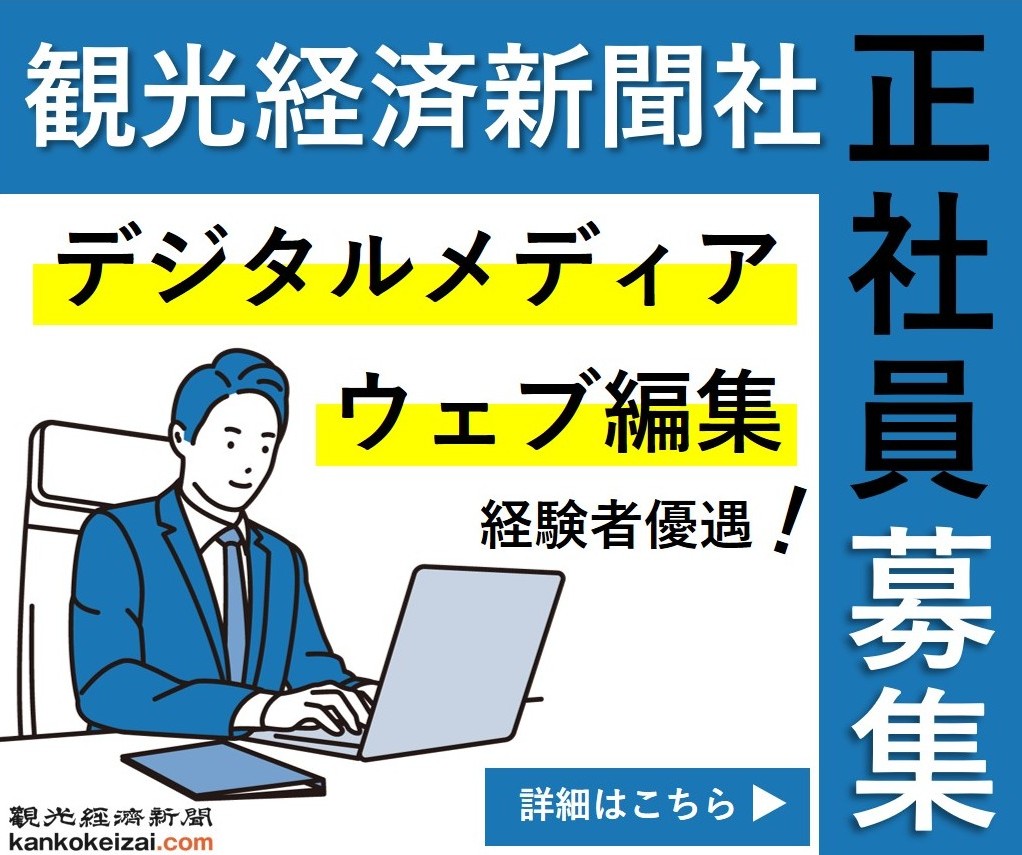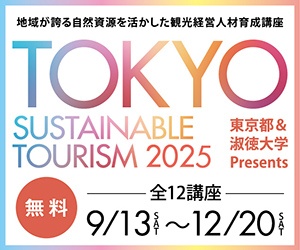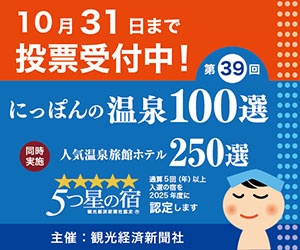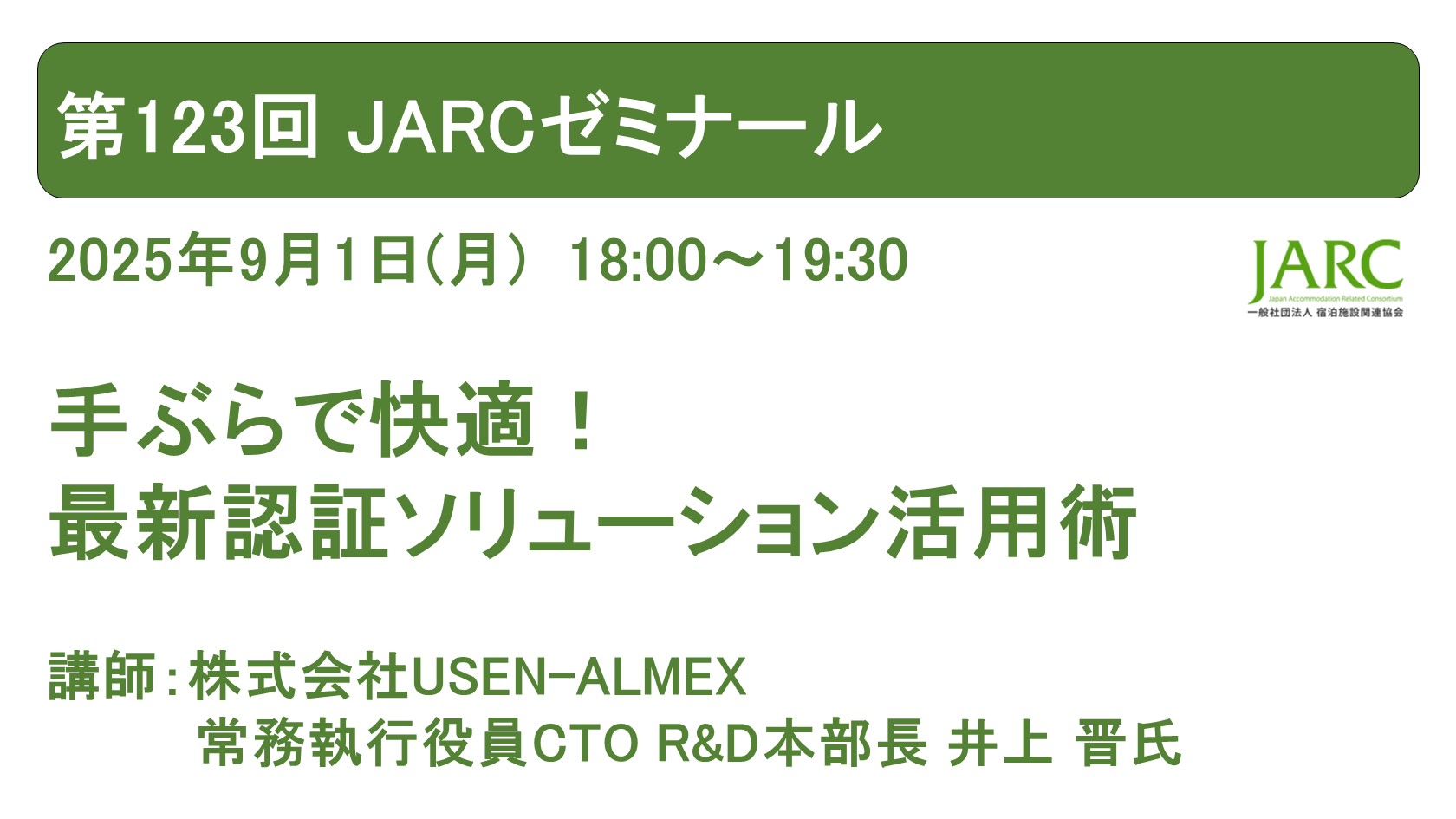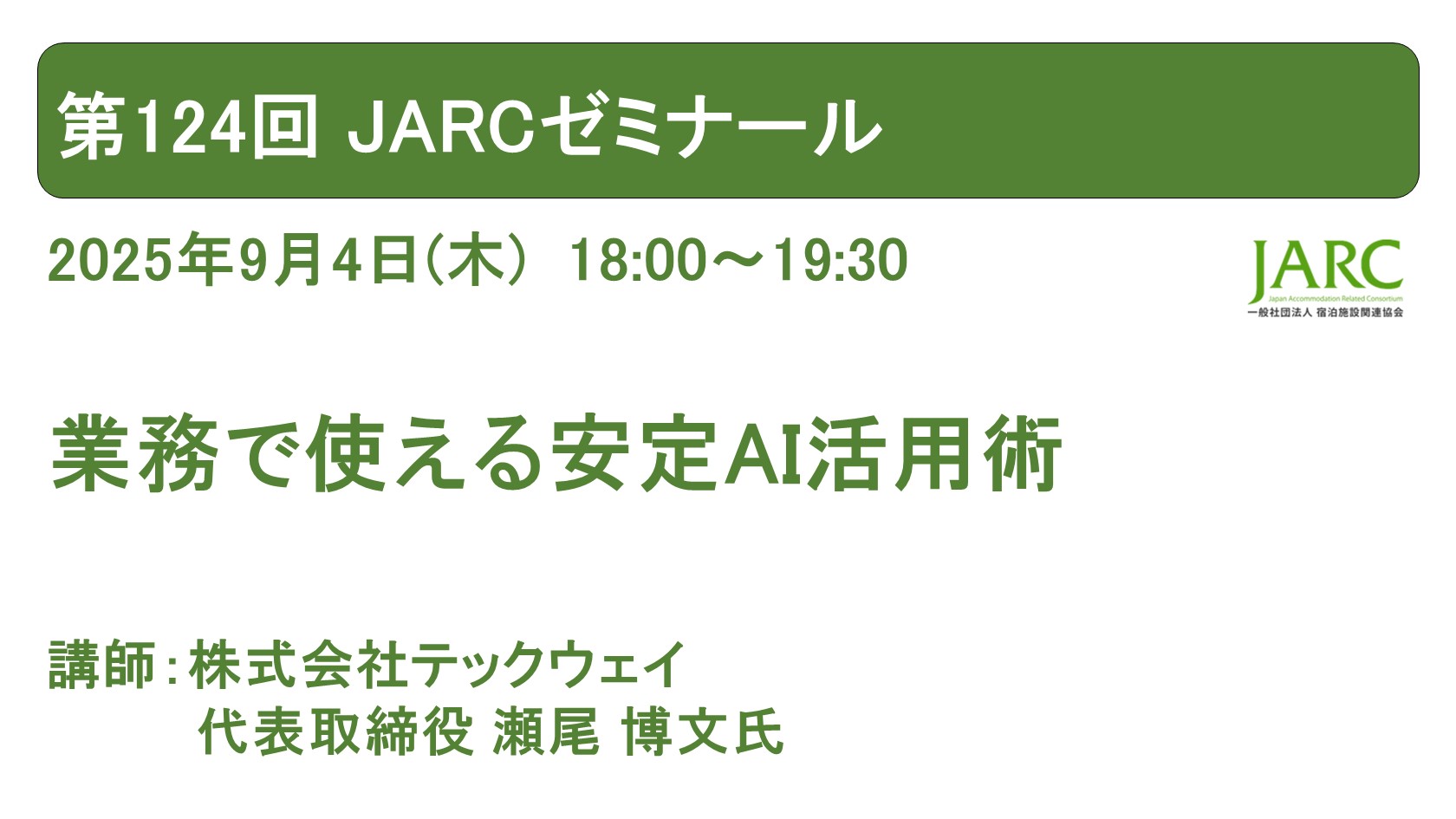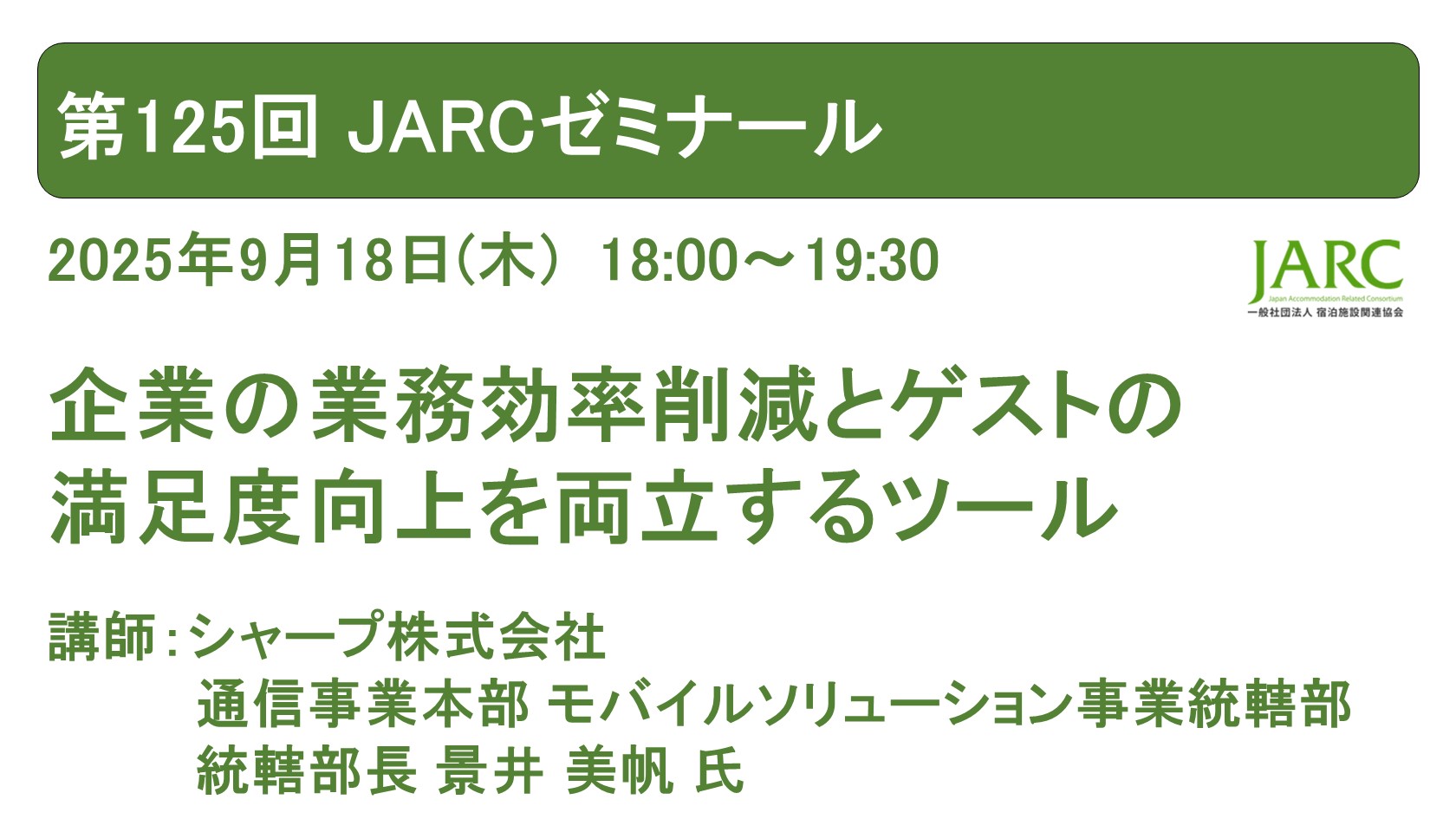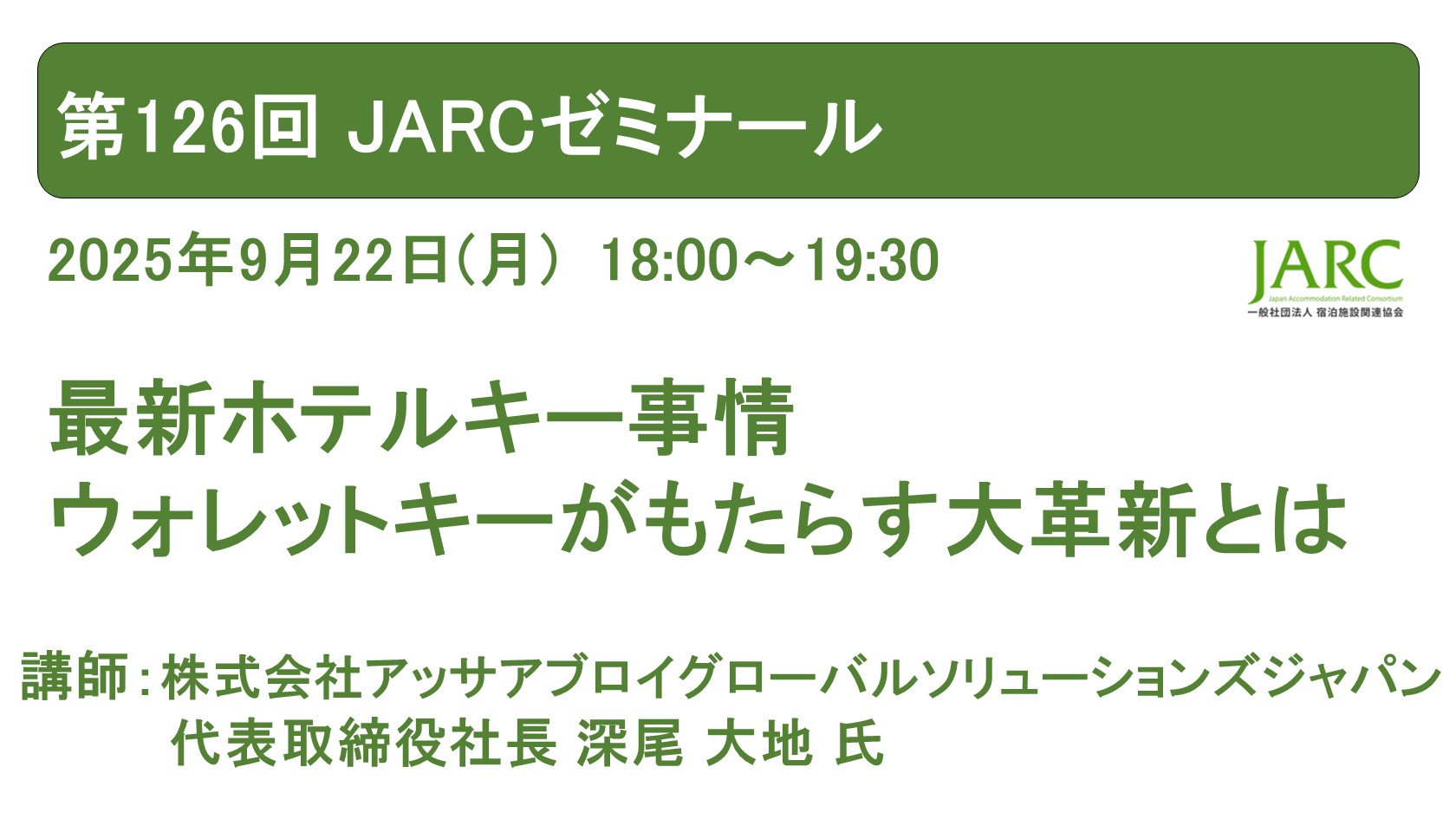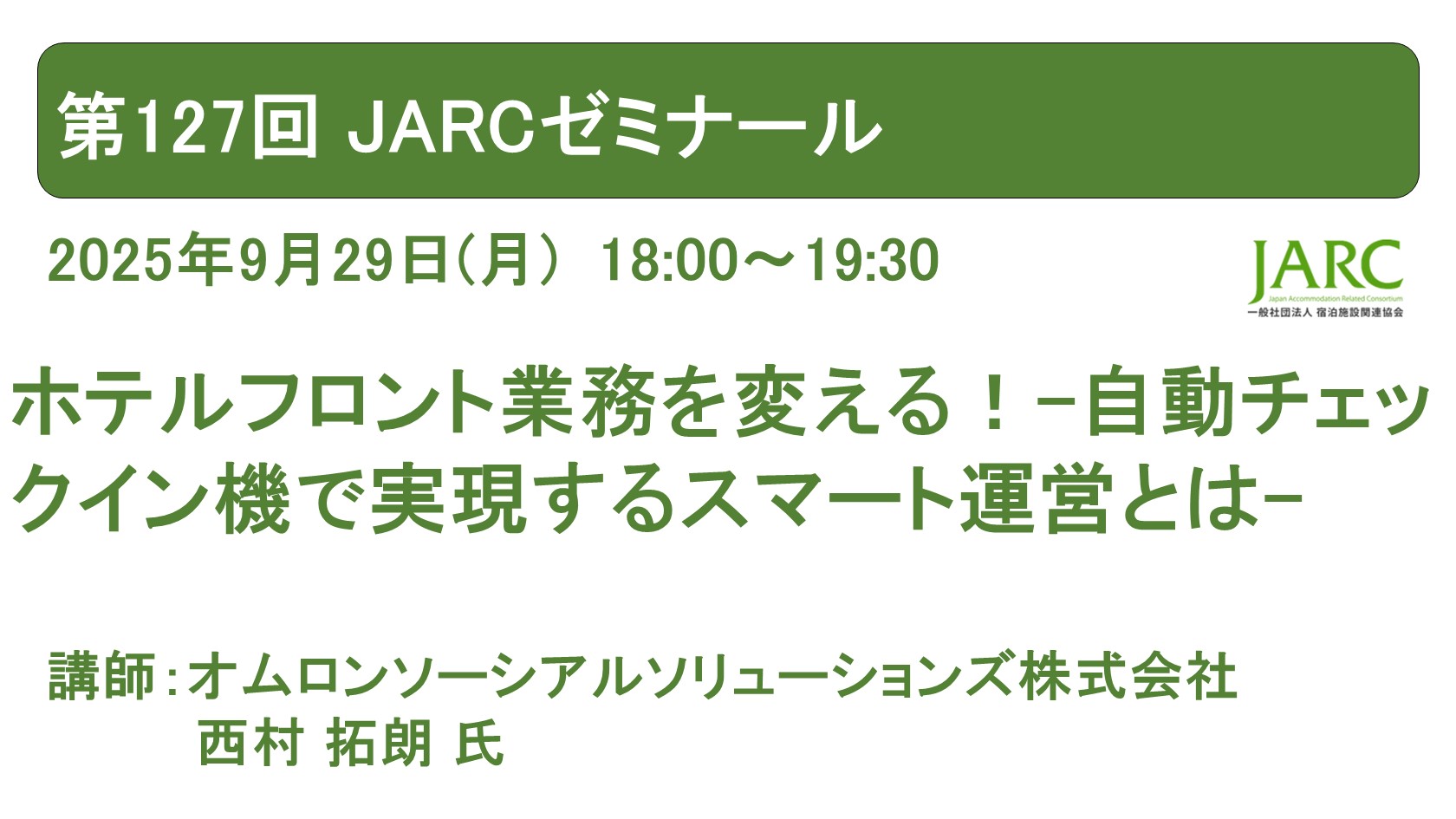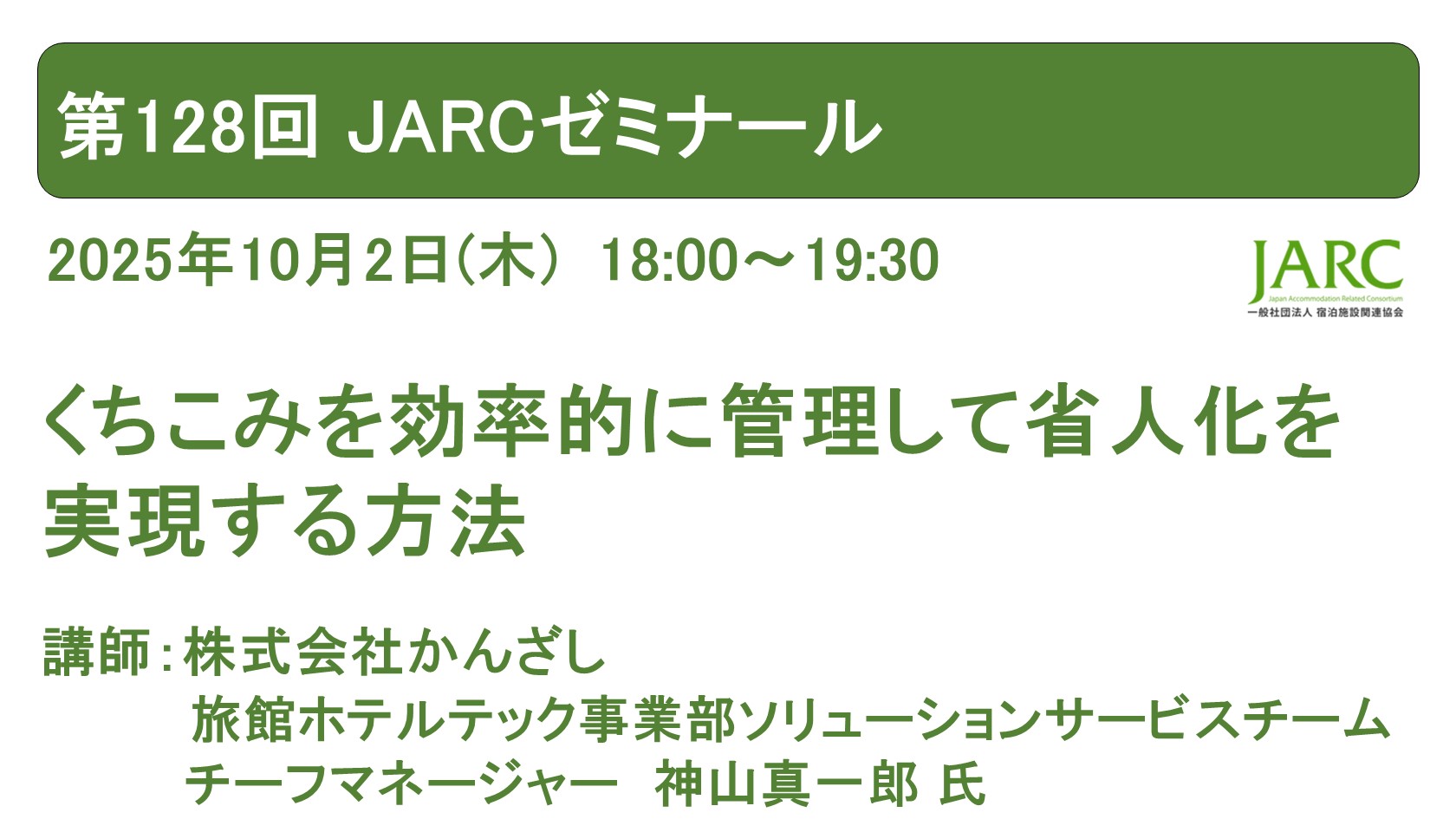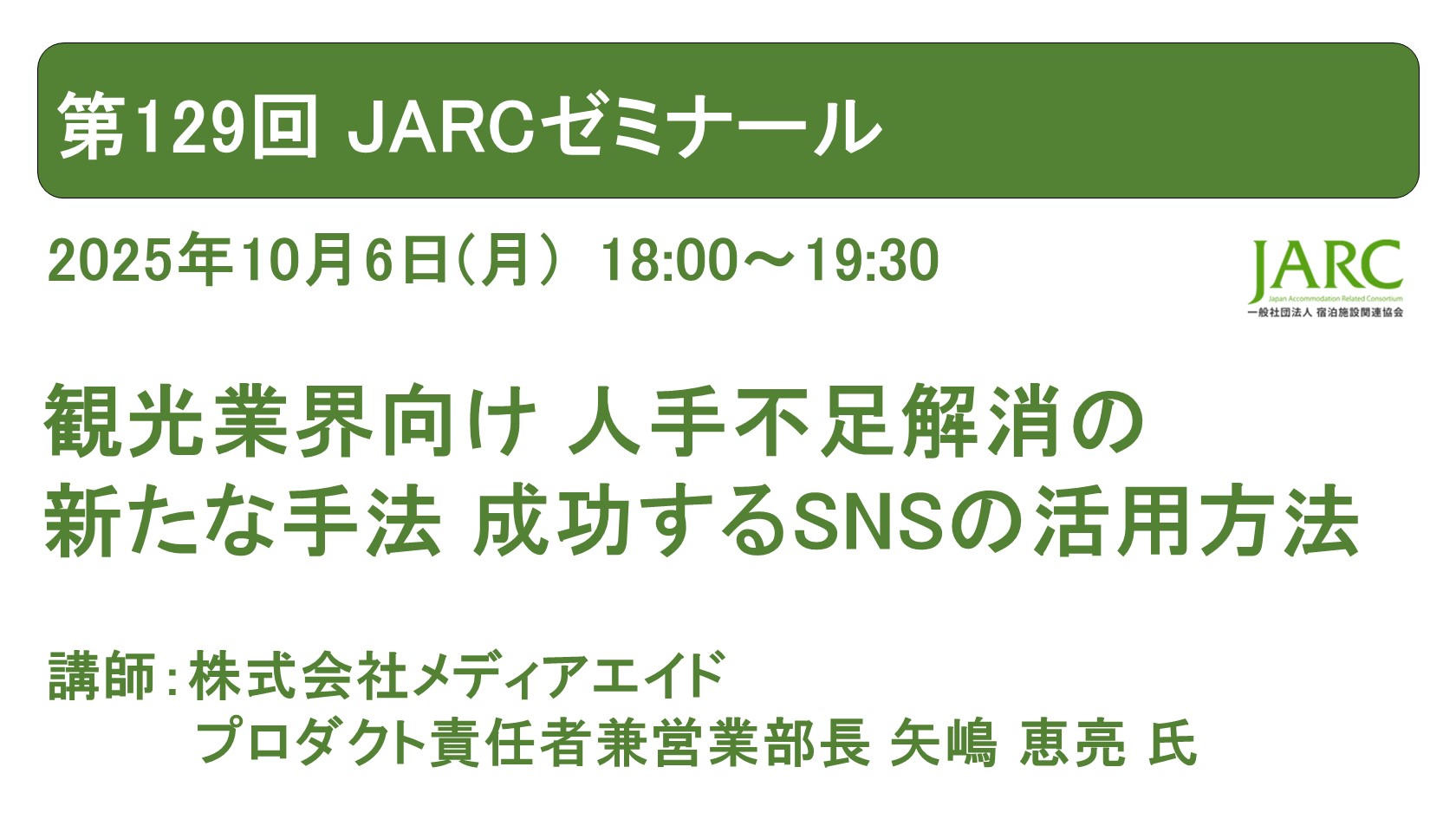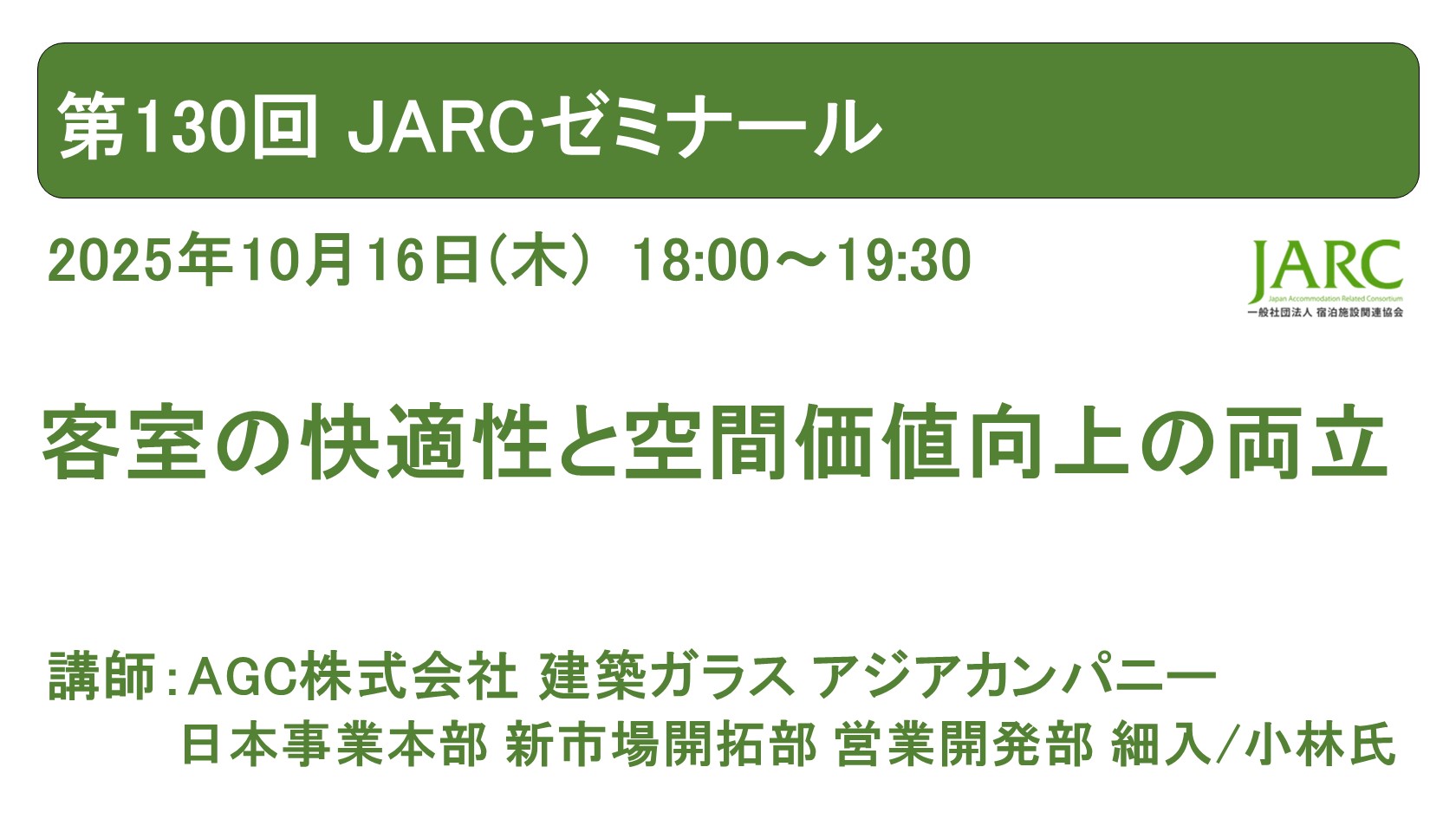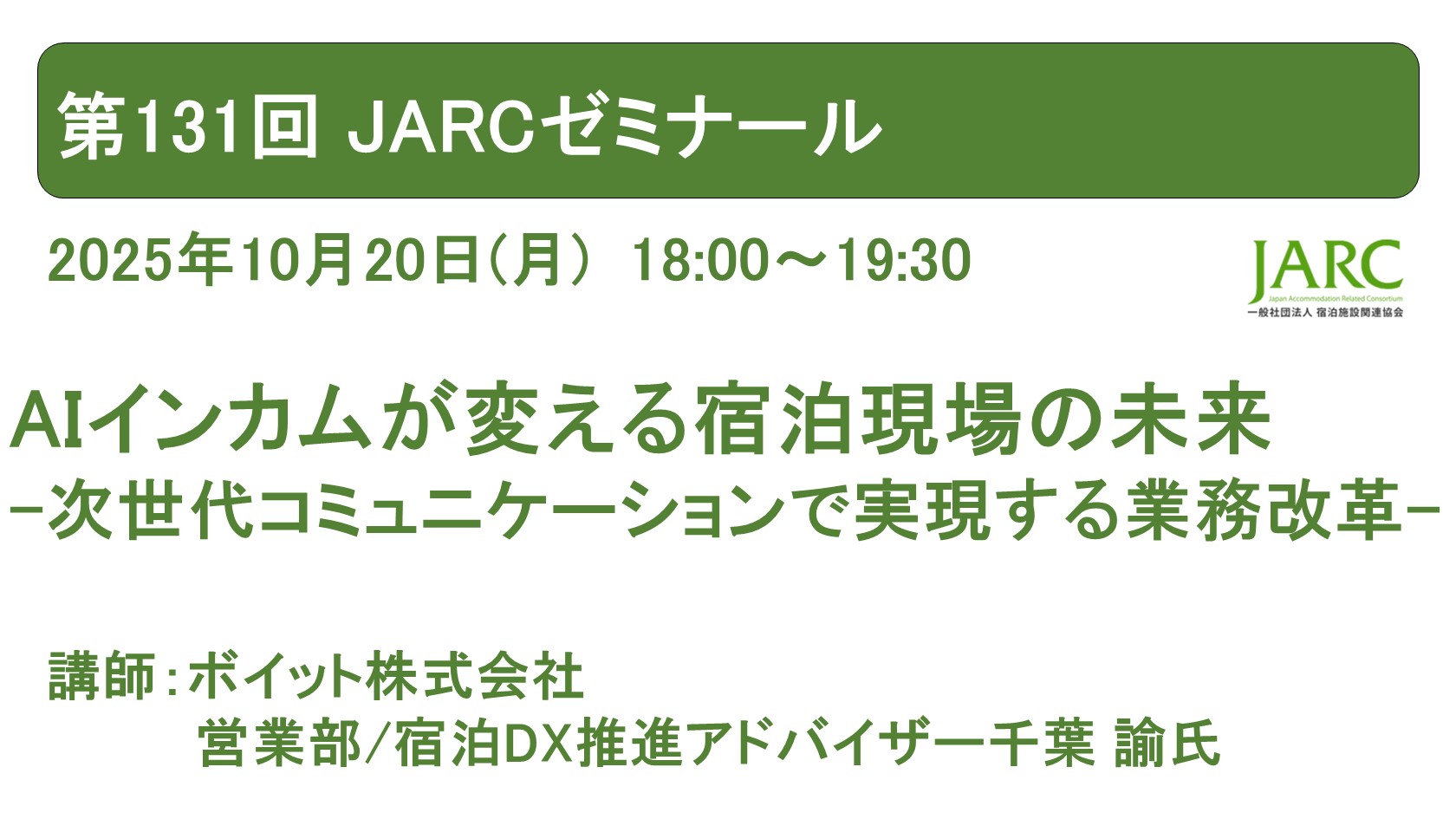おてつたびCEO 永岡里菜氏
手伝い通して思いや魅力共有 地域と宿のファン拡大に貢献
――事業内容は。
「地方に興味がある人や旅費を抑えていろいろな地域へ旅してみたい人と、繁閑期の差が激しい旅館・ホテルや収穫時期などに人手が欲しい農家などとをマッチングするウェブプラットフォーム『おてつたび』の運営を主に行っている。『お手伝い』と『旅』を掛け合わせることで、『どこ、そこ?』という地域にも人が訪れるきっかけを作り、その地域を好きになって帰ってもらうのがミッションだ」
「参加者である『おてつびと』は、事業者が提示するお手伝い内容、報酬、期間などを参考におてつたびに申し込み、事業者が承認すると参加できる。事業者は登録、掲載無料で、マッチングできた場合に手数料を当社に支払う」
――おてつびと登録者と登録事業者について、人数や件数、内訳はどのようになっているか。
「現在おてつびとの登録者数は18歳から84歳まで約3.6万人。このうち約6割が20代で、その他世代は各1割ほどだ。以前は学生が多かったが、最近は60代以上の利用も増えてきており、人生100年時代を実感している」
「受け入れ事業者は、47都道府県、約千カ所。当初は旅館・ホテルに絞ってサービスを開始したが、現在は農業等の1次産業の事業者が増え、登録数は半々といったところだ」
「コロナ禍中では、度重なる感染拡大や、Go Toトラベル事業の開始などによる需要の波で、正規雇用、長期の人材派遣を利用しにくい中、宿泊事業者の利用が拡大した。結果的にコロナ禍前に比べて、登録事業者は3倍になった」
「おてつびとの登録も増加した。海外留学を予定していた人がこれに代わる国内での体験として利用したり、講義がオンラインになった大学生が現地で講義を受けながらおてつたびに参加したり。参加の仕方も多様になった」
――おてつびとは若い方が良いのか。
「事業者次第だ。体力の面では若い人に来てほしいという声も多いが、会社員やアクティブシニアなど、社会経験も豊富で、礼儀を知り、コミュニケーションの部分もスムーズに対応できる人に来てほしいという声もある。飲食店経営の経験者が花の飾り方などのアイデアを出して採用された例などもあった」
――おてつびとと受け入れ先のミスマッチを避けるための工夫は何か。
「お手伝い内容について『力仕事の多さ』『人手不足をより解消したいのか、地域魅力を発信したいのか』などをパラメータにして表示している。受け入れ先によっては、『何キログラム以上のものを運ぶ』などの具体的な説明もある」
「受け入れ先のレビューもあるが、おてつびと一人一人についても、申し込みがあった段階で、前のおてつたび参加先の事業者からのレビューやコメントを参照できる。その内容やプロフィールを見て、事業者が参加を承認する」
――旅館ホテルへのおてつたびはなぜ人気なのか。
「旅館に行った若いおてつびとは『めっちゃハードだった』と(笑い)。だが、『観光客が心地よく過ごすために裏側で旅館・ホテルの皆さんが支えてくれていたことに気付けて良かった』とも言っていた。おてつびとには観光を学んでいる学生も多い。実際に現場に立ち、スタッフの言動ひとつで目の前のお客さまの満足度が変わるのを目の当たりにして、ホスピタリティ産業に就きたいと思うようになったという話も聞いた。受け入れ先のオーナーは地域課題の解決などに関心のある人も多く、地域や働くことについて、一緒に話したり考えを聞けたりすることもおてつびとにとって価値になっている」
「実はおてつたび後に、その地域を観光客として再訪する人は非常に多いのだが、宿泊業の場合、宿の人にまた会いたいと思えば、客として予約して会いに行けるのも魅力の一つだ」
――宿泊業は待遇面の問題が取り沙汰されるが、課題はあるか。
「賃金は最低賃金以上で自由設定なのだが、時給の高さよりも、レビューであったり、地域の人の思いであったりを総合的に見て判断するおてつびとが多いので、特に問題はない」
「長時間労働については相談も多い。おてつびとが午前中働くことで、従業員は午後から出勤でゆとりを持て、おてつびとは午後観光できる、そういうハイブリッドな形がもっと増えるといいのかなと感じている」
――読者にメッセージを。
「創業前に宿のお手伝いをする中で、観光客として泊まるだけでは見えなかったオーナーの思いやこだわりに魅了された。OTAのサイトでは見えなくなってしまうオーナーの思いこそが宿の一番の価値だと思う。その思いがおてつたびを通じて見える化され、宿のファンづくりにつながる世界を作っていきたいし、日本の観光業がにぎやかになっていくためにできることはぜひ一緒にやっていきたい」

ながおか・りな 千葉大学卒業後、PR会社勤務等を経て、2018年7月におてつたび創業。三重県尾鷲市出身、32歳。
【聞き手・小林茉莉】