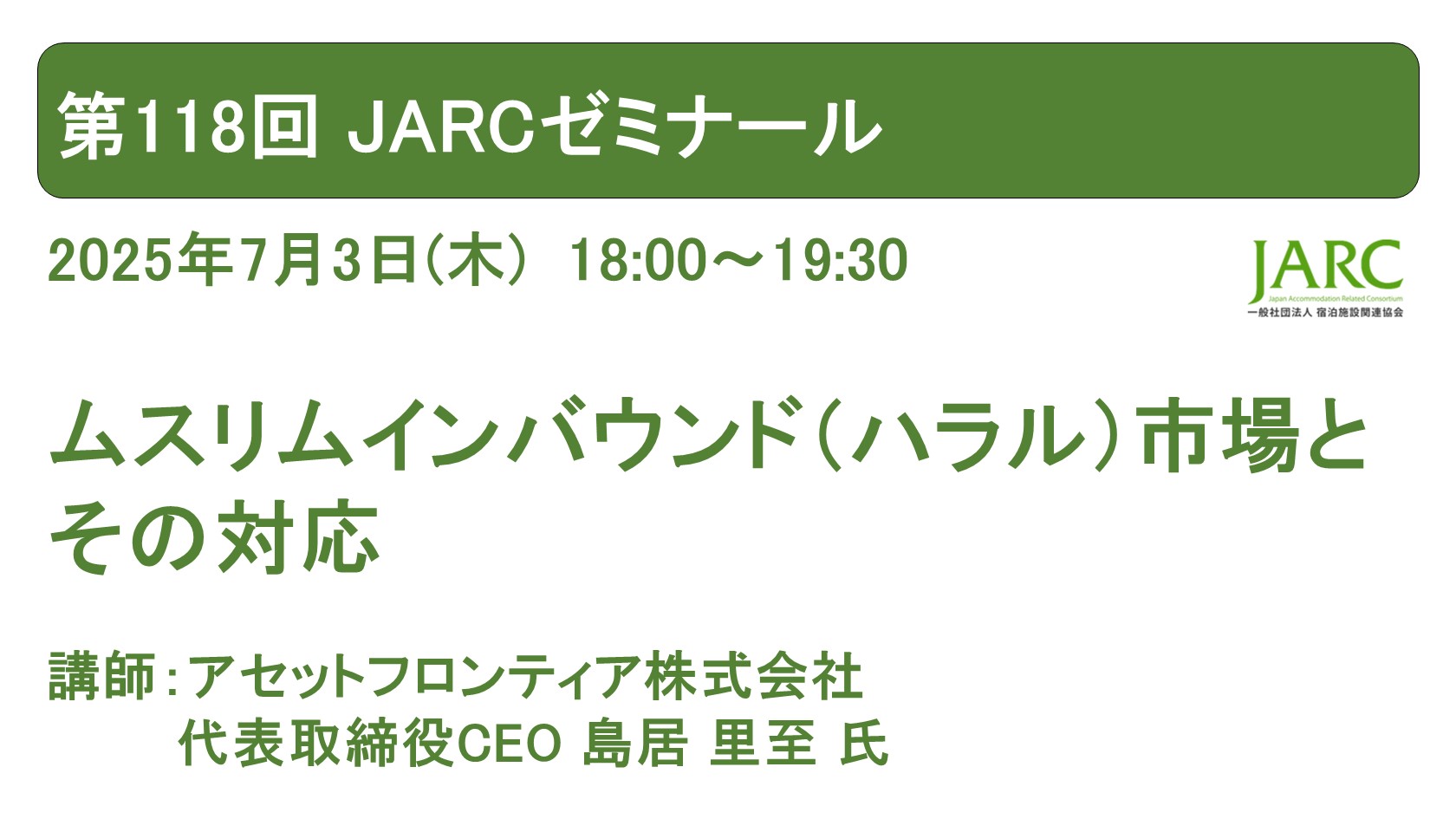山田氏
ポストコロナがどのようになるかは、いまだ、見通すことはできないが、新しい行動様式は、人々の行動を中長期的に規定していくことになると考えておくべきであろう。
宿泊事業の歴史をひも解くまでもなく、宿泊は旅行と密接な関係を持っている。われわれには睡眠が必要であり、自宅を離れて移動するには、安全に睡眠を取ることができる仕組み、施設が必要となるからだ。
さらに、われわれは宿泊や旅行に「睡眠」という機能的な価値だけでなく、同行者との懇親や食事の楽しみ、温泉の楽しみといった情緒的な価値を付加した需要を作り出してきた。こうした複合的な「宿泊」需要に対応してきたものが、わが国の「旅館」である。
しかしながら、われわれは、今回のコロナ禍において、いとも容易に「宿泊」需要が蒸発することを経験した。こうした状況認識に立脚すれば、旅館業が今後とも事業価値を「宿泊」のみに限定することは大きな事業リスクとなる。旅館業が持つ今日的な強みを生かしながら、事業に多様性を持たせていくことが求められると考えられる。
旅館業が持つ今日的な強みとは何か。それは、域外の人々との「つながり」だと私は、考えている。
2000年代の市場縮小期以降、多くの旅館は、地域の観光資源の発掘、活用を展開してきた。地域に所属する一つの主体として、観光まちづくりに取り組んできた施設も少なくない。
こうした取り組みは、域外の人々(顧客)の心の中に、地域や施設に対する思い入れ、信頼感を育ててきた。コロナ禍の中で、クラウドファンディングや、宿泊券の前売りに取り組んだ施設が、一定の成果をあげたのは、顧客の思い入れ、信頼感があってこそだろう。ポストコロナにおいては、この顧客とのつながりを、宿泊していない時間にも広げていくことを検討したい。例えば、顧客との一種のサブスクリプション契約を結び、顧客のライフスタイルや価値観に合わせて、旬の農産品を届けたり、オンラインで料理人による料理学校や、地域のまち歩きツアーを配信したりといったことが考えられる。
宿泊日だけなら年に数日だけのつながりであるが、日常生活と、ゆるやかにつながり続けることで、マネタイズ手法は多様化できるだろう。これは、旅館業のレジリエンスを高めることにつながる。さらに、こうした取り組みは、関係人口の拡大など、新しい観光地域づくりにもつながっていくと期待できる。
新型コロナは、未曽有の危機ではあるが、新しい時代への転換点とも考えられる。旅館業がこれまで培ってきた「つながり」資産を活用し、持続可能性を高めていくことを期待したい。

山田氏