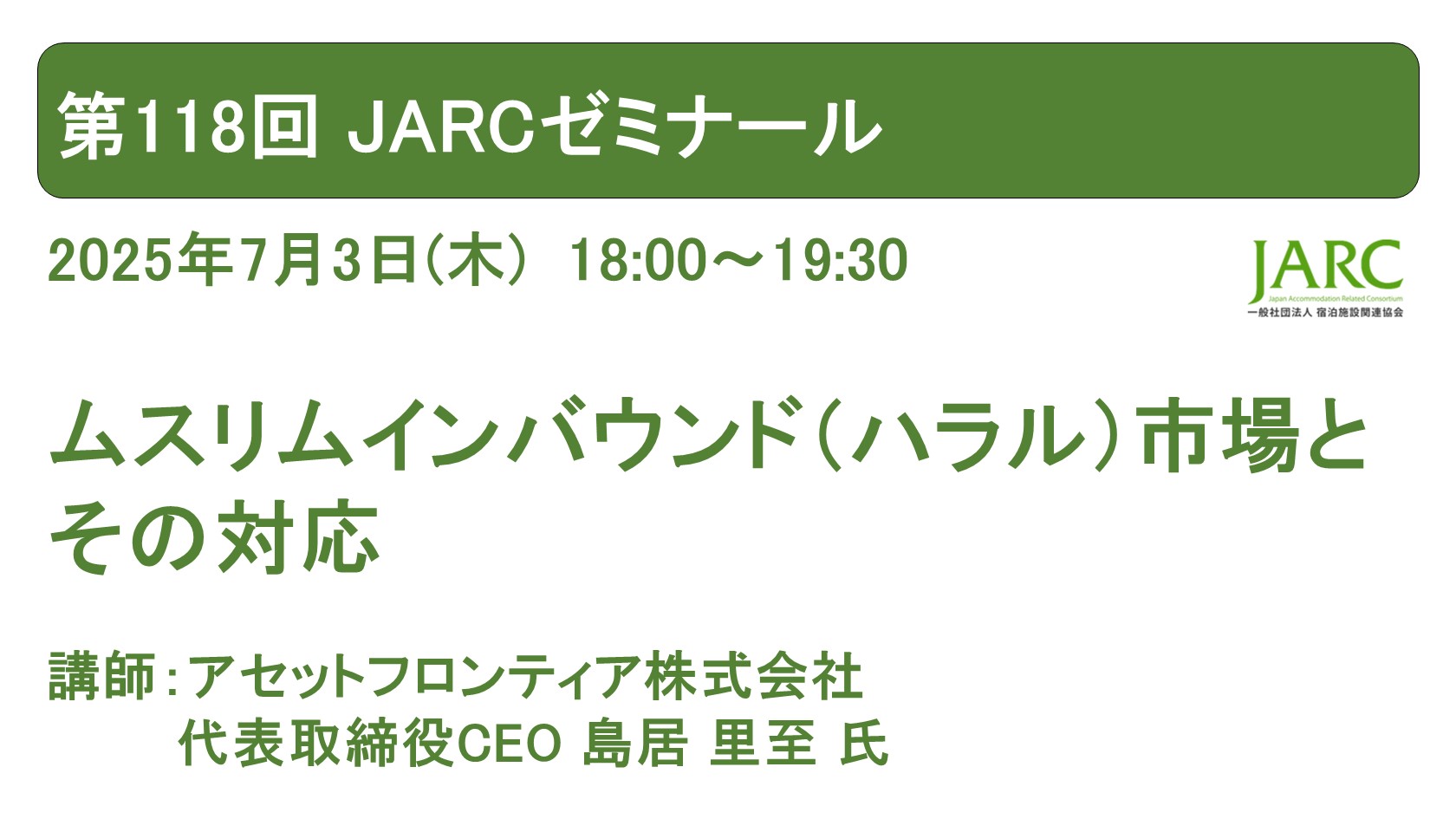高野氏
コロナ後も積極的な受け入れを
景気の低迷等により旅行市場が落ち込むと、旅行会社や観光団体の間では「困ったときの教育旅行」とよく言われる。実際に、このコロナ禍においても唯一動いていたのが教育旅行である。教育旅行は「旅行」とは付いているものの「旅行」ではなく学校の教育課程で行われる学校行事だからである。このコロナの影響で、今まで教育旅行を受け入れていなかった地域や施設に方面変更などによる教育旅行特需が発生し、その重要性を認知し誘致に取り組み始めたところも多くある。
インバウンド市場は、水際対策緩和と円安効果により、コロナ以前を超える需要回復が予想されている。個人的には、また一部の地域、施設で教育旅行の受け入れをやめて、インバウンドに傾注するのではないかと心配している。
私は、外国人観光客と修学旅行生のニーズには類似性があると考えている。海外の人々は日本のことをよく知らず、日本の子どもたちも日本のことを十分に知らず、似たような見学地を好んだりする。現に、コロナ直前の京都の清水寺や伏見稲荷などは、外国人客と修学旅行生であふれかえっていた。これは、子どもたちに人気がある場所や体験は外国人にも人気があると言える。教育旅行向けのプログラムを作り磨き上げたものはインバウンドに対しても転用が利く。
最近の教育旅行は学習指導要領の改訂もあり、学びの要素が強くなっている。訪日旅行の主となるアジアは今後の経済発展に伴い成熟し、欧米のお客さまと同様に観光における学びの要素が強くなってくると思われる。教育旅行向けの学びのプログラムを整備することは、今後のインバウンド対応にもつながる。教育旅行をやめてインバウンドにかじを切ることより、どちらも積極的に受け入れる取り組みをぜひ行っていただきたい。
現在、観光業界ではコロナによる打撃により、人手・人材不足が続いている。積極的に各地域で教育旅行を受け入れることは、子どもたちに「旅」や「観光」の力を通じて「学び・気づき」を与えることになる。早い段階で、旅行先でさまざまな体験、学習をすることによりその魅力に触れさせることは、将来の観光人材の育成に非常に有効なことだ。
若いうちに各地域に来てもらい、その地域の魅力、地域課題を見て体験し学んでもらい、現地の人とつながりを持ち、関心を持ってもらうことは、各地域のリピーターや将来のファン作りになる。ぜひ、観光業界の皆さまには、コロナ後も教育旅行の受け入れに積極的に取り組んでいただきたいと切に願う。